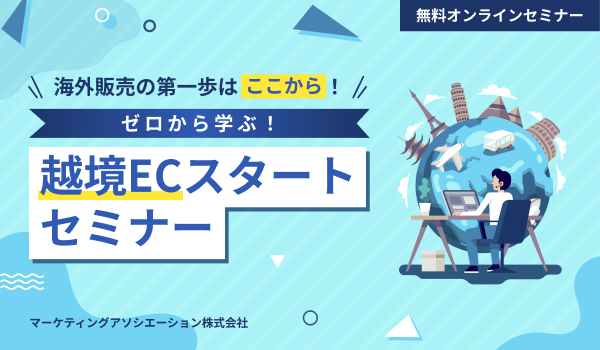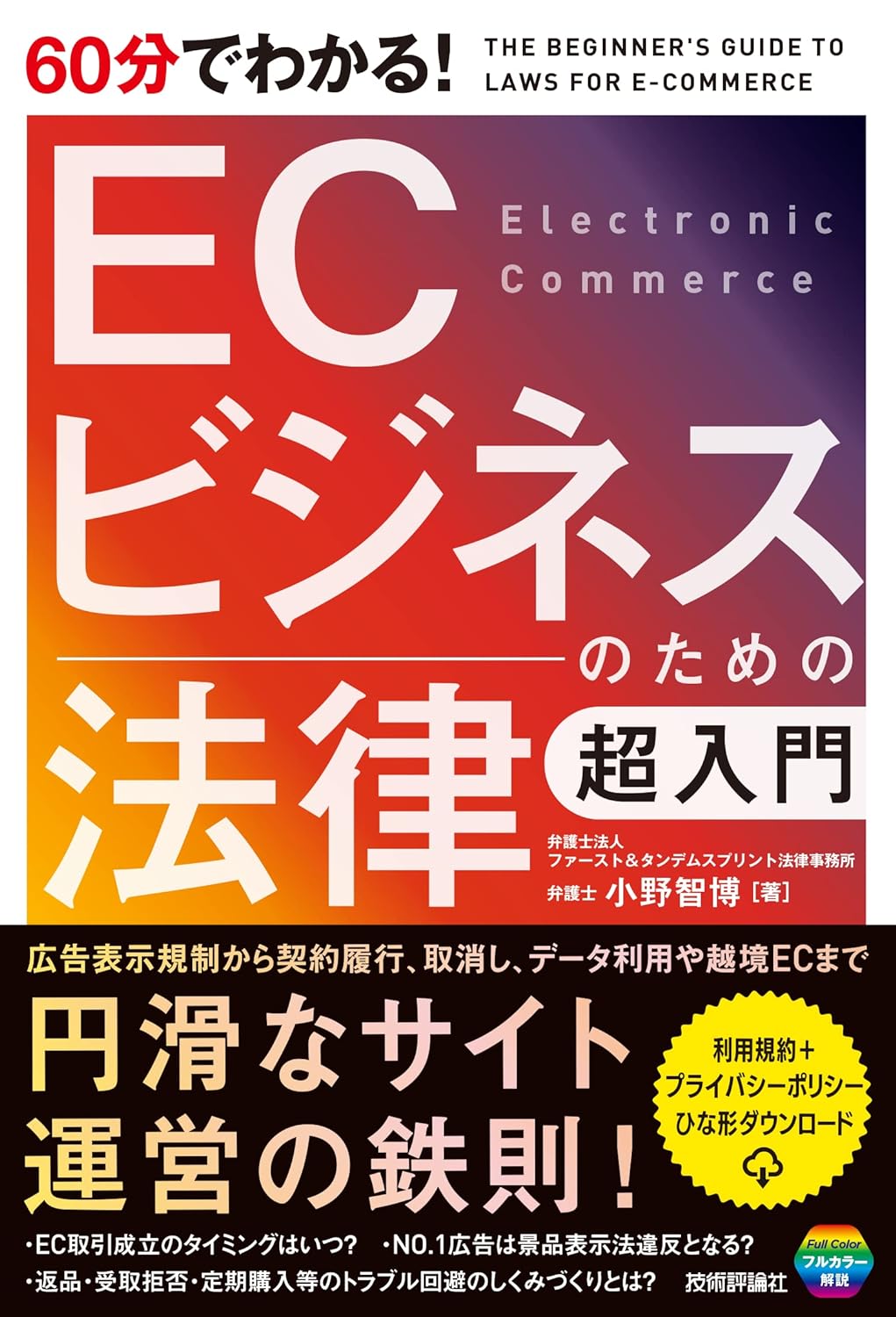ECサイト運営に役立つナレッジ共有ツールとは?おすすめツール6選と選定ポイント、運用のコツ
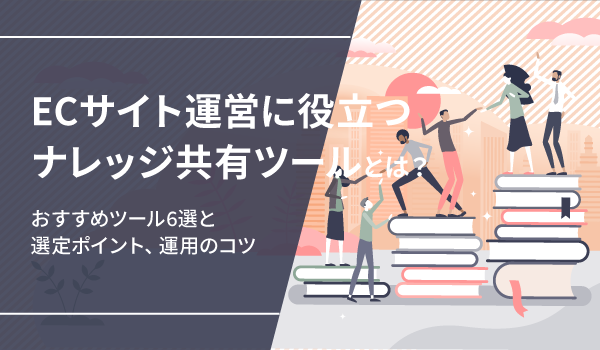
ナレッジ共有ツールとは、ノウハウや知識などの「ナレッジ」を、組織で共有するためのツールのこと。ナレッジ共有ツールを使ってナレッジを効果的に共有することは、ECサイト運営時においても役立つだろう。そこで本記事では、ナレッジ共有ツールの概要やECサイトの運営でナレッジ共有が役立つケース、おすすめのナレッジ共有ツール6選を紹介する。ツールを選定する際のポイントや運用時のコツについても参考にしてもらいたい。
ナレッジ共有とは?
ナレッジ共有とは、社員が業務を通じて取得した「知識」や「ノウハウ」、「成功事例」などの情報を、組織全体で共有すること。ナレッジ共有は組織の生産性を向上させることに繋がるため、企業において大切な取り組みとなる。
組織内で共有すべきナレッジは、2つの種類に分類される。まずは、把握しておくべきナレッジの種類について説明する。
ナレッジの種類
ナレッジは、「暗黙知」と「形式知」に分類される。以下で、それぞれの定義を見ていこう。
・暗黙知
「暗黙知」とは、簡単に言語化するのが難しいものを指す。例として、業務を円滑に進めるための「コツ」や、長年の経験に基づく「ノウハウ」などがある。
・形式知
暗黙知を言語化して誰にでも理解できるようにしたもの。具体的には、「社内wiki」や「マニュアル」「顧客データ」などが挙げられる。
暗黙知は、経験や勘に基づくナレッジとなるため、言葉で伝えにくいナレッジだ。一方、形式知は、数値やデータなどを使い具体的に示すことができるため、言語化し、伝えやすいものだと言える。ナレッジは、「暗黙知」のままでは社内で共有しにくいため、「形式知」に変換することが大切だ。
ナレッジ共有を行うことで得られるメリット
ナレッジ共有を行うことは、組織にとってどのようなメリットがあるのだろうか。以下で詳しく見ていきたい。
・業務効率の向上
個人の持つナレッジを社内で共有できれば、「業務の効率化」が期待できる。社内でナレッジ共有が適切になされていると、業務の進め方や注意点など、知りたい情報を必要なときに手に入れられるため、業務を円滑に進めることが可能だ。また、個々の経験やスキルを問わずにスムーズに業務を行えるため、組織の生産性も向上するだろう。
・属人化の防止
ナレッジ共有は、特定の社員のみしかできない業務が存在する「属人化」の防止にも役立つ。組織において、「担当者が急に休んだ際に業務が回らない」「特定の社員に業務負担が偏っている」といった課題を抱えるケースもあるだろう。ナレッジを社内で共有できれば、担当者以外のメンバーで業務に対応することができるほか、特定の社員に業務が集中することもなくなる。社員間の知識にバラツキがなくなるため、誰でも同じ品質で作業することもできるだろう。
ECサイトの運営でナレッジ共有が役立つケース
では、ECサイトの運営においてナレッジ共有が必要となるのは、どのような場面なのだろう。ここからは、ECサイトの運営でナレッジ共有が役立つケースを見ていく。
ECサイトの成長に伴う社員の増加
ECサイト立ち上げ時は少人数で始めた組織が、サイトの成長に伴い社員が増えることで、情報共有に対する課題を抱えるケースもある。例えば、各自が持っているナレッジが新しいメンバーに共有されていないと、担当者が不在だったり退職したりした際に対応できない、一から作業を行わなければならないという問題が生じるだろう。
こういったケースに、ナレッジ共有は役立つ。業務運営に関して必要な情報をチームや組織内に公開しておくことで、誰でも簡単にその情報を確認できるようになる。担当者だけでなく他のメンバーでサポートすることが可能となり、スムーズなサイト運営が可能になるだろう。
顧客への対応業務
ECサイト運営では、オペレーターによる電話やメールでの対応のほか、チャットボットを使って顧客対応を行うこともあるだろう。顧客への対応次第で商品の売上が左右されるため、ECサイト運営時の顧客への問い合わせ対応は、重要な業務の1つだ。
顧客への対応業務においてナレッジが共有されていないと、正確な情報を迅速に探し出すことができないため、問い合わせの対応品質が低下する。しかし、オペレーター同士でナレッジを共有すれば、顧客への対応業務を速やか且つ適切に行えるため、業務を円滑に進めることができるだろう。
ナレッジ共有ツールの選定ポイント
ナレッジを蓄積したり探し出したりするのに手間がかかると、社内でナレッジが活用されにくくなる。そのため、ナレッジ共有を効果的に行うためには、情報を共有しやすい環境の整備が鍵となる。そこでおすすめなのは、ナレッジ共有に特化した「ナレッジ共有ツール」の活用だ。ツールを活用すると情報が効率的に共有できるため、ナレッジ共有の文化が企業内に浸透する。ここからは、ナレッジ共有ツールを選定する際に、注目したいポイントを紹介する。
用途や目的に合った機能
ナレッジ共有ツールには、さまざまな種類がある。導入の目的や用途を明確にし、自社に合ったツールを選ぶとよいだろう。例えば、ナレッジを簡単に探し出したい場合は高度な「検索機能」がついているツール、マニュアルや社内wikiなどを簡単に見やすく作成したい場合は「Markdown形式」を活用できるツールがおすすめだ。このほか、自社の課題を解決してくれるツールを選ぶことも、ツール選定時のポイントとなる。
使いやすい操作性
使いやすい操作性であるかも、ツール選定時のポイントとなる。初めてツールを使う場合やツールの使用に不慣れな場合など、ITリテラシーが低い社員でも直感的に操作できる、シンプルな操作性のツールを選ぶとよいだろう。ツールによっては無料トライアルを設けているケースもあるため、まずは実際に社内で試してから検討するのがおすすめだ。
セキュリティの安全面
組織にとって重要な情報を適切かつ安全に管理するためには、セキュリティ面も考慮したい。蓄積したノウハウやデータなどが社外に流出した場合、組織にとって重大な損失となるだろう。ウイルスによる被害や情報漏洩などからナレッジを守ることができるのか、ツールごとのセキュリティ対策を事前に確認することが大切だ。
おすすめのナレッジ共有ツール6選
ここからは、おすすめのナレッジ共有ツールについて、それぞれの特徴を見ていこう。
esa
「esa」は、情報を育てるという視点で作られた、チームのための情報共有ツール。「Markdown形式」や「Webhookによる各種サービスとの連携」、「記事の外部公開とスライドショー」といった、情報を育てるためのさまざまな仕組みがある。不完全な情報も一度共有し、情報を更新しながらチームで育てていくというコンセプトも特徴だ。フリートライアルを2カ月間利用でき、フリートライアル終了後は一人あたり月額500円(税込)から利用できるため、始めやすいツールの一つだろう。
(サービス詳細はこちら)
NotePM
「NotePM」は、使いやすい設計が特徴の、ナレッジ共有・社内wikiツールだ。高機能エディタやテンプレートを使い、マニュアルや社内wikiをウェブ上で簡単に作成することができる。また、全文検索など強力な検索機能を備えているため、欲しい情報をすぐに見つけることも可能だ。ユーザー数8人までなら月額4,800円(税込)から利用でき、無料トライアルも設けている。
(サービス詳細はこちら)
Qast
ナレッジ経営クラウド「Qast」は、Q&Aやwikiを使ってナレッジを蓄積できる。操作説明や使い方についてサポートしてくれるため、ナレッジを組織に定着させることが可能だ。10名以下であれば無料でご利用できるフリープランがあるため、一度試してみるとよいだろう。
(サービス詳細はこちら)
iTutor
「iTutor」は、マニュアル作成の効率化を図れるツールだ。業務マニュアルや動画マニュアル、eラーニング教材などあらゆるマニュアルを自動で作成することが可能だ。フリープランは無いが、27.5万円(税込)から利用できる。
(サービス詳細はこちら)
Kibela
「Kibela」は、中小企業から大企業まで、業界や職種を問わずに簡単に情報を共有できるツールだ。Markdown形式やリッチテキストエディタ形式にも対応。フリープランや無料トライアルもあり、1ユーザーあたり月額550円から利用できる。
(サービス詳細はこちら)
Scrapbox
「Scrapbox」は、チームに必要なナレッジを集約できるツール。フォルダやラベルによる「階層分類管理」で情報を共有するのではなく、ページ間をリンクで繋いで共有する機能を備えているのが特徴的だ。また、画像や動画、地図などを簡単に添付できることも特徴の一つ。無料で試せるトライアルを設けているため、活用してみるとよいだろう。
(サービス詳細はこちら)
ナレッジ共有ツールを効果的に運用するためのコツ
ナレッジ共有ツールを導入しても、社員が積極的に活用しなければその効果は期待できない。ここからは、ナレッジ共有ツールを組織で運用する際に、知っておきたいコツを紹介する。
運用担当者を置く
ツールを運用する際は、運用担当者が運用・管理を一貫して行うことがコツとなる。運用担当者は、「ツールの活用方法や重要性を組織で共有する」「ツール使用時に生じた不具合などの課題に対して解決策を講じる」「効果的に運用されているかを定期的にチェックする」といった役割を担うとよいだろう。
また、運用担当者が率先してナレッジを投稿したり、活用したりすることもポイントだ。社員の見本となることで、組織全体のナレッジを共有する意識が高まるほか、社員のナレッジ共有への心理的ハードルも下がるだろう。
運用時のルールを定める
運用時のルールを定めることも、運用時のコツの1つだ。例えば、「運用する時間帯はどうするのか」「ナレッジはどのように分類し社内に共有するのか」といったルールを定めるとよいだろう。ただし、ルールを細かく設定しすぎると、ツールが活用されないケースもあるため注意が必要だ。
まとめ
ナレッジ共有ツールとは、有益な情報であるナレッジを、組織内で効果的に蓄積・運用できるツール。ECサイト運営時においても、「属人化の防止」や「業務の効率化」に役立つため、検討するとよいだろう。ナレッジ共有ツールにはさまざまな種類があるが、自社の利用用途や目的に見合ったものの中から、使いやすい操作性であるツールを選ぶのがおすすめだ。
ナレッジ共有ツールを運用する際のコツも参考にしながら、組織内でナレッジを効果的に活用し、組織の生産性向上に繋げよう。