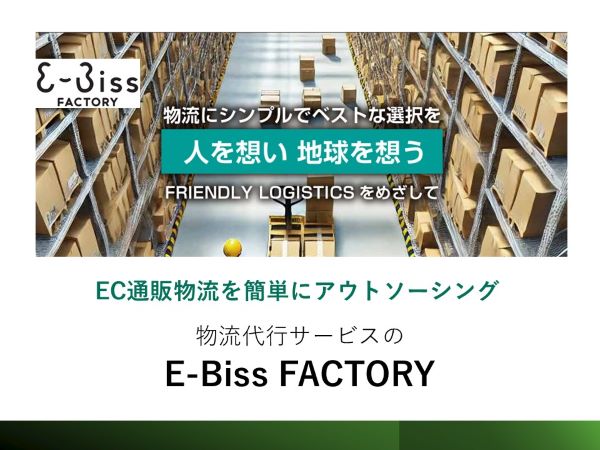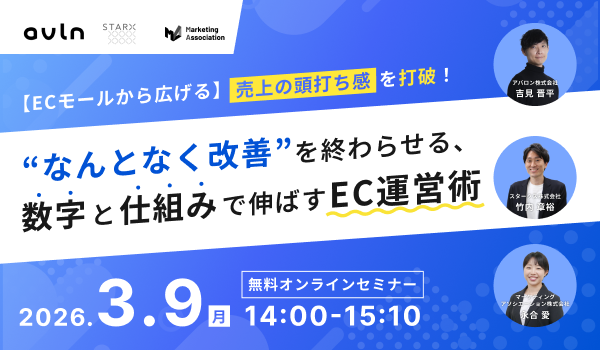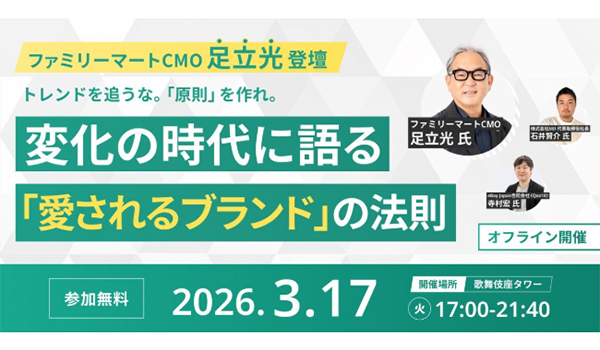ECサイト制作の完全ガイド:費用・構築手順から成功事例まで

ECサイトとは?種類と役割
EC(E-Commerce:電子商取引)サイトとは、インターネット上で商品やサービスの売買を行うWebサイトの総称です。物理的な店舗を持たずともビジネスが可能であり、近年では単なる販売チャネルを超え、ブランドの世界観を伝えるメディアとしての役割も強めています。
ECサイトの主な種類
取引の主体が「誰」かによって、大きく以下の3つに分類されます。
BtoC (Business to Consumer):企業が一般消費者に販売する形態。Amazonや楽天などの「モール型」と、自社ブランドを直接販売する「自社サイト型(D2C含む)」があります。
BtoB (Business to Business):企業間取引。卸売や受発注システムがこれに該当します。市場規模はBtoCよりも遥かに大きく、近年急速にデジタル化(FAX・電話からの脱却)が進んでいます。
C2C (Consumer to Consumer):個人間取引。メルカリなどのフリマアプリが代表的です。
ECサイト最大の役割は、「商圏(時間と場所)の制約を取り払うこと」です。24時間365日、世界中から注文を受けられるため、実店舗ではリーチできない層へアプローチ可能です。 また、「顧客データの蓄積」も重要な機能です。「誰が・いつ・何を・どれくらい見たか」という行動データを取得・分析できるため、実店舗以上に精度の高いマーケティングや、オムニチャネル戦略(実店舗とWebの融合)のハブとして機能します。
ECサイトの作り方はビジネス規模で変わる
ECサイトの作る方法には、カートASPやクラウドEC、パッケージ、オープンソースなどがあります。どの方法を選択すべきかどうかは、ビジネス規模によって変わります。まずは個人か法人か、次にECサイトの年商を基準として、利用するプラットフォームを選択すべきでしょう。
以下では、ビジネス規模に応じたECサイトの構築方法について紹介します。
①個人の場合は無料カートASPから始めるのがおすすめ
個人でECサイトを開設する場合、無料のカートASPがおすすめです。カートASPとは、オンラインでアプリケーションを利用できるプラットフォームです。サーバーへのインストールなしでECサイトを構築できます。代表的な無料カートASPには、BASEやSTOERSなどがあります。
無料カートASPは、初期費用、月額費用ともに無料です。はじめのうちは売上の予測がたたないため、わずかな固定費でも打撃になりかねません。コストを抑えてスモールスタートしたい方は無料ASPから始めてみるとよいでしょう。
②年商1億未満の企業は有料カートASPから始めるのがおすすめ
法人でECサイトを開設する場合、売上のめどがたっていないのであれば有料カートASPがおすすめです。代表的な有料カートASPには、MakeShopやShopifyなどがあります。有料カートASPは、月額制となっているケースが一般的です。安いものでは月額1,000円前後ですが、高いものでは月額50,000円を超えるプラットフォームもあります。有料カートASPは、無料カートASPよりも機能が充実しており、本格的なECサイトを立ち上げられます。
法人で運営するのであれば、月額費用の負担は大きなコストにはならないうえ、将来的な拡張性にも優れているため、有料カートASPを利用するとよいでしょう。
③年商1億円以上の企業は「クラウドサービス」「パッケージ」「オープンソース」を検討
法人でECサイトを開設する場合、年商1億円以上の売上が見込まれるのであれば、クラウドECやパッケージ、オープンソースなどがおすすめです。代表的なプラットフォームには、ecbeingやEC-orange、ebisumartなどがあります。
パッケージやオープンソースは拡張性の高さが強みです。ECサイトの規模が大きくなるにつれて、独自の要件やシステム連携が必要となるため、拡張性の高いプラットフォームを選ぶことが大切です。
また、クラウドECはオンラインでアップデートを完了できるため、最新性を維持できます。つねに最新のシステムを利用できることは、セキュリティやユーザビリティの面においても重要です。
ECサイト構築方法の全比較:メリット・デメリットと最適な選び方
ECサイトの構築方法は、予算、技術力、事業規模によって最適な選択肢が異なります。ここでは代表的な6つの手法について、特徴と選び方を解説します。
1. ECモール(Amazon、楽天市場など)
既存の巨大プラットフォームに出店する形式です。
特徴:圧倒的な集客力が最大の魅力。自社での集客活動が不安な立ち上げ期に適しています。
費用感:初期1〜5万円、月額1〜5万円+販売手数料(10〜15%程度)。
導入フロー:出店審査申し込み → 書類提出 → 店舗ページ作成(審査通過後) → オープン。
2. ASPカート(Shopify、BASE、futureshopなど)
クラウド上のシステムをレンタルする形式。現在の主流です。
特徴:低コストかつ短期間で導入可能。自動アップデートによりシステムが陳腐化しません。
費用感:初期無料〜、月額0〜数万円(プランによる)。
導入フロー:アカウント開設 → テンプレート選択・デザイン設定 → 商品登録・決済設定 → 公開。
3. オープンソース(EC-CUBE、WooCommerceなど)
無償公開されているプログラムを自社サーバーにインストールする形式です。
特徴:ライセンス料が無料。自由なカスタマイズが可能ですが、セキュリティ対策や保守は自社責任となります。
費用感:ソフト無料。サーバー費・開発費(数十万〜数百万円)。
導入フロー:サーバー契約 → プログラムのインストール → デザイン・機能開発 → 公開。
4. パッケージ(ecbeing、ebisumartなど)
開発会社が提供する基本システムをベースに、独自機能をカスタマイズする形式です。
特徴:年商数億円以上の中〜大規模EC向け。安定性と拡張性に優れます。
費用感:初期500万円〜、月額数万円〜(保守費)。
導入フロー:ベンダー選定 → 要件定義 → カスタマイズ開発 → テスト → 公開。
5. フルスクラッチ
既存のシステムを使わず、ゼロから完全に独自開発する形式です。
特徴:独自のビジネスモデルや特殊な物流フローに完全対応できますが、コストと期間が膨大です。
費用感:数千万円〜青天井。
導入フロー:開発会社と綿密な要件定義の上、半年〜1年以上かけて開発。
6. SNS連携EC(Instagramショッピング、TikTok Shop)
SNSの投稿に商品タグを付け、購入ページへ誘導する手法です。
特徴:ファンとのエンゲージメントを直接販売に繋げられます。通常はASPなどと連携して利用します。
費用感:SNS自体は無料(連携するECサイトの費用は別途)。
導入フロー:ビジネスアカウント取得 → Meta Business Suite等でカタログ作成 → 審査 → 投稿へのタグ付け。
ECサイト制作にかかる費用・相場は?
ECサイト制作において予算計画を立てる際は、「イニシャルコスト(制作費)」と「ランニングコスト(維持費)」を分けて考える必要があります。
制作費には、システム構築費、デザイン費、要件定義費、コンテンツ制作費(撮影・ライティング)が含まれます。一方、維持費には、サーバー・ドメイン代、システム利用料、決済手数料、保守サポート費が含まれます。見落としがちなのが「決済手数料」で、売上規模が大きくなるほど利益を圧迫するため、初期段階でのシミュレーションが不可欠です。
| 構築方法 | 費用相場(目安) |
|---|---|
| 1)1から作る方法(フルスクラッチ) | 500万円〜 |
| 2)オープンソースを活用して作る方法 | 300万円〜 |
| 3)構築ツール(ECパッケージ)を使って作る方法 | 100万円〜 |
| 4)クラウドECで作る方法 | 50万円〜300万円 |
| 5)ASP(ショップ作成サービス)で作る方法 | 無料~10万円 |
ECサイト構築費用を左右する「8つの要素」と費用を抑えるポイント
見積もりが変動する主な要因は、以下の8つの要素の複雑さと量に依存します。
1.システム選定:ASPかスクラッチか(最大の変動要因)。
2.デザイン:テンプレート利用か、完全オリジナルデザインか。
3.ページ数・商品数:商品登録代行の有無や、LP(ランディングページ)の枚数。
4.機能開発:ギフト対応、定期購入、予約販売などの追加機能。
5.外部連携:基幹システム、倉庫管理システム(WMS)、POSとの連携開発。
6.コンテンツ素材:商品撮影や原稿作成をプロに依頼するか。
7.データ移行:旧サイトからの顧客・注文データの移行作業。
8.SEO・マーケティング:分析ツール導入や初期SEO対策の深さ。
【費用を抑えるポイント】
予算内で最大の効果を出すには、「初期要件の絞り込み(MVP開発)」が鉄則です。最初はASPのテンプレートを活用してデザイン費を抑え、撮影や商品登録は自社で行うことで、初期費用を大幅に削減できます。まずは「売る」ことに集中し、売上規模の拡大に合わせて機能を追加(リニューアル)していく段階的な投資が成功の鍵です。
ECサイト制作の具体的な手順:計画から公開後の運用まで
ECサイト構築は、採用するプラットフォーム(ASP、パッケージ、オープンソースなど)によって作業負荷や難易度は異なりますが、成功させるための大枠のプロセスは共通しています。
ここでは、制作の流れを「計画・要件定義」「デザイン・開発」「テスト・公開」「運用・改善」の4つのフェーズに分け、各段階で実施すべきタスクと、手法ごとの注意点を解説します。
計画・要件定義フェーズ:成功の土台を作る
プロジェクトの成否を分ける最も重要なフェーズです。「誰に・何を・どう売るか」を明確にします。
コンセプト策定:ターゲット層、取扱商材、競合優位性(USP)を決定します。
システム選定(構築手法の決定): ここで、予算と自社の技術力(リソース)に合わせてプラットフォームを選びます。
カートASP:コスト重視で手軽に始めたい場合に最適。Web知識がなくても導入可能です。
パッケージ・クラウド:年商数億円を目指す場合や、独自の業務フローがある場合に適しています。ベンダーへの提案依頼書(RFP)作成が必要です。
オープンソース:社内に技術力があり、コストを抑えつつ自由なカスタマイズをしたい場合に検討します。
要件定義: 「決済方法は何を入れるか」「物流倉庫と連携するか」「ポイント機能は必要か」など、実装する機能(スコープ)を確定させます。ASPの場合は「どのプラン/アプリで実現するか」、パッケージの場合は「開発仕様書」として落とし込みます。
デザイン・開発フェーズ
要件定義に基づき、実際にサイトを構築します。手法によって作業内容が大きく異なります。
環境構築(サーバー・ドメイン): ASPやクラウドEC(SaaS型)では不要ですが、オープンソースやインストール型パッケージの場合、自社でサーバーを選定・契約し、ソフトウェアをインストールする必要があります。
デザイン制作
・ASP:用意されたテンプレートから選び、ロゴやバナーを配置します。制限があるため、大幅なレイアウト変更は難しい場合があります。
・パッケージ・オープンソース:TOPページ、商品詳細、カート画面など、全ての画面をオリジナルでデザイン・コーディング可能です。
システム設定・機能実装: 決済代行会社との契約・接続設定、送料設定、メール通知設定などを行います。パッケージの場合は、この期間にプログラム開発(3ヶ月~半年程度)が行われます。
商品登録・コンテンツ作成: 商品画像、商品説明文、価格、在庫数などを登録します。「ささげ(撮影・採寸・原稿)」業務のリソース確保が必須です。
テスト・公開フェーズ
完成したサイトが正しく動作するかを確認し、公開(ローンチ)します。
動作検証(テスト): 実際に注文を行い、「決済が通るか」「注文確認メールが届くか」「管理画面に受注が入るか」を確認します。スマートフォンやタブレットでの表示崩れも必ずチェックしましょう。
法対応の確認: 「特定商取引法に基づく表記」や「プライバシーポリシー」のページが正しく掲載されているかを確認します。
公開: DNS設定(ドメインの向き先変更)を行い、一般ユーザーが閲覧できる状態にします。
運用・改善フェーズ
ECサイトは「作って終わり」ではありません。公開後が本当のスタートです。
集客・マーケティング: SNS運用、Web広告、SEO対策を行い、サイトへの流入を増やします。
受注・配送業務: 注文が入ったら、在庫を引き当て、梱包・出荷し、発送完了メールを送ります。
保守・メンテナンスとリスク管理: 手法によって負担が異なります。
ASP/クラウドEC:システムは自動更新されるため、保守の手間はほぼありません。
オープンソース:セキュリティの脆弱性が発見された場合、自社でパッチを当てるなどの対応が必須です。情報漏洩リスクが高いため、専門知識のある担当者か保守ベンダーの契約が欠かせません。
パッケージ:システムの老朽化に伴い、数年ごとのリニューアルやアップデート費用が発生するケースがあります。
<>分析と改善(PDCA): Googleアナリティクスなどでアクセス解析を行い、「カゴ落ち率」や「転換率(CVR)」などの数値を見ながら、デザインや動線を継続的に改善します。ASPでは機能追加に制限があるため、事業拡大に伴いパッケージ等へ移行(リプレイス)することもあります。
ECサイトを作る際に注意したい3つのポイント
ECサイトを作成する際、構築方法やデザインの工程があります。開設前の段階ではありますが、売れるサイト設計ができていなければ、ローンチ後に失敗しやすくなります。準備のタイミングから集客や顧客体験を意識することが大切です。
以下では、ECサイトを構築するうえで注意すべきポイントについて解説します。
商材・サイト規模に合った構築方法を選ぶ
前述のとおり、ECサイトの構築方法は多種多様です。どんなプラットフォームを利用すべきかどうかは商材やサイト規模によって異なります。たとえば、定期購入商品やBtoB販売を取り扱う場合、対応していないカートシステムも少なくありません。
また、安価なカートASPは一度に大量のアクセスがあると処理できない可能性もあります。システムエラーによって機会損失が発生するリスクもあるため、要件やサイト規模に応じてプラットフォームを選択すべきです。
ユーザー視点でデザインする
ECサイトをデザインする際は、つねにユーザー視点を意識することが重要です。商品を探しやすいか、購入までのフローはわかりやすいかなど、ECサイトを訪れたユーザーが利用しやすい設計を目指しましょう。
デザインが洗練されていたり、豊富な機能を備えていたりしても、商品の検索・購入の方法がわかりにくければ離脱されやすくなります。顧客体験を第一に考える意識がないと、ユーザビリティに欠けたサイトになってしまいます。
改善しやすいサイト設計にする
ECサイトを運営する中では、ユーザーの意見や反応をもとに改善を図ることも必要です。Googleアナリティクスやヒートマップなどのデータを参考にして、サイト改善に向けたPDCAを繰り返しましょう。
たとえば、Googleタグマネージャを活用すると、個々のページのHTMLを編集せずにタグを一元管理できます。はじめに管理体制を整えて、改善しやすいサイト設計にしておくこともポイントです。
ECサイトを作る際に参考になる本
近年ではECサイト制作が非常にポピュラーになっています。もともと物販を手がける法人はもちろん、個人でもECサイトを開設するケースが増えています。しかし、ECサイトの構築や運用には知識やノウハウが必要です。そこでECサイトの開設に際して、本から情報を得るのがおすすめです。
以下では、ECサイトをつくる際に参考になる本について紹介します。
新人IT担当者のための Webサイト 構築&運営がわかる本
ECサイトの構築や運用における基本をまとめた書籍です。
タイトルのとおり、初心者向けにわかりやすく解説する内容となっています。イラストや図解が多い点が特徴的です。必要な知識、具体的なノウハウを含めて、ECサイトについて横断的に学習できる一冊です。
気付けばプロ並みPHP 改訂版-ゼロから作れるようになる
PHPでECサイトを制作するうえで参考になる書籍です。PHPはWeb制作に適したプログラミング言語です。初心者でも比較的理解しやすく、本書を参照すれば基本的なサイト構築はできるようになるでしょう。ただ、発行年が2017年のため、一部情報が古くなってしまっている点に注意すべきです。
すっきりわかるJava入門
JavaでECサイトを制作するうえで参考になる書籍です。Javaは、OSに依存せず動作する言語のため、iOSやAndoroidを問わず安定したパフォーマンスを発揮できます。処理の速さやセキュリティの面においても優れていて、ECサイトの構築にも向いています。
先輩がやさしく教えるEC担当者の知識と実務
ECサイトを運営するうえで必要な知識や実務を理解できる書籍です。とくにECモールを利用したショップ運営を中心としています。Amazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングの3大モールをメインに解説しており、モールを含めて検討している方におすすめです。チャネルごとの特性を理解するには最適な一冊です。
成功するネットショップ集客と運営の教科書
ECサイトの作り方だけでなく、構築後の集客やロイヤリティ向上までを含めて解説している書籍です。売れるECサイトの特徴を60のポイントとして列挙しており、読み進めるうちに要点をおさえた運用ができるようになるはずです。初心者はもちろん、ECサイトの運営に悩む中堅担当者にとってもヒントになるでしょう。
はじめてのネットショップ 開店・運営講座
ECサイトの構築から運用までを、講座形式で解説している書籍です。商品紹介ページの作成方法などを実践形式で学べる点も特徴的です。具体的なノウハウを身につけられるため、EC運営の即戦力にもなれるでしょう。
小さな会社のWeb担当者・ネットショップ運営者のためのWebサイトのつくり方・運営のしかた 売上・集客が1.5倍UPする プロの技101
中小事業者や個人向けに、ECサイトの構築や運用について解説している書籍です。
中小規模のECサイトは、大規模なサイトに比べて、流入の確保やファンの育成が難しいため、本書は参考になるでしょう。とくに集客や販促についての情報が充実しており、SEO施策や分析ツールの利用方法なども学べる一冊となっています。
まとめ
ECサイトの作り方は、ビジネスの規模によって適切な方法を選択すべきです。プラットフォームごとの特徴やメリット・デメリットを把握しておくと、選びやすくなるはずです。また、ユーザー視点や運営中の改善を意識したデザインを組むと、売れるECサイトを構築しやすくなります。本やネット上の情報を参考に、しっかりと準備したうえで土台を構築することが大切です。