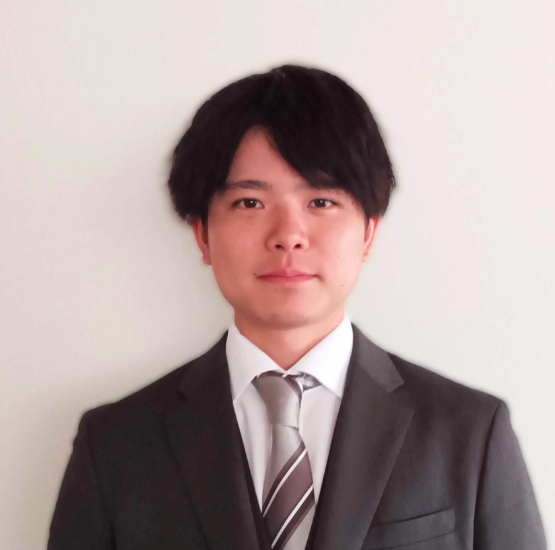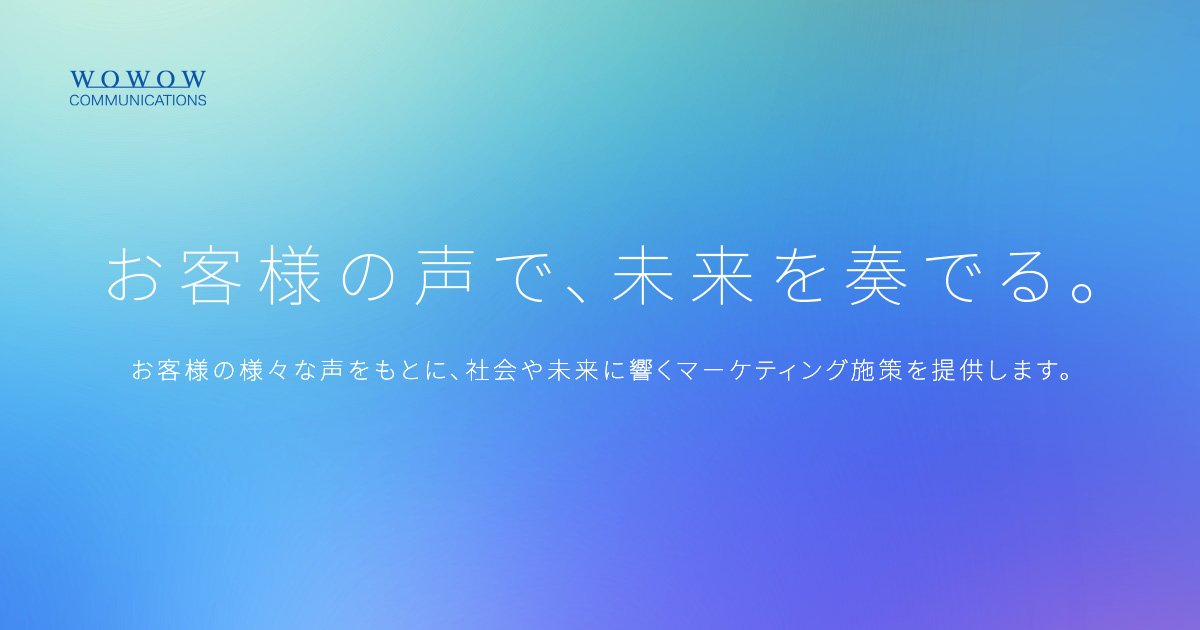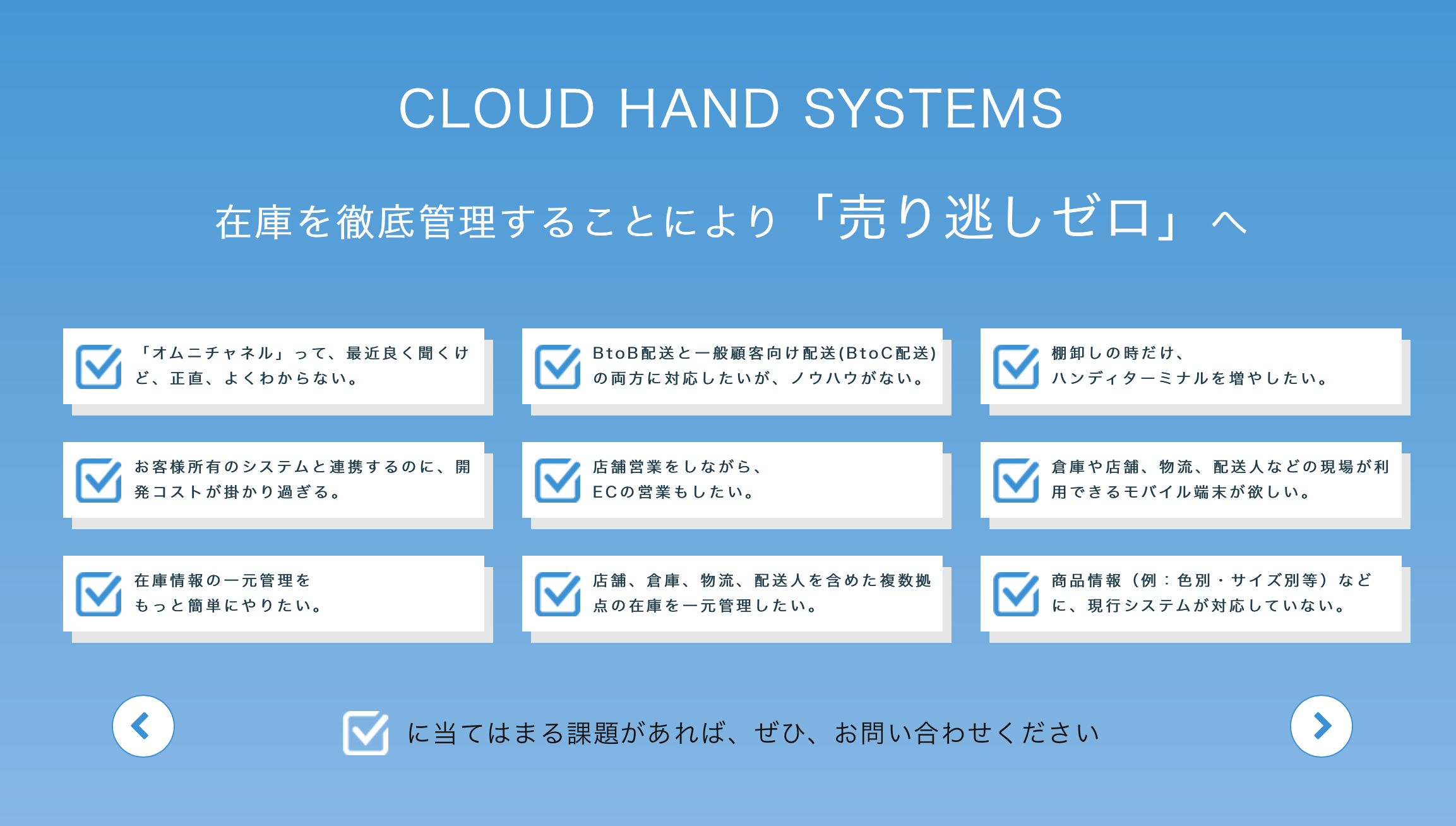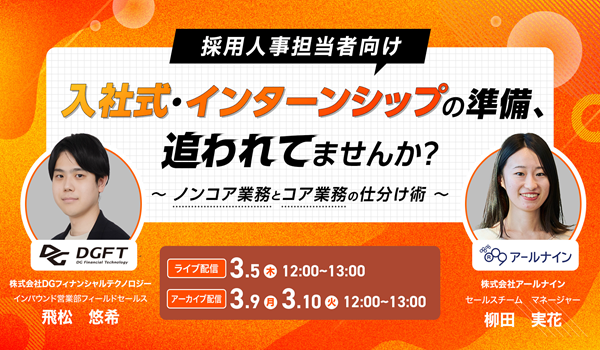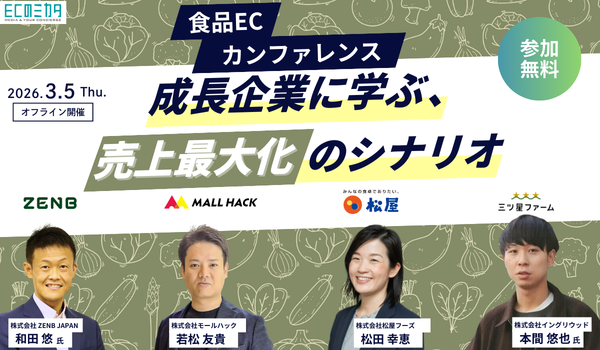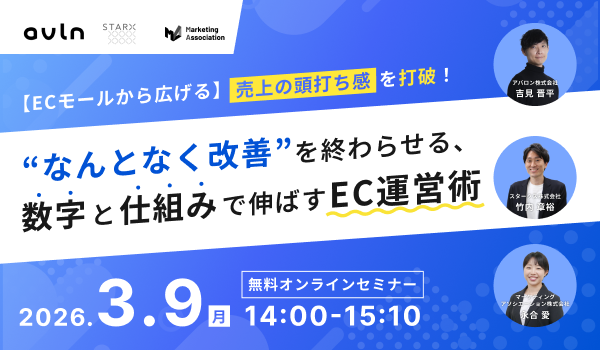実際どうだった? 中小企業の成功事例に学ぶ「インフルエンサーマーケ運用のコツ」《前編》
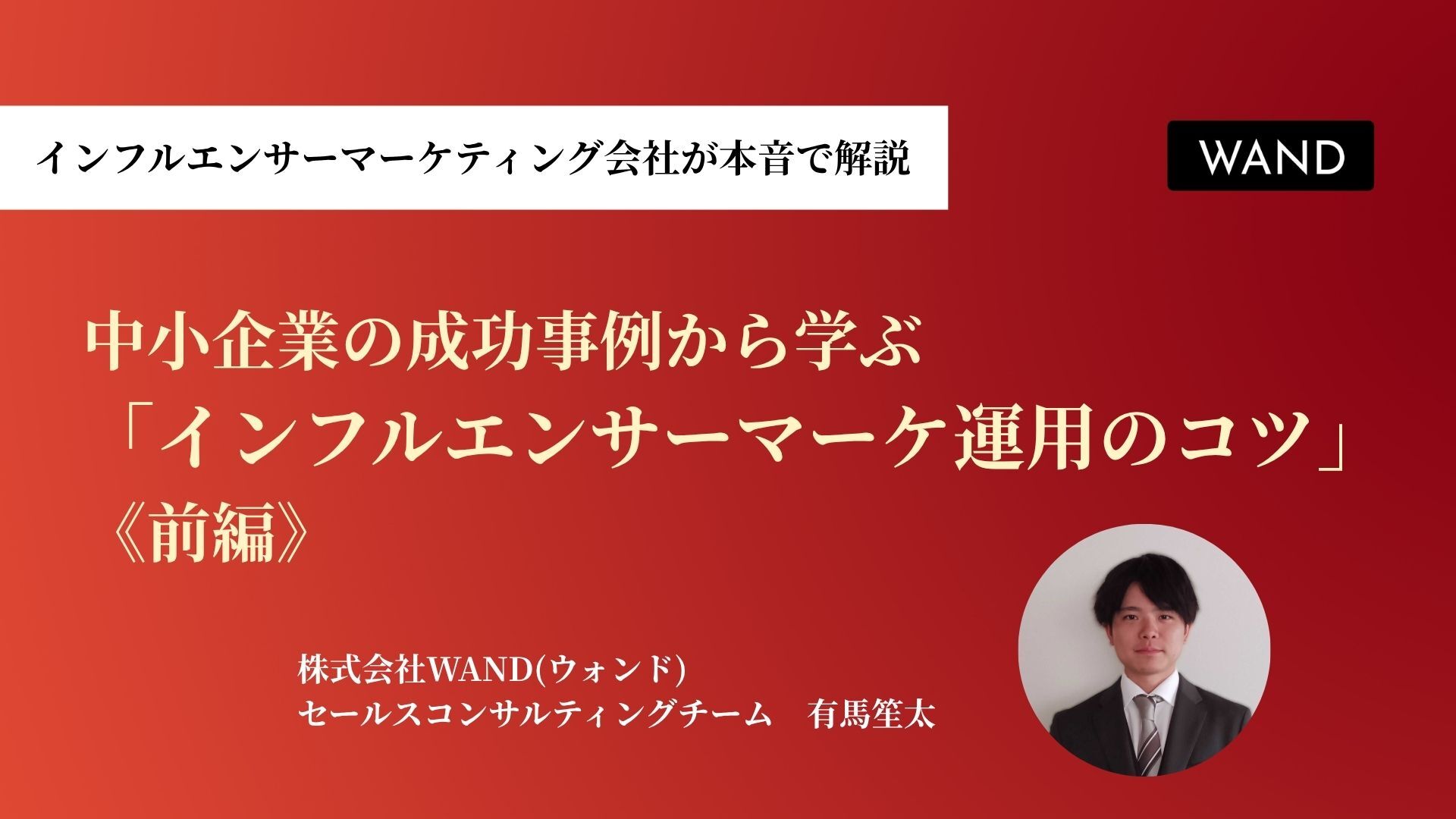
こんにちは、株式会社WANDの有馬です。株式会社ファンコミュニケーションズの連結子会社で、SNSマーケティング支援と約30,000人のショート動画クリエイター向け企業案件プラットフォーム「LUMOS」を提供しています。
これまでの3回では、
◆第1回:インフルエンサーとは何か?
◆第2回:施策を始める前の設計の仕方
◆第3回:インフルエンサーの選定とアプローチ方法
といった、“準備”の部分を解説してきました。
今回は少し視点を変えて、実際に中小企業がどのようにインフルエンサー施策に取り組み、どんな成果を出したのか、リアルな事例をもとに運用のコツを学んでいきましょう! 前編・後編の2回に分けてご紹介するのでお楽しみに。
SNS時代の「信頼設計型マーケティング」とは?
SNSで商品を知り、口コミで購入を決める。
いまのEC市場では、”誰が、どんな文脈で薦めるか”が購買行動を左右します。大きな予算をかけられない中小ブランドが成果を出すには、フォロワー数よりも「共感と信頼」をどう設計するかがカギです。
今回は、実際に成果を上げた2つの事例をもとに、“小さなブランドがSNSで勝てた理由”を整理します。
◆事例1|新発売のシャンプー・トリートメント

背景:
商品力には自信があるが、新発売の商品のため認知度が全くないという状態。予算的に大手企業のように派手なキャンペーン施策を行うのは難しい
施策:
TikTokで、ターゲット層である20~30代前後の女性ファンを多く抱えたインフルエンサーを32名起用(3カ月の累計起用数)。特に効果の良かったインフルエンサーの投稿を活用して広告運用も実施
結果:
・総再生数が120万回を突破。SNS上での話題創出・口コミ増加に成功
・ECモール上でもレビュー30件、☆4.3を達成し、発売直後の購入に貢献
・美髪ハウツー動画の投稿により「同じシャンプーで同じケアをしたい!」といった、購買意欲のあふれるコメントも多数見られた
成功ポイント:
普段からヘアケア等の美容に関する投稿をしている、かつエンゲージメントの高い方を起用。インフルエンサーの普段の投稿フォーマットの中に、自然な形でシャンプーの使用シーンを入れ込んだことで、PR感が少なく抵抗感なく受け入れやすかった
◆事例2|健康を意識した宅食系サービス

背景:
競合と比較してSNS上でのUGC数(口コミ数)に課題あり。認知施策は実施済みのためアフィリエイトをメインで実施
施策:
・Instagramで、ターゲット層である30代前後の主婦層を多く抱えたインフルエンサーを約50名起用
・インフルエンサーのコアファン向けに、ストーリーズ+ハイライトでの訴求を行った
・商品の強みや特徴については伝えたが、投稿内容に関してはインフルエンサーに一任した
結果:
特別価格のキャンペーンも組み合わせることで月間2,000CVを達成。相性の良い顧客獲得により、定期への引き上げ率も10%増加
成功ポイント:
特別キャンペーンによりインフルエンサーの投稿ハードルが大きく下がり、想定を超える実施人数となった。成果報酬型によりコストを抑えながら実施人数を増やせたことで、相性の良いインフルエンサーの特徴や訴求の仕方が発見でき成果伸長につながった
成功した企業に共通していた3つのこと
2社の事例を振り返ると、成果を出した企業には共通点があると感じます。
《1》「日常の延長線上」にPRを置く
フォロワーが違和感を持たずに受け入れられる“自然体の導線”が最も効果的。「広告を打つ」のではなく、「推しが普段使っているものを紹介する」流れを設計することで、購買意欲の高いユーザーにスムーズに訴求できます。
《2》“再現性のある成功構造”を早期に発見し、広告運用に展開
反応率の高い投稿を広告素材として再利用することで、クリエイティブ開発コストを最小化しながら成果を拡張。PR投稿と広告配信の両輪で「認知→購買→リピート」の導線を設計できます。
《3》背景や目的が明確だった
先ほどの2社は、マーケティングにおいて現状どのような課題があり、何を目的とした施策を打つかが明確に定まっていました。これらの背景や目的を明確化していることで、関係者間でのズレが生じにくく、施策選定やクリエイティブにロジックの通った状態を作ることができました。
【まとめ】地に足のついた運用がブランドの信頼を育てる
中小企業にとって重要なのは、一度の施策での爆発的な反響ではなく、「共感」と「信頼」を少しずつ積み上げていく継続的な取り組みです。小規模なテスト施策を繰り返しながら、「刺さるポイント」を見つけていきましょう。
次回も実際に成果を上げた中小企業のリアルな成功事例を解説し、どのようなインフルエンサーマーケティング施策を行い、どのような「成功ポイント」があったのかをご紹介します。