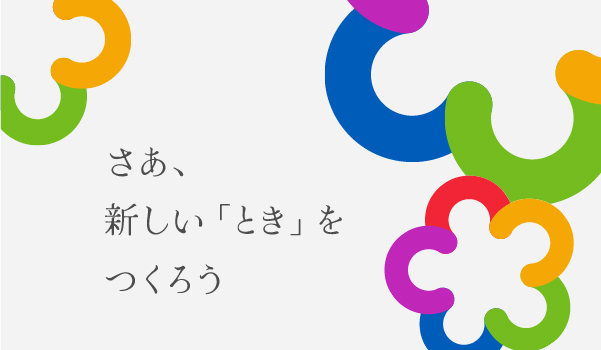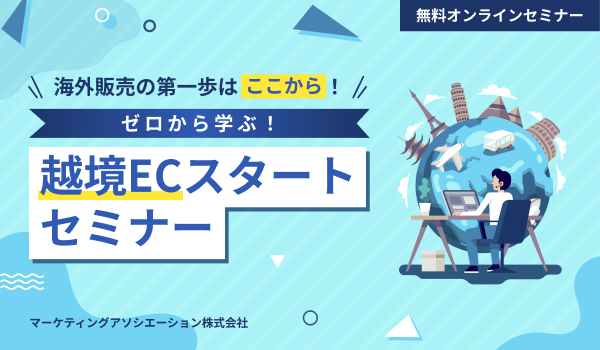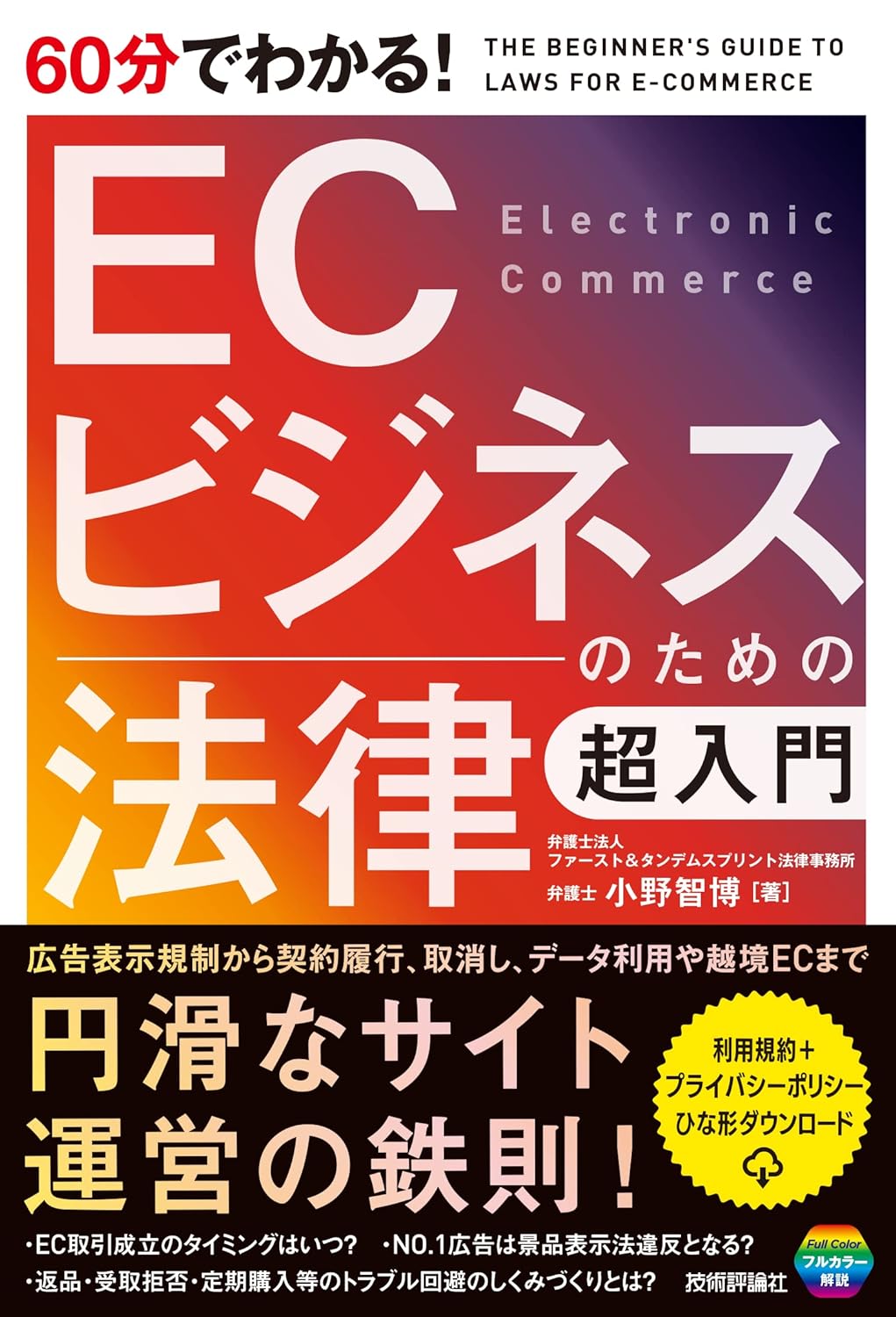SMOとは?EC集客に必要なマーケティング用語を初心者向けに解説

SMOとは、ソーシャルメディア最適化を意味し、ソーシャルメディアから自社サイトへ誘導させるためのマーケティング施策です。近年ソーシャルメディアの普及率は増えているため、ECサイトの集客においても重要で効果的な施策の一つとなっています。今回はそんなSMOの基礎知識から概要までをマーケティング初心者の方へ向けてわかりやすく解説します。
SMOとは
SMOとは、「Social Media Optimizaition」の略語で「ソーシャルメディア最適化」のことを指し、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアから自社のWEBサイトへ誘導させるためのWEBマーケティング施策です。ソーシャルメディアで話題となったコンテンツは2次3次と情報が拡散され、自然リンクを発生させる場合が多いため外部リンク獲得の手段や評判管理に繋げるための手法で活用されます。
なぜSMOは重要とされているのか
なぜSMOは重要とされているのか、それはユーザーの購買行動が関連しています。商品やサービスを購入しようとしたとき多くのユーザーがGoogleなどの検索エンジンを利用しますが、公式サイトの情報だけでなくブログやSNSなどの口コミ情報を一緒に確認する行動が当たり前となっています。公式以外の場で良質な口コミや評判が多くあればあるほどユーザーの興味関心を高めることができ、購入への後押しにつなげることができます。
逆も然り、口コミなどの情報が全くヒットしない場合や、悪い口コミばかりで溢れる場合は購入意欲を下げてしまう原因にもなりかねます。そのため、ただ自社サイトの検索順位を上げる対策だけではなく自社の商品・サービスがソーシャルメディア上でどのように評価されているかをしっかりモニタリングをし、対策をすることが非常に重要であると言えます。
また、自社サイトでは商品やサービス情報をメインに発信しますが、SNSではお役立ち情報やキャンペーン情報の発信だけでなく、直接ユーザーともコミュニケーションを取ることができるので信頼関係を築き上げファンを獲得を得ることにも繋がります。そのためより多くの集客と売上を構築するために自社サイトとソーシャルメディアの運営を同時に行うことが求められるのです。
SMO=ステルマーケティングではない
ステルスマーケティングとは、ユーザーに宣伝であると悟られないように一般ユーザーを装って商品の口コミを書いたり、芸能人にPRを依頼したりするマーケティング手法です。SMOでは口コミや評判が多くユーザーの目に触れることが大切であると先述しましたが、SMO=ステルマーケティングであるという誤解はしないようにしましょう。
意図的に口コミを増やすのではなく、自然と口コミを増やせるような対策が必要です。そのためにはユーザーにとって有益な情報を発信し続け、シェアしてもらうことがSMOにおいて非常に重要であると言えます。
SEM、SEO、リスティング広告それぞれの違いは?
SMOと関連するWEBマーケティングの用語にSEM、SEO、リスティング広告というものがあるので併せて覚えておきましょう。SEMとは、Search Engine Marketingの略語で検索エンジンマーケティングのことを指し、検索エンジンからWEBサイトやLPの訪問者を増やすためのマーケティング手法を意味します。
そしてその訪問数を増やすための手段としてSEO、リスティング広告が活用されており、SEO施策の一つにSMOが該当するという構造です。つまりSEMはSEOやリスティング広告を含むWEBマーケティング全般を意味しているのです。
SEMを構成するSEOとリスティング広告についてもう少し詳しく解説していきます。
SEOとは
SEOとは、Search Engine Optimizationの略であり、検索エンジン最適化のことを意味します。GoogleやYahooの検索エンジンで検索されたときに上位表示させ、集客数や売上を増やす目的で行います。サイト設計の見直しを行ったり、ユーザーにとって良いコンテンツを発信し続けることで検索エンジンからの評価を受け、上位に表示させる手法です。
対策から効果が出るまで3ヶ月〜1年以上かかる場合もあり中長期的な施策となりますが、広告と違い費用はかからず、上位に表示されることで継続的な売上を作り上げる仕組みを構築することが可能になることが特徴です。
リスティング広告とは
リスティング広告とは「検索連動型広告」のことを指し、GoogleやYahooなどの検索エンジンであるキーワードを検索した時に表示される広告です。すでに検索している事柄に興味がある検索ユーザーに対して広告配信するため、他のWeb広告に比べてコンバージョンの確率が高いと言われています。リスティング広告は「広告ランクによるオークション制」なので、まとまった広告費用が必要となりますが、即効性もあり特定のターゲティングに対して高い費用対効果が見込める施策であることが特徴的です。
SMO施策で大切なこと
①適切なプラットフォームを選ぶ
一言でソーシャルメディアと言ってもTwitter、Facebook、Instagram、YouTubeなど様々なプラットフォームが存在し、ユーザー属性や特徴が異なります。そのためまずは自社はどのプラットフォームと相性が良さそうかを見極め、選定することが重要です。それぞれのソーシャルメディアの特徴も併せて紹介します。
Facebookのユーザー数は世界で26億人、日本の月間アクティブユーザー数は2600万人と言われており、年齢層は40代〜50代が多いことがわかっています。多くのビジネスマンが仕事上でも活用しており、BtoB向けの情報発信と親和性が高いことが特徴です。
Twitterは月間アクティブユーザー数は世界で3億3500万人、日本国内では4,500万人を誇っており10代、20代の若年層を中心に支持されています。話題性やオリジナリティのあるツイートは広く拡散される傾向があり、マーケティングを大きく成功させられる可能性を秘めています。情報の拡散性が高く、リアルタイムで情報発信ができるので認知拡大に有効的ですが、良い情報だけでなく悪い情報も拡散されることが特徴としてあります。
Instagramのユーザー数は世界で10億人、日本国内では3,000万人を誇っておりFacebookに劣らないユーザー数で、利用率は10代〜50代の幅広い年齢層から利用されています。画像、動画がメインのプラットフォームなので自社ブランドの世界観を視覚で伝えられることが特徴的です。
YouTube
YouTubeは世界20億人、日本国内で6,500万人のユーザー数を抱えている世界最大級の動画専用プラットフォームです。なんと10代~40代すべてで利用状況は90%を超えており、幅広い年齢層から利用されています。動画の制作や登録者数を増やすにはかなりのリソースがかかりますが、YouTubeマーケティングは見込み客の拡大や企業のイメージ向上に有効的なため、マーケティングで取り入れる企業が増えています。
②シェアされるような情報を常に発信する
役立つ情報や最新の情報を発信し続けると、良いと思ってくれたユーザーがまた別のユーザーにシェアしてくれるという良い連鎖を起こしてくれます。Twitterではよく「バズる」という表現でも使われますが、話題性のある情報は一気に拡散され、テレビなどのメディアでも取り上げられることもしばしばあるので、常に質の良い情報を継続して発信することは必須です。
③キーワードのリサーチをする
ただ闇雲に情報を発信するだけでなく、自社のユーザーやターゲットとする層はどのような話題やキーワードに対して興味を持つのかを調査し、ハッシュタグと共に投稿に反映させましょう。また過去の投稿で人気があったものの調査や分析をすることでユーザーが求めている情報や話題を探ることもできるので、これまでの投稿を分析し新たな投稿へのヒントとして活用することも大切です。
④投稿のタイミングを考える
活用するプラットフォームのユーザー属性やターゲットに応じて投稿するタイミングも考慮しましょう。例えばビジネスマン向けのコンテンツであれば通勤時間にスマホをよく見る可能性が高いので朝の8時や夕方の6時に投稿をしたり、主婦向けのコンテンツであれば家事が落ち着く12時〜15時の時間を狙うなど、より多くのユーザーに見てもらうための工夫が大切です。
⑤ユーザーと積極的に交流する
ソーシャルメディアの良いところはユーザーと直接コミュニケーションが取れるということです。投稿に対してコメントしてくれたものに返したり、質問があった場合に回答することによってカスタマーサクセス的要素も含まれるので、ユーザーとの関係構築を図ることができます。
まとめ
SMOの概要から運用においてポイントとなることを解説しました。ユーザーの購買行動も常に変動している時代に併せて自社のマーケティングを行っていくことがこれからは求められます。特に今回紹介したソーシャルメディアは今後ますます発展していく可能性が大きいため、うまく活用して集客、売上を構築できる運用や仕組み作りを整えていきましょう。