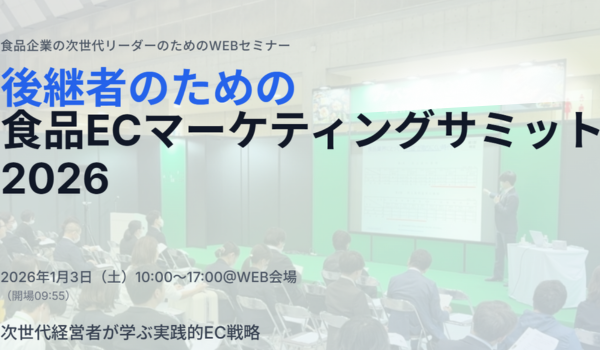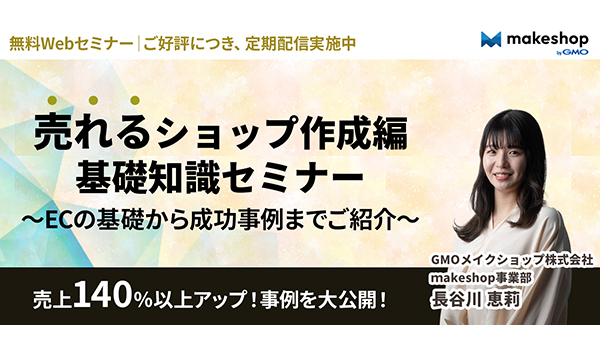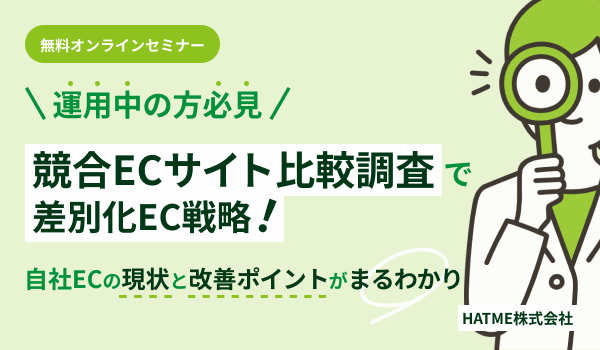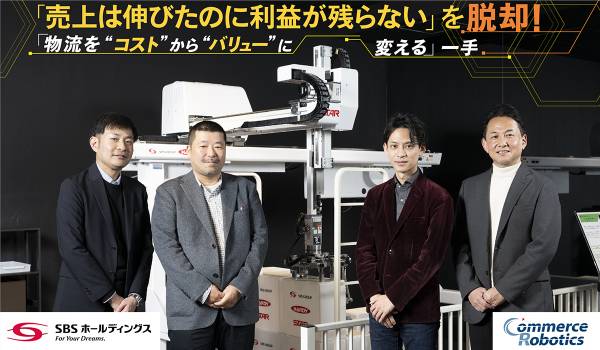販売戦略とは?代表的な手法、戦略策定に役立つフレームワークを解説

販売戦略は、商品やサービスを販売するための戦略です。市場全体の動向や自社と他社の位置づけ、顧客のニーズなどをもとに、販売指針を定めます。なお、戦略を実行した結果を振り返ることも大切です。あらかじめ設定しておいた評価指針から分析してみましょう。
販売戦略とは
販売戦略とは、自社の商品やサービスをどのように販売していくかについての戦略です。具体的には、商品の強み、ターゲットの属性、顧客のニーズなどの要素から販売戦略をたてていきます。
商品の強みとは、競合他社の商品と比較した際に優位に立てる部分です。強みにあたる部分には、価格、スペック、アフターフォローなどがあります。
ターゲットの属性とは、ビジネスを展開するうえでメインとなる顧客層です。属性には、年齢、性別、居住地などがあります。
顧客のニーズとは、顧客がどんな商品を求めているかということです。顧客のニーズは、ターゲットの属性とあわせて検討することがポイントです。たとえば、年齢層が高めの方をターゲットとする商品の場合、低価格よりも高品質や落ち着いたデザインなどがニーズとしてあげられます。
営業戦略やマーケティング戦略との違い
販売戦略は、営業戦略やマーケティング戦略と似ていますが、厳密にはすこし意味合いが異なります。
営業戦略とは、企業が営業活動を行ううえでの戦略です。最終的なゴールが売上の拡大である点は販売戦略と同様ですが、あくまでも営業活動における戦略を指します。たとえば、どのように新規顧客を開拓して商談に進めるかは営業戦略の一部ですが、販売戦略にはあたりません。
一方、マーケティング戦略は、営業戦略よりも販売戦略に近い考え方です。マーケティング戦略においては、経営目標や販促指針をもとに、どのようにマーケティングを推し進めていくべきかを検討します。販売のみに限定せず、ブランディングや企業の社会的価値などの面についても戦略を策定します。

販売戦略を立てるメリット
企業において商品やサービスを販売する際は、事前に販売戦略をたてるのが基本です。市場全体や自社・競合商品、顧客の分析をせず、やみくもに販売するのは非効率的であるうえ、一度成功を収めたとしても再現性がありません。
以下では、販売戦略を立てるメリットについて解説します。
リソースを有効活用できる
企業活動においては、限られたリソースをいかに効率よく活用できるかがポイントです。人・モノ・コスト・時間を有効活用することは、販売効率を高めることにつながります。たとえば、広告を出稿する際、適切にターゲットを絞れていないとコストばかりかかってしまい、なかなか売上につながりません。
同様に店舗ごとや業務ごとの人員配置、各種施策への時間投下などの面からもリソースを管理するとよいでしょう。
適切な効果測定ができる
施策の効果を測定するには、前もって前提条件や施策の内容を固めておく必要があります。具体的な部分がつめられていない状態で施策を講じても、なぜ成功・失敗したのか、次回以降はどう改善すべきかがわかりません。
一方、販売戦略にもとづいて実行した施策は、いつ誰に対してどんな方法でアプローチしたのかが明確化されています。そのため、ターゲット設定、アプローチ方法、訴求の方向性のそれぞれについて適切に効果を測定できます。
また、適切に効果測定ができる状態を整えることによって、スピーディーなPDCAの実現も可能です。PDCAは一度で終わるものではなく、日々改善を繰り返してよりよい効果を発揮していくため、スピード感も重要なポイントです。
販売戦略のテンプレート
販売戦略の重要性がわかっていても、実際にどのように戦略を策定していくべきかわからない方も多いのではないでしょうか。販売戦略には、基本的な考え方をまとめたテンプレートがあります。ランチェスター戦略やニッチ化戦略などは、販売戦略の代表例です。
そのため、はじめはテンプレート化されている販売戦略をもとに、自社の戦略を検討してみるのがおすすめです。
以下では、代表的な販売戦略について解説します。
ランチェスター戦略
ランチェスター戦略とは、自社にとって有利な戦局をつくりだす戦略です。もともと戦争理論として用いられており、企業どうしの競争においても同様の考え方が有効です。
ランチェスター戦略は幅広い内容を含むため、一言で説明することはできませんが、概要としては自社の強みを活かせる分野に特化することを指します。たとえば、資本力に差のある大企業と中小企業では、多くの場において前者の方が有利です。
しかし、中小企業ならではの強みを活かせる分野で勝負すれば、後者にも勝ち目があります。この「弱者逆転」の考え方もランチェスター戦略のうちの一つです。
ニッチ化戦略
ニッチ化戦略とは、競合他社の手が及んでいない分野に展開する戦略です。一般的にはニーズの多い分野に展開した方がより多くの見込み顧客を獲得できますが、その分競合他社も多く、競争も激しくなります。
一方、ニッチな分野においては見込み顧客は少ないものの、競合他社も少ない分、競争に巻き込まれずに多くのシェアを獲得できます。そのため、一定の利益を確保しやすい点がメリットです。
コストリーダーシップ戦略
コストリーダーシップ戦略とは、競合他社に対して価格で差別化を図る戦略です。価格の面で優位性をとることからコストリーダーシップと名づけられています。具体的な手法としては、物流コストや人件費の削減、大量仕入れによるディスカウント、DtoCによる直接販売などがあります。
ECの普及によって、スマートフォン一つで商品価格を比較できるようになった現代において、コストリーダーシップ戦略は非常に効果的です。一方、原価率と利益率のバランスを保てなくなってしまうと、将来的な経営悪化につながるリスクもはらんでいます。
サンドイッチ戦略
サンドイッチ戦略とは、特定の商品・サービスを売れやすくするための戦略です。具体的には、松竹梅のように3つ以上のグレードを設けて、もっとも販売したい商品を竹の位置(中間)にすえます。
サンドイッチ戦略では、複数のグレードがある場合、中間のグレードを選びやすくなる消費者心理を活用しています。中間グレードに利益率の高い商品、高品質でリピートされやすい商品などを置けば、利益向上やブランディングに役立てられるでしょう。
バンドル戦略
バンドル戦略とは、複数の商品をセットにして販売する戦略です。飲食業界ではフードとドリンクをセットにしたり、アパレル業界ではセットアップで販売したりする方法があります。バンドル戦略では、割引が適用されるお得感によって、顧客の購入を後押しします。
一方、企業側も利益率の高い商品と低い商品を組み合わせたり、クロスセルにつなげたりと、さまざまなメリットを得ることが可能です。ただし、消費者の欲しがる商品と欲しがらない商品を不当にセット化する「抱き合わせ販売」は違法とされているため、注意すべきです。
販売戦略の立て方
販売戦略を立てる際は、現状の課題や問題を把握したうえで、目標や評価指標を設定していくことが大切です。戦略策定のプロセスは、適切なアプローチを考えるだけでなく、目標や評価の指標を設定するうえでも重要です。
以下では、販売戦略を立てるプロセスについて解説します。
現状を調査する
戦略を立てる際には、現状の課題や問題を洗い出す必要がありますが、はじめに現状を整理すべきです。いきなり課題や問題を出そうとしても表層化しているものしかあがらず、時間が経つにつれて新たな課題・問題が明らかになるケースがあります。
現状を整理するうえでチェックしたいポイントは、市場の動向、自社の商品やサービス、顧客のニーズの3つです。
課題や問題を明確化する
現状を正確に把握できたら、自社の抱える課題や問題を明確化します。たとえば、利益率の低さ、リピート率の低さ、差別化要因の不足などです。自社における課題や問題は、市場全体や競合他社と比較すると、よりわかりやすくなります。
また、顧客アンケートや他部署へのヒアリングを実施するのも効果的です。顧客アンケートではニーズに応えられていない部分、他部署へのヒアリングでは特定の部署が抱える課題を知ることができます。
目標・評価指標を設定する
販売戦略を立てたあとは必ず目標、目標に対する評価指標を設定します。はじめに長期的なゴールを設定したうえで、ゴールを達成するために必要な要素を決めます。たとえば、KGIを年商1億円とした場合、年商1億円を達成するにはどんなKPIをたてられるかということです。
販売戦略においては、利益率、月間売上、リピーター率などの要素がKPIとしてあげられます。
パワーポイントや資料にまとめる
目標・評価指標まで固められたら販売戦略の策定は完了です。最後にパワーポイントや資料にまとめて関係各所に共有します。策定後のドキュメント化と共有は、非常に重要なフェーズです。
戦略は実行後の効果測定をしてこそ意味がありますが、ドキュメント化ができていないと存在自体忘れられてしまうおそれがあります。また、戦略や目標が共有できていなければ、メンバーや部署ごとに異なるビジョンをもって業務にあたることになってしまいます。

販売戦略に役立つフレームワーク
前述のとおり、販売戦略を立てる際は、現状の課題や問題を把握することが不可欠です。しかし、課題や問題の中には表層化しておらず、メンバーさえ気付けていないものもあります。そのため、さまざまな分析手法を駆使して、課題を洗い出せるとよいでしょう。
以下では、販売戦略の策定に役立つフレームワークについて紹介します。
PEST分析
PEST分析とは、自社を中心とする外的要因を分析するフレームワークです。PESTは、以下の頭文字をとったものです。
● Politics(政治)
● Economy(経済)
● Society(社会)
● Technology(技術)
外的要因は自社のみでコントロールできる部分ではありませんが、ビジネスにおいて外的要因を無視することはできません。自社がどんな状況に置かれていて、外的要因をどう活用できるかを検討しましょう。
STP分析
STP分析とは、自社の位置づけとターゲティングに特化したフレームワークです。STPは、以下の頭文字をとったものです。
● Segmentation(セグメント化)
● Targeting(ターゲット設定)
● Positioning(立ち位置)
セグメント化によって年齢・性別・居住地をはじめとする顧客属性を分析して、アプローチすべきターゲットを設定します。さらに、業界内における自社の立ち位置を把握しておくことも大切です。
どうすれば競合他社に対してアドバンテージをとれるかを検討してみましょう。
SWOT分析
SWOT分析とは、内部・外部の強みと弱みを分析するフレームワークです。SWOTは、以下の頭文字をとったものです。
● Strength(強み)
● Weakness(弱み)
● Opportunity(機会)
● Threat(脅威)
SWOT分析では、弱みをつぶして強みを活かす戦略を策定できます。内外の要因をもとに分析できるため、さまざまな角度から戦略を立てられる点がメリットです。
AIDMAの法則
AIDMAの法則とは、商品の認知から購入に至るまでを分析するフレームワークです。AIDMAは、以下の頭文字をとったものです。
● Attention(認知)
● Interest(興味・関心)
● Desire(欲求)
● Memory(記憶)
● Action(行動)
AIDMAの法則は、見込み顧客をフェーズごとにセグメント化する際に役立ちます。フェーズごとに最適化した戦略を立てられるため、より精緻なマーケティングにつながるでしょう。
AISASの法則
AISASの法則とは、デジタル時代における購入プロセスを分析するフレームワークです。AISASは、以下の頭文字をとったものです。
● Attention(認知)
● Interest(興味・関心)
● Search(検索)
● Action(行動)
● Share(共有)
AISASの法則は、消費行動の前後に「検索」と「共有」のフェーズが設けられており、検索エンジンやECサイト、SNSなどを活用した購買プロセスを示しています。コンテンツマーケティングや口コミマーケティングをはじめとする戦略においてよく用いられます。
VRIO分析
VRIO分析とは、内部リソースを分析するフレームワークです。VRIOは、以下の頭文字をとったものです。
● Value(経済的価値)
● Rareness(希少性)
● Imitability(模倣可能性)
● Organization(組織)
内部リソースのみに着目する指標であるため、VRIO分析だけですべての課題を発見することはできませんが、内的な課題を洗い出す際に向いています。
ペルソナ分析
ペルソナ分析とは、ターゲティングに特化したフレームワークです。ペルソナとは、商品やサービスの訴求をする対象となる顧客像を指します。一般的なターゲティングにおいては、ある程度の年齢層や性別をざっくり指定しますが、ペルソナの場合は細かな属性までを設定します。
カスタマージャーニーマップ
カスタマージャーニーマップとは、顧客の購買プロセスを分析するフレームワークです。AIDMAやAISASと似ていますが、カスタマージャーニーマップではさらに細分化して時系列ごとに図式化します。
近年では、購入プロセスやチャネルの多様化によって、AIDMAやAISASなどの画一的なモデルで示すことが難しくなっています。そのため、ペルソナを細かく設定して、カスタマージャーニーマップで可視化する方法がおすすめです。
EC運営のお困りごとの無料ご相談はこちらから
ECのミカタでは、販売戦略立案などのECコンサルティングや運営代行などをはじめ、ECサイト運営に関する外注先を無料でご紹介しております。何かお困りのことや、ECサイトを運営していく上で効率化されたいことなどがございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
専門のコンシェルジュがヒアリングをさせていただいた上で、ご希望の条件に合う会社様を募集、効率良く自社にマッチした会社様をご紹介できます。ぜひご活用下さい。