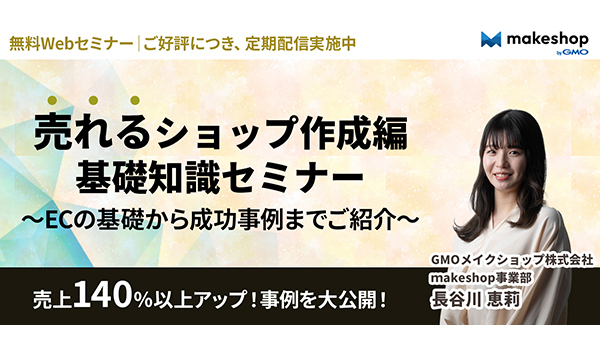【購入率を下げない】ECサイトの送料の決め方と安く抑える方法とは?
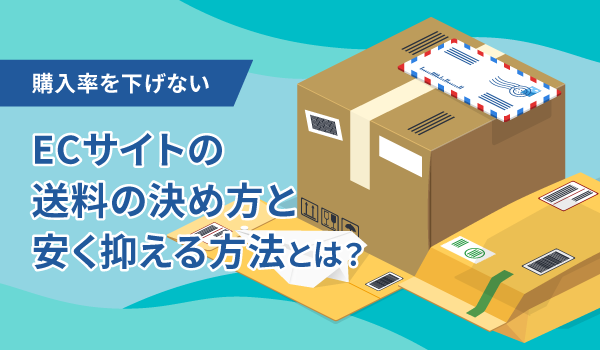
ECサイト運営者を悩ます送料設定の課題。送料の値段次第では、購買率までも下げかねない重要な問題ですよね。今回は、そんな送料の適切な決め方と安く抑えるコツやポイントを分かりやすく解説していきます。
目次
EC運営のパートナー企業を紹介してもらえるって本当?
ECサイトの送料設定にはどんなパターンがあるの?
ECサイトの送料をどのように設定すればいいのか悩んでいる方も多いはず。まずはじめに、どのような設定方法があるのか、送料設定のパターンをご紹介します。
配送地域ごとに設定
地域ごとに細かく配送料金を分ける設定です。地域で分けることで、消費者から見ても納得いく送料で商品を購入してもらいやすくなります。ここで気をつけることは、配送拠点から遠い地域に届ける場合、送料が高額になるケースもあるため、受注に地域差が出てしまう傾向があります。
全国一律に設定
どの地域に配送しても送料を全国一律とするパターン。消費者も理解しやすく、事業者も地域ごとに送料を調べる必要がないことがメリットです。しかし、配送場所が遠くなると送料が高くなり、事業者の負担が大きくなるため、スタート時の設定金額をどうするかが課題となります。あまりに高額な金額で送料を全国一律にしてしまえば、購入率を下げることにもなりかねません。
商品ごとに設定
商品によって送料を設定する方法です。自社の商品の場合、他社から仕入れた商品を販売する場合など、様々な組み合わせで送料を自由に設定できます。しかし、消費者側から見れば複雑で分かりにくく、事業者側も発送管理に注意が必要になってくることがデメリットです。
発送手段別に設定
配送方法には様々な種類があり、メール便のようにサイズや重さによって全国一律で配送してくれるサービスもあります。メール便や宅配便など、どのような形で発送するのかによって値段も大きく変わってきますので、自社の商品に合った発送手段を選びましょう。
一定金額以上で送料無料
例えば、「5,000円以上で送料無料」などといった送料バーを上回った場合に、送料無料を適用するという方法です。このパターンは、平均客単価を上げることができるというメリットがあります。デメリットは、北海道や離島などの遠方地域に配送する場合や、送料無料の設定金額に達しない顧客への対応はどうするかという点です。遠方の場合は、上記の設定に送料を上乗せする形で対応している事業者が多い傾向にあります。また、設定金額に達しない場合に関しては、お得感が感じにくく、購入に至らないケースが多いようです。
全品送料無料
消費者にとって最も分かりやすく、サイトからの離脱率を下げるのが送料無料のパターンです。商品代以外のお金を支払う必要がなく、決済までスムーズに商品購入が行われやすいというメリットがあります。しかし、ここで注意しなければならないのは、商品の価格。事業者が送料を負担しなければならないため、利益を圧迫しない価格設定が必要となります。
ECサイトの送料を決める上で重要な3つのポイント
ここまで、送料設定のそれぞれのパターンについて解説してきました。続いては、ECサイトの送料を決める上での大切なポイント3つをご紹介いたします。
利益率を軸に設定する
利益率は、自社が取り扱う商品の価格と配送業者に支払う金額によって利益率を算出します。どんな商品がどのような組み合わせで購入されるのか、サイズや重量を含めた配送料の概算から送料設定を行いましょう。また、ここで配送料のコスト削減できれば、利益率のアップや送料無料を実施することが可能です。
消費者が納得する送料ラインを見つける
消費者の立場に立って、どの程度の送料であれば購入の妨げにならないのか、というボーダーラインを抑えておきましょう。自社の利益だけを考えて送料設定を行えば、1円でも安い競合他社へと消費者が離れていってしまうことも考えられます。例えば、最も安い定形外郵便は、追跡サービスがないため、商品を紛失した際の保証がありません。万が一のことを考え、消費者が安心して商品を購入できる配送サービスを選定し、送料を決定することも必要です。
競合他社の相場を知る
同じ商品を取り扱う競合他社の相場をリサーチすることで、送料が決めやすくなります。ECサイトの送料は、他社と比較されやすい傾向にあるため、1円でも安く送料を決定したいところですが、適正価格を見極めた上で、自社の利益が十分に確保できる金額を設定しましょう。
ECサイトの送料を安く抑える方法やコツを解説
できる限り送料を安く抑えたいというのが事業者側の悩みですよね。
続いては、配送料を安く抑える方法やコツについて解説していきます。
梱包コストの削減
安価な梱包資材を使うことはもちろんですが、今使用している梱包資材が、自社が取り扱う商品のサイズに合っているのか見直してみましょう。ご存知の通り、配達業者はサイズや重さを計測して料金を決定するため、商品に対して大きいサイズの梱包資材を使用すると、無駄に送料がかかってしまいます。
また、チラシなどを同封している場合は、それがどれくらの宣伝効果を発揮しているのか、費用対効果を分析しているでしょうか?本当に必要なコストなのか、利用目的を明確にすることが大切です。さらに、梱包資材だけでなく、梱包にかかる作業も簡略化できるところがないか調査することもおすすめです。なるべく余計な工数をかけず、効率的に発送できる工夫を行いましょう。
配送会社と法人契約
一定の量を依頼できるのであれば、配達業者と法人契約を検討してみましょう。また、既に法人契約を行っている場合でも、取り扱う商品の売上規模や出荷数の予測を交渉材料に、値下げ交渉してみることもおすすめです。規模が小さい場合でも、今後どのくらいの出荷数が見込めるのかを交渉材料にすることで、良い条件で契約できる可能性もあります。
商品に合った配送方法を選ぶ
ECサイトが激化している今、配送業者や配送手段はいろいろあります。配達業者の比較を行い、サービスに対する価格をかんがみて検討してみましょう。サービスは金額だけでは判断できない部分でもありますし、消費者に信頼感を与える重要なポイントです。ECサイト向けの安い配達業者もありますので、商品によって配達業者を使い分けることも選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
大手3社!ECサイトで利用する宅配業者を比較
ここまで、送料のパターンや送料を安く抑えるポイントについてご紹介してきましたが、では「どのような宅配業者がいいのか」疑問になりますよね。続いては、宅配業者大手3社の特徴を解説していきます。自社の商品に合ったサービスなのかを参考にしてみてください。
日本郵政
日本郵政は、営業拠点数が他の宅配業者に比べて圧倒的に多いのが特徴で、最近ではLINEで配送状況を受け取ることができます。また、小型郵便サービスの種類が豊富で、「スマートレター」の配送料は全国一律180円です。
ヤマト運輸
ヤマト運輸は、様々な宅配サービスを提供しているのが特徴です。生鮮食品を配送する「クール宅急便」や専用資材を使用して精密機器を配送する「パソコン宅急便」など多彩なサービスが魅力です。また、小さいサイズの荷物をポスト投函できる「ネコポス」サービスが開始されてからは、ECサイト事業者からの需要が高まっています。
佐川急便
佐川急便は、60サイズの配達料金が他社より安く、個人や小規模でECサイトを運営している事業者から選ばれているのが特徴です。また、2021年からコロナ渦のニーズをいち早く取り入れて、個人宅以外でも「非対面・非接触配達サービス」を実施しています。
まとめ
いかがでしたか?自社に合った送料設定を見つけることはできたでしょうか?
それぞれのメリット・デメリットを知った上で、送料無料だけにこだわらず、自社の利益とのバランスを見ながら送料を決めることが大切です。送料だけでなく、同時に他でコスト削減に繋がるところはないか考えながら、効率よくECサイトを運営していきましょう。