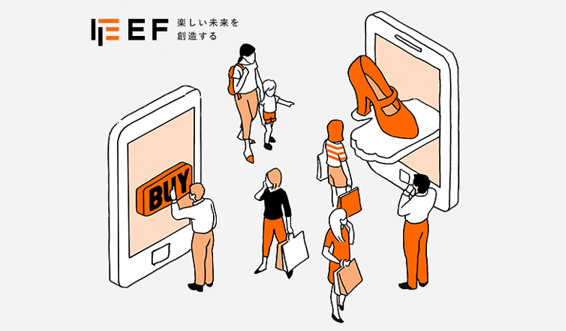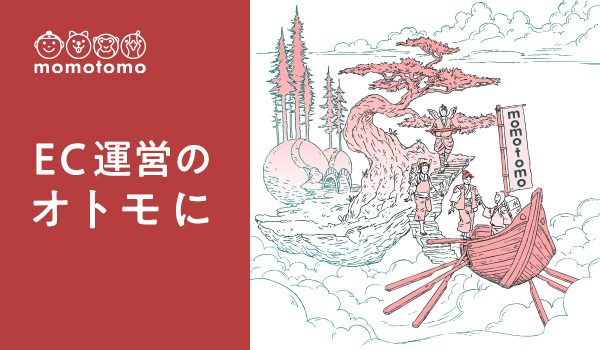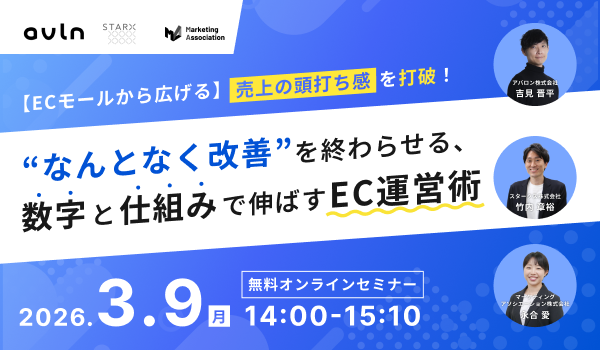外部倉庫(委託倉庫)とは?料金相場や選び方について解説
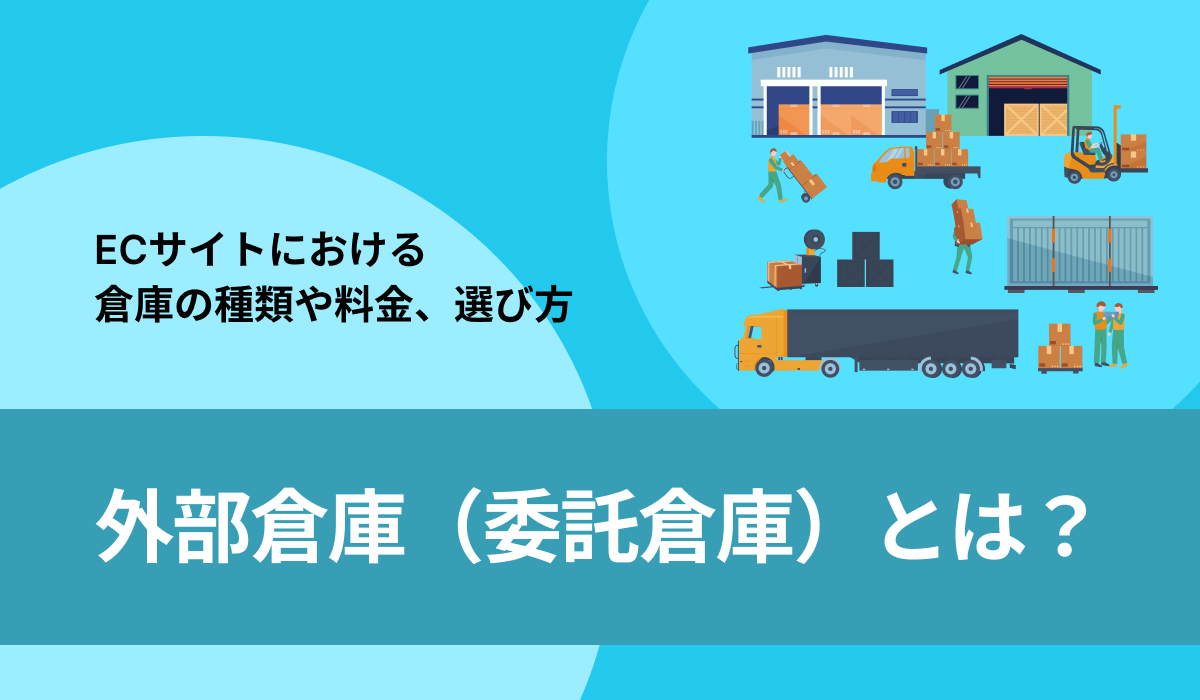
運営するECサイトが一定規模を超えてくると、外部倉庫(委託倉庫)を活用するメリットが大きくなります。
この記事では、これから外部倉庫を使って物流の効率化を図ろうとしている方に向けて、外部倉庫選びで押さえておきたいポイントをまとめました。
一般的な外部倉庫とは
まずは、「外部倉庫」の定義を整理します。
外部倉庫といえば、一般的には、物流業者や倉庫業者が所有する「自社倉庫以外の倉庫」を指します。場合によっては、不動産事業者から賃借して利用する倉庫も外部倉庫と呼ぶことがあります。
この意味の外部倉庫は、自社倉庫がない場合や、自社倉庫に物を置ききれない場合に利用されます。そして、その主な役割(機能)は「保管」です。

EC業界における外部倉庫(委託倉庫)とは?
EC業界では「保管」だけでなく、「商品管理」「梱包」「配送」などの役割を持つ倉庫を指して、外部倉庫と呼びます。
外部倉庫(委託倉庫)を使うことは、すなわち外部の専門業者に物流業務を委託することを意味することがあるというわけです。
外部倉庫(委託倉庫)の種類
EC業界では物流業務を委託する外部倉庫が細分化されており、それぞれにメリット・デメリットがあります。
以下は、EC業界で使われる外部倉庫の種類をまとめた表です。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている事業者 |
|---|---|---|---|---|
| 販売主体型倉庫 | モールの販売サービスを向上させるための倉庫(「フルフィルメント by Amazon」「楽天スーパーロジスティクス」など) | コストパフォーマンスの高さ。販売主体型倉庫と同レベルの環境を整える場合、かなりの額を投資しなければならない。 | ルールが厳密に決まっているため、カスタマイズできないこと。 | モールに出店していて在庫の回転が早いEC事業者 |
| アナログ倉庫 | スペースの貸し出し、人材手配がメインで、システム導入などは荷主側で対応する倉庫 | 自由度が高いこと。 | 自由度の高さゆえ、スペースと人材以外は自社で手配しないといけないこと。 | 物流に関してのノウハウがあり、明確に流れや業務イメージが固まっている、メーカーや卸などの事業者 |
| 専門業種特化型倉庫 | その業種の流通加工に対応している倉庫 | 自社で必要な機械をそろえるよりも、圧倒的にコストを抑えられること。 | 在庫管理がネット通販型倉庫ほど得意ではないケースもあること。 | その業種の事業者 |
| 倉庫サービス主体のネット連携型倉庫 | 物流倉庫が主体となって展開するEC物流サービス | 自社が求める倉庫にカスタマイズしていけること。 | 要望が多いほどコストがかさんでいくこと。 | 規模が大きく予算があるEC事業者 |
| システム会社主体のネット連携型倉庫 | 物流のシステム会社が物流倉庫と提携して提供する倉庫サービス | システム化されているため、安価に利用できること。 | 物流会社とは直接打ち合わせをしない場合は、運用がスタートしてからトラブルが発生するかもしれないこと。 | システムのルールに沿って運用できる、物流業務がシンプルなEC事業者 |
| ネット通販型倉庫 | 品種数やロット数関係なく利用できる、ECと相性がいい倉庫 | 在庫はWMSなどシステムで管理するので、在庫管理が正確なこと。 | システムでルールを明確に決めて運用している場合はイレギュラーな要望が受けられないこと。 | 在庫誤差が発生しない管理をしているため、多品種小ロットや仕入れ先が複数あるEC事業者 |
外部倉庫(委託倉庫)と自社倉庫(自社物流)の違い
外部倉庫(委託倉庫)と自社倉庫(自社物流)の違いはいくつかあります。以下に主な違いをまとめました。
| 自社倉庫 | 外部倉庫 | |
|---|---|---|
| 所有・管理 | 自ら倉庫を所有・運営し、在庫管理や物流プロセスを自社で管理。 | 物流業者や倉庫業者が所有・運営する倉庫を利用し、在庫管理や物流プロセスの一部をアウトソース。 |
| コスト | 倉庫のロケーション選定、建設(購入し所有する場合)、WMS(在庫管理システム)導入などの初期費用や、維持費や保管費、人件費など。 | 利用料(保管費や入出庫料)やサービス費用(その他付随業務などで発生した費用)など。 |
| 柔軟性・拡張性 | 施設やリソースの拡張には時間と資金がかかり、かつ移動や解約がしづらい。土地を購入し専用の倉庫を建築した場合は、事業縮小のリスクも大きい。 | 需要の変動に柔軟に対応でき、必要に応じて増床や縮小、拠点拡大が可能。 |
| 専門知識 | 内部で専門知識を取得・ノウハウを構築。うまくいけば他社と差別化が可能。 | 物流や在庫管理において専門的な知識や最新技術を習得せずに活用可能。 |
| リスク | すべてのリスクや責任が自社に帰属。 | 倉庫業者が運営するため、一部のリスクを回避。ただし、適切な契約やコミュニケーションが必要。 |
外部倉庫(委託倉庫)と自社倉庫(自社物流)、それぞれのメリット・強みは?
「規模が大きくなれば外部倉庫に委託すべき」というわけではなく、自社倉庫にもメリットがあります。そのため、違いを明確に理解し、その上で意思決定をすることが大切です。
ここで、外部倉庫と自社倉庫、それぞれのメリット・強みを整理しましょう。
外部倉庫(委託倉庫)のメリット
主なメリットは、以下の3つです。
- 他社技術・ノウハウの活用
- 拡大・縮小の柔軟性
- リスク低減
他社技術・ノウハウの活用
外部倉庫では、物流や在庫管理業務に注力できるため、最新の物流技術を取り入れていたり運用を重ねて高度なノウハウを構築していたりします。また、近年はロボットを導入する倉庫も増えており、自動化による効率化も進んでいます。
そのため、自社に技術やノウハウがない場合、単なる物流倉庫以上の価値を得ることができます。それと同時に、自社のリソースをほかの販売戦略や経営などに集中させられるようになります。
拡大・縮小の柔軟性
契約内容によりますが、利用規模を柔軟に変更できるため、ビジネスの変化に伴って倉庫スペースやサービスをスケールアップ・スケールダウンできます。
また、固定コストを変動コストに変換できるため、コスト管理や税務・会計面でのメリットも享受できます。
リスク低減
倉庫の運営や物流プロセスのリスクが外部に委託されるため、企業が直面するリスクが一部軽減されます。
物流や在庫管理においては多くのリスクがあるため、それが部分的であっても、得られるメリットは大きいでしょう。
自社倉庫(自社物流)のメリット
- 直接管理
- 顧客サービスのカスタマイズ
- 長期的な投資
直接管理
倉庫や物流プロセスを自社で直接管理できるため、業務の透明性が担保され、戦略的な意思決定や急な変更に対してスピード感を持って現場に反映させることができます。
また、外部との意思疎通が不要なので、齟齬やコミュニケーションコストもなくすことができます。
顧客サービスのカスタマイズ
自社で物流を管理することで、顧客に対してカスタマイズされたサービスを提供しやすくなります。外部に委託した場合、会社によっては規格が厳密に決まっており、それができません。
専門業種特化の倉庫もありますが、特殊な商材を扱う場合は自社倉庫を選ぶケースも多くなるでしょう。
長期的な投資
自社倉庫の建設や設備の導入は初期にはコストがかかりますが、投資の観点ではメリットもあります。長期的にリターンを得られる運用であれば、十分に検討の余地があるといえます。
また、自社にノウハウを溜めることができる点も、ある意味では投資です。実際、自社倉庫で物流プロセスの効率を高め、競合優位性を築いている事業者もあります。

委託できる業務内容の範囲:物流倉庫の具体的な役割
外部に委託できる物流倉庫業務には、以下のような業務があります。
- 入庫業務
- 保管業務
- 出荷業務
- 在庫管理業務
- 返品業務
各業務について、詳しくは「物流代行(アウトソーシング)とは?メリット・デメリットや費用相場について解説」の記事で解説しています。
委託する会社やサービスにより範囲はことなりますが、基本的には、ECサイトの物流に関わる業務すべてを委託することが可能です。
どこまでを委託するか、社内の方針と照らし合わせて検討するとよいでしょう。
物流倉庫委託のデメリットと賢い回避策
物流のアウトソーシングは、業務効率化やコスト削減という大きなメリットがある一方で、運用方法を誤ると深刻なデメリットを招くリスクがあります。ここでは主な3つのデメリットと、それを回避するための賢い対策を解説します。
1. 業務のブラックボックス化とノウハウの空洞化
【デメリット】 委託先に業務を「丸投げ」してしまうと、社内から「商品の保管状況」や「出荷手順」を把握している人間がいなくなります。これにより、トラブル発生時に原因究明ができなくなったり、将来的に委託先を変更したり自社運営に戻すことが困難になります。
【賢い回避策】
定例ミーティングの実施:月に一度は運用報告会を開き、現場の課題を共有する。
WMS(倉庫管理システム)の共有:クラウド型WMSを導入し、社内PCからリアルタイムで在庫状況や作業進捗を確認できる環境を整える。
2. 柔軟性の低下とイレギュラー対応の難しさ
【デメリット】 自社倉庫なら「今すぐこれを出荷して!」と声を掛ければ済むことも、委託倉庫では所定の手続きや締め切り時間を厳守する必要があります。また、急なギフト対応や検品項目の追加などは、契約外作業として断られるか、高額な追加料金が発生する場合があります。
【賢い回避策】
SLA(サービスレベル合意書)の締結:契約時に「どこまでのイレギュラーに対応するか」「緊急時の連絡ルート」を文書化しておく。
標準化とオプションの整理:基本業務はマニュアル化して安価に抑え、イレギュラー対応は事前に単価を取り決めておく。
3. 顧客接点(配送品質)のコントロール不足
【デメリット】 梱包の丁寧さや同梱物の入れ方など、ブランドが大切にしたい「開封体験(Unboxing Experience)」が、作業員のスキルや倉庫の方針によってバラつく恐れがあります。
【賢い回避策】
具体的な作業指示書(仕様書)の作成:写真付きの梱包マニュアルを作成し、感覚ではなくルールで品質を担保する。
現場視察とテスト注文:定期的に倉庫を訪問するほか、自社サイトで実際に商品を購入(テストバイ)し、顧客として届いた荷物の状態をチェックする。
外部倉庫(物流倉庫委託)にかかる費用相場と見積もり依頼のポイント
外部倉庫でかかる費用について、大きく「固定費」と「変動費」に分かれます。見積もりを取る際は、総額だけでなく、どの項目がどのように課金されるか(内訳)を詳細に把握することが重要です。
6つの主要コスト項目と費用相場
一般的なEC物流における費用項目の内訳と、関東圏を中心とした標準的な相場は以下の通りです。 項目,分類,相場(目安),解説 1. 初期費用,一時金,"0円〜50,000円",アカウント開設やデータ連携設定費。無料の業者も増えています。 2. システム利用料,固定費,"10,000円〜50,000円/月",WMS(倉庫管理システム)の利用料。 3. 保管料,固定/変動,"4,000〜6,000円/坪(または10〜30円/個)",スペース貸し(坪単価)か、商品数に応じた従量課金(個建て)か確認が必要。 4. 入庫・荷役料,変動費,入庫:10〜30円/個出荷:150〜300円/件,商品の棚入れや、注文ごとのピッキング・梱包作業費。 5. 配送料,変動費,500〜700円/件,60サイズ(関東→関東)の法人契約運賃目安。物流費の最大比重を占めます。 6. 流通加工費,変動費,30〜100円/件,チラシ同梱、ラッピング、タグ付けなどのオプション費用。| 項目 | 分類 | 相場(目安) | 解説 |
|---|---|---|---|
| 1. 初期費用 | 一時金 | 0円〜50,000円 | アカウント開設やデータ連携設定費。無料の業者も増えています。 |
| 2. システム利用料 | 固定費 | 10,000円〜50,000円/月 | WMS(倉庫管理システム)の利用料。 |
| 3. 保管料 | 固定/変動 | 4,000〜6,000円/坪 (または10〜30円/個) | スペース貸し(坪単価)か、商品数に応じた従量課金(個建て)か確認が必要。 |
| 4. 入庫・荷役料 | 変動費 | 入庫:10〜30円/個 出荷:150〜300円/件 | 商品の棚入れや、注文ごとのピッキング・梱包作業費。 |
| 5. 配送料 | 変動費 | 500〜700円/件 | 60サイズ(関東→関東)の法人契約運賃目安。物流費の最大比重を占めます。 |
| 6. 流通加工費 | 変動費 | 30〜100円/件 | チラシ同梱、ラッピング、タグ付けなどのオプション費用。 |
費用については、以下の記事で詳しく解説しています。
失敗しない見積もり依頼のポイント
見積もり額は、倉庫側の「空き状況」や「得意な商材」によって大きく変動します。適正価格を引き出すためには、以下の3点を準備して依頼しましょう。 1.前提条件の数値化(RFPの作成) 「だいたいこれくらい」ではなく、「SKU数」「月間出荷件数」「商品のサイズ(3辺合計)」「保管ボリューム(パレット数や段ボール数)」を具体的な数値で伝えます。この情報が曖昧だと、倉庫側はリスクを見込んで高めの見積もりを出さざるを得ません。 2.「個建て」か「坪貸し」かのシミュレーション スタートアップ期は、在庫が減れば費用も減る「個建て(保管料変動型)」が有利です。一方、在庫量が常に一定以上ある場合は、「坪貸し(場所代固定)」の方が単価を抑えられるケースがあります。両方のパターンで見積もりを依頼し、損益分岐点を確認しましょう。 3.燃料サーチャージと更新料の確認 配送料に含まれる「燃料サーチャージ」や、契約更新時の手数料など、見積書に記載されない隠れコストがないか必ず確認してください。外部倉庫(委託倉庫)の選び方
外部倉庫を探す際は、どこに着目すべきなのでしょうか。また、選ぶ際の注意点はあるのでしょうか。
ここで、外部倉庫を探すときに押さえておくべきポイントを整理します。
ロケーション
どこにある倉庫を選ぶかによって、差がでてきます。
最も影響が大きいのは、コストでしょう。費用の章で紹介した通り、倉庫は位置によって料金が違います。物流が活発な首都圏のベイエリアは、需要が集中するぶん料金が高くなります。
物流の効率化を優先するのかコストを優先するのか、自社の状況にあわせてロケーションを決定しましょう。
契約する敷地面積
物量を把握し、それを賄うために必要な敷地面積を把握する必要があります。契約する敷地面積(坪数)が大きすぎれば無駄が発生し、小さすぎれば契約変更などのコストが発生します。
もちろん、物量に応じて自動で対応してくれる外部倉庫も多いですが、契約先によっては自社で把握する必要があることを押さえておきましょう。
料金形態
外部倉庫に委託する業務内容にもよりますが、どのような形で課金されるのか確認しておくことも大切です。
例えば、坪契約と体積あたりの契約があった場合、坪であれば、積み上げられる物量を管理・コントロールしなければ無駄なコストが発生する可能性があります。
料金形態は多様なので、数パターンの試算をして、適切な外部倉庫を選びましょう。
物流ノウハウ・システム
委託したい商品の取り扱い経験の有無など、自社の期待に添えるノウハウを持つかどうか確認する必要があります。
また、物流や在庫管理のシステムを導入できているかどうかも重要です。システムの有無で効率やコストが変わります。そのシステムの使いやすさもポイントで、自社との連携面でストレスがないかどうかもチェックしましょう。
探すときは、複数の会社を比較する
外部倉庫を探すときのポイントは、「比較すること」に尽きます。見比べなければ、どこが自社に合うかわからないからです。
時間やコストはかかりますが、実際に見積書を取得したり現地に足を運んだりして、複数の外部倉庫を比較してみましょう。違いがみえてきて、きっと自社に合う外部倉庫を見つけることができます。

ECのミカタなら自社に合った外部倉庫(委託倉庫)が見つかる◎
自社に合った外部倉庫や委託先を見つけるには、複数の会社比較が大切です。
とはいえ、外部倉庫の事業者は多く、サービス内容や倉庫の種類などを都度調べて探すのは大変ですよね。
ECのミカタに相談すれば、自社の状況や希望に合った委託先を紹介してもらえます。
EC運営のプロであるコンシェルジュが、状況のヒヤリングから事業者の紹介まで徹底的にサポートしてくれるので、初めての外部倉庫探しでも安心です。
また、ECのミカタで受けられるサポートはすべて無料。紹介された事業者候補の中からどこを選べばよいか迷っている場合も、コンシェルジュに相談すればアドバイスをくれます。
ECのミカタは、外部倉庫の委託先探しの強い味方になってくれるはずです。まずは気軽に問い合わせてみてくださいね。