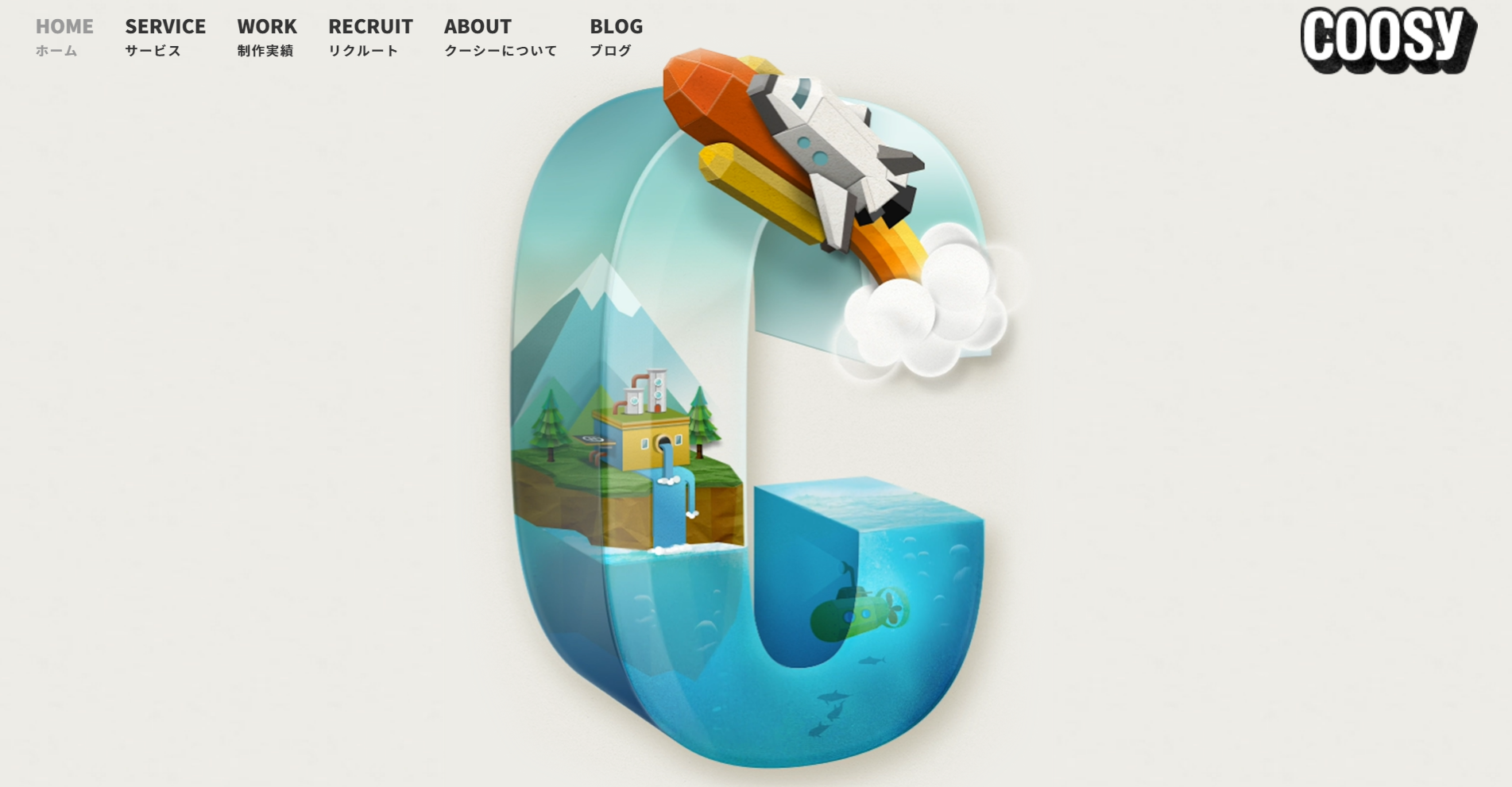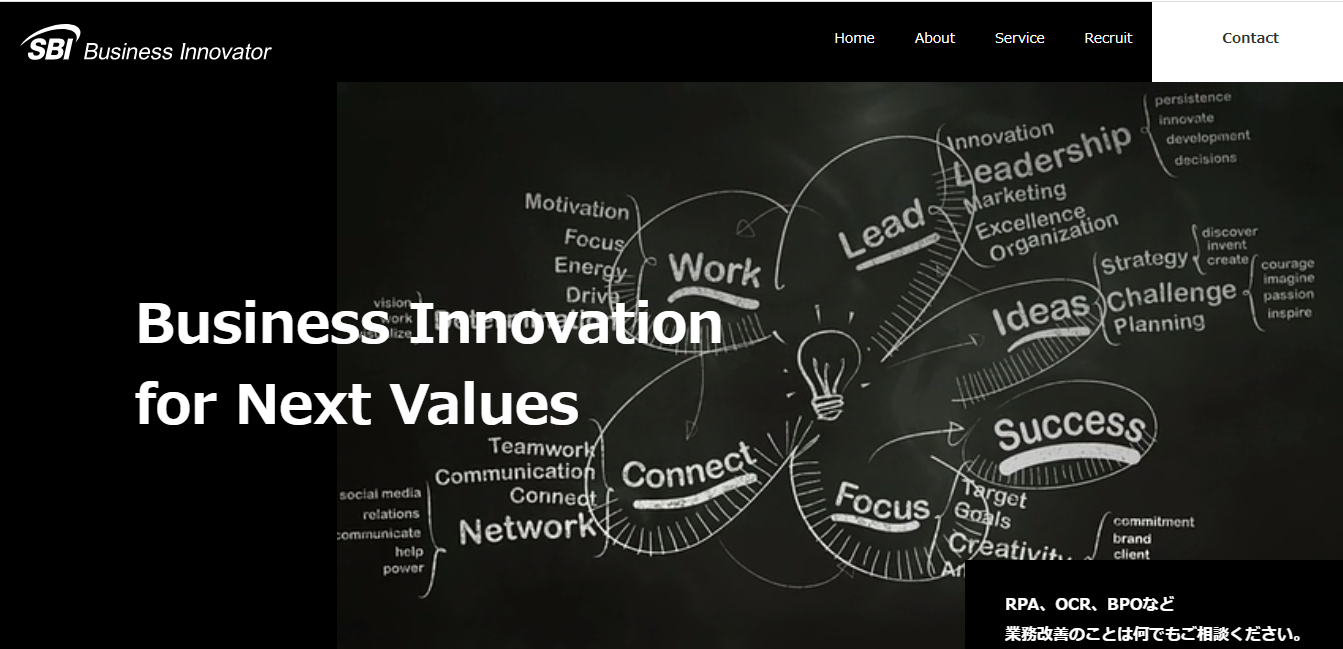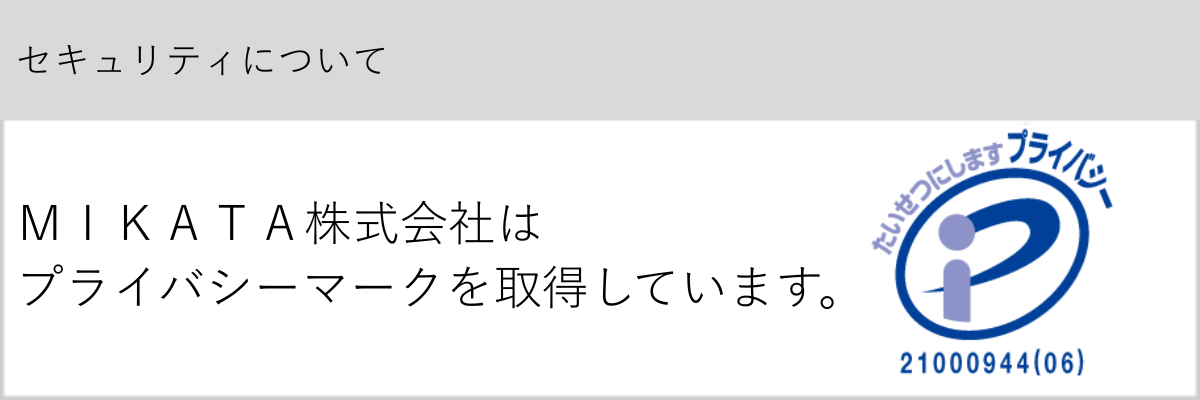AnkerのD2Cはいかにして成功したのか。「顧客体験」を起点にした事業戦略とは
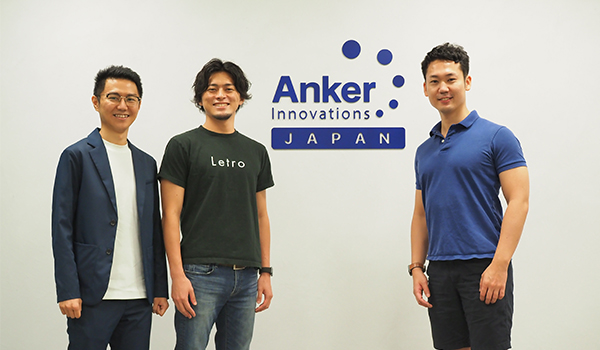
“D2C”や“サブスクリプション”等のビジネスモデルの変化に合わせ、昨今では通販ビジネスの戦略やあり方にも進化が求められている。
一方で、新しい概念への理解が浅いばかりに既存の手法から脱却できず、新しい手法に挑戦できないなど、変化に対応できていない企業も未だ多く存在している。
これらの背景を踏まえ、ECのミカタではD2CブランドとD2C支援企業の対談連載記事をお送りする。上記課題を払拭し、より多くの企業がビジネスをアップデートできる事例や生の情報をお伺いする。
多くのプレイヤーが乱立したことでその本質が見えにくくなっている今、連載6回目では、改めて注目したい「アンカー・ジャパン」の顧客体験を起点とした取り組みについてお伝えする。
Ankerグループは、2011年の創業時から時代に先駆けてD2Cモデルを採用。チャージング関連製品やオーディオ機器、ロボット掃除機、プロジェクターといったハードウェアを世界100ヶ国以上で販売し、2020年にはグループ本社のAnker Innovationsが深圳証券取引所の新興企業向け市場「創業板 (ChiNext) 」で上場も果たしている。
「顧客体験」を起点にした事業戦略とD2Cビジネス成功の秘訣について、SUPER STUDIOの真野氏とアライドアーキテクツの村岡氏が、アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEOの猿渡氏に話を聞いた。
「顧客体験を起点にしたプロダクト開発」は自然な考え方
真野:Ankerグループでは創業当初から、顧客体験を起点にしたプロダクト開発をされていると聞きます。どのような経緯で、「顧客体験を起点にしたプロダクト開発」に行き着いたのですか。
猿渡:率直に言って、「顧客体験を起点にしたプロダクト開発」が特別なことだとは考えていません。古き良きメーカーの人にとっては斬新な考え方なのかもしれませんが、異なる業界出身の私にとっては自然な考え方です。
ひと昔前は、モノを作ってマス広告で宣伝すれば、商品が悪くない限り売りやすい時代でした。しかし、レビューシステムやSNSなどを介して、商品への評価がより見える化されている現在は、消費者の情報収集の仕方も変わってきています。
いいモノを作れば評価される時代でもあるので、消費者の生の声を商品開発に活かし、自社の強みに変えていくことは、メーカーとして当然の姿勢ではないかと思います。今は商品レビューやSNSでのコメントなど、お客様の意見や感想が拾いやすい環境なので、お客様の考えやニーズを知るために、それらを活用しない手はありません。
真野:私自身、数年前に知らないうちに買っていたモバイルバッテリーがAnkerの商品だったという経験があります。どのような消費者のニーズをもとに商品開発に至ったのでしょうか。その起点を教えてください。
猿渡: Ankerグループとしての最初の商品は、ノートPCのスペアバッテリーでした。これはグループCEOのスティーブン・ヤン自身の顧客体験と深く繋がっているのですが、その当時は、品質が高くサポートも良いけれど高額な純正品か、値段は安いけれど品質もサポートも期待できない無名のサードパーティーの商品のどちらかしか選択肢がありませんでした。そこで純正品と同等の品質とサポートの商品を納得感のある価格で出せばニーズがあると考えたんです。
当時は「D2C」という概念はありませんでしたが、Ankerグループでは最初からオンライン、特に大手ECプラットフォームを軸に販売する戦略を採用しました。その後スマホの普及に伴ってモバイルバッテリー市場が拡大の兆しを見せたので、モバイルバッテリーを主軸にチャージング分野を強みとして伸ばしていきました。
お客様がいるところで勝負する
真野: アンカー・ジャパンは、お客様の口コミによって知名度や評価を高めていったと思います。色々なD2Cビジネスを見ていて思うのは、初期はまず買ってもらうまで大変なのではないかということです。ビジネスの初期段階で、買ってもらうための仕掛けなどはありましたか。
 アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡 歩氏
アンカー・ジャパン株式会社 代表取締役CEO 猿渡 歩氏
猿渡:我々がフォーカスしたのは、「お客様がいるところで勝負する」ことです。一般的なECビジネスは、まず自社ECから始めて、他チャネルに拡大していくパターンが多いと思います。しかし誰も知らないようなブランドは、自社ECへの自然流入も検索流入も見込めないので、広告への依存度が高くなりがちです。
一方、Amazonや楽天といったECプラットフォームにはすでに潜在購買者が集まっているので、集客にはあまり注力する必要がありません。お客様がいるところで良い商品を良い価格で販売することで買っていただける可能性は格段に高くなります。「いいモノを作る」というのがメーカーのやるべきことであって、そこに注力せずにデジタルマーケティングの力でECサイトにお客様を呼び込むというのは本質的ではありません。最初からお客様がいるところで勝負したほうが合理的であると考えました。
当初は、Ankerというブランドを知らないまま商品を購入するお客様も少なくありませんでした。Amazonのカテゴリーランキングで1位を獲っていて、良いレビューが並んでいて、価格も手頃で人気商品らしいことがわかれば、ブランド名を知らなくてもお客様は選んで頂くことはできると思っています。
2000~3000円程度のコモディティ商品のカテゴリーで、品質と価格のバランスが取れたコストパフォーマンスの高い製品を世に送り出し、ユーザーに「これいいじゃん、Ankerっていうんだ」と認識してもらうことで、次の商品の購入につながったと考えています。
真野:確かに。私もいつの間にか「Ankerでしょ」と周りにすすめていました。
村岡:初期のAnkerは先進的なニッチな人たちが使っているイメージで、小さいけれど強い渦のようなものがありましたよね。
猿渡:そうなんです。目利きのできるイノベーター的な人たちが「Ankerいいよ」とおすすめしてくださることで、メーカーからの発信だけでなくC2Cでも消費者にブランドの良さを知っていただければ嬉しいなと思っています。
Amazonからのスタートが成功につながった
村岡:「お客様に満足していただくのがベース」という考えが出発点で、初期のチャネルとしてAmazonが最適だったということですが、「まずはここでしっかりスケールの種を作っていこう」という戦略があったのですか。
猿渡:私が参画した2014年当時、日本法人のビジネス部門は私1人でしたが、初年度で売上20億円を達成できました。なぜできたかというと、AnkerグループにはAmazonに出品して「お客様がいるところで勝負する」という戦略に基づいて何をすべきかを分析し、戦術を組み立て、それを徹底的に実行していったからです。
Amazonに特化したもうひとつの理由として、FBA(フルフィルメント by Amazon)があります。自社でサプライチェーンのオペレーションを構築するには膨大な費用と負荷がかかるので、ベンチャー企業にとって既にある仕組みを利用できるというメリットは大きいです。売上が100億円くらいになるまでは販売実績をしっかりと作っていくことを最優先に、大々的なプロモーションはやらずに、主にプロダクトの数を増やすことで売上を伸ばしていきました。
村岡:Amazonという枠組みに御社の戦略がぴったりはまったことが、最初のスケールの火種になったということでしょうか。
猿渡:そうですね。2013~2014年は、ECで買うという習慣は今ほどはなく、特に電化製品は家電量販店をはじめ店頭で買う人が多い時代でした。しかしその後、本だけではなく電化製品もネットで買う人が増えてきたので、EC化の流れに乗れたことも勝因だと考えています。
また、当時はECプラットフォーム側にも「電化製品の販売を盛り上げたい」という意向があったので、プラットフォームのニーズが合致したことも追い風でした。EC化やスマホの普及といったトレンドに加え、プロダクトもプレイスも良く、時代に合った戦略を採ったことが成功につながっています。
村岡:Amazonではなく、自社ECからスタートしていたら今の成功はあったと思いますか?
猿渡:おそらく難しかったと思っています。Amazonは入金サイクルが早いので、売上をどんどん投資に回せるという点も我々のようなベンチャー企業にとっては魅力でした。
村岡:最近は、必ずしも「D2C=自社EC」という流れではなくなってきています。お客様とダイレクトにつながってお客様の行動パターンをとらえ、サブスクリプションでLTVを上げていくというアプローチはECの基本ですが、アンカー・ジャパンの採った戦略は、その時代で御社の商品だったからこそ成功したのでしょうか。それとも、商品カテゴリーが異なるD2Cビジネスでも再現性があると思われますか。
 Anker Japan公式サイト:https://www.ankerjapan.com/
Anker Japan公式サイト:https://www.ankerjapan.com/
猿渡:再現性はあると思います。他の企業の経営者からも同様の質問を受け、アドバイスを差し上げることもあるのですが、私がアンカー・ジャパンで採った戦略は単品通販でも再現性があり、売上を伸ばすことに成功しています。
自社ECをメインの販売チャネルにしているD2Cブランドもありますが、大手ECプラットフォームも商品やブランドを認知してもらう場としては非常に有効です。当社も自社ECサイトを持っていますが、その購入導線の一つとしてAmazonのリンクも掲載しており、お客様が買う場所を選べるようにしています。利益率は下がりますが、買っていただける方が私たちにとってはプラスですし、どこで買うかはお客様が決めることだと考えています。
村岡:お客様の購入体験をどう自然なものにしてあげるかが本質的である、ということですね。
猿渡:そうですね。ただし、プロダクトの特徴によって、自社EC、ECプラットフォーム、直営店など、さまざまなチャネルの中でどれを優先するかは変わってきます。絶対的な正解というのはなく、業種やプロダクトの特徴に基づいて、チャネルごとに適切なKPIを設定することが大切です。
直営店は「オフラインのD2C」
真野:御社では、リアル店舗の出店もされていますよね。出店にあたってはどんな背景や狙いがあったのでしょうか。
猿渡:2018年に実験的にポップアップストアの出店を行って以来、継続的に直営店を出しています。ECプラットフォームへの出店、家電量販店での販売、自社ECを経て、お客様とのコミュニケーション強化のためにリアル店舗の出店を計画しました。
ECに比べると直営店の利益率は低いですが、お客様とリアルな接点が持てる意義は大きいです。毎日店舗から上がってくる日報には、店舗でのお客様の行動やリアルな声など、EC上で確認できる情報とはまったく異なる情報が詰まっています。
真野:当社のクライアントからも「オンラインで買うお客様とリアル店舗のお客様の層が違う」という話を聞きます。御社でも客層の違いは感じますか。
猿渡:両方で買ってくださる方もいらっしゃいますが、リアル店舗の場合、Ankerを知らなくてもふらっと見にきてくれるお客様が少なくありません。ECでは接点を持ちにくい年配のお客様が来店してくださるケースもあり、直営店の存在はリーチの拡大にも役立っています。
直営店は、言ってみれば「オフラインのD2C」。今後も、この発想を大事にしていきたいですね。
合理性と全体最適を重視した組織
 アライドアーキテクツ株式会社 取締役 村岡 弥真人氏
アライドアーキテクツ株式会社 取締役 村岡 弥真人氏
村岡:会社組織においては部門間の連携など、調整が難しい問題も多々あります。アンカー・ジャパンとしての意思決定の軸や、組織の設計において工夫されていることはありますか。
猿渡:当社のコーポレートバリューに「Rationalism」というものがあります。「合理的に考えよう」という姿勢で、言い換えれば「メーカーが作りたいものを売るのではなく、お客様が求めている製品を作るべきである」という考え方です。また、この姿勢は組織マネジメントにも通じており、「全体最適」という視点を重視しています。メンバーには、「個人のKPIだけではなく、アンカー・ジャパン全体のKPIを見ましょう」と口を酸っぱくして言っています。
体制の面で言うと、私がマーケティングとセールス両方の責任者を務めているところに特徴があります。マーケティングディレクターとセールスディレクターが分かれていると、「販売視点を持たず、ブランディングだけに偏ったクリエイティブを作って満足する」というようなことも起こりえます。
そうならないよう、当社ではマインドと組織体制の両面で「メンバー全員が売上と利益を最大化する」ことを目指しています。もしチーム間で意見が相反するような場合は企業全体として最適な答えは何かという視点を持って関係者間で話し合い、結論を出すようにしています。
村岡:強い組織やカルチャーはアドバンテージですよね。
猿渡:D2Cビジネスはほとんど組織で決まると思っています。そして、経営陣の意思決定と組織作りがビジネスの半分を占めていると考えています。
真野:お話を聞いていると、弊社のようなSaaSの企業と組織作りが似ているなと感じます。組織作りは戦略を立ててもなかなか一筋縄では行きませんが、御社ではどのようにして今のカルチャーや風土を作ってきたのでしょうか。
猿渡:当社が求めている発想を持っている人を採用しています。具体的に言うと、合理的に考えられて数字に強く、仮説思考のできる人。ビジネスは未来を予測することが大事なので、「何となく」ではなく、「これをやればいいんじゃないか。なぜそれをやったほうがいいのか」を論理的に考える意識と能力のある人を集めています。
村岡:合理性を重視されるということは、昨日入社した人が「それはアンカー・ジャパンらしくありません。なぜなら…」と物申すこともできるということですか?
猿渡:はい。「誰が言っているか」よりも「何を言っているか」「なぜそう言っているか」を重視します。当社には合理的に考え、発言できる人であれば、社歴や肩書に関係なく耳を傾けてもらえる風土があります。
ダイレクトにメッセージを伝えられるのがD2Cの意義
 株式会社SUPER STUDIO 取締役CRO 真野 勉氏
株式会社SUPER STUDIO 取締役CRO 真野 勉氏
真野:最近は「D2C」という言葉が独り歩きしているようなところもありますが、D2Cの定義やあるべき姿について、御社ではどのように考えられていますか?
猿渡:「D2C」はここ2年くらいのバズワードです。私たちAnkerグループは創業以来D2Cをやっていますし、さかのぼれば、1980年代にGAPが始めたSPA(製造小売業)の拡張版で、D2Cはなにも新しいビジネス形態ではありません。
D2Cと言うと、「中間マージンを省ける」「ECで手軽に始められる」といったメリットが強調されがちですが、メーカーが伝えたいマーケティングのメッセージをダイレクトにお客様に伝えられるところにD2Cの本質的なメリットがあるように思います。
また、D2Cのもう一つのメリットはお客様の声を近くで聞けることにあります。当社にもカスタマーサポート等を通じて、毎日およそ1,000件程度のお問い合わせが入ってきます。販売後もお客様としっかりコミュニケーションを取ることでお客様の声を確実に吸い上げ、次に求められる商品を作りやすくなります。
そのサイクルをしっかりと構築できれば、メーカーは売上を伸ばし、お客様にも喜んでいただけるというwin-winの関係が生まれます。お客様に喜ばれる優れた製品を作ることは、お客様に今までなかった新しい体験を提供することであり、ひいては社会を良くすることにもつながります。そこまでを見据えて日々ビジネスに取り組んでいます。
村岡:今後お客様との関係性を深化させていくイメージや、関係性深化のための取り組みはありますか?
猿渡:CRMはまだまだ強化の余地があると考えています。2021年からスタートした、「Ankerアンバサダープログラム」をはじめ、お客様とのコミュニケーション機会の増加に取り組んでいるところです。
村岡:SNSなど色々な場所でお客様との会話を増やしていくイメージでしょうか。
猿渡:はい。最近では、Twitterで「#Ankerのある生活」というハッシュタグを付けてユーザーに投稿してもらうキャンペーンなども実施しました。インフルエンサーに広告料を支払ってレコメンドしてもらうことも一手ですが、一般ユーザーが「良い」と思った感覚を素直に発信してもらい、自然発生的な良い口コミを醸成する方がファンの輪の拡大につながるのではないかと考えています。
村岡:アライドアーキテクツでは「Letro」というUGCのサイト掲載から効果測定まで行えるツールを運営しているのですが、それを見ると、面白いほどインフルエンサーよりも一般の方がコンバージョン率に与える影響が高いことがわかります。一番影響力が大きいのが、ブランドが独自に任命しているアンバサダーです。
やはり、コアなファンはお客様が購入を判断する際に本当に知りたいことを書いてくれるので、今後のUGC施策においてはアンバサダー制度のようなアプローチが増えていくんだろうなと思います。
猿渡:AnkerアンバサダーはすでにAnker グループ製品を愛用してくださっていた方にお声掛けをしており、投稿の強制や文言の指定などはしていません。「気に入ったら投稿してもらう」というスタンスでやっています。
村岡:「リーチ」のようなわかりやすい指標から、「ユーザーの声」「中身」など、従来の指標では言語化できなかったものがマーケティングにおいてより重要になってきていますよね。
猿渡:そうですね。一過性のインフルエンサー施策のような表層的なものよりも、お客様満足度を上げてファンになってくれる人を増やし、自然なUGCを広げていくことを大切にしています。
ブランドを育てるのは時間がかかるが、失うのは一瞬
真野:御社がブランドを育てるうえで大切にされていることを聞かせてください。
猿渡:当社では、直営店の出店やカスタマーサポートの内製化を含め、中長期的にアセットを貯めることを重視しています。
また当社では、自社製品はもちろん、競合やその他企業の製品について従業員による製品レビューを全面的に禁止するなど、厳格な内部統制を行っています。自作自演の良いレビューを書けば一時的に売上は上がりますが、それによって信頼を失うことのほうがはるかに重大です。ブランドを育てるのは時間がかかりますが、失うのは一瞬。遠回りにはなっても、丁寧にやったほうが報われるなと感じます。
目先の利益ではなく、社会がより良くなることにつながるビジネスでないと面白くないですし、社会の役に立たない事業で儲けても長続きしません。その視点はD2C事業をやるうえで持つべきだと思います。私たちも「Empowering Smarter Lives(ハードウェアの力で、人々のスマートな生活を後押しする)」をコーポレート・ミッションとして掲げ、お客様の生活をよりスマート&快適にすることを目指しています。
結局、お客様のためになるアクションができるかどうかがすべて。短期的に消費者をだますことはできても、消費者の方を向いていないメーカーは淘汰されていきます。あとは過去の栄光にしがみつくことなく、スピード感を持ってビジネスのサイクルを回していけるかですね。