
【ECグロース戦略】EC年商10億円の壁を超える! 事業成長を実現させるための本気の構想【ネクトラス セミナーレポート】
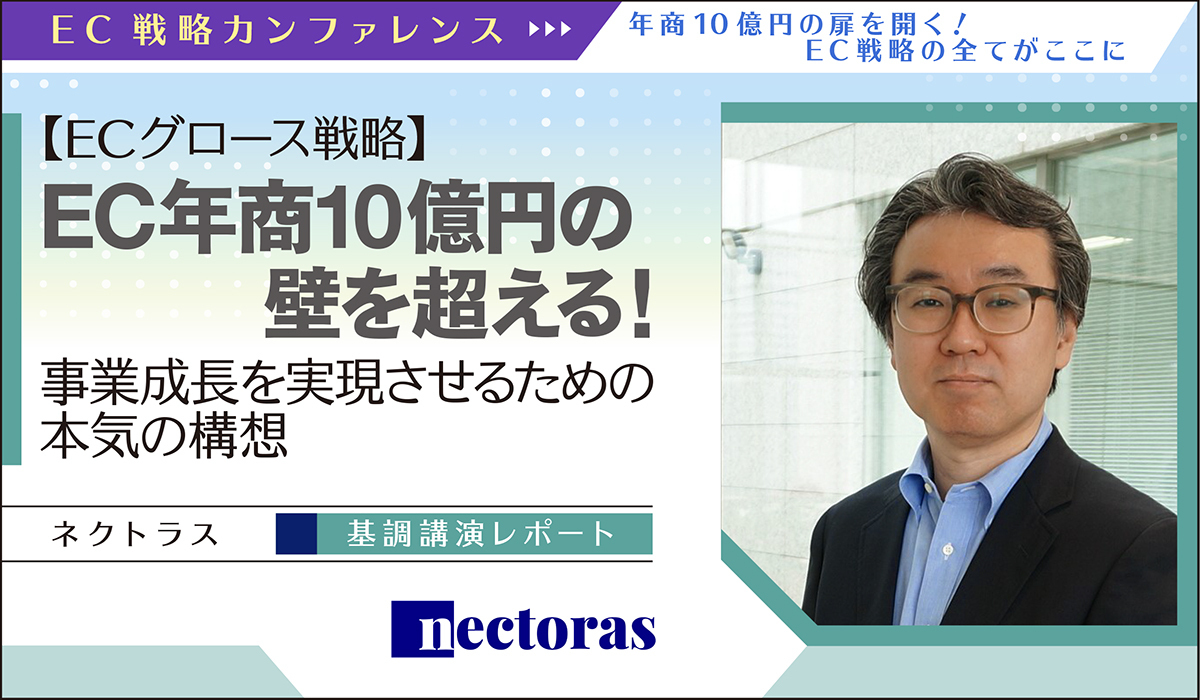
EC市場が拡大を続ける一方で「売上が思うように伸びない」「事業が成長しない」といった悩みを抱える事業者は少なくない。特に「年商10億円」は、多くの事業者にとって一つの壁となっている。なぜ、多くのEC事業は成長途中で伸び悩んでしまうのか。
その原因として、「ECを本気で考えているか」と問題を提起するのが株式会社ネクトラス 代表取締役 中島郁氏だ。EC・オムニチャネルのコンサルティングを手掛ける同氏は、名だたる企業のEC事業をゼロから数百億円規模へと成長させた実績がある。大型EC3社の責任者経験を持つ中島氏が明かす「年商10億円の壁を突破するための『本気の構想』の作り方」とは。中島氏が登壇したセミナーの要点をレポートする。
本記事は2025年5月に開催したオンラインカンファレンス「EC年商10億円を突破するためのEC戦略カンファレンス」でのセミナー内容を基にしています
ECで成長できない理由は「本気じゃない」から
セミナー序盤で中島氏は、日本のEC市場の現状を示すデータを紹介。中島氏の調べでは、2023年時点でEC売上高が100億円を突破している企業はわずか119社であった。しかも、トップ100社を見ても、約半数は成長が鈍化、あるいはマイナスに転じているという。このことからわかるのは、EC市場が拡大しているのは新規参入が多いからであり、既存事業者でも思うように成長できていないという現実だ。
では、なぜ多くのEC事業は成長できないのだろうか。
「人材不足もよく言われますが、一番の問題は『本気じゃない』ことです。結局、トップ企業を除けば、本気じゃない会社が多いのです。しかし、それは裏を返せば、伸びしろとチャンスしかないということです」(以下、発言部分は全て中島氏)
一般的に、ECをはじめとする既存企業の新規の取り組みは、社内でわかる人がいないうえに、タフでハードワークが求められ、本気で取り組まないと、施策ややるべきことがブレ、くじけてしまうのだという。
「ECを始めるきっかけは『市場が伸びているから』『競合他社がやっているから』でも何でも構いません。ただし、やるなら本気でやる。これが私のメインメッセージです」
成長している会社は「本気で」考えて、「ちゃんと」決めて、それを徹底している
中島氏が定義する「本気」とは、「ちゃんと考えて」「ちゃんと決めて」「決めたことを徹底する」というシンプルな3つを指す。特に重要なのが、最初の「ちゃんと考える」プロセス、すなわち本セミナーのメインテーマである「構想」だ。
「他社の成功事例を真似たり、ありものの資料を並べたりして、どこの会社のためにも言えそうなありきたりな計画を作り『考えたつもり』になっている会社が多い。そんなことでうまくいくはずがありません。『あなたの会社のECは、どんなECですか?』という問いに、ちゃんと答えられますか? そして、その答えはわかりやすいですか? こんなものでいいやと、いい加減な検討ではじめられたECは、ユーザーに見透かされます」
「構想」や「コンセプト」という事業の根底にある首尾一貫した考えがないと、何かを決めるのに時間がかかったり、ブレてしまう。すると「品ぞろえの豊富さをベースにするコンセプトなのに、品ぞろえよりも価格や利便性をウリにする施策を頻発する」といったことが起きる。消費者はこうした取り組みのあいまいさを見透かして離れていくので「構想」がないECは成長できない。反対に、構想がしっかりしていればそれが基準になるので、意思決定も早くなり、一貫性も保たれるという。
構想の第一歩はアイデアを吐き尽くし、「ふわっと」考える
では、事業の核となる「構想」はどのように作ればよいのだろうか。中島氏は、「まずは、なぜECをやることになったのかといった会社の期待である『お題』から始める」と言う。
そして、考えるべき「切り口」として、B2BかB2Cか、モール出店か自社ECか、物販かサービスかデジタルか、メーカーか仕入販売か、単品通販か一般小売型ECか、食品かアパレルか、などが無数にあり、さらにECの種類、規模等によっても、考えること、やることは違う。
「会社の期待(新しい顧客を獲得したいなど)、会社の中でのECの位置づけ、顧客へ提供したい体験など、さまざまな背景があるでしょう。まずは、あるべききれいごとで、理想のECを考えるのが大事ですが、自社の状況やリソース、ECを始めたきっかけも非常に重要です。それによって、考えること、やることが変わってくるからです。会社ごとに状況は全く違うので、絶対的な標準解など存在しません。今日お話しする『考え方』に、自社の要素を試しに当てはめてみてください。そうして自社ならではの戦略を『ちゃんと考える』ことが何より大事なのです」
そのためには、まず、ECで何をやりたいのか、やるべきなのかを考えるときは、まず厳格過ぎず「ふわっと考える」ことから始めることが大事だという。
「最初はあまり決めつけずに、あいまいなレベルでもいいので考えを出し合うブレインストーミング的なことが重要です。しかしながら、会議は発散させてはいけないと教育されてきた日本の組織人は、多くの場合、メンバーが『落としどころ』に向かってしまい、ブレストといえず、考えが十分広がりません。この段階では、あまり厳格に考えすぎず、自分たちの提供したい本質的な価値などを、メンバーで吐き出し尽くし、いわゆる「発散」させ、「ふわっと」した考えをまとめていきます。その後、できた考えを評価し、調査、検証を行います。この流れを間違うと、あってもなくてもいいような、始めるだけが目的のありきたりの構想になってしまいます」
EC事業に「標準解」はない。考えること、やることは企業ごとに違うからこそ、他社の事例やありきたりな正解に当てはめるのではなく、内部で手を動かしながら自分の頭で考え、自社にとっての「最適解」を見つけることこそが、構想作りの本質なのだという。
EC全体をプロダクトとして考える
ECの構想を練る際の重要なポイントとして、中島氏は「顧客体験をECビジネス全体で捉える」ことを強調する。
「顧客体験を考えるとき、商品やWebサイトの使用感の体験だけを見ていては不十分です。何らかの情報に触れてサイトを訪れ、商品を探し、見つけ、評価し、購入を決定し、支払い、商品が届くのを待ち、開封し、使い、誰かに話したり再注文したりするという一連のプロセス全てが顧客体験です。掲載される商品のマーケティングだけではなく、このプロセスを実現する顧客との接点、サイトデザインから物流、決済までのECビジネスに関わる全てを一つのプロダクトとして捉え、マーケティング戦略を考えていく必要があります」
この全体像を捉えた上で、ECの構想を練るために中島氏が考えるのが、次の問いだ。
•どんなこと/もの(価値)を=What
…自社が顧客に提供しようとしているものの本質は何か
•どんな人に=Who
…その価値を届けたい人は誰か
•どのように届けて=How
…価値を対象顧客に届けるためのタッチポイント
•どのような体験をしてもらうか=Why/Goal
…その価値が、対象顧客に、設定したタッチポイントを通じて届けられた結果、どのような体験が生まれるか
「最も重要なのは、起点となる自社のバリュー(本質)です。自社のバリュー(本質)は事業規模が拡大して、顧客の対象が広がっていっても大きく変わらないはずです。このようにしてECの『あるべき姿』を描いた上で、それが目指す事業規模(例えば10億円)に到達するイメージが持てるかどうかを検証します」
構想に正しい正しくないはありません。あえて言えば、ロジカルでストーリーがあるか、シンプルでわかりやすいか、既存事業と整合性があるか、流行(バズワード)に振り回されていないか、などである。そして、事業計画を立てる中で「このコンセプトは良いけれど、年商1億円にしかならないな」ということであれば、構想を見直す必要がある。新しいことをやる際は、この程度の行ったり来たりは当然。
構想はブレないための「旗印」。徹底してこそ価値が生まれる
こうして考え抜いて作られた構想は、事業を導く「旗印」となる。これさえ決まれば、次は組織としての決定、すなわち「ちゃんと決める」を行い、メンバーに刷り込むフェーズに入る。
「決めたことが『徹底』されなければ、うまくいかなかった原因が、考えの内容が悪かったのか、徹底できなかったからなのかがわかりません。トップが繰り返し発信し、メンバー全員に刷り込み、全ての活動を構想に基づかせることが重要です。そして、本気であれば、会社としても組織、人材、制度、リソース配分も、構想に沿った形にしていけるはずです」
EC事業を成長軌道に乗せるために必要なのは、小手先のテクニックや「飛び道具」ではない。自社の提供したい本質的価値と向き合い、進むべき道を示す「本気の構想」を練り上げ、それを徹底する。その地道な取り組みこそが、10億円の壁を突破し、その先の成長へとつながる唯一の道筋なのだ。
経営/事業コンサルタント。豊富なEC、オムニチャネル、デジタル経験に加え、アナログを含む新規事業と成長の実現に強い。ベンチャー⇒外資⇒老舗と通常と逆の経歴で、小売、EC、デジタル/リアル、IT、メディア、サービスビジネス等を経験。トイザらスのマーケティング部門/EC法人立上げ、ジュピターショップチャンネル役員本部長(EC・マーケティング・番組編成)、GSI commerce(eBay Enterprise)APAC代表兼日本法人社長、コンサルタントとしての関与後に役員兼EC事業部長に就任した三越伊勢丹では、オムニチャネル、デジタル等も推進。大型EC3社の責任者経験は珍しい。現在、ベンチャーから大企業までさまざまな業種・業態の事業構想、戦略、マーケティング、EC、小売、リアル・デジタルを支援。共著に『いちばんやさしいEC担当者の教本』(インプレス、2022年)等がある。





















