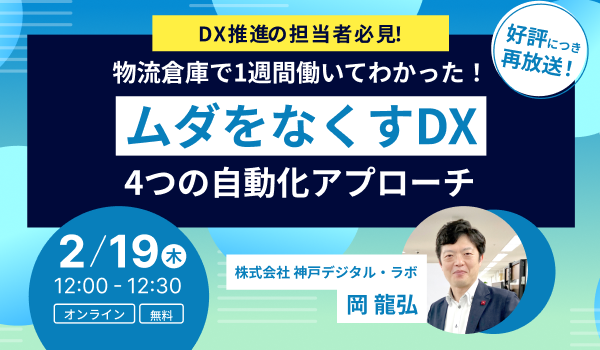中川政七商店の「クラスタリング」と「生成AI」を活用したブランドコミュニケーション

1716年(享保元年)に創業し、「日本の工芸を元気にする!」というビジョンのもと、工芸に根差した生活雑貨の製造小売業や業界特化型のコンサルティング、販路開拓のための展覧会などを展開する株式会社中川政七商店。同社が接客において大切にするのは、顧客の心に接し、ブランドを好きになってもらう「接心好感(せっしんこうかん)」という考えだ。
本記事では、2025年7月29日にECのミカタ(MIKATA株式会社)主催の「長期的に選ばれるECのつくり方 ~CRM・CX・ファン化戦略大公開~」で、同社経営企画室の中田勇樹氏が語った、顧客・購買データを独自の切り口で分析する「クラスタリング」の手法と、生成AIを活用してパーソナライズされたコミュニケーションを効率的に実現する具体的な取組についてレポートする。
その場で商品を買ってもらうことに、とらわれなくてよい。「接心好感」の精神
株式会社中川政七商店(以下、中川政七商店)では、ブランドを「差別化され、かつ一定の方向性を持ったイメージにより、商品・サービス・会社にプラスをもたらすもの」と定義している。そのイメージを作り上げるためには、あらゆるタッチポイントをコントロールし、あるべきイメージを作っていくことが不可欠だ。それは販売員や店舗、自社メディアだけでなく、本社や倉庫スタッフ、さらには自社以外のメディアまで含めた「総力戦」だと中田氏は強調する。
また、中川政七商店では接客において「接心好感」という造語も掲げている。
「『接心好感』とは、お客様の心に接し、心地よいブランド体験を提供することで、商品、お店、ブランド会社を好きになってもらうことだと定義しています。私自身、入社後の店舗研修で『その場で商品を買ってもらうことに、とらわれなくてよい』と言われたことが印象に残っています。今、商品を買わなくても、お店を好きになって帰っていただけたら、そのお客様はきっとまた足を運んでくださるからです」(以下、発言は中田氏)
属性や購買金額だけでは見えない顧客像を可視化する「クラスタリング」
デジタル上で「接心好感」を実現するために、中田氏が最初に取り組んだのは「セグメントの見直し」だ。多くのEC事業者が顧客をセグメントする際、年齢・性別といった属性や、購入金額に基づくランク分けを用いるのが一般的だ。
そこで中川政七商店は「クラスタリング」を導入した。クラスタリングとは、購買データから行動が似ている顧客をグループ分けする手法。このグループ分けがもたらすメリットは、顧客のライフステージの変化、すなわちカスタマージャーニーを可視化できることだ。
「例えば、クラスターの『内祝い』に分類されるお客様の初回購入は、結婚祝いに贈るようなペアカップやお皿が中心です。ところが2回目の購入では、ベビー用品に変わります。これは、結婚祝いを贈った夫婦に赤ちゃんが生まれたというストーリーを予測できます。さらに購入を重ねると、今度は自分用にバスタオルやハンドタオルといったサニタリーグッズの購入が始まります。ベビー用品の品質の良さを実感し、『赤ちゃんの肌にいいなら自分の肌にもいいかもしれない』と、まずは試しやすい商品から自分用に購入されるのです。そして最終的には、化粧水やシャンプーといった、よりパーソナルな商品へと移行していきます」
 画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
一人ひとりの購買履歴をN1(顧客一人ひとりを深く分析する手法)で分析するのは困難だが、クラスターという集団で捉えることで、顧客がブランドとどのような関係性を築いていくかの「ストーリー」が浮き彫りになる。中川政七商店では、このクラスターと購入頻度を組み合わせることで顧客のジャーニーを分析し、それぞれに最適なコミュニケーションを設計しているのだ。
このアプローチはWebサイトのUI改善にも活かされている。一般的なABテストでは、結果が良かったほうを全てのユーザーに適用するが、中川政七商店ではクラスターごとにABテストの結果を集計し、クラスター単位で表示を変えている。
 画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
また、メルマガについても、クラスターと購入頻度を起点にして配信している。これは、各商品の在庫数が少ない中川政七商店にとって、配信中や配信前の売り切れといったリスクを避けられるメリットもある。
 画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
画像提供:株式会社中川政七商店(カンファレンス登壇資料より)
「ブランドらしさ」と「効率化」を両立する生成AI活用術
クラスターごとにコミュニケーションを最適化することで、それだけ運用工数も増加するという課題が生じる。そこで中川政七商店が活用しているのが、生成AIだ。
「クラスタリングと生成AIの相性が良い理由が2つあります。1つ目はセキュリティリスクの低さです。クラスタリングされたデータは、あくまで平均値であり、個人情報は希薄化されています。そのため、そのまま生成AIに入力しても個人情報流出のリスクがほとんどありません。2つ目は、購入回数が少ないお客様にも精度の高いアプローチができる点です。1回しか購入歴のないお客様に最適な提案をするのは難しいですが、そのお客様の属するクラスターが将来どのような商品を購入するかという予測データを使えば、先回りしたコミュニケーションが可能になります」
実際に、メルマガを一括配信からクラスターに合わせたコンテンツにパーソナライズしたところ、クリック数は平均して120〜150%向上した。ここで生じた新たな課題は、いかに効率的に運用するかである。
セミナーでは、AIを活用したメルマガコンテンツの自動生成のデモンストレーションが紹介された。実際にAIが作成した件名と人間が作成した件名とを比較検証したところ、開封率に有意差はなかった。しかし、トーン&マナーについては、人間の作ったものに中川政七商店らしさが表れる。
「進め方としては、AIで骨子を作った後、最終的にブランドらしさを担保するチューニングや編集を人間が行う形にしています。また、AIにレイアウトを作ってもらった場合、クリック数が約120%向上し、運用工数を約50%削減することに成功しました」
今後は、クラスターの行動特性を学習させたAIエージェントにECサイト上を自動で回遊させ、その行動ログをレコメンドエンジンの精度向上に活用する取組も検証中だという。また、会員登録をしていないゲストユーザーであっても、サイト内の行動からクラスターを推定し、最適なポップアップを表示させる取組も進めている。
「あくまでAIは業務を効率化するためのサポート役です。手仕事を大切にしている会社だからなおのこと、コミュニケーションにおいても『人が関わること』、『人にしかできない仕事』を大切にしています。AIが精度を磨きこみ、その上で、より重要な領域に人のリソースを注げるようにすることが私たちの目指すところです」
1989年生まれ。AOKIで商品開発と新規事業立ち上げを経験し、課題分析から販路構築まで経験。2019年からはEC・デジタルマーケティング領域のコンサルタントとして多業種の売上最大化を支援。2021年より中川政七商店に入社、ECからコミュニケーションデザイン室を経て、現在は経営企画室に所属。データとテクノロジーを活用し、顧客と従業員の「心地よい体験」づくりを推進中。