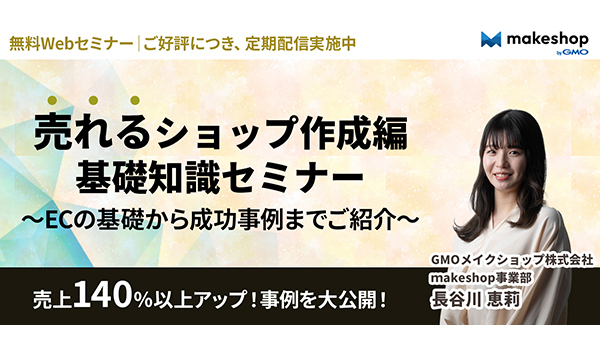価格競争から抜け出せ! 八代目儀兵衛×モンマルシェ×ヤッホーブルーイングに学ぶ「体験価値」EC戦略の極意【ECのミカタ カンファレンスレポート】

モノがあふれ、広告費が高騰し続ける現代。多くのEC事業者が、終わりなき価格競争に疲弊しているのではないだろうか。どうすれば顧客から「高くても、あなたから買いたい」と選ばれるブランドになれるのか――その答えは、顧客の心を動かす「体験設計」にあるようだ。
ECのミカタが2025年8月28日に開催した「ギフトECカンファレンス」では、京都の老舗米屋・八代目儀兵衛、常温スープで急成長を遂げたモンマルシェ、クラフトビール市場を牽引するヤッホーブルーイングら業界のトップランナーが、ファンを熱狂させ、確かな利益を生み出す戦略の神髄を披露した。
【八代目儀兵衛】売上の7割が「新規顧客」。感動を連鎖させる高付加価値戦略
 株式会社八代目儀兵衛 取締役CMO 神徳昭広氏
株式会社八代目儀兵衛 取締役CMO 神徳昭広氏
米の消費量は減り続け、業界の営業利益率はわずか0.8%……そんな逆境の中、京都の老舗米屋・株式会社八代目儀兵衛は、高付加価値ギフトで独自のポジションを築いている。取締役CMOの神徳昭広氏は、その根幹に「体験価値を設計し、循環させる思想がある」と語る。
「贈る人が選び、受け取った人が開封して感動し、お礼を伝える。その感動が、また次のギフトへとつながっていく。この循環の仕組み化こそが我々の戦略です」
驚くべきことに、購入者の7割は同社のお米を食べたことがないという。「娘と一緒に箱を開けた瞬間、“うわー!”と歓声が上がった」という顧客の声が象徴するように、商品そのものだけでなく、箱を開ける瞬間の感動まで緻密に設計されているのだ。
神徳氏が入社後に断行した「EC売上を飛躍させた4つの改革」は、全てのEC事業者の参考になるだろう。
【1】ECサイトの全面刷新: 止まっていた更新を再開し、現代の顧客体験に最適化
【2】広告投資の選択と集中: 「香典返し」「結婚内祝い」など実需ワードに絞り、費用対効果を最大化
【3】高価格帯ギフトの開発: 利益率の高い2万円超の「瑠璃」シリーズなどを展開し、客単価を向上
【4】データ分析基盤の強化: 低コストのDMPを導入し、顧客理解を深化
これらの結果、自社EC比率は7割に達し、利益構造は劇的に改善した。
さらに、セブン‐イレブンやバーガーキングとの協業でブランド想起を高め、今後はGEO(生成エンジン最適化)も見据えるなど、伝統産業でありながらDXの最前線を走る。八代目儀兵衛の挑戦は、「体験価値」がいかにして強力な収益エンジンとなりうるかを証明している。
【モンマルシェ】わずか15人で年商22億円! 「野菜をMOTTO」の体験設計と物流逆算思考
 モンマルシェ株式会社 常務取締役 河野雄士氏
モンマルシェ株式会社 常務取締役 河野雄士氏
従業員15名の少数精鋭ながら、月商50万円から年商22億円へとV字回復を遂げたモンマルシェ株式会社。その原動力となった常温保存スープ「野菜をMOTTO」のギフト戦略を、常務取締役の河野雄士氏が語った。
通販初心者だった河野氏の転機は、「商品を“モノ”ではなく“贈り物”として再設計する」というシンプルな発想だった。高級さば缶で得た知名度を武器に、常温保存可能なスープに事業を集中。「冷蔵庫の容量を気にせず贈れる安心感が、贈り手と受け手双方の心をつかんだ」と河野氏は分析する。
河野氏はギフトECのメリットとして、新規顧客の自然な獲得や高単価化、モール販路との相性の良さを挙げる。「母の日」商戦では広告とランキングを組み合わせて「売れる動き」をつくり出し、1日100件だった注文を5000件超へと押し上げた。
河野氏は、「贈る体験」を4つの要素に分解し、緻密に設計している。
【1】感情の存在: 「ありがとう」「おめでとう」という気持ち
【2】メッセージ性: カードやラッピングを通じた心遣い
【3】体験価値: 開けた瞬間の喜びや感動
【4】特別感: 「あなたのために」と感じさせる演出
この思想を体現したスープとカーネーションの限定バスケットは、今年3万個を売り上げた。しかし、同社の強みは華やかなフロントエンドだけではない。「機会損失ゼロ・在庫ゼロ」を掲げ、親会社の物流網を活かした徹底的なバックヤード改革だ。
「お客様は、高いものを買ったら必ず『良かった』と思いたい。だから3000円の商品を5000円に見せる工夫が不可欠なんです」
体験設計と物流からの逆算、そして価格以上の価値提供。少人数で大きな成果を上げる秘訣が、このセッションには詰まっていた。
【ヤッホーブルーイング】売上だけがKPIではない。「よなよなエール」が生み出す“特別な認知”とは
 株式会社ヤッホーブルーイング YES!通販団 星組 Unit Director 植野浩樹氏
株式会社ヤッホーブルーイング YES!通販団 星組 Unit Director 植野浩樹氏
「私たちのミッションは『ビールに味を!人生に幸せを!』」。そう語るのは、国内クラフトビール市場No.1の株式会社ヤッホーブルーイングで通販部門を率いる植野浩樹氏だ。同社にとってビールは飲料ではなく“体験”そのもの。ECの役割は売上獲得ではなく「ファン化の入り口」だと断言する。
「売上はKPIの最上位ではありません。体験を通じてファンを増やし、その結果として売上がついてくる。この構造を大切にしています」
その戦略の核となるのが「特別な認知」という考え方だ。象徴的なのが「父の日ギフト」。
「父の日ギフトは、娘さんには“喜んでもらえた”という記憶を、お父さんには“娘からもらった特別なビール”という感動を残します。1件の購入が、親子2人分の特別なブランド体験になるのです」
顧客から届く「うれしくて缶をペン立てにしています」という声は、ギフトが単なる消費ではなく、人生の記憶になっている証拠だ。
また、顧客との対話から生まれた「卒乳祝いセット」のように、売上規模は小さくともブランドへの共感を深める施策も積極的に展開。同社では、ギフトの特性に応じて「売上」「利益」「ブランディング深化」などKPIを柔軟に使い分ける。
「まずは小さくやって振り返る」「レビューをAIで分析し、高速で改善を繰り返す」――ギフトを「体験」と捉え、ファンとの絆を育む仕組みとして磨き上げる同社の姿勢は、多くの事業者に新たな視点を与えるだろう。
トップランナー3社が激論! ギフトEC「勝者の条件」【パネルディスカッション】

セッション後には3名が再び登壇。EC事業者が直面するリアルな課題について、本音の議論が交わされた。
――ここ数年のギフト市場の変化について、どのように感じていますか。
河野氏(モンマルシェ) やはりコロナ以降、消費者行動は大きく変わりました。以前は衝動買いも多かったのですが、今はAIやSNSを駆使して徹底的に調べてから買うようになった。こうした変化に対応するために、私たち事業者は、常に仮説を立てて挑戦していく必要があります。
植野氏(ヤッホーブルーイング) ギフト市場のプレーヤーが急増し、Qoo10やLINEギフトのような新しいプラットフォームも台頭しています。そんな中で選ばれるためには「わざわざそこで買う理由」がますます大事になっています。AIで効率的に調べられる時代ですが、最後の決め手になるのはレビューや人間らしさではないでしょうか。
神徳氏(八代目儀兵衛) 当社は結婚祝いや出産祝いを中心に展開してきましたが、少子高齢化でその市場は縮小しています。その一方で法事関連は伸びていて、さまざまなマナーがある法事とお米は相性が良い。数年前は月商300万円程度でしたが、今では4000万円を超えるまでになりました。
――価格戦略についてはいかがでしょうか。
河野氏(モンマルシェ) 3000円台は競合が多く利益が出にくい。広告費をかければ赤字になることもあります。一方で、1万円以上の商品は競合が少ないので、高価格帯を狙っていくことが大事です。商品開発において大事なのは価格以上の価値が感じられるようにすること。化粧箱の紙質や梱包材、冊子の質にもこだわって、1万円以上の高価格帯で、価格以上の価値を感じてもらえるよう意識しています。
植野氏(ヤッホーブルーイング) ギフトは「予算ありき」で選ばれます。楽天市場にも価格帯ごとの広告枠がありますから、まず価格帯を起点に考えることが多いですね。ただ、ビール単体での高価格帯は限界があるので、職人手作りのグラスと組み合わせるなど「体験価値」で価格を上げるなど試行錯誤しています。
神徳氏(八代目儀兵衛) お米は重さがあるため送料負担が大きく、3000~5000円帯では利益を出しにくい。だから1万円以上の商品に注力しています。ただ、3万円のギフトとなると、単に量を増やすだけでは食べきれないので、1カ月ほどで消費できるお米と「お米券」と組み合わせたり、日比谷花壇とコラボして生花とのセットを作ったりしています。ギフトは用途ごとにニーズが異なるため、慶事と弔事で風呂敷の色を変えるなど、目的に合わせた商品設計・集客戦略を意識しています。
――差別化のために大切にしていることは。
河野氏(モンマルシェ) 熨斗や名入れ、仏事用の手提げ袋など、他社が面倒だと感じることをあえてやっています。名前の漢字が「はしご高」か「立ち高」かを確認するような作業も欠かせません。「いいもの」の逆は「悪いもの」ではなく「無関心」。熨斗の漢字一つを確認するような、他社が面倒がることを徹底的にやる先に差別化がある。
植野氏(ヤッホーブルーイング) 私たちのミッションは「ビールに味を!人生に幸せを!」。それを販売ページでも伝え、顔を出して語りかけています。それによって、私たちが「実現したい世界」をお客様に感じてもらうと同時に、社員一人ひとりがその感覚を常に持ち続けることにもつながっています。私たちのビジョンに共感してくださったお客様が、自分も「クラフトビール文化を広めることに貢献しよう」とギフトとして友人・知人に贈りたくなる動機になっています。
――販売チャネル戦略についてはどうでしょうか。
神徳氏(八代目儀兵衛) やはり初期は楽天で実績を積むのが王道だと思います。当社も初動は楽天市場でした。まずは楽天市場で実績を積み、「ショップ・オブ・ザ・イヤー」を目標に掲げるなど、わかりやすい成果を取ることが大事ではないでしょうか。
自社ECが7割を占めるようになった今も、お客様の入口はさまざまなので、複数のチャネルを持つことは大事だと感じています。例えば当社は高島屋オンラインにも出店していますが、売上より「百貨店で扱われている」という信頼を得る意味合いが大きい。そこでの認知が自社ECでの購入につながるケースもあります。
植野氏(ヤッホーブルーイング) 私も最初はモール展開が基本だと思います。モールは検索流入が強く、広告を打って集客してくれるのも大きなメリットです。もちろん手数料はかかりますが、その分ポイント付与などで販売を後押ししてくれる。そうしたモールの仕組みをうまく活用することが重要だと感じています。
EC支援事業者による最新トレンド解説 活発な情報交換が生まれる場に
カンファレンスでは、支援事業者による最新ソリューションも紹介された。株式会社ギャプライズは、ショート動画を活用してギフトECのコンバージョンを高める手法と成功事例を披露。Shopify Japan 株式会社は、Shopifyユーザーであるモンマルシェの「野菜をMOTTO」が急成長を遂げたギフト戦略の舞台裏について、具体的な実装方法とともに紹介した。
またソリューションピッチには株式会社shizai、AnyReach株式会社、株式会社ロックウェーブの3社が登壇し、ギフトECを支援する自社サービスの魅力を解説。
セミナー後の懇親会では、登壇者と参加者が一体となり、リアルな場ならではの熱気あふれる情報交換が行われ、イベントは盛況のうちに幕を閉じた。
 (左)株式会社ギャプライズ セールス担当 田島雅大氏、(右)Shopify Japan株式会社 Lead, Business Development 梅田志桜里氏
(左)株式会社ギャプライズ セールス担当 田島雅大氏、(右)Shopify Japan株式会社 Lead, Business Development 梅田志桜里氏