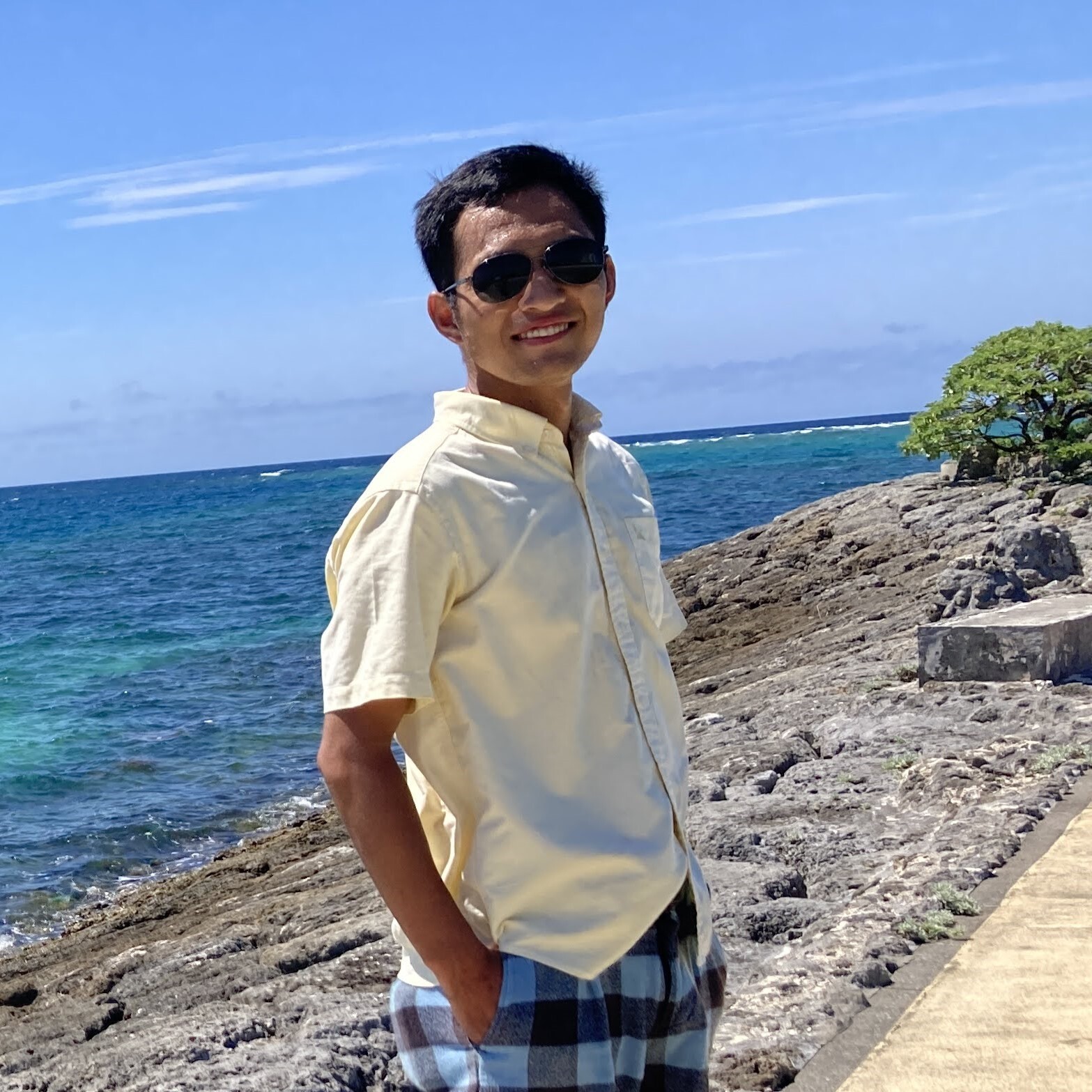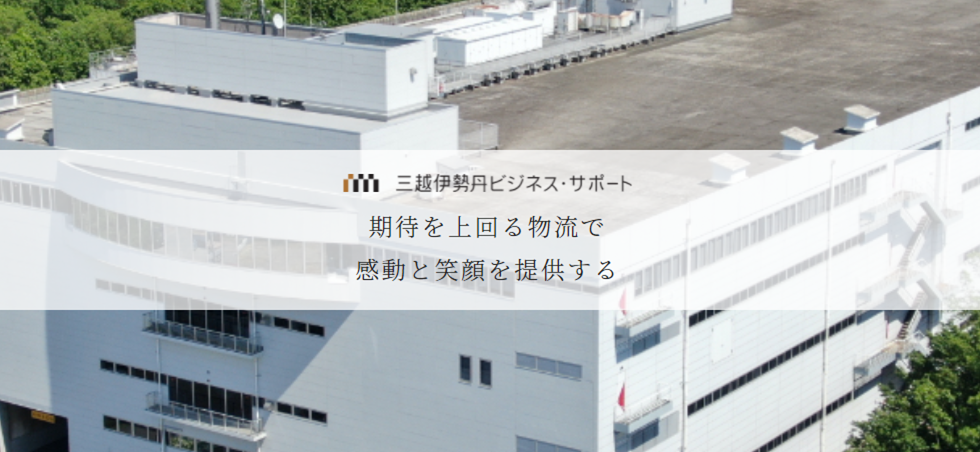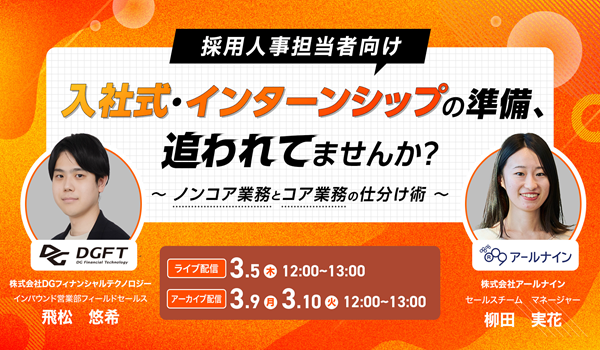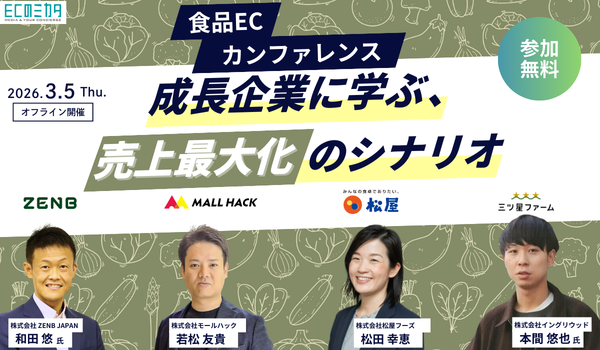YouTube Brandcast 2025レポート 広告主とクリエイターが語るYouTubeマーケティング

2025年10月30日、グーグル合同会社は、企業向けイベント「YouTube Brandcast 2025」を東京ガーデンシアター(東京都江東区)にて開催。企業のマーケティング担当者など多くの聴衆が詰めかけた本イベントでは、YouTubeの最新動向に加え、一部の商品のテレビCM予算をデジタルに振り切ったアサヒビール株式会社や、EC売上の7割以上をYouTube経由で達成する「Mr.Chairs」といった企業の活用事例が多数紹介された。本レポートでは、このBrandcastで語られた内容の一部をお届けする。
「信頼」がYouTube成長の源泉
オープニングに登壇したYouTube Japan 代表 山川奈織美氏は、20周年を迎えたYouTubeの歴史を振り返った。2008年のパートナープログラム開始、2016年のV-Tuber登場による「推し」を中心とした経済圏の発生、2020年の医療・健康領域情報の充実、2022年にEC機能が実装されたYouTube ショッピングなどが紹介された。2025年にはコネクテッドテレビにおける視聴時間で、YouTubeが最長になったという。
山川氏は以下の三点によってYouTubeがユーザーの支持を集めて成長してきたと語る。
①ユーザーの興味関心に近いコンテンツを見つけられる「Relevance」
②ユーザーが強い興味を持ち、集中して視聴している「Focus」
③ユーザーがクリエイターやコンテンツを信頼している「Trust」
なかでも「Trust」が最も重要で、「多様多種な情報源を自分で比較できること、多くのユーザーの意見が可視化された状態で確認できること」の2点を「Trust」が成立するための条件だと山川氏。
 YouTube Japan 代表 山川奈織美氏
YouTube Japan 代表 山川奈織美氏
また、YouTubeが日本国内で4600億円のGDPと8.5万人の雇用を創出したとも説明。その背景にはコンテンツにおけるジャンルの「広さ」、スポーツの舞台裏なども見せる「深さ」、コメントや購入といったエンゲージメントを生む「奥行き」があると語った。
山川氏はオープニングの最後に「この20年、YouTube はコンテンツの多様化を推進することで、ユーザーの情報摂取の在り方を変え、暮らしに寄り添ってきました。そしてこれからの20年、AI と共に進化しながら、YouTubeはさらに多様性を広げ、新しい時代のメディアを形作っていきます」と述べた。
比べやすく、納得感のあるコンテンツで購買へ誘導
トークセッションには「Mr.Chairs」を運営するしばたまる氏と、自身のYouTubeチャンネルも運営する「FORZA STYLE」編集長 干場義雅氏が登壇。両名はYouTube動画を介して多くの販売実績を上げており、セッションでは購買を生み出すコンテンツへのこだわりが語られた。
しばたまる氏が運営するECサイト「Mr.Chairs」の売上は、同名YouTubeチャンネルからの流入が70%以上を占めるという。YouTube運営のKPIにしているという視聴回数当たりの購買率を高めるためのこだわりは、「視聴者の椅子選びを終わらせる体験」。
「様々な価格帯の商品を横並びにして比較することで比べやすくなっています。また、腰のランバーサポートなどの専門的な部品には名前がついていないこともあるので、『独立型』『ソフト型』のような定義づけと言語化をして話すようにしています。他のチャンネルにはない指標で椅子を見られるので、見ざるを得ない動画作りをかなり心がけてます」(しばたまる氏)
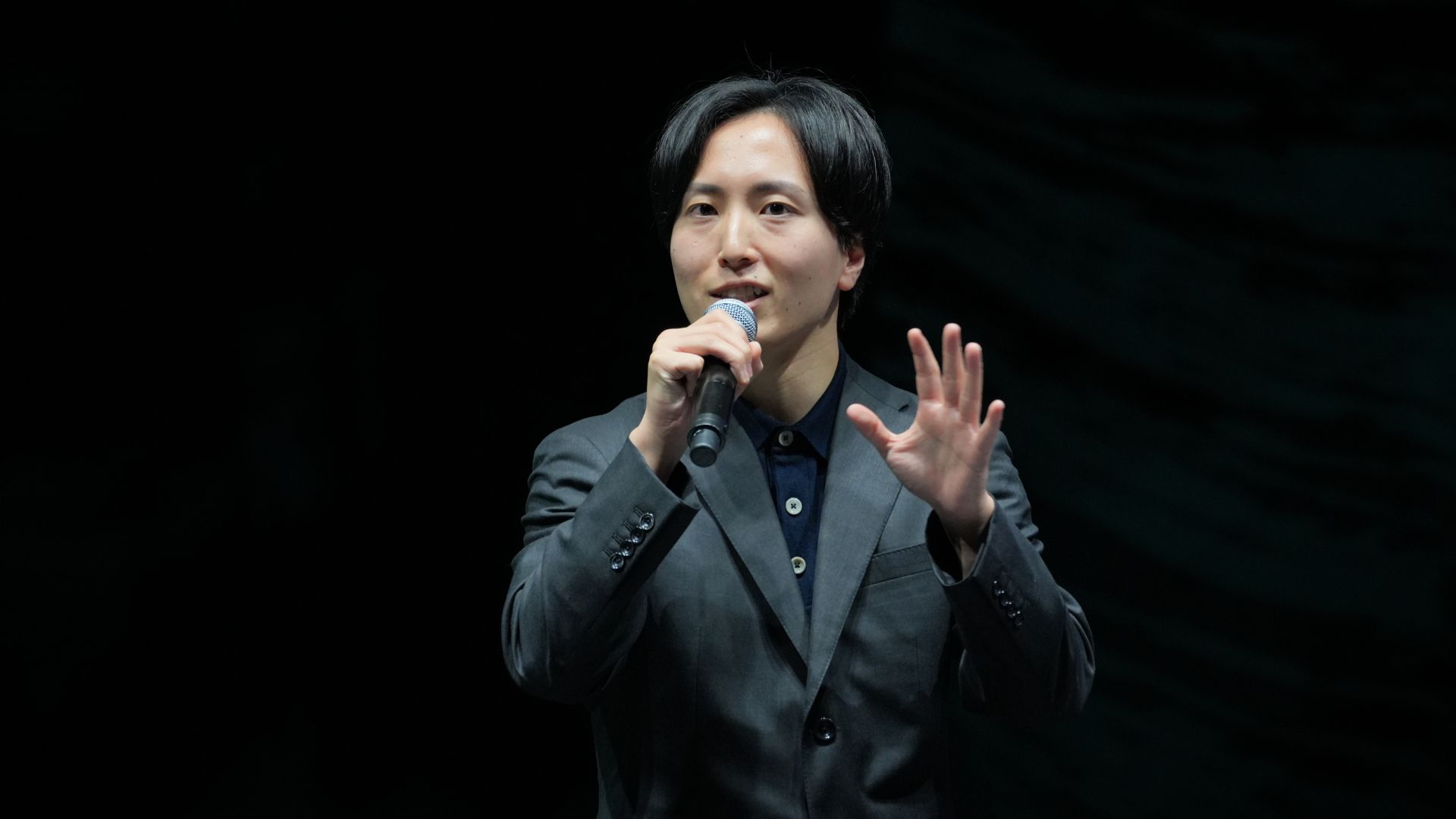 「Mr.Chairs」しばたまる氏
「Mr.Chairs」しばたまる氏
しばたまる氏はコメント欄を掲示板として活用することにもこだわっている。しばたまる氏は視聴者からコメントで寄せられた質問に逐一回答。生のQ&Aが動画に付属した状態を作ることで、視聴者同士の意見交換も活発になり、コミュニティが形成されているという。
「商品購入前の最終チェックをする場としてYouTubeを利用している人はとても多いと思います」
しばたまる氏が商品を選出するにあたっては「Mr.Chairs」らしさを重視し、「納得して買う」購買導線を作っていると語る。商品や寸法を映すタイミングでYouTube ショッピング機能を利用し、スペックを直接確認・比較できるようにして、衝動買いではない体験を提供しているという。
わかりやすさと濃密な長尺を織り交ぜて「爆売れ」
長年のファッションメディア経験から、すでに一定の信頼を獲得している干場氏は「自分が自信をもっておすすめできる商品しか紹介しない」と語った。動画ではイタリアやイギリスなどに赴いて作り手に出演してもらう、商品の背景情報や価値観を共有するといった方法で視聴者にアイテムの理解を促している。
「すごい売れる」と語る干場氏は動画を通して、「深い関係性が(干場氏と視聴者の間に)生まれて、購入までつながっていると思います」と手ごたえを伝えた。干場氏が商品を紹介する動画でのこだわりは「シンプル・上質な素材で流行に関係なく長く愛用できる商品」を「わかりやすく」解説し、「没入型の疑似体験」を提供することだ。
「わかりやすさ」について干場氏は「素材、色、デザイン、サイズ、シルエット、どういう風に着るかに至るまで、見ている方にわかりやすく伝わるように、ワイドな画角や寄りと引きを、写真と動画を駆使して仕上げます」と語った。
 「FORZA STYLE」編集長 干場義雅氏
「FORZA STYLE」編集長 干場義雅氏
干場氏は情報量の多い長尺動画で実際に接客されているような「没入型の疑似体験」を生み出し、ショート動画で効率的なファッション情報収集需要に応えているという。
「約30分の長尺動画であっても、内容が濃ければ離脱せずに最後まで見てもらえます。動画を通じて視聴者も納得していただけるから商品がクリックされ、高価なものでも『爆売れ』するんです」(干場氏)
干場氏、しばたまる氏ともに、YouTubeの動画は資産として残り続けるため、過去動画からもアクセスやコンスタントな売上があるという点をプラットフォームの特長として挙げた。
アサヒビール株式会社、広告予算をデジタル100%に
広告の成功事例としてアサヒビール株式会社からはコミュニケーションデザイン部 担当副部長 栗岩洋平氏が登壇し、「アサヒスーパードライ」の広告比率をデジタル100%にする大胆なデジタルシフトの背景を解説した。同社は性年代に加えて「飲める」「飲めない」など、分散化したクラスターへのアプローチに危機感を覚えており、テレビCMなどの従来型のマス広告が特に若年層へ届きにくいという課題があった。
最初に述べられた施策は組織改革だ。従来は広告宣伝を行う宣伝部とCRM構築などを担うデジタルマーケティング部が並立しており、部門での個別最適化が存在していたという。同社は対策として「コミュニケーションデザイン部」を創設した。
「フルファネル全体を俯瞰して、一貫性、ストーリー性のあるコミュニケーション施策を行っていくことが私たちのミッションです」(栗岩氏)
 アサヒビール株式会社 コミュニケーションデザイン部 担当副部長 栗岩洋平氏
アサヒビール株式会社 コミュニケーションデザイン部 担当副部長 栗岩洋平氏
アサヒビール株式会社はマーケティング施策の実行にあたって、テレビ広告予算をすべてデジタル広告とリテールメディアに振り向けた。ドラスティックな予算配分は奇策ではなく、「メディアニュートラルに考えて出した自然な結果」だという。
「アサヒスーパードライ」の広告には韓国の4人組ガールズグループ「BLACKPINK」を起用。黒岩氏は狙いを「若年層まで届ける新たな生活者コミュニケーションを実現し、態度変容、行動変容につなげることです」と語る。
アジア5か国で同時にリリースされた同広告は「BLACKPINK」ファンでの話題化から「同心円状に」20代、30代へと波及させるミッションを担っていた。「小回りの利く広告配信で新たなコンテンツを小出しにし、期待感を徐々に調整していくことがポイントでした」と、黒岩氏は運用を解説。商品の購入意向は他のクリエイティブと比べて10%以上伸長した。
AIと新機能が広告運用の諸工程を支援
イベントの終盤では、グーグル合同会社 代表 奥山真司氏が全体のラップアップをしつつYouTubeのアップデートを紹介した。「YouTubeというエコシステムは変化しています」と奥山氏は述べ、広告主の事業成長に貢献するYouTubeの「広さ」「深さ」「奥行き」を強調した。
アップデートについて奥山氏はクリエイター一覧から広告主がオファーなどを行える「クリエイターパートナーシップハブ」の日本語版リリースを目指していること、クリエイターのオーガニック投稿を企業が広告として運用できる「パートナーシップ広告」およびコネクテッドテレビでトップ画面に大きな広告枠を表示する「イマーシブマストヘッド」を紹介した。
AIは「試す段階」を終え、価値を創造するためのエンジンに
 グーグル合同会社 代表 奥山真司氏
グーグル合同会社 代表 奥山真司氏
奥山氏はAIの進歩と活用方法の紹介でイベントを締めくくった。「AIは『試す段階』を終え、価値を創造するためのエンジンになっています」と2025年の現状を述べた。同社のAIサービス「Gemini」は、生活者のクラスターごとにインサイトを与えることでマーケティングのターゲットを明らかにし、クリエイティブ面ではコンテンツ制作を後押しするという。
YouTubeは若年層のコンテンツプラットフォームとして、支配的な地位を守り続けている。それだけに広告の競合は多いが、商材と向き合い、クリエイターと相性の良い強みを発掘できれば、同予算でテレビCMにも劣らない広告効果を発揮することがある。事業者としては、無料で提供されているものも多いGoogleのサービスを使い倒してマーケティングを押し進めていきたいところだ。