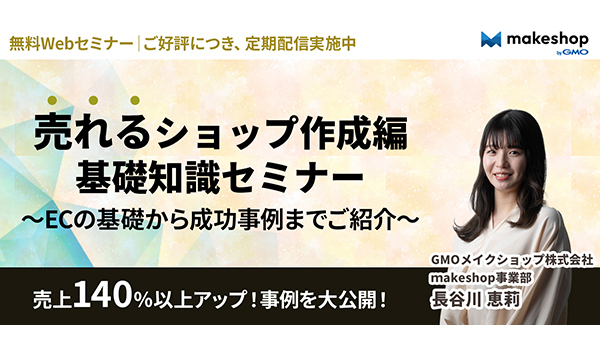ECサイトのKPIはどう設定する?設定の手順やポイントを事例とともに解説

ECサイトの運営において、目標を設定して定期的に振り返ることは必須です。そこで活用すべき指標がKPI(Key Performance Indicator)です。KPIは、目標値に対する達成度の評価だけでなく、あらゆる施策の効果を測定して目標達成までの近道を探るうえでも役立ちます。この記事では、KPIの概要や活用方法、KPIツリーの設計について解説します。
KPI(Key Performance Indicator)とは
KPIとは、Key Performance Indicatorの頭文字をとったマーケティング用語です。「重要業績評価指標」とも呼ばれており、最終的な目標に対して中間目標を意味しています。
KGIとKPIの違い
KGIとは、Key Goals Indicatorの略称です。「重要目標達成指標」とも呼ばれており、事業やプロジェクトの最終的なゴールを指しています。たとえば、年商や売上などをKGIに設定するのが一般的です。
KGIが最終的なゴールとして設定されるのに対して、KPIはKGIを達成するうえで必要となる要素が指標として設定されます。売上をKGIとする場合、KPIに設定する指標は、売上の構成要素である顧客数と顧客単価です。
また、顧客数の構成要素であるユニークユーザー数とコンバージョン率のように、ツリー状にしてKGIを達成するまでの構成要素を並べたものをKPIツリーとして作成するケースもあります。
ECサイトにおいてKPIが重視される理由
KPIはオンライン・オフラインを問わず活用すべき指標ではありますが、とくにECサイトにおいてはKPIによる管理が重視されています。オンラインにおいては、顧客行動をトラッキングしやすく、さまざまな指標をKPIに据えて分析できるためです。
たとえば、売上をKGIとして顧客数と顧客単価をKPIにする場合、顧客数を商品ページのセッション数とコンバージョン率に分けられ、商品ページのセッション数をサイト全体のセッション数と購入フォームへの遷移率に細分化できます。
さらにECサイト全体のセッション数をチャネルごとに分けて、広告経由や自然検索経由のようにツリー化すると、チャネルごとのセッション数をKPIとすることも可能です。個々のユーザーの流入からコンバージョンまでの行動を細かく分けられるため、ECサイトにおいてはKPIによる管理が効果を発揮しやすいといえるでしょう。
ECサイトにおいてKPIにすべき指標
前述のとおり、ECサイトにおいてPDCAを回すうえでは、KPIによる管理が非常に効果的です。しかし、具体的にどのような指標をKPIに設定すべきなのでしょうか。
以下では、ECサイトにおいてKPIにすべき指標について解説します。
訪問者数(セッション・ユニークユーザー)
訪問者数は、セッションとユニークユーザーのいずれかを指標として測定します。セッションはユーザーがECサイト内に流入した回数、ユニークユーザーはECサイト内に流入した人数を指しています。つまり、一人のユーザーが同じサイトに3回アクセスした場合、セッション数は3、ユニークユーザー数は1です。
ECサイトの場合、一人のユーザーが複数回購入するケースが考えられるため、セッション数を訪問者数として計測するケースが一般的です。一方、学習塾のように一人のユーザーが複数回コンバージョンしないビジネスモデルでは、ユニークユーザー数を訪問者数として計測します。
購入率(コンバージョン率)
購入率は、コンバージョン率とも呼ばれる指標です。ECサイトを訪れたユーザーのうち、商品の購入に至ったユーザーの割合を指しています。つまり、一定期間内に1,000回のセッションが記録されており、コンバージョン数が30の場合、購入率は3%となります。
購入率を改善させられると、流入数が同じであっても売上が向上するため、KPIのなかでも重要度の高い指標です。流入数を増やすには広告やSEOなどの方法がありますが、いずれも本格的に実施すると大きなコストがかかる施策です。
一方、購入率はランディングページや購入フォームの小さな変化などから改善できるケースもあり、積極的に取り組むべき部分といえるでしょう。
顧客単価
顧客単価は、購入一件あたりの平均単価を表す指標です。一度の購入で複数商品が売れた場合、合算した金額が顧客単価となります。
顧客単価を上げる施策としては、アップセルとクロスセルの2種類があります。アップセルはより金額の高い商品の購入、クロスセルはほかの商品との同時購入を促す施策です。
具体的には、商品ページに滞在するユーザーに対して上位商品のレコメンドを表示したり、特定の商品をカートに入れたユーザーに対して、ほかのユーザーが同時購入した商品のリストを出したりする方法があります。
LTV
LTVは、ライフタイムバリューや生涯顧客価値とも呼ばれる指標です。一人の顧客が生涯を通じて、どれくらい売上に貢献するかを表しています。顧客単価は短期的な売上を算出するのに適していますが、中長期的な売上を試算するにはLTVを含めて検討することが大切です。
たとえ顧客単価がそれほど高くなかったとしても、LTVの高いロイヤルカスタマーを育成できれば、将来的な集客コストの削減や売上の安定にもつながります。
リピート率
リピート率は、商品を購入した顧客のうち、過去にECサイトで商品を購入したことがある割合を表す指標です。一般的に新規顧客の獲得コストに比べて、リピーターの獲得コストは低いといわれており、集客コストを抑えて安定した売上をあげるにはリピート率の改善が必須です。
CPA(顧客獲得単価)
CPAは、顧客一人あたりを獲得するのにかかる単価です。集客コストとも言い換えられるため、CPAを低く抑えて顧客単価やリピート率を高められると、売上効率を改善できるでしょう。
また、CPAとよく似た指標としてCACがあります。CACはCustomer Acquisition Costとも呼ばれる指標です。CPAと同じく、顧客一人あたりの獲得単価を示すものではありますが、CPAがマーケティング施策ごとに算出されるのに対して、CACはあらゆるマーケティング施策を合算した指標となっています。
KPI設定に欠かせないKPIツリーとは
KPIツリーとは、KGIを最終的なゴールとして、構成要素となるKPIを図式化したものです。ロジックツリーのような構造になっており、KGI達成に向けたステップを一つずつ示しています。
KPIツリーを設定する理由
KGIを達成できれば業務上の目標を達成したことになりますが、ただやみくもにKGIを目指すのは現実的ではありません。KGIの構成要素となる指標をKPIツリー化して、KGI達成に向けたステップを明確化することで、各自が起こすべきアクションをイメージしやすくなります。
また、KPIツリーを設定する理由として、KGIを達成できなかったときに原因を明らかにできる点もあります。KGIの構成要素となるステップのうち、どの指標が未達だったのかを理解できれば、未達の原因を探って改善施策を検討可能です。
KPIツリーを設定する方法・手順
KPIツリーの重要性を理解していても、具体的な設定方法がわからなければ実際に活用することは難しいでしょう。しかし、KPIツリーの作成はそれほどたいへんな作業ではないうえ、マーケティングにおいては必須となるスキルです。
以下では、KPIツリーを設定する方法と手順について解説します。
KGI達成に向けた仮説をたてる
KPIツリーを作成する前に、KGIを達成するうえで仮説をたてます。KGIを売上とした場合に、新規顧客とリピーターに分ける方法もあれば、顧客数と顧客単価に分ける方法もあります。KPIツリーは仮説をもとに設定していくことが大切です。
KPIにすべき指標と目標値を決める
仮説をたてると、どのような指標をKPIに設定すべきかが明らかになります。また、最終目標であるKGI、KPIにすべき指標が決まれば、おのずとKPIの目標値も設定できます。
なお、目標値を設定する際は、KGIをもとに一つずつステップをさかのぼる形で検討するのがポイントです。
データを分析してPDCAを回す
KPIツリーの設定後は、データを分析してPDCAを回します。近年、KPIを用いてマーケティングを管理する企業が増えているものの、一部ではKPIの設定が目標になってしまっているケースもあります。
KPIは設定して終わりではなく、設定した数値に対する達成度を観測するとともに、達成・未達の要因を探ることが重要です。
KPIを設定する際のポイント
前述のとおり、KPIはECサイトの目標設定や効果測定において、重要な役割を担っています。そのため、適切な指標をKPIに据えて、KGIに対する達成度を定点観測することが大切です。
以下では、KPIを設定する際のポイントについて解説します。
SMARTを意識する
SMARTは、KPIを設定する際に意識すべきポイントの一つです。SMARTとは、以下の5つの単語の頭文字をとったものです。
●Specific(具体的な)
●Measurable(計測可能な)
●Achievable(達成可能な)
●Relevant(関連した)
●Time-bound(期限を定めた)
たとえば、KPIが具体性を欠いていたり、計測できなかったりと、上記の5つを満たしていない指標になっていると設定しても意味がありません。
カスタマージャーニーをもとに仮説をたてる
KPIは、コンバージョンに至るまでのカスタマージャーニーと連動しています。たとえば、興味や認知の段階からECサイトへの流入、サイト内の回遊を経て商品を購入というような流れです。カスタマージャーニーをもとに仮説をたてていかないと、KGIとKPIの関連性が薄くなってしまうおそれがあります。
KPIの数を増やしすぎない
前述のとおり、KPIはKGIを構成する要素です。しかし、細かな要素を一つひとつ洗い出していくと、きりがなくなってしまいます。また、KPIの数が増えるほど、一つの指標に対して向き合える時間は少なくなります。そのため、多くても3つから5つ程度になるよう取捨選択すべきでしょう。
ECサイトにおけるKPI設定の事例
KPIをたてるロジックや観測の方法自体は、業種によって大きく変わるものではありませんが、どのように改善につなげるかは企業ごとに異なります。KPIをうまく活用している大手各社では、ECサイトのKPIからどのような改善行動を起こしているのでしょうか。
以下では、セブンイレブンとAbercrombie & Fitchの事例をもとに、KPIの活用事例について紹介します。
【コンビニエンスストア】セブンイレブン
コンビニエンスストアのセブンイレブンでは、顧客データを活用しきれていない点が課題となっていました。
そこでKPIをダッシュボード上で管理してPDCAに注力しました。KPIの活用自体は以前からしていたものの、共通認識に落とし込めていない点や振り返りが甘い点などを改善すべく、ダッシュボード化して顧客データを活用しています。
【アパレル】Abercrombie & Fitch
アパレルブランドのAbercrombie & Fitchはオンライン・オフラインのショップを幅広く展開していましたが、事業が拡大するにつれて、一貫性をもってPDCAを回すことが難しくなっていました。最終的な目標値があっても、KGIに至るまでのKPIを丁寧に設定できておらず、遠回りしてしまう状態です。
そこで自社の顧客データをもとにKPIを設定して、仮説をもとにした改善アクションに取り組んでいます。その結果、複数のチャネルにおいて共通の目標をもって事業を推進できるようになっています。
まとめ
ECサイトの運営を成功させるには、KPIにもとづく管理や改善が重要です。しかし、最終的な目標となるKGIは設定していても、仮説をもとにKPIを設けてPDCAを回せている企業はそれほど多くありません。
また、KPIを設定する際はカスタマージャーニーを意識して、ロジックツリーを構築するのもポイントです。KPIをツリー状に図式化して管理することによって、自社のKGI達成に向けた課題点やボトルネックを明確化して、スムーズなPDCAの実行につながるでしょう。