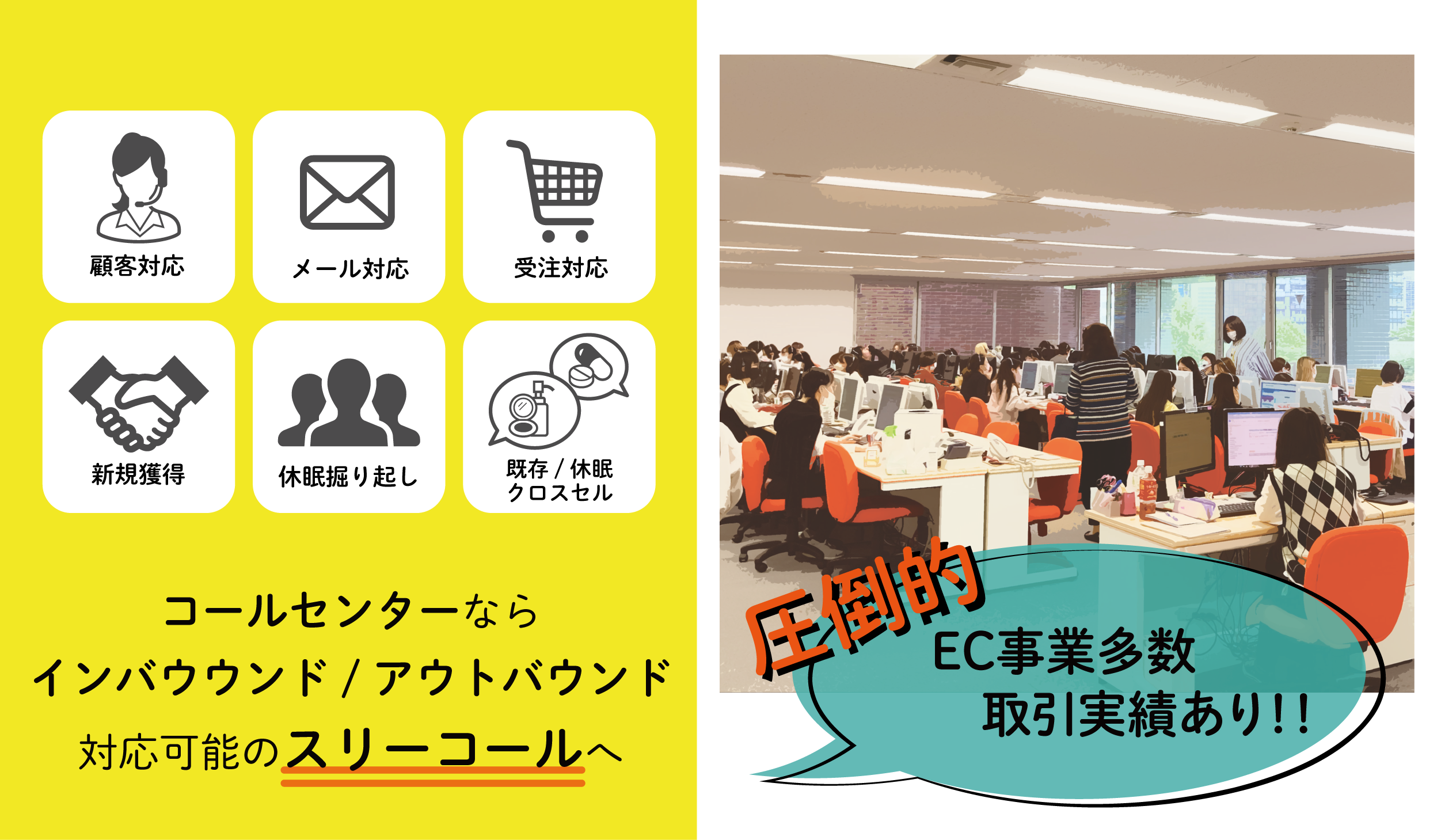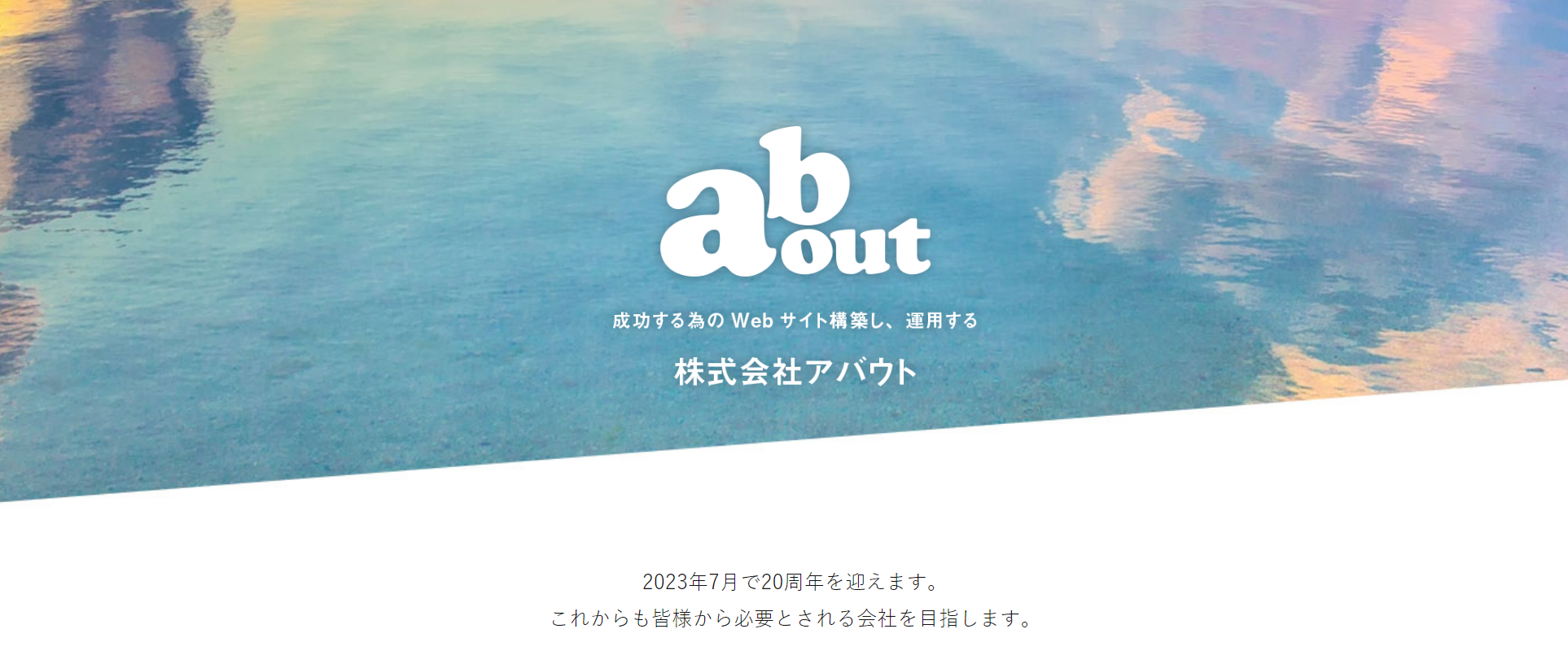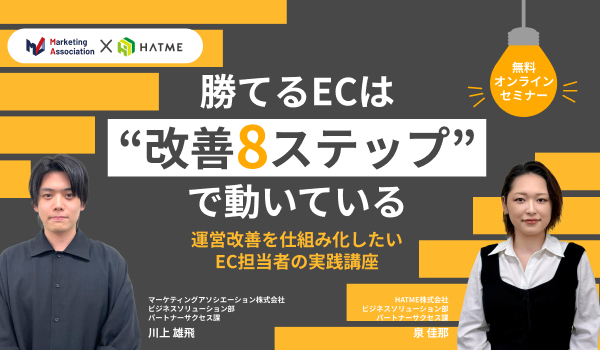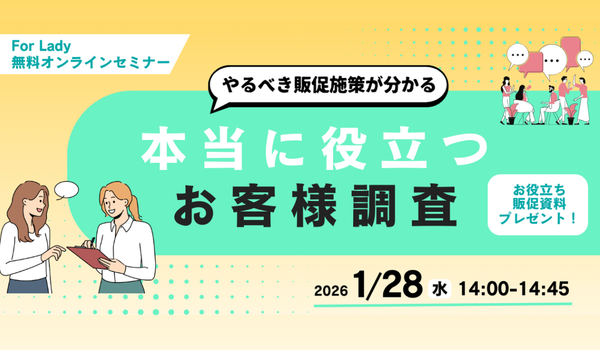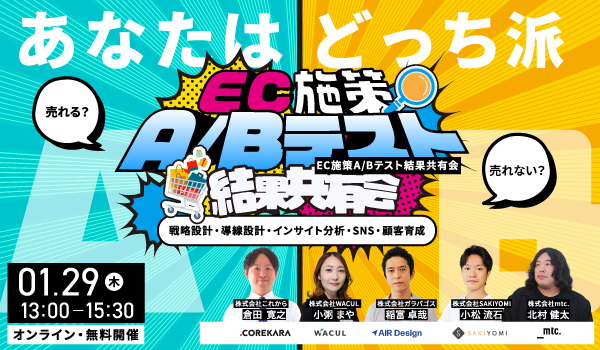飲食店がECを始める方法や運営ステップ。メリットや注意点を徹底解説

新型コロナウイルスの影響により、飲食店がECを始めるケースが増加傾向にある。一方で、注意点やEC展開する際のステップが分からずEC導入に躊躇している事業主もいるだろう。今回は、飲食店がECを展開するメリットや注意点、ECを始める方法を紹介する。最後に、飲食店がECを運営するまでのステップについても具体的に紹介するので、EC展開する際の参考にしてほしい。
目次
●飲食店がECを始めるメリット
●EC展開を検討する際の注意点
●飲食店がECを始めるための4つの方法
●飲食店がECサイトを運営するステップ
●まとめ
飲食店がECを始めるメリット
まずは、飲食店がECを始めるメリットについて確認していこう。
複数の収入源の確保
一番のメリットは、店舗営業だけでなく、EC販売を取り入れることで収入源が増え売上増加が期待できることだ。店舗運営の場合、天候による来店客数の増減や感染拡大を抑えるための人数制限などから、売上にバラつきが生じやすい。一方で、EC販売は天候や時間に制限がなく、いつでも注文してもらえることから、売上の安定化を図りやすいだろう。
時間の平準化
ECは、営業時間や来店者の人数に左右されることなく、均一に作業ができるといった時間の平準化もメリットの一つだ。飲食店の多くは、ランチとディナータイムがピークとなり忙しいが、ECはピークとなる時間がないため、店舗運営の空いている時間に作業を進めることが可能だ。時間と設備・人材を最大限に活用できるだろう。
商圏の拡大
さらに、店舗に限らず全国に向けて販売できることは、新たなファンの獲得につながることも大きなメリットだ。新規顧客の獲得で、売上向上はもちろん、プロモーションによってはこれまでとは異なる客層を獲得でき、商圏の拡大も期待できる。実店舗が地方であっても、ECでの集客に成功すれば知名度が上がり、新しい店舗を出店する際も、集客に困らないだろう。
EC展開を検討する際の注意点
ECを始めるメリットが大きい一方で、飲食店ならではの注意点があることも理解しておきたいポイントだ。EC展開を検討する際の注意点を確認していこう。
扱う食品に応じた許認可が必要
飲食店がECを始める場合、販売する食品や内容に応じては「営業許可書」と呼ばれる営業許可が必要となる。許可が必要なのに無許可で販売すると処罰の対象になるため、必ず確認しておきたい内容だ。なお、営業許可には、食品衛生法で定められたものと各都道府県の条例で定められているものがあるためそれぞれの内容を確認しておこう。すでに許可を受け飲食店で営業している場合でも、店舗販売と同じようにECで販売できないケースがあるため、確認は必須だ。
例えば、店舗で提供している商品を缶詰や瓶詰にして新たに製造する場合は「密封包装食品製造業」、製造した食品を冷凍して発送する場合は「冷凍食品製造業」というように、新たに営業許可が必要になる。EC展開を進める場合、個々の営業方法に応じて必要な許可が異なるケースが考えられるため、必ず管轄の保健所に相談することをおすすめする。
食品ラベル等の添付
ECで食品を販売する場合、「食品表示法」により食品表示ラベルを貼付する必要があることも忘れてはならない。また、店舗と異なり顧客が口にするまで日数が経過する場合は、消費期限や賞味期限を設定する必要もあるため注意が必要だ。食品表示ラベルは詳しい業者へ、消費期限・賞味期限は、生菌検査を行う外部機関へ依頼して、消費者の食の安全を確保する対応を意識していきたい。
EC販売導入へのコスト
EC販売導入時は、店舗運営とは異なる費用が、製造時から顧客の手元に届くまで発生するため注意が必要だ。飲食店の設備によっては、ECで販売するにあたり真空パックの機械を導入する事業者が増えている。他にも、食品の特性に応じた梱包材や配送料など、EC展開に向け発生する費用の全容をきちんと把握した上での検討が重要だ。
飲食店がECを始めるための4つの方法
ここからは、飲食店がECを始めるための4つの方法を紹介する。なお、前半に紹介するデリバリーは、厳密に言うとECサイトとは異なるがインターネットを利用したサービスとなるため、併せて解説していく。
デリバリーサービスへの登録
自社でECサイトを始めるには、時間や専用のノウハウも必要となる。そのため、まずは「デリバリー」に力を入れていきたいという場合は、デリバリーサービスへの登録という方法がある。「Ube Eats」や「出前館」といったデリバリー専用のサービスは、集客力があり運営側で事前決済まで対応してくれるため、自社の労力を減らしながら収入源を増やす効果が期待できる。サービス利用料が発生するが、温かいうちに食べてもらいたいお弁当や中華、ファーストフードなどは加工の手間も省けるためおすすめだ。なお、飲食店で調理した料理をデリバリーで販売する場合は、新たな許可などは必要ない。
オンライン決済機能を活用したデリバリーの実施
自社でデリバリーを展開しており、その際の決済をスムーズにしたい場合は、オンライン決済機能の活用がおすすめだ。自社で導入しているスマホ決済端末が「STORESターミナル」や「スクエア」などであれば、オンライン決済の実施が可能だ。自社専用の決済用ページを作成し、顧客へのメールやLINEなどでURLを送付すれば、事前決済が実現できる。ECサイトや自社のホームページがない場合でも利用でき、決済手数料も安価なため、最も手軽に自社で始められる方法といえる。
ECモールへの出店
自社で扱う商品が配送できる食品であれば、Amazonや楽天市場などのECモールへ出店する方法もある。商品の掲載から決済に至るまで、モール側が提供するシステムを利用できるため、ECサイト構築から運営までの手間を省くことが可能だ。ECモールは集客力が高く、サイトへの信頼性も高いため、購入につながりやすいといった特徴がある。「お菓子にメッセージを加えられる」「ドリンクにオリジナルのラベルを貼れる」など、競争企業と差別化を図れるような取り組みがあると、顧客獲得に役立つだろう。
ECサービスを利用した自社サイトの開設
「手軽に自分のお店を持ちたい」「全国に向けて商品を販売したい」といった場合、「ASP」と呼ばれるクラウド上で提供されたEC構築サービスを利用してネットショップを開設する方法がある。利用するサービスに応じて、初期費用や月額費用、決済手数料が発生するが、初心者でも簡単に自社サイトを開設し運営が可能だ。代表的なサービスに「STORES」や「BASE」というECサービスがある。「無添加の食材を使用した焼き菓子」や「独自手法のお酒」といった食品は、オリジナリティを打ち出しやすいECサービスを活用した自社サイトでの販売がおすすめだ。
飲食店がECサイトを運営するステップ
最後に、飲食店がECサイトを運営して食品を販売するステップを紹介する。
保健所に相談をする
どのような食品を扱うのかある程度決まってきた場合は、まず管轄の保健所に相談してみるところからスタートしよう。前述したように、扱う食品や提供方法によって必要な許可や食品表示ラベル等が必要となるため、どのような対応が必要になるのかを前もって相談しておくのが得策だ。製造業系の許認可が必要な場合は、飲食店の設備だけでは対応できず追加設備や工事が必要になるケースもあるため、自社の設備関係も踏まえた上で相談できるとよいだろう。
出店方法を決定し商品を作る
保健所の許可の取得が完了したら、出店方法を決定し商品を製造していく。食品をECサイトで販売する場合は、食品表示ラベルの作成が必要となるため、記載ルールの確認も大切だ。食品表示ラベルには食品成分や消費期限、賞味期限などを記載していくため、専門機関に依頼しよう。なお、ECサイトで食品を配送して販売する場合、真空梱包機を活用することで、食品の保存期間を長く保ち、味や香り食感なども長持ちできるためおすすめだ。クオリティが高い食材を提供したい場合には、導入を検討してみるのもよいだろう。
出店方法に応じた商品登録を行う
商品を出店する際、商品登録時の料理や食品の写真はとても重要だ。顧客の興味や食欲をそそるような写真を複数掲載し、購買意欲を高めることができるだろう。その際、おしゃれに撮影することだけでなく、どのくらいの大きさなのか、どのくらいの量が入っているのか、購入する側が知りたい情報を意識した写真を掲載することがポイントだ。また、商品の情報も、明確に記載しておくことで購入判断がしやすくなるだろう。
ECサイトができたことを告知する
最後は、ECサイトができたことを、自社のホームページやSNSを活用して告知をしていく。顧客リストがある場合は、メールやLINEなどでの告知も有効的だ。SEO対策を行い、ネット検索の際に上位に入るよう対策を行い、訪問者を増やす方法もある。
まとめ
飲食店がECを始めるメリットは大きく、今後は実店舗とオンラインの2つの軸で経営していく企業も増加していくと考えられている。ECを活用した運営方法はいくつかあるが、デリバリー以外で販売する場合は、許認可や必要な対応があるため注意が必要だ。自社の扱う食品に適したEC展開を検討してみてはいかがだろうか。
EC専門の委託先選定はECのミカタへ
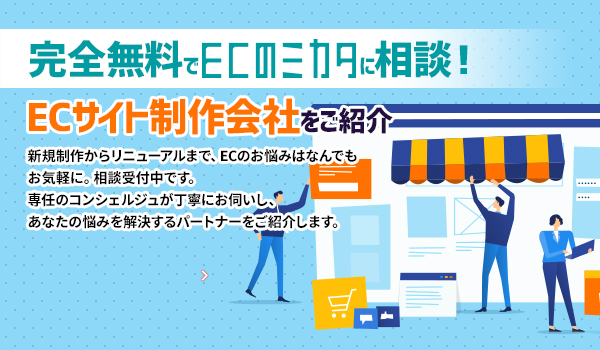
ECのミカタが運営するマッチングサービスです。ECサイトに特化したメディアを運営する専門コンシェルジュが、丁寧なヒアリングを行った上で、最適な企業をご紹介します。
そのため業務の知識が全くなくても、マッチ度の高いパートナーさんと出会うことが可能です。希望する会社が決定すれば、最短1営業日で企業との商談のセッティングを行います。商談日や商談方法だけでなく、断りの依頼も全てコンシェルジュに任せることができるため、じっくり選定に時間をかけることが可能です。