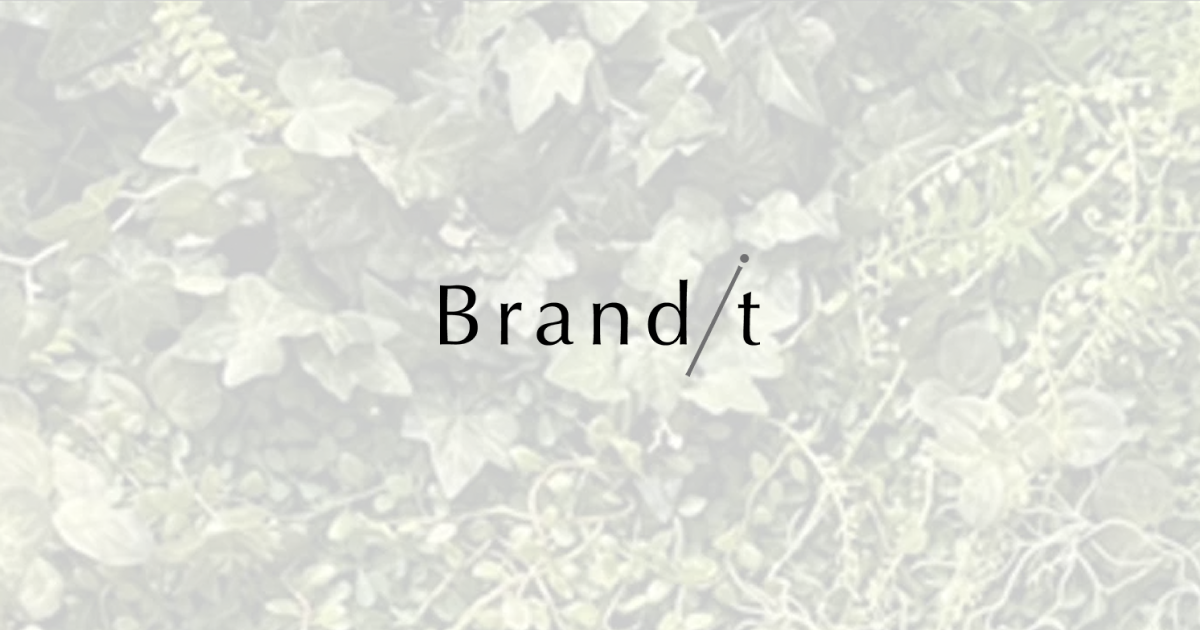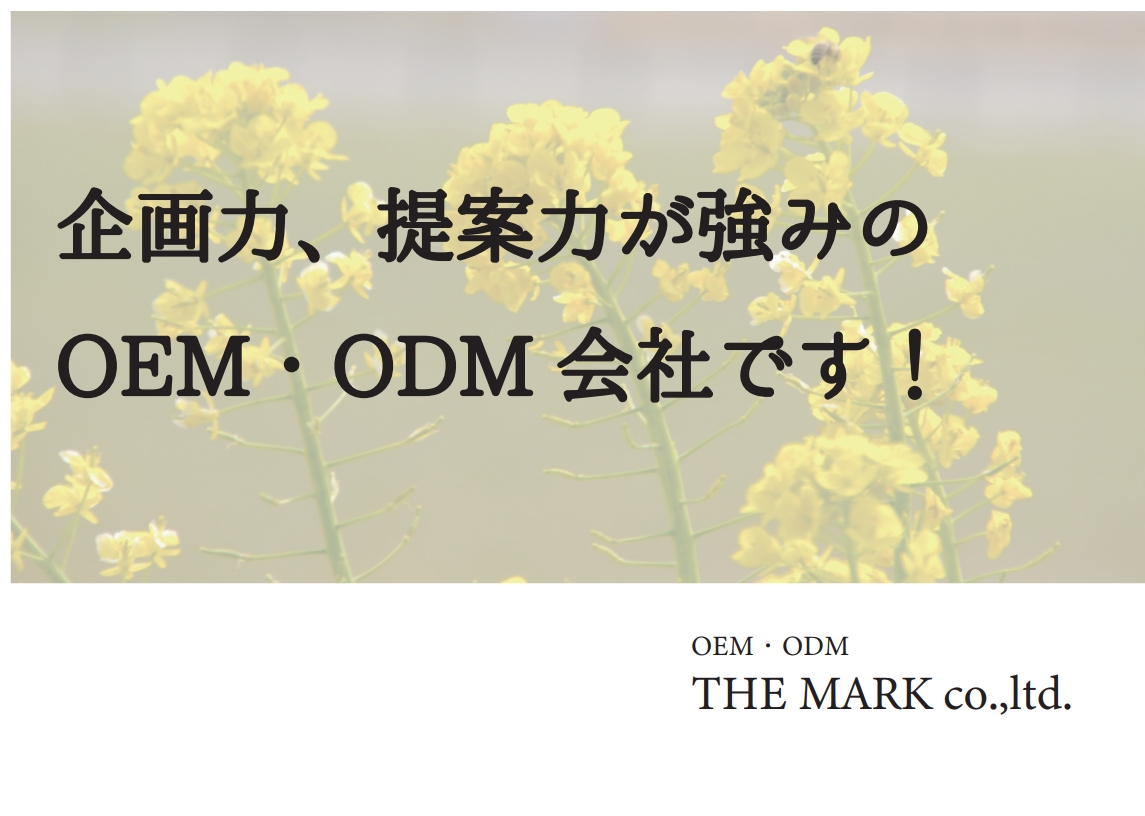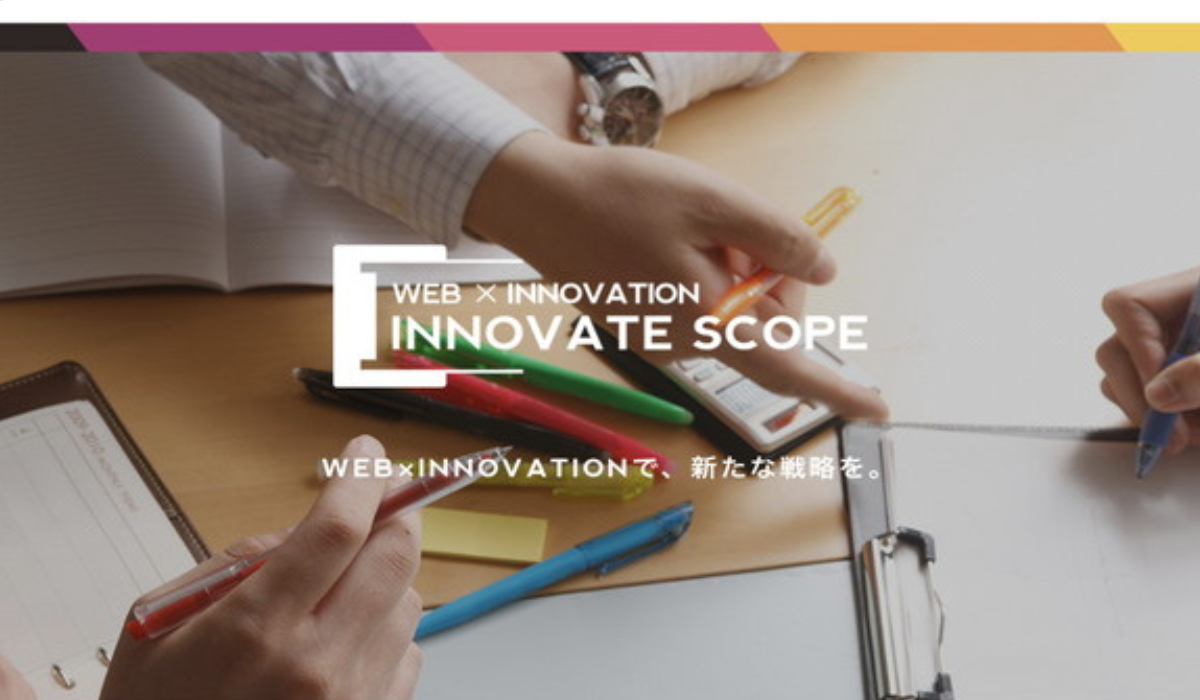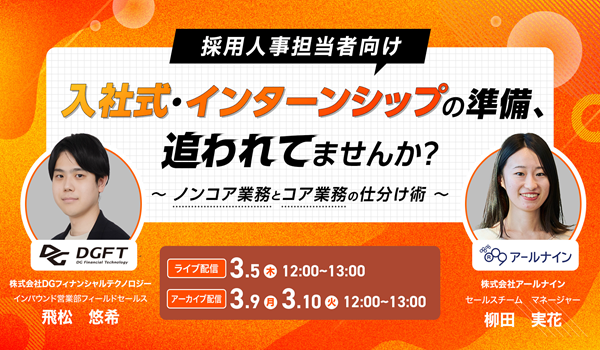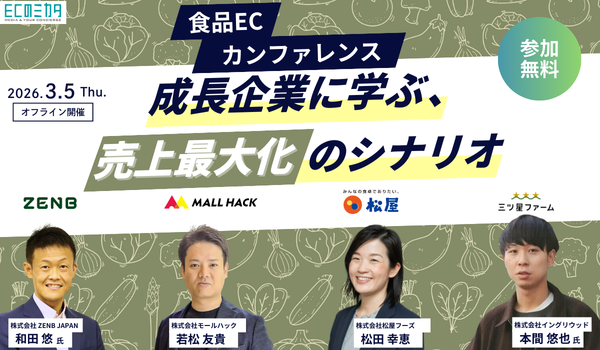温度帯変更も流通加工も、EC特化だからここまでできる! 食品ECを加速させる冷凍冷蔵倉庫「大阪コールドセンター」へ
 株式会社スクロール360 西日本営業ユニット長 小林尭哉氏
株式会社スクロール360 西日本営業ユニット長 小林尭哉氏
食品ECマーケットがコロナ禍での急伸を経て緩やかな成長を続ける中、株式会社スクロール360が食品EC物流への支援体制を強化している。“次世代CRM物流”を掲げ、物流代行をメインにEC・通販に関わるさまざまなソリューションを提供する同社は、2024年12月、大阪・舞洲に冷凍冷蔵倉庫「大阪コールドセンター」を開設。EC物流のエキスパートである同社ならではの対応力を武器に2025年6月には保管スペースを拡大し、その設備と機能をさらに充実させている。
そこで今回は、スクロール360としての新たな食品EC拠点となる「大阪コールドセンター」について、同社 西日本営業ユニット長の小林尭哉氏に話を聞いた。
食品ECに「効く」冷凍冷蔵倉庫
──まずは貴社の事業概要と、「大阪コールドセンター」を開設した経緯・狙いについて聞かせてください。
スクロール360は物流代行のほか、マーケティング、受注代行、決済代行といったサービスでEC事業者様をワンストップで支援しており、現在はそこから深掘りしてBtoB事業や冷凍冷蔵倉庫に領域を拡大しています。もともと親会社である株式会社スクロールの通販部門から出発した会社ですので、他の物流会社様と比較して、事業者としての視点やノウハウを持ち合わせたサービスを提供できることが強みです。
昨年12月に開設した「大阪コールドセンター」は、北海道の「石狩センター」、静岡県の「東海コールドセンター」、関東エリアの「東京・千葉コールドセンター」に続く食品ECの新しい拠点です。温度帯変更を含め、食品ECのためのよりきめ細かいサービスを提供したいと考える中で今回、当社の持つECのノウハウを活かせる施設・環境が整い、「大阪コールドセンター」の開設に至りました。
──食品ECにおける冷凍冷蔵倉庫の重要性について教えてください。
日本の食品ECマーケットは拡大していますが、成功している会社と苦戦している会社で二極化してきているように思います。冷凍物流はまだまだ細やかな対応が行き届いていないケースが見られ、保管・ピッキング・出荷といった物流の基本的な工程をしっかりと行えるか、さらにフローズンチルド食品の保存温度帯変更、ギフト対応や販促物同梱などのユーザーニーズに応えられるのかといった、物流の「品質」の部分で差が出てくると考えています。
また、保存温度帯変更に関して言えば、ずっと冷蔵保存しているよりも賞味期限は長くなるというメリットがあります。食品の品質・おいしさという観点でも、冷凍からいきなりご家庭の電子レンジで温めるよりも、冷蔵に解凍されたものをチルドで配送して温めるほうが味が落ちにくい食品もあるでしょう。こうしたことから、冷凍冷蔵倉庫のニーズは今後も高まっていくと考えています。
──温度帯変更によって賞味期限をコントロールできるのは、食品EC事業者にとって大きなポイントになりますね。
一番のメリットは在庫のバッファが持てる点です。冷蔵では食品工場から出た瞬間から賞味期限へのカウントダウンが始まりますが、冷凍で保管することでその期間を長くとれるわけです。在庫管理の面でこのバッファを持てるのは大きいと思います。せっかく商品を作っても賞味期限切れで廃棄となってしまってはコストの無駄遣いとなりますし、賞味期限を気にして生産数を抑えたとしても在庫切れで販売できなければ機会損失となってしまいます。
──そうした温度帯変更のニーズが高い、相性の良い食品には、どのようなものがありますか。
「多く作って在庫として保管しておきたいけれど、品質は落としたくない」商品と相性が良いと考えています。冷凍冷蔵機能は、「販売数の見通しが立ちにくい状況でも、品質を担保しつつ保管しておきたい」という事業者の課題解決につながるでしょう。
具体的には総菜やスイーツ、宅食などが挙げられます。「大阪コールドセンター」では、冷凍で保管していたものと初めから冷蔵のものをセットにした宅食でも、冷凍のものだけを解凍し、お客様には全てをチルド状態で配達するといったことにも対応しています。

 「大阪コールドセンター」内での作業風景
「大阪コールドセンター」内での作業風景
拡大する食品ECの新たな拠点「大阪コールドセンター」
──そうした冷凍冷蔵倉庫を、今回大阪に開設された理由を教えてください。
大阪のクライアント企業様から、自分たちのマーケットに近い場所に拠点を置きたいという声があったんです。お客様からすると、倉庫が近くにあればすぐに商品の状態を確認でき、安心感も生まれます。食品ですので、配送を考慮してもより近くが望ましい。当社としても大阪は東京に次ぐ大きなマーケットだと捉えており、そこに拠点を構えることは重要でした。
──「大阪コールドセンター」の施設としての特徴をお聞かせください。
広さは6月から区画が増えて冷凍エリアが1000坪、冷蔵エリアが400坪の規模となります。専従スタッフは20名ほどで、ECで培ってきたノウハウを活かしながら運営しています。
最大の特徴は、先ほどもお伝えした温度帯を管理・変更できることです。関西で「ECの冷凍冷蔵」に対応できている倉庫はなかなかないので、そこをしっかりとやり切れるのは強みだと考えています。港湾地区の冷凍冷蔵倉庫は基本的にBtoBで、パレット単位でコンテナに積み込んでトラックで出荷するといった形態が多いのですが、当社ではそこにECのノウハウを融合して、月に1万件以上の食品を出荷することも可能です。
──温度帯管理に加えて、EC・通販に特化しているからこそ提供できる御社のサービスについてもお聞かせください。
例えば、顧客データと連携したOne to Oneマーケティングを提供しています。購入者属性ごとに異なる販促物や試供品を同梱する複雑な個別対応も行っており、当社の「関西物流センター」にあるオンデマンドプリンターはバリアブル印刷(※1)に対応しているので、今後いろいろなサービスに応用できると考えています。
──お客様一人ひとりに個別で対応できるのはCRMとしても有効ですね。同じく「大阪コールドセンター」ならではの、オペレーションや対応についてご紹介ください。
「大阪コールドセンター」では、温度帯変更に伴う賞味期限の貼り付け作業を行っています。基本的に冷凍の商品はチルド(冷蔵)に切り変える時点で賞味期限が決まるため、例えば冷凍保管していた商品を冷蔵で2日間寝かせる場合は、冷蔵に変えたタイミングで賞味期限のラベルを貼り付けます。解凍後の賞味期限は商品ごとに異なるため、個別の対応が欠かせません。
──現在実施している品質向上への取り組みについてお聞かせください。
お客様がより安心して利用できるように、HACCP(ハサップ ※2)への対応をさらに進めていくことです。もちろんすでに温度帯変更を行うために必要な基準などは達成していますが、さらにブラッシュアップして環境を整えることに取り組んでいます。
また、日々の「5S」も徹底し、作業現場の品質と生産性の向上を目指しています。将来的には、当社の他の物流センターで実施しているような、EC事業者様に向けた倉庫見学会も開催したいですね。

 「大阪コールドセンター」内
「大阪コールドセンター」内
需要高まる冷凍冷蔵物流を幅広い展開を目指す
──物流市場における冷凍冷蔵倉庫の今後について、どのように捉えていらっしゃいますか。
冷凍冷蔵技術は今後も発展していくことに加え、冷凍食品の流通はさらに増加すると考えています。
さまざまな事業者が市場に参入する可能性がある中、ECで冷凍冷蔵商品を販売していくためには、商品の魅力だけではない独自の価値やサービスを提供することが重要です。当社としても、単に物流機能を提供するだけでなく、EC事業者様の事業成長とブランド価値向上に貢献できるよう、グループ全体の力を活かしながら支援をしていきたいと考えています。
──「大阪コールドセンター」としての展望もお聞かせください。
今後は、宅食などの取引実績を横展開して、生産性を高めていくことを考えています。また、すでに協力会社様と連携してインターネットカフェや百貨店への配送を実現していますが、共同配送ができるようになれば時間やコスト面を抑えながらサービスを提供できます。将来的には「『総合物流』のできる大阪コールドセンター」を目指したいです。
全社的な展開としては、冷凍冷蔵機能を持った拠点を増やしていく方針です。関西にとどまらず、ニーズに応じてさらに西のエリアへの展開も検討していきます。当社には外部アセットを活用した物流構築の実績もあるので、お客様の拠点から離れていても、最適なソリューションを提案できるよう取り組んでいきます。
※1:データを基に顧客一人ひとりに異なる内容を印刷すること。納品書へのバリアブル印刷は販促チラシよりもリピート促進効果が高いと言われている(スクロール360「360通販note」より)
※2:HACCP=Hazard Analysis and Critical Control Pointの略で、「危害要因分析・重要管理点」と訳される(参考:厚生労働省)
 「大阪コールドセンター」内
「大阪コールドセンター」内
 「大阪コールドセンター」の拡張エリア
「大阪コールドセンター」の拡張エリア