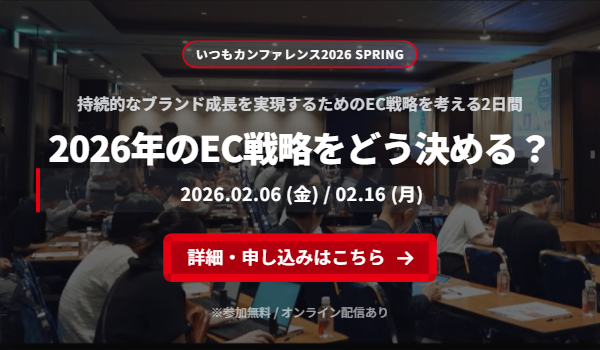ソーシャルコマースとは。EC事業者が取り組むメリットや成功事例を紹介

ソーシャルコマースは、SNSを活用して、商品やサービスの発見から購入までをシームレスに完結させる新しい販売手法として注目を集めています。
本記事では、ソーシャルコマースの基本から具体的な活用事例まで、ECサイト運営に役立つ情報を紹介します。
ソーシャルコマースとは
ソーシャルコマースは、SNSと購買を組み合わせた新しい販売形態です。
従来のECサイトでは、ユーザーが目的の商品を探し出して購入するという流れが主流でした。一方で、ソーシャルコマースは、SNSを閲覧する中で偶然に商品と出会い、興味を持った瞬間に購入まで進むという、より直感的で自然な購買体験をユーザーに提供します。
また、インフルエンサーや一般ユーザーによる投稿が話題になることで商品の認知度が急速に広がる「バズ効果」も大きな特徴です。
ソーシャルコマースの市場規模
ソーシャルコマースの市場規模は急速に拡大しており、2023年には6,721億1,000万ドルに達し、2024年には7,738億4,000万ドルに達すると予測されています。
この成長は、年平均成長率(CAGR)15.1%という急成長を遂げており、今後も拡大が期待されています。
日本国内でも、ソーシャルコマースの影響力は増しています。Glossom株式会社の「ソーシャルコマースに関する定点調査2022」によれば、商品・サービスの購入時にSNSを情報源とする割合が若年層で特に高く、10代女性では80%を超えると報告されています。
また、SNSを通じて商品を知るきっかけとなる商材として、「衣服・ファッション」や「化粧品」が高い割合を占めており、これらの分野でのソーシャルコマースの影響は特に顕著です。
さらに、インフルエンサーの影響力も無視できません。同調査では、商品購入時にインフルエンサーを参考にする割合が前年より増加し、特に「衣服・ファッション」や「化粧品」分野で高い傾向が見られます。
今後も市場の拡大とともに、その影響力はさらに強まると考えられます。
参考:
Social Commerce - Global Strategic Business Report|RESERACH AND MARKETS
【ソーシャルコマースに関する定点調査2022】|Glossom株式会社
海外と日本におけるソーシャルコマースの違い
海外、特に中国ではソーシャルコマースが一般的な購買手段として定着しています。TikTokの中国版である抖音(ドウイン)では、ライブ配信を通じた商品販売が日常的に行われ、多くの視聴者がリアルタイムで商品を購入しています。
一方、日本のソーシャルコマースは発展段階です。InstagramやLINEでの買い物機能は充実してきましたが、ライブコマースは海外諸国ほど盛んではありません。
日本の特徴として、企業が消費者に販売するB2C取引が中心であり、消費者同士の取引であるC2C取引は、中国など海外市場と比べて活発とはいえません。
こうした違いの背景には、各国の消費者特性が関係しています。日本の消費者は商品の品質や信頼性を重視する傾向が強く、企業からの直接購入を好む傾向にあります。一方、中国では価格や利便性を重視し、個人間取引にも抵抗が少ないという特徴があります。
ソーシャルコマースの今後
ソーシャルコマースは進化を続けています。
AIを活用した商品レコメンデーションやAR/VR技術による仮想試着など、より魅力的な購買体験の提供が可能になってきました。
特に注目されているのが、インフルエンサーによるライブコマースです。商品の詳しい説明を視聴者とコミュニケーションをとりながら行えるため、購入前の不安を解消できます。実際の店舗での接客に近い体験ができることから、今後さらなる普及が期待されています。
日本市場においても、Instagramショッピングの利用者は増加傾向にあり、若い世代を中心に新しい購買スタイルとして定着しつつあります。
ECサイト運営者にとって、ソーシャルコマースは今後重要な販売チャネルになっていくでしょう。
ソーシャルコマースの種類
ソーシャルコマースの形態は、販売方法や特徴によって7つの種類に分類されます。企業は自社の商品やターゲット層に合わせて、最適な形態を選択することが重要です。
それぞれ解説します。
C2C型
C2C型のソーシャルコマースは、フリマアプリに代表される個人間の売買取引です。
メルカリやラクマなどのプラットフォームでは、出品者が使わなくなった洋服やゲーム、本などを手軽に販売でき、購入者は商品の状態を実際の使用者から確認できます。
SNS・ソーシャルメディア型
SNS・ソーシャルメディア型のソーシャルコマースは、日常的なSNS利用の中で商品との出会いを創出する販売形態です。代表例のInstagramショップでは、企業が投稿写真やストーリーズに商品タグを付けることで、ユーザーは気になった商品をすぐに購入できます。
販売商品としては、ファッションやコスメなど、ビジュアル訴求が重要な商品との相性が特に良く、インフルエンサーを活用したプロモーションも効果的です。
ライブコマース型
ライブコマース型のソーシャルコマースは、商品の魅力をライブ配信で伝える販売手法です。
配信者が商品の特徴や使用方法を実演しながら紹介し、視聴者はリアルタイムで質問やコメントができます。化粧品やファッションアイテムなど、実際の使用シーンを見せることが重要な商品で高い効果を発揮します。
特に中国市場では、TikTokの中国版「抖音」を中心に普及が進んでいます。インフルエンサーによる商品紹介は高い購買率を記録し、若い世代からの支持を集めています。日本国内でも、アパレルブランドのZOZOTOWNがスタイリストによるコーディネート提案を実施するなど、導入企業が増えています。
あわせて読みたい:
ライブコマースとは?市場規模や日本での成功事例なども解説
グループ購入型
グループ購入型のソーシャルコマースは、購入者が増えるほど商品価格が下がる、ソーシャルな要素を活用した販売形態です。
代表例の中国Pinduoduoでは、友人を誘って商品を購入すると割引が適用される「お友達割引」や、SNSでシェアすることで価格が下がる「シェア割引」などの機能を提供しています。
日用品や食品など、リピート購入が見込める商品カテゴリーとの相性が良く、まとめ買いによる物流コストの削減も実現できます。購入者にとってはお得に商品が手に入り、企業側は効率的な販売が可能になるという、双方にメリットのある仕組みといえるでしょう。
一方で、割引価格を設定するため利益率が低下しやすく、大量購入による在庫管理の調整が必要になります。
レコメンド型
レコメンド型のソーシャルコマースは、AIがユーザーの購買履歴やブラウジング履歴を分析し、ユーザーの好みに合った商品を提案する販売形態です。
もっとも身近な例として、Amazonの「この商品を見た人はこんな商品も見ています」機能が挙げられます。近年では、SNSでの「いいね」や閲覧履歴も分析対象となり、提案精度が向上しています。
ユーザーキュレーション型
ユーザーキュレーション型のソーシャルコマースは、商品選びのプロセスをユーザー同士で共有する販売形態です。
代表的なプラットフォームのPinterestでは、ユーザーが気に入った商品をボードにピン留めして共有でき、同じ趣味や好みを持つユーザー同士での商品発見を促進しています。
ファッション分野における活用事例として、LOCARIのプラットフォームがあります。ここでは、ユーザーが自身のコーディネートを投稿し、使用アイテムにリンクを付ける仕組みが定着しています。実際の着用イメージや組み合わせ方がわかりやすく、購入検討の参考になります。
ユーザー参加型
ユーザー参加型のソーシャルコマースは、商品開発やマーケティングにユーザーを巻き込む販売形態です。
先進的な事例として、無印良品のMUJI Labでは、商品開発の過程でユーザーの意見を積極的に取り入れ、市場ニーズに合った商品を生み出しています。
また、注目すべきプラットフォームとして、クラウドファンディングのMakuakeがあります。ここでは、ユーザーが商品のアイデアや開発費用を支援し、完成品を先行購入できる仕組みを提供しています。開発段階からの参加により、商品への強い愛着が生まれ、SNSでの情報拡散も活発に行われています。
ソーシャルコマースのプラットフォーム
企業がソーシャルコマースに取り組む際は、各プラットフォームの特徴を理解し、自社の商品やターゲット層に合わせて選択することが大切です。
ここでは、主要なプラットフォームの機能や特徴を詳しく解説していきます。
Instagramは、SNSを活用したソーシャルコマースを代表するプラットフォームです。投稿やストーリーズに商品タグを付けることで、ユーザーが直接購入ページにアクセスできる仕組みが整っています。
ビジネスアカウントを活用すれば、商品カタログの作成が可能です。企業は、投稿やストーリーズに商品をタグ付けして詳細な情報を届けたり、リール機能を使って短時間で商品PR動画を配信したりできます。
特にファッションやコスメ、雑貨など、ビジュアルの魅力が重要な商品カテゴリーでは、Instagramの効果が期待できます。
さらに、2023年にはライブショッピング機能が加わり、インフルエンサーとのコラボレーションを通じた販売が活発化しています。
あわせて読みたい:
インスタ(Instagram)のショッピング機能とは?開設・設定方法を解説
Facebookは、SNSとレコメンド機能を組み合わせたプラットフォームです。豊富な利用者データを活用し、広告を通じて効果的に商品を訴求できるのが特徴です。
利用者の年齢層は30代以上が多く、特に40代以上のユーザーが多い点がほかのSNSとは異なります。広告配信では、年齢や性別、興味関心など細かな条件を設定できるため、ターゲットに合わせたアプローチが可能です。
Facebookショップでは、商品カタログの作成、在庫管理、決済といった販売に必要な機能がすべて揃っています。
なお、InstagramとFacebookを連携すれば、広告配信やデータ分析がより効率的に行えます。Instagramで投稿した商品情報をFacebook広告に流用できるため、両プラットフォームの異なるユーザー層にリーチできます。
あわせて読みたい:
Facebookショップとは? 基礎知識からメリット、運用の注意点を解説
TikTok
TikTokは、短時間の動画投稿を中心としたプラットフォームで、ライブコマースとSNSの両方の特徴を持っています。特にZ世代(10代〜20代)からの支持が高い一方で、近年では30代〜40代以上の中年齢層の利用者も増加しており、多世代にわたるプラットフォームとしての広がりを見せています。
動画投稿では、商品の使い方や効果を15秒から60秒の短い映像で紹介できます。音楽やエフェクトを組み合わせることで、商品の印象をわかりやすく伝えられます。
また、TikTokは若年層に人気のファッション、コスメだけでなく、健康やウェルネス関連の商材とも高い親和性を持っています。
中年齢層以上の利用者は、健康意識の高さやライフスタイルの質を向上させたいというニーズが強く、こうした分野の商品がトレンド化するケースも増えています。例えば、短いエクササイズ動画や、健康的な食事のレシピを紹介するコンテンツなどです。
さらに、「TikTok Shop」機能を利用することで、動画内で商品にタグを付けたり、ライブコマースを通じてリアルタイムで商品を販売したりすることができます。
Pinterestは、ユーザーが写真や画像を「ピン」として保存し、自分の興味やテーマごとに整理できるビジュアル重視のプラットフォームです。この「ピン」を使ってアイデアを集められるのが大きな特徴です。
多くのユーザーが、商品を購入する前の検討段階でPinterestを利用しています。そのため、DIY、インテリア、ファッション、レシピなど、見た目の魅力が重要な商品ジャンルとは相性が良いプラットフォームです。
さらに、Pinterestでは、商品のアイデア探しから実際の購入までがスムーズにつながる仕組みが整っています。そのため、ユーザーは自然な流れで購買まで進むことができます。
X(旧Twitter)
Xは、情報のリアルタイム性が特徴のプラットフォームです。タイムセールや期間限定のキャンペーン情報を素早く届ける等に適しています。
また、投稿が「バズる」ことで爆発的に拡散される可能性がある点も特徴的でしょう。例えば、商品を紹介する投稿が話題になれば、短時間で多くの人の目に触れます。これにより、広告費をかけずに自然な形で商品の認知度が向上するほか、フォロワー数の増加やリピート購入の促進といった長期的なメリットも期待できます。
プロフィール画面にある「ショップタブ」では、商品を直接販売できます。また、投稿に商品タグを付けることで、簡単に商品詳細ページへユーザーを誘導できます。
さらに、企業とユーザーが直接やり取りできるのもXの強みです。商品に関する質問に答えたり、要望を聞いたりすることで、顧客との信頼関係を築きやすくなります。
LINE
LINEは、メッセージアプリを基盤とした独自のサービスを展開するプラットフォームです。企業は公式アカウントを活用して、直接ユーザーに情報を届けることができ、特にメッセージの開封率が高いのが特徴です。
LINE公式アカウントでは、クーポンの配布や商品の案内、セール情報を手軽に配信できます。また、顧客のセグメントを細かく設定し、特性に合わせた個別のコミュニケーションを行えます。事前にシナリオを設計することで、効率的かつ一貫性のある顧客対応を管理できる点も大きな魅力です。
ショッピング機能を使えば、複数のECサイトの商品を1度に検索・購入することが可能です。さらに、LINEギフトは、友人や家族に商品を簡単にプレゼントできる便利な機能として多くの人に利用されています。
LINEは国内でインフラ化したコミュニケーションツールであり、多くのユーザーが利用しているため、企業が配信した情報が目に留まりやすいという利点もあります。
あわせて読みたい:
ECサイトのLINE活用方法まとめ。公式アカウントやショッピング機能について解説
Amazon
Amazonは、幅広い商品ラインナップと便利な配送サービスを特徴とする大手ECプラットフォームです。特に、個々のユーザーに合った商品を提案する「レコメンド機能」が大きな魅力です。
レコメンド機能では、ユーザーの購入履歴や閲覧履歴をもとに、AIが最適な商品を提案します。例えば、「この商品を見た人はこんな商品も見ています」や「よく一緒に購入されている商品」といった形で、ユーザーが気になる商品を簡単に見つけられるようサポートしてくれます。
また、Amazonプライム会員向けには、動画配信サービスやポイント還元など、ショッピング以外の付加価値も豊富に用意されています。
ソーシャルコマースのメリット
ここでは、EC事業者がソーシャルコマースを導入するメリットについて解説します。
新規顧客層へのアプローチ
ソーシャルコマースは、SNSの利用者を新規顧客として獲得できる有効な販売チャネルといえます。特に、従来のECサイトでは難しかった若年層へのアプローチが可能になります。
インフルエンサーとのコラボレーションやハッシュタグキャンペーンなど、SNSならではの施策を展開することで、商品の認知度を効果的に高められるでしょう。特にバズ(話題化)の発生時には、ユーザーの投稿やシェアによって情報が自然に拡散されるため、広告費を抑えながらブランドの露出を増やすことができます。
また、商品の使用シーンや活用方法をビジュアルや動画で訴求できるため、テキストや静止画よりもユーザーに商品の価値がより伝わりやすくなります。
さらに、実際の使用者による口コミやレビューは、新規顧客の購買決定を後押しする重要な要素です。
購買ステップの短縮
一般的なECサイトでは、商品との出会いから購入までに複数のステップが必要になります。一方、ソーシャルコマースでは、SNSでの商品発見から即座に購入へ移行できるため、購買までの導線が大幅に短縮されます。
例えば、Instagramの投稿で商品を見つけた場合、数回のタップで購入画面まで進みます。この手軽さにより、ユーザーの衝動買いや感情的な購買が促進され、売上の増加につながります。特に、期間限定商品やタイムセールなどの訴求では効果が高いです。
また、決済機能と連携できる点もポイントです。LINE PayやAmazon Payなど、普段使用している決済手段をそのまま利用できることで、購入時の心理的ハードルが下がるのです。
ブランド価値の向上
ソーシャルコマースでは、商品を軸としたユーザーとのコミュニティの形成が可能です。商品のファンが集まり、使用感や活用法を共有することで、自然とブランドの価値が高まっていきます。
ブランドの考え方や商品に関する質問や相談をユーザー同士で行える環境を整えることで、企業が全く想定していなかった使い方や、期待する以上の新しい価値が見つかることもあります。この発見をブランディングや商品開発に活かすことで、より魅力的な商品展開が可能になるでしょう。
また、ユーザーと継続的にコミュニケーションをとることで、信頼関係を築けます。商品の改善要望や不満の声にも素早く対応できるため、ブランドへの信頼度も向上するでしょう。
ソーシャルコマースの成功事例
ここでは、異なる業界から3つの特徴的な成功事例を紹介します。
ルイヴィトン
高級ブランドのルイ・ヴィトンは、中国の人気プラットフォーム「小紅書(RED)」で斬新なソーシャルコマース戦略を展開しました。特に注目を集めたのは、高級ブランドとして初めてライブコマースを実施し、15万2,000回以上の視聴を記録した点です。
このライブ配信では、商品の紹介だけでなく、視聴者とのリアルタイムな対話を重視し、高級ブランドの持つ世界観を保ちながら、オンラインならではの新しい購買体験を提供しました。その結果、ルイ・ヴィトンはブランドの伝統的価値を損なうことなく、現代の消費者ニーズに応えることに成功しています。
さらに、このデジタル戦略によって、若い世代の顧客層を開拓し、ブランドの現代性をアピールするという成果も得ています。
ソーシャルコマースを通じて、伝統的な高級ブランドとデジタル時代の消費体験を見事に融合させたルイ・ヴィトンの取り組みは、今後の業界の手本となるでしょう。
参考:ルイ・ヴィトンも参入したソーシャルコマース。世界のトレンドと中国の先行事例に学ぶ小売業者が注目すべき理由|ネットショップ担当者フォーラム
Shein
ファストファッションブランドのSheinは、SNSを活用した独自のマーケティング戦略で急成長を遂げています。世界のソーシャルメディアでもっとも話題になったブランドの1つとして、InstagramやTikTokでの存在感は圧倒的です。
特に効果を発揮しているのが、インフルエンサーマーケティングとユーザー投稿の活用です。3万人以上のインフルエンサーが、Sheinを13万6,000回以上メンションし、実際の着用写真や動画を共有しています。商品の実用性や着こなしの提案が、若い世代の購買意欲を刺激しています。
また、独自のアプリを通じて、パーソナライズされた商品レコメンドや限定セールなどを展開し、顧客エンゲージメントを高めています。
こうしたデジタルネイティブ世代の購買行動を深く理解した戦略が、Sheinの急速な成長を支える原動力となっています。
参考:中国発のファストファッション「Shein」が圧勝。世界のソーシャルメディアを席巻した「10のブランド」|Business Insider Japan
銀のさら
宅配寿司チェーンの銀のさらは、LINEを活用した顧客体験の向上に成功しています。LINEの友だち数は370万人を突破し、メッセージの反応率は一般的なメールマガジンの3倍という高い数値を記録しています。
特に注目すべきは、ユーザーの行動パターンや時間帯に合わせた配信戦略です。例えば「平成最後の締め寿司」というメッセージ配信では、時期に合わせた消費者心理を巧みに捉え、多くの反応と注文につながりました。
こうした戦略により、LINE経由の売上は前年比160%増を達成し、特にステイホーム期間中は大きな効果を発揮しました。
参考:ソーシャルコマース成功のカギはやっぱりCX(顧客体験) 〜LINE活用の成功事例から見えてきたこと〜| Dentsu Digital
ソーシャルコマース戦略は専門家へのアウトソーシングがおすすめ◎
ソーシャルコマースは、SNSの選定から運用、データ分析まで、専門的な知識と経験が必要です。効果的な施策を実現するためには、ECサイトの構築や運用に詳しい専門家のサポートを受けることをおすすめします。
ECのミカタでは、ソーシャルコマースの導入から運用まで、豊富な実績を持つ企業を紹介しています。
企業登録数は2,000社以上。プラットフォームの選定からコンテンツ制作、データ分析など、EC事業者様のニーズに合わせた最適なパートナーが見つかります。
まずは、専門のコンシェルジュがご要望やお悩みを丁寧にヒアリングいたします。お急ぎの場合は最短1営業日で企業との商談をセッティングいたしますので、まずはフォームからお気軽にお問い合わせください。