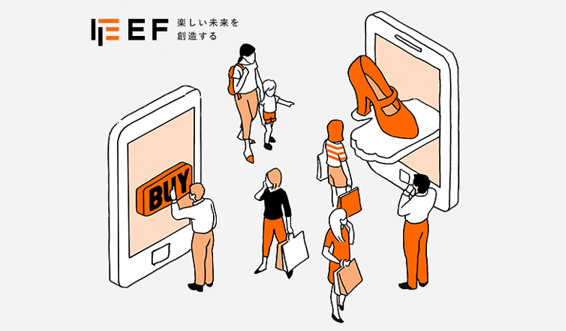食品ECとは?成功企業の事例や市場規模についても解説

食品ECの運営には、商品の鮮度や品質の管理、物流体制の整備、そして競争に勝つための独自戦略が欠かせません。
本記事では、食品ECの基本的な特徴や成功事例を交えながら、具体的な始め方や成功の秘訣を解説します。
食品ECとは
食品ECとは、インターネットを通じて食品を販売・購入するビジネス形態のことを指します。
食品メーカーや飲食店、農業事業者が自社の商品を直接消費者へ届ける手段として利用されています。
昨今ではコロナ禍の影響もあり、食品ECは急速に普及し、注目を集めています。
食品ECの市場規模とEC化率
食品ECの市場規模は年々拡大を続けています。
経済産業省の「令和5年度電子商取引に関する市場調査」によると、2023年の「食品、飲料、酒類」におけるEC市場規模は2兆9,299億円に達し、前年から6.52%の成長を遂げました。
一方、矢野経済研究所の調査では、2022年度の国内食品通販総市場規模は4兆5,752億円と推計されています。
こちらでは前年度比0.3%減となっており、コロナ禍の需要増加後の反動減や物価上昇による節約志向が影響したと考えられます。
また、価格高騰による購買頻度の減少や需要そのものの低下も影響している可能性があります。
食品EC市場の成長を支える要因には、共働き世帯や高齢者層の需要増加、冷凍食品や長期保存可能な食品の需要拡大が挙げられます。
現状、食品はほかのカテゴリに比べEC化率が低い現状がありますが、このEC化率の低さは、今後の市場拡大の可能性を示しているとも考えられます。
食品業界のEC化率が低い理由には、消費者の購買行動や食品の特性が挙げられます。
特に鮮度や品質保持が求められる食品では、消費者が実際に手に取って選びたいという習慣が根強く、ECサイトでの購入に心理的なハードルを感じることがあるのです。
また、その日の食事に必要な分を購入するというニーズは、近隣のスーパーやコンビニエンスストアで簡単に満たすことができますが、ECでは注文から配送までに最低でも1日を要し、即時性のあるニーズに応えにくい面があります。
さらに、少量購入では商品代金が一定金額を下回り、送料負担が加わることで、コスト面でも実店舗に比べて不利になる場合が多いです。これらの要因が重なり、食品業界のEC化率がほかの業界と比較して低い水準に留まる要因となっています。
しかし、冷凍食品や保存が利く加工食品の需要が高まっているため、今後は食品業界のEC化率がさらに上昇していく可能性があるでしょう。
出典:
令和5年度電子商取引に関する市場調査報告書|経済産業省
食品通販市場に関する調査を実施(2024年)|矢野経済研究所
食品ECの課題
食品ECには大きな可能性がある一方で、克服すべき課題も多くあります。
特に、食品の品質管理や物流コストの負担が大きな課題です。
物流においては、冷蔵・冷凍輸送が求められる食品では鮮度を損なわないような管理体制が不可欠であり、これがコスト増加の主な要因となっています。また、送料の上昇や配送時間の短縮ニーズへの対応も、事業者の負担を増大させています。
さらに、食品ECを運営するには、関連する法律の理解が必須です。
例えば、食品衛生法は、純粋なECサイト運営のみを行う場合には適用されないケースもありますが、食品を直接取り扱う事業者に適用されます。
一方で、食品表示法に基づき、原材料やアレルゲン情報の正確な表示は、すべての食品EC事業者に求められます。
これらの規制を満たさないと、事業停止や消費者トラブルに発展するリスクがあります。
また、食品EC市場では競争が激しく、他社との差別化を図るためにブランド戦略や独自の商品開発が必要です。
食品ECの特徴
食品ECはほかのEC事業とは異なり、商品の特性に合わせた注意点が多いという特徴があります。
食品は消費者の健康や安全に直接関わるため、品質管理や衛生面での配慮が不可欠です。
ここでは、食品ECならではの特徴を取り上げます。
運営には資格や許可が必要なケースが多い
食品ECを運営するには、事業者が必要な資格や許可を取得し、関連する法律を守る必要があります。
具体的には、食品を直接保管・加工・梱包する施設を運営する場合、食品衛生責任者の選任が義務付けられます。
また、オンライン販売に特化した「特定商取引法」も食品ECに関わる重要な法律です。
この法律では、販売サイトに事業者情報を明記し、消費者が事前に十分な情報を確認できる環境を整備することが求められます。また、返品・返金ポリシーを明確にしたり、消費者とのトラブルを未然に防いだりする取り組みも必要です。
食品ECを始める際には、これらの法律や資格要件を事前に理解し、必要な手続きを確実に行わねばなりません。
特に、事業規模が拡大するにつれて監査や消費者からの指摘が増える可能性があるため、法令遵守の体制を早い段階で整えることが求められます。
参考:
インターネット販売における食品表示の情報提供に関するガイドブック | 消費者庁
通信販売|特定商取引法ガイド
温度管理など物流での配慮が必要
食品ECの物流は、商品の特性に合わせた高度な管理が必要であり、これが事業運営の大きな課題の1つとなっています。
特に生鮮食品や冷凍食品では、適切な温度での管理ができていないと、食品の品質や安全性に影響を及ぼす可能性があるため、輸送中の温度管理が不可欠です。
食品ECでは、物流業者が提供する「コールドチェーン」と呼ばれる仕組みを活用することで、食品の品質を維持した配送が可能です。
コールドチェーンは冷凍・冷蔵トラックや専用倉庫だけでなく、温度センサーによるリアルタイムモニタリングや、輸送中の異常を通知するアラートシステムを含みます。
さらに、近年の食品EC市場拡大に伴い、配送スピードの向上や効率的な在庫管理が求められています。
当日配送や翌日配送といった短納期を実現するためには、配送拠点の適切な配置や、リアルタイムでの在庫管理システムが求められており、Amazonの「FBA」や楽天の「楽天スーパーロジスティクス」のようなサービスを活用する企業も増えています。
あわせて読みたい:
食品物流とは。課題やEC事業者向けの効率化の方法を解説
品質と安全性が求められる
食品ECでは、商品が消費者の健康に直結するため、品質と安全性の管理が最重要課題となります。特にリコール対応や食品検査体制の整備は、消費者の信頼を確保するうえで欠かせません。
また、定期的な品質チェックと商品ロットの追跡可能性(トレーサビリティ)を確保する仕組みも求められます。
生鮮食品の鮮度を保つためには、適切な温度管理が必要です。冷蔵配送の場合は2~10℃、冷凍配送の場合は-18℃以下を維持することが推奨されており、近年では、IoTセンサーを活用した温度監視システムや、リアルタイムで異常を通知するアプリケーションが普及しています。
衛生管理の面では、HACCP(危害分析重要管理点)やISO22000(食品安全マネジメントシステム)の導入が推奨されます。
さらに、食品表示法に基づいて正確な情報を提供することで、消費者が安心して商品を購入できる環境を整えることが大切です。
具体的には、アレルゲン情報や原材料の産地を明確にすることなどが挙げられます。
これらの取り組みを徹底し、さらに、消費者の信頼を得るためには、レビュー管理や返品ポリシーの整備も重要です。
食品ECの主なカテゴリ
食品ECは、取り扱う商品の種類によっていくつかのカテゴリに分けられます。
食品ECを始める際は、それぞれの商品特性や消費者ニーズに応じた取り組みを検討しましょう。
ここでは、食品ECで特に注目される4つのカテゴリについて解説します。
生鮮食品
生鮮食品は、食品ECのなかでも特に品質管理が重要なカテゴリです。生鮮食品には、以下のような食材が含まれます。
- 野菜
- 果物
- 肉類
- 魚介類
これらの商品は消費者にとって鮮度が最優先されるため、輸送中の温度管理が欠かせません。
コールドチェーンを活用した冷蔵・冷凍配送に加えて、短納期の配送システムを採用することが求められます。
また、生鮮食品ECでは、消費者に「新鮮さ」を感じてもらうための工夫も必要です。
例えば、産地直送の商品を提供し、生産者との提携を前面に打ち出したマーケティングが効果的です。さらに栽培や漁獲の日付や場所を明示するトレーサビリティ情報を表示することで、購入者の信頼が高まるでしょう。
また、サブスクリプション形式での定期配送サービスも人気があり、特定の地域で収穫された有機野菜を毎週配送するサービスなどは、消費者との長期的な関係構築に役立っています。
生鮮食品ECは、競争が激しい分野である一方、地域特産品などを活用することで差別化が図れるカテゴリでもあります。地元でしか手に入らない食材を販売することで、消費者に希少価値を感じてもらいやすくなるでしょう。
冷凍食品
冷凍食品は保存性が高く輸送中の品質維持が比較的容易であるため、食品EC市場で成長が著しいカテゴリです。
このカテゴリでは、冷凍食品メーカーの商品に加え、家庭料理を冷凍加工した商品など、特に家庭用冷凍食品の需要が拡大しています。この成長の背景には、共働き世帯の増加や一人暮らしの消費者ニーズの高まりなどが関係しています。
近年では、簡単に調理できるミールキットや高品質な冷凍スイーツの人気が高まっています。また、高級スイーツブランドは冷凍ケーキやアイスクリームを展開しており、ギフト需要にも対応しています。
また、冷凍食品は賞味期限が長いため、大量購入や定期購入を提案しやすいという特徴もあります。
健康食品・オーガニック食品
健康志向の高まりとともに、健康食品やオーガニック食品は食品ECのなかでも急成長している分野の1つです。
サプリメントやプロテインといった健康食品、農薬や化学肥料を使用せずに栽培されたオーガニック食品などが挙げられます。
これらの商品は、「生活習慣病予防」「腸内環境の改善」など、特定の健康課題を解決したい消費者に支持されています。また、環境に配慮した農業や生産プロセスを重視するエシカル消費のトレンドも需要を押し上げているといえるでしょう。例えば、フェアトレード認証を取得したオーガニックコーヒーや、生分解性包装を採用した商品が注目されています。
また、健康食品・オーガニック食品のEC運営では、商品の安全性や品質を保証するために以下のような信頼性の高い認証を取得することが重要です。
- 有機JASマーク
- フェアトレード認証
- GMP(適正製造規範)認証
また、商品の魅力をより明確に伝えるために、商品の成分や研究データを発信したり、レシピや使用例の提案をしたりすることも効果的です。
加工食品
加工食品は、幅広い層に需要があり、食品ECのなかでも多くの事業者が参入しています。
このカテゴリには、缶詰、瓶詰、レトルト食品、調味料、菓子類など、さまざまな商品が含まれ、特に調味料や健康志向の菓子類が人気を集めています。
加工商品は賞味期限が長いことから、在庫管理や輸送が比較的容易であり、初心者の事業者でも参入しやすい分野です。例えば、常温で保管可能な商品はコスト効率が良く、輸送中の品質管理の手間を軽減できます。
加工食品ECでは、商品の魅力を最大限に伝えるマーケティング力がカギです。
商品ページに調理方法やレシピ例を掲載したり、ギフトセットとして販売したりすることで付加価値を高められます。
また、消費者のニーズに合わせた小ロット販売や定期購入サービスを導入することで、リピーターを獲得する戦略も効果的です。
【事例】食品ECの成功企業3選
食品ECで成功を収めている企業は、消費者ニーズに応えた独自の戦略を展開しています。
ここでは日清食品、ハウス食品、エスビー食品の3社について簡単に紹介し、それぞれが成功を収めた理由を解説します。
日清食品
日清食品は即席麺業界のリーディングカンパニーとして知られていますが、食品EC分野でも大きな成功を収めています。
同社の成功要因は、消費者がオンラインで購入しやすい体験を提供した点にあります。
公式オンラインストアでは限定商品や新商品の先行販売を行い、ほかの販路では手に入らない付加価値を提供したのです。
また、個々の消費者に寄り添ったマーケティング戦略にも目を見張るものがあります。
購入履歴を活用したおすすめ商品の提案や、季節ごとのプロモーションキャンペーンを実施することで、リピーターの増加に成功しています。例えば、「行列のできるラーメンシリーズ」を季節限定で展開するなど、消費者の興味を引きつける工夫を行っています。
さらに、配送の効率化と迅速な対応を可能にするシステムを導入し、消費者の満足度がアップ。
このようなデジタル技術を活用した消費者対応が、日清食品の成功のポイントです。
参考:日清がECサイト刷新で売り上げ100倍、それでも顧客刈り取りに慎重なワケ|日経クロストレンド
ハウス食品
カレーやスパイス製品で知られるハウス食品は、食品ECにおいても着実な成果を上げています。
同社の成功の背景には、EC運営ツールの活用が挙げられます。
PENCIL(ペンシル)社のデジタルツールを用いて、消費者の行動データを分析し、ECサイトの効率化を図っています。具体的には、サイト上での購買プロセスを改善し、顧客が商品にたどり着きやすい仕組みを構築しました。
また、広告効果を可視化し、最適なタイミングで適切な広告を配信することで、集客と購入率の向上を実現しています。
これらのデータ活用に基づいた戦略的な運営が、ハウス食品のEC事業の成功を支える柱といえるでしょう。
参考:ハウス食品株式会社 クライアントボイス〜メーカーがECでなにをすべきなのかを考えて戦略を立ててくれる。ペンシルの一番のポイントはメーカーへの理解度が高いことです。|株式会社ペンシル
エスビー食品
エスビー食品は、香辛料や調味料の分野で高いブランド力をもつ企業であり、食品EC市場でも注目されています。
同社の成功要因は、オンラインコミュニティを活用した顧客との関係構築にあります。
エスビー食品は「S&B Community」というプラットフォームを通じて、消費者に対して新商品の情報提供やレシピの提案を行いました。
また、このコミュニティでは消費者同士が意見交換できる仕組みを整備しており、ブランドロイヤルティの向上につながっています。
さらに、購買データを分析し、消費者の嗜好に合わせた商品を提案することで、ECサイトでの購入率を高めています。
こうしたコミュニケーション重視のアプローチが、エスビー食品のEC成功のカギとなっています。
参考:おいしさ、健やかさを届けたい。進化を続けるエスビー食品の「お届けサイト」|SPICE&HERB COMMUNITY
食品ECを成功させるためのポイント
食品ECで成功するためには、食品ならではの特性を考慮した運営が求められます。
消費者は食品の品質や安全性を重視するため、これらを保証する体制を整えることが事業成功のカギです。
ここでは、食品ECに特化した成功の秘訣を3つ解説します。
鮮度と味の維持
食品ECでは、鮮度と味が消費者の満足度を左右します。
特に、生鮮食品や冷凍食品の場合、商品の品質を維持するための温度管理が必須です。
冷蔵・冷凍配送の仕組みを整備し、輸送中の温度変化を防ぐことで、消費者が自宅で受け取った際も店舗で購入した食品と同じレベルの鮮度を感じられるようにする必要があります。
また、鮮度や味の維持は配送だけでなく、製造や在庫管理にも関わります。
在庫の回転率を高めるための需要予測を行い、新鮮な商品をタイムリーに消費者に届けることが大切です。
食品の鮮度や味の維持を徹底することは、消費者の信頼を得るだけでなく、リピーターを増やすための基本的な取り組みといえます。
パッケージと配送の工夫
食品ECにおいては、パッケージや配送は単なる付随サービスではなく、商品価値を直接的に左右する重要な要素です。
消費者が手に取る最初の部分であるパッケージは、食品の鮮度を守るだけでなく、ブランドイメージを向上させる役割も担っています。
外装には断熱性や防湿性を備えた素材を使用し、内装には食品が傷つかないような工夫を施すことで、配送中の品質劣化を防ぐことができます。また、内装には食品が動かないようなクッション材を使用し、配送中の破損リスクを低減する工夫も必要です。
また、クール便や冷凍配送の利用はもちろん、翌日配送や指定時間配送など柔軟な選択肢を与えることで、消費者満足度を高められます。特に生鮮食品の場合、配送スピードは商品の品質と直結するため、配送体制の整備は無視できません。
独自商品戦略による差別化
食品EC市場は競争が激しく、価格競争だけでは他社との差別化が難しい状況にあります。
そのため、独自の商品戦略を構築し、競合他社と異なる価値を提供することが重要です。
地域特産品やオリジナルの加工食品を扱うことで、消費者に「ここでしか買えない」という独自性を感じさせることができます。
さらに、消費者の健康志向や環境配慮のニーズに応える商品開発も効果的です。
具体的には、オーガニック食品や低糖質食品といった健康志向の商品を販売することで、新しい顧客層を獲得できる可能性があります。
このような取り組みは、商品そのものの魅力だけでなく、企業としての信頼性や価値観への共感を呼び起こすでしょう。
また、商品の販売形式にも工夫が必要です。
例えば、ミールキットや定期購入サービスを提供することで、忙しい家庭や一人暮らしの消費者に支持されやすくなります。
食品EC市場で差別化を図るには、商品そのものだけでなく、消費者のライフスタイルや価値観に寄り添った考え方が重要です。
食品ECの始め方
食品ECを始める際には、準備から運営までの各ステップを効率的に進めることが重要です。
食品ECを立ち上げるための基本的な流れとしては、以下のステップを踏みましょう。
- 市場調査とターゲット設定
- 必要な資格・許可の取得
- 商品の選定と仕入れ先の確保
- ECサイトの構築
- 物流と配送体制の整備
- プロモーションと集客施策の実施
- 運営開始後の改善と対応
1からサイトを構築して戦略立てていくには、食品ECに精通した専門事業者のサポートを受けることをおすすめします。
食品ECの運営・構築は、プロのコンサルに相談しながら進めるのがおすすめ
食品ECは多くの可能性を秘めていますが、成功させるには専門的な知識やスキルが求められます。
商品の選定や物流、法令遵守、ECサイトの構築、プロモーション戦略に至るまで、各工程で専門的な知識が必要です。
これらの業務を自社だけで行うと負担が大きくなるだけでなく、非効率的な運営につながるリスクもあります。
食品EC事業を成功に導くためには、プロのコンサルタントにサポートを依頼することをおすすめします。
「ECのミカタ」では、食品ECに特化したコンサルティング企業や、食品ECサイトの構築を得意とする企業などとのビジネスマッチングサービスを提供しています。
まずは、専任のコンシェルジュが現状の課題や不安なポイントなどをヒアリングさせていただきます。そのうえで、課題解決に役立つ有力な事業者を無料でご紹介します。
食品ECは競争が激化する市場ですが、適切なサポートを受けながら進めることで他社との差別化を図り、成果を上げることが可能です。
ぜひ「ECのミカタ」のサービスを活用し、食品EC事業を成功させましょう。