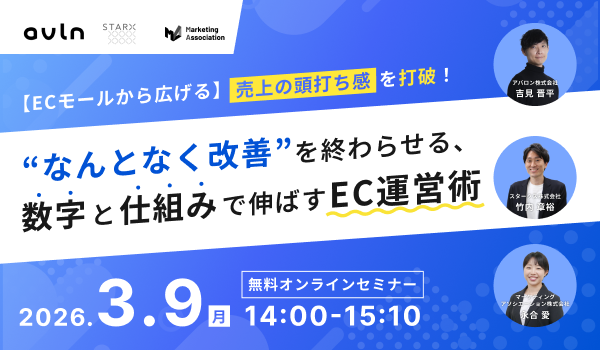Bカートで業務の9割をデジタル化、U-KOMIでマーケも強化 志成販売のEC×DX改革

インテリア・生活雑貨・服飾小物などの輸入卸売販売を行う株式会社志成販売は、今から約10年前の2014年にBtoB向けの自社ECサイト「shesay」をBカートで構築した。これを機に進んだ社内のDXは同社の業績を押し上げ、業務効率化や生産性向上を実現。2022年には「U-KOMI」の導入でUGC(ユーザー生成コンテンツ)活用に乗り出すなど、デジタル領域での業務を強化してきた。志成販売の戦正典社長とU-KOMIを提供する株式会社サブスパイアの岡村芳広氏に、卸売販売業者がBtoB ECに取り組むメリットやDXの成果・効果、今後の展望などについて話を聞いた。
アナログな受注業務でミスや機会損失が多発
――まずは志成販売様の事業内容について教えてください。
株式会社志成販売 代表取締役社長 戦正典氏(以下、志成販売・戦)当社はナチュラルテイストのインテリアや生活雑貨、服飾小物などの企画・販売を行う卸売企業です。BtoB事業がメインで、約2000SKUのアイテムを取り扱っています。商品の約7割は中国やインド、フィリピン、タイなどからの輸入品で、残りの約3割が日本国内で企画・製造したオリジナルアイテムになります。
――Bカートを導入する前、BtoB事業において受注面の課題や業務に関するお悩みなどはありましたか。
志成販売・戦 Bカートを導入する前は、紙カタログからの電話・FAXが主な受注方法でした。当時は展示会や自社イベントでカタログを配布し、顧客から届く注文情報を営業スタッフが手作業で基幹システムに入力していました。
そのため受注処理に手間と時間がかかり、聞き間違い・書き間違いが頻発するなどミスも目立っていました。営業時間外は電話注文を受けられなかったので、機会損失も多かったと思います。
 Bカートで構築した卸仕入れ販売専門サイト「shesay」のトップページ
Bカートで構築した卸仕入れ販売専門サイト「shesay」のトップページ
――Bカートを導入した時期と、その経緯について教えてください。
志成販売・戦 Bカートを導入したのは2014年です。導入の目的は受注業務の効率化と、EC事業の強化でした。卸売業は受発注業務や商習慣においてデジタル化が遅れており、FAXや紙の請求書、電話でのやり取りがビジネスの中心でしたが、今後はECでの取引が増えるだろうと考え、BtoB ECの強化を図りました。
――Bカートを選んだ決め手は何だったのですか。
志成販売・戦 カート選定時にはいくつかのサービスを比較検討しました。BカートはBtoB取引に特化したカートシステムであり、コスト面で優位性があったため導入を決めました。本社のある大阪市中央区の船場は繊維の卸問屋が軒を連ねるエリアで、Bカートを使っている同業者が多かったことも導入を後押ししました。
Bカート導入をきっかけに社内のDXが推進
――Bカートをお使いになって10年以上が経過していますが、どのような点で導入メリットを感じていますか。
志成販売・戦 BtoBビジネスは顧客ごとに取引条件が異なるため、業務が複雑で時間と労力がかかります。しかし、Bカートは取引先ごとに販売価格や割引率を調整したり、商品の表示・非表示のコントロールもできます。取引の規模や実績に応じて顧客ごとの決済方法を決められるなど、BtoB特有の商習慣にも対応しているので、非常に使い勝手がいいですね。
Bカートサイトでお客様が注文すると、注文内容が自動でお客様と当社の双方にメールで送信されるため、確認ミスが劇的に減りました。社内的には、電話やFAXによる受注処理の手間が省けたほか、在庫に関する問い合わせ対応の負担も大幅に軽減されています。
――業務効率化という当初の目標は達成できたということですね。
志成販売・戦 Bカートの導入をきっかけに、業務のデジタル化が一気に進みました。現在では業務の約9割がデジタル化され、効率とスピードの両面で飛躍的な向上を実感しています。さらなるステップとしてRPA技術の活用を検討したり、Web広告の運用を強化できるようにもなりました。まさにBカートの導入を起点に“かけ算”で社内のDXが進んだ印象で、これがUGC活用ツール「U-KOMI」の導入にもつながりました。
――サブスパイア様にお聞きしますが、U-KOMIとはどのようなツールなのでしょうか。
株式会社サブスパイア 取締役 岡村芳広氏(以下、サブスパイア・岡村) U-KOMIは商品レビューや口コミ、SNS投稿などのUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)を効果的に収集・活用し、ECサイトにおけるレビュー獲得率の向上、SEO強化、コンバージョン改善などを支援するプラットフォームです。
ユーザーごとに最適化されたレビュー入力フォームをメールやQRコード、LINE経由で配信します。レビュー投稿はログイン不要で、フォームから直接書き込むことができます。ユーザーはストレスなく投稿できるため、高いレビュー獲得率を実現しています。
――BtoB ECにおいても、UGCの活用は重要なのでしょうか。
サブスパイア・岡村 企業間取引でもUGCは非常に重要だと思います。レビュー投稿は購買の「安心感」を高めますし、リピート購入やクロスセルの促進にもつながります。品揃えや広告戦略を見直すこともできるでしょう。顧客からのフィードバックは、商品開発や営業戦略にも役立ちます。
UGCの活用で増した自社サイトへの信頼感
――志成販売様はU-KOMIの導入でどのようなメリットが得られましたか。
志成販売・戦 2022年4月にU-KOMIを導入し、すぐに新規顧客獲得でプラスの影響がありました。当時はSEO対策としてBカートの「自由ページ」でLPを作成し、そこにU-KOMIで集めたレビューを掲載していました。
集まったレビューにはネガティブな口コミや意見もありましたが、どんなコメントに対しても真摯に回答するよう心がけました。そうした当社の対応・コメントを見て安心感を抱いてくださるお客様が多くなり、爆発的に新たな取引先を増やすことができました。
――レビューへの返信は重要なのでしょうか。
サブスパイア・岡村 そうですね。BtoC・BtoBを問わず、レビューへの対応姿勢は企業の信頼度を示す重要な要素になります。レビューに丁寧に返信することで、取引先には「顧客を大切にする姿勢」が伝わります。特にネガティブなレビューへの誠実な対応は、見込み客にとって店舗への信頼につながるでしょう。
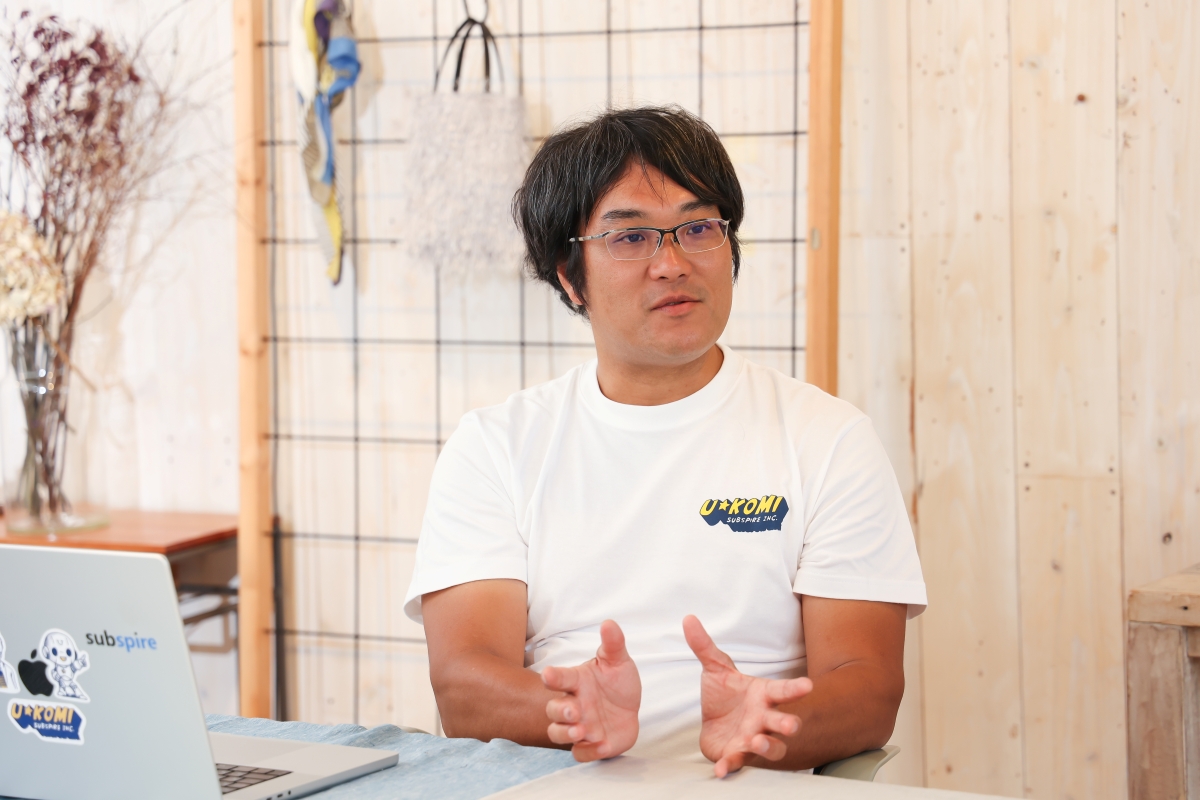 株式会社サブスパイア 取締役 岡村芳広氏
株式会社サブスパイア 取締役 岡村芳広氏
志成販売・戦 U-KOMIには企業側がレビューに返信できる機能が標準搭載されています。ECページ内で双方向コミュニケーションが可能だったので、回答の“見える化”に役立ちました。
サブスパイア・岡村 実はこうしたレビューに対する返信業務ができていない事業者様は結構多いです。UGCのような一次情報はAIで生成できるものではないので、顧客の信頼を得るためには志成販売様のようにしっかりと積み上げていくことが大切です。
――獲得したレビューはどのように活用されていますか。
志成販売・戦 BtoB ECサイトに集まるレビューは、商品に対する“プロの声”です。一般顧客とはまったく異なる目線のコメントをデータとして蓄積できるため、レビュー情報は仕入れや商品開発、マーケティングなどにも活用しています。
 株式会社志成販売 代表取締役社長 戦正典氏
株式会社志成販売 代表取締役社長 戦正典氏
――最後にBtoB EC領域における事業拡大に向けた今後の目標や、同じ卸売事業者へのメッセージなどがあればお聞かせください。
志成販売・戦 当社ではBカートの導入を機に、U-KOMIなどのツールを活用しながら業務効率化・顧客ロイヤルティ向上などに努めています。卸売事業のデジタル化・DX化を進めるという方針は、今後も変わることはありません。
社会全体でDX化が進んでいますが、卸売業者も旧来のビジネスモデルに縛られることなく、BtoB ECに取り組まなければ時代に取り残されてしまいます。EC化は日本全国、世界にマーケットを拡大するためには、非常に有効な手段です。
Bカートを提供される株式会社Dai様もU-KOMIのサブスパイア様も、カスタマーサポートが充実しており対応力も高いので、BtoB ECに慣れていない企業にとっては心強いパートナーになってくれると思いますよ。