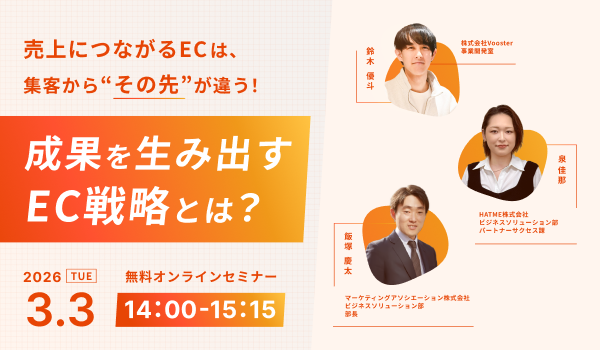次世代CRMの「持続的成長のシナリオ」に学ぶ! 長期戦略思考に基づくECの作り方【ECのミカタ カンファレンスレポート】

ECのミカタ(MIKATA株式会社)は2025年7月29日、東京都渋谷区のSCC千駄ヶ谷コミュニティセンターで「長期的に選ばれるECの作り方」と題したオフラインセミナーを開催した。
國學院大學の宮下雄治教授による「サイレントカスタマー(物言わぬ顧客)」に関するセッションは、最前線でEC事業運営の課題に向き合う参加者を魅了。また、CRM・CX・ファン化戦略で成果を上げる株式会社中川政七商店とカンロ株式会社、EC支援領域からも株式会社ギャプライズをはじめとする企業が登壇し、EC運営の戦略思考とCRM成功の秘訣を明かした。
顧客が離脱するメカニズムを理解せよ
 國學院大學 経済学部 宮下雄治教授の講演題目は「顧客離脱の実態と長期的に選ばれ続ける極意」
國學院大學 経済学部 宮下雄治教授の講演題目は「顧客離脱の実態と長期的に選ばれ続ける極意」
顧客との関係性を強化し、継続するという課題は、いまやEC事業担当者に与えられた課題そのものである。それゆえEC事業者はAI・デジタル技術を駆使した顧客データの収集、分析がルーチンとなり、最適なタイミングと価格、適切なチャネルを通じて製品・サービスを勧め、顧客満足をリピートで囲い込むファン化マーケティングでしのぎを削っている。ところが一方で、顧客の「静かな離脱」は置き去りにされているようだ。いわゆる「サイレントカスタマー(物言わぬ顧客)」というマーケティング課題である。
顧客定着率が高い企業の特徴とリテンションマーケティング(既存顧客のリピート化や長期契約)を研究する國學院大學の宮下雄治教授は、「なぜ顧客が離れていくのかという課題に向き合う企業は多くはありません。強固なブランドを備えた企業であっても、実のところ離脱していく顧客の実態や心理を理解していないケースも散見されます」と言う。
本カンファレンスにおいて宮下教授は、「顧客の離脱状況に関する独自調査」からの検証結果に基づいた、顧客離脱の主要因やサイレントカスタマーの分析、離脱を回避するリテンションマーケティングなどの要点を披歴した。
「顧客離脱の主要因は、自社の魅力低下、他社の魅力向上、各種パフォーマンスへの不満、必要性の消滅(ニーズ・利用環境の変化)の4つです」
中でも離脱の主要因として最も多いのが、「自社の魅力低下」と「他社の魅力向上」である。「自社の魅力低下」は、不祥事のような落ち度がある場合は当然だが、落ち度がなくても離脱する顧客がいる。後者の原因は百人百様であるため、認識はおろか把握や対策に手つかずの企業がほとんどだという。さらに、昨今の景気状況から消費者理解は進んだとはいえ、ステルス値上げ(シュリンクフレーション)に対する不信感も根強い。
「消費者は常に良い商品・サービス・顧客体験を求めて、各社を比較して、総合的な判断をしているということを肝に銘じなければなりません」
他社への乗り換え、あるいは何らかの理由で使用するメリットや必要性がなくなったのかもしれないが、いずれにしても、企業は世の中の移り変わりと顧客への深い理解が求められる。その点において宮下教授は、「各種パフォーマンスへの不満」という現代の消費者特有のトピックを取り上げた。コスパ(Cost)、タイパ(Time)はよく知れたワードであるが、これに加え、リスパ(Risk)、ウェルパ(Well-Being)の4つへの理解と対策が重要であると指摘した。

EC事業に限らずパフォーマンス分析はマーケティングの定石であるが、消費者の「不満」という心理状況を軸にしたインサイトを得ない限り、解約率の改善は無策のままとなる。
「顧客の離脱を未然に防ぐためにコスパとタイパへの対策の遅れは、顧客離脱に致命的な影響を及ぼします。加えて、昨今はリスパ(失敗したくない)を重視する若い消費者が増えています。また未来の社会の良い状態を志向する企業を応援したいというモチベーションからウェルパ(心身の充足)が好まれる傾向が強くなっていることに留意すべきでしょう」(以上、発言部分は宮下教授)
ユーザー体験に直結するサイト表示速度の改善効果
こうした宮下教授の指摘に応えるような施策やツール、改善例が出始めている。例えば、アパレルのセレクトショップを展開する株式会社ユナイテッドアローズは、画像の最適化や配信の効率化などに日夜取り組み、サイトの読み込み時間はグーグル基準(LCP=2.5秒以下 ※)をはるかに上回る1.4秒を達成していたが、これに満足せずユーザーの使い勝手向上を目指して、ギャプライズの「Speed Kit」を導入した。すると、スピードは65%向上、購入完了率は4%改善したという。
表示スピードの改善がいかにECサイトのUI/UXを改善するかについて、カンファレンスに登壇した株式会社ギャプライズ CXO事業部 セールスグループ ヴァーラモフ・ダニイル氏は、「売上高とスピードには明確な相関関係があります。サイトの読み込み時間が速いとユーザーのサイト回遊のストレスが減ることで離脱を防止し直帰率は減少、コンバージョン率は上がり売上が向上するのです」と解説した。
サイトのスピード向上がもたらす直帰率低下は、「タイパ」の観点から顧客エンゲージメント強化策として非常に有益である。しかも、広告単価やSEOランキングの上位表示といった効果を期待できる。ダニイル氏は「スピードの改善はECの売上を増やす最もシンプルな方法ですが、スピードアップを一時的な施策で終わらせず、継続的に行い、改善し続けることが重要です」と提言した。
 株式会社ギャプライズ CXO事業部 セールスグループ ヴァーラモフ・ダニイル氏による講演は「ユナイテッドアローズが実証! 商品ページLCP約1秒改善&CVR4%向上! EC光速化の秘策」
株式会社ギャプライズ CXO事業部 セールスグループ ヴァーラモフ・ダニイル氏による講演は「ユナイテッドアローズが実証! 商品ページLCP約1秒改善&CVR4%向上! EC光速化の秘策」
※LCP=Largest Contentful Paint(最大視覚コンテンツの表示時間)
ファン化から良循環を形成するCRM・CX戦略
宮下教授が挙げた4つのパフォーマンス要因と次元が違う課題もある。「必要性の消滅(ニーズ・利用環境の変化)」だ。言い換えれば、社会の変化は生活スタイルの変化をもたらすものであり、「生活者の視点で何が必要か、どうすれば快適か」といった顧客ニーズを把握することが重要になる。
これを含めて「サイレントカスタマー」という課題に向き合わなければならない。その根源は、「表面化していない不満」である。これについて宮下教授は670人を対象とする「サブスクリプションに関するヒアリング調査」(2023年)を行った。サブスクを解約した理由について聞いたところ、不満なくやめた人は50%であった。ところが、解約時にその理由を聞き取る機能がついているにもかかわらず、解約の理由を企業に伝えていない人が70%を占めたのである。
「諸外国における同様の調査では解約理由を企業に伝えない人は20~30%なので、この調査結果は、諸外国と比べて日本にサイレントカスタマーが圧倒的に多いことを裏づけることになりました。問題は、解約者による口コミです。SNSによる発信も増える傾向にあることから、ネガティブなコメントや低い評価によるレピュテーションリスクは今後ますます増加する可能性が高いといえるでしょう」(宮下教授)
マーケティングの重要な命題として、新規顧客の獲得に目を奪われがちだが、宮下教授は、賢くシビアな目線の消費者が増えている競争市場において、リテンションマーケティング(既存顧客のリピート化や長期契約)の重要性を強調する。
「リテンションマーケティングは、守りの経営を強化するような地味な施策に映りがちですが、実は、顧客と向き合う自社の姿勢やポリシーを再点検する機会であり、これに気づけば、顧客ロイヤリティ・顧客生涯価値(LVT)・ブランドイメージの向上、収益の安定をもたらし、表面化しなかった物言わぬ既存顧客(サイレントカスタマー)への対応強化を通じたサービス品質の充実・魅力化を実現しうるのです」(宮下教授)
宮下教授の指摘は、EC市場で消費者にダイレクトにつながるようになり顧客接点が拡大する今日、どのようにして新規顧客を獲得し、既存顧客のロイヤリティを高め、顧客生涯価値を拡大していくかに多額の金と時間を投じるEC事業者に「ファン化とその良循環(CRM、CX)の形成」の重要性を再認識させるものである。
これについて、本カンファレンスから2つの事例を紹介する。
中川政七商店の「パーソナライズされたブランドコミュニケーションの実現」
 株式会社中川政七商店 経営企画室 中田勇樹氏
株式会社中川政七商店 経営企画室 中田勇樹氏
1つ目は、創業(享保元年<1916年>)300余年の老舗ながらSPA(製造小売)業態の確立やCRMデータのフル活用を通じてブランド戦略を成功へ導いた株式会社中川政七商店のブランド戦略である。同社は「デジタル上の『接心好感』を実現する」という価値基準のもとで、膨大な顧客データをベースにしたCX(顧客体験価値)向上で「パーソナライズされたコミュニケーション」を徹底している。
具体的には、約4000点に及ぶ商品のカテゴリーに基づくクラスタリングである。属性や購買行動による従来のセグメンテーションではなく、顧客データから「行動が似ているユーザー」をいくつかのクラスター(括り)に分けるアプローチだ。
「お客様の購買金額に基づくランクやセグメントは、『接心好感』から見て適切ではないという課題を感じていました。またお客様一人ひとりのCXをストーリーとして理解するのは困難ですが、クラスターと購入頻度などを総合的に分析することでストーリーを浮き彫りにします」(株式会社中川政七商店 経営企画室 中田 勇樹氏)
ストーリーが見えれば、別のクラスターへの移行といった顧客の行動変化に伴うコミュニケーション対応も推測できる。メルマガ、ROAS(広告費用対効果)などの管理コストを大幅に削減できることにもクラスタリングの優位性がある。「伝えるべき情報を整理し、クラスターごとに正しく伝えることは、中川政七商店のブランディングの根幹を成すと考えています」と中田氏が語るように、AIをはじめとする最先端の技術、ツールを駆使する中川政七商店の取り組みは、CX戦略がブランドの屋台骨となる好例である。
カンロが取り組む「EC×ファン化戦略」
 カンロ株式会社 マーケティング本部 CX推進部 チーフマネージャー 武井優氏による講演は「カンロが取り組んできたEC×ファン化戦略 ~戦略策定から実現に向けて乗り越えた壁とは~」
カンロ株式会社 マーケティング本部 CX推進部 チーフマネージャー 武井優氏による講演は「カンロが取り組んできたEC×ファン化戦略 ~戦略策定から実現に向けて乗り越えた壁とは~」
2つ目は、2021年にオープンしたオンラインショップ「Kanro POCKeT(カンロポケット)」が成功を収める大正元年(1912年)創業の老舗菓子メーカー、カンロ株式会社のファン化戦略である。
カンロは主要商品の飴やグミの《ファンづくり》に徹するCRM戦略を追求し、売上、利益とも過去最高を更新している。その原動力となっているのは、企業ブランドとECを連携させるファン化戦略だ。カンロ株式会社 マーケティング本部 CX推進部 チーフマネージャー 武井優氏いわく、「目指したのは、WEBやテクノロジーをテコにしてカンロが積み上げてきたビジネス資産を活用・強化し、CXを向上させ選ばれるブランドになること」。
こうして「カンロのファン醸成」を目的に掲げたデジタルマーケティングのプロジェクトが発足した。目的が決まれば、顧客エンゲージメントの強化策を全社的な取り組みに展開したいところだが、既存の流通プロセスや商品パッケージではブランド価値を十分に伝えきれない。となれば、「WEB上のコンテンツや専用商品などのCRM強化によるコミュニケーションによって顧客に正しく伝える」ことに集中する必要がある。具体的には、コミュニティの育成、コミュニケーションの強化、特典やイベントなどの導入、アンケートやSNSを通じた顧客の声の収集・活用などである。
「オンラインショップはもちろん、コミュニティサイト、全商品のブランドサイト、商品情報、お客様サポートなどの顧客接点を『Kanro POCKeT』に集約しています」(武井氏)
同社が挑んだ改革は、顧客データの収集・分析に始まる「顧客起点のマーケティング改革」の縮図である。その道のりは、組織体制の構築、部門間連携など、組織を活性化する取り組みでもあった。
両社に共通するのは、企業ブランドとECの連携、CXの向上を目指したCRMシナリオである。ECサイトの持続的成長を導く両社のようなCRMマネジメントの継続と進化に注目していきたい。
懇親会で新たな出会いも
ソリューションピッチには株式会社ReviCo、株式会社ADWAYS DEEE、successfee株式会社、STORES株式会社、株式会社QuickCEPの5社が登壇し、自社のサービスを紹介。セミナー後に開催した懇親会では登壇企業と参加者が集まり、対面ならではの活発な情報交換が行われた。

写真左から株式会社ReviCo 執行役員 / グロース・プロダクト・マネージャー 吉岡真宏氏、株式会社ADWAYS DEEE アドテクノロジーDiv シニアプロダクトマネージャー 小田修平氏、successfee株式会社 COO 萩原竜希氏、STORES株式会社 ビジネスグロース部門 事業推進本部 事業推進グループ 橋本桃子氏、株式会社QuickCEP 代表取締役 李佳騏氏
 「顧客体験を向上させる『CRM物流』の重要性 ~物流でEC通販の売上を飛躍させる秘訣とは?~」をテーマに、セミナーに登壇した株式会社スクロール360 中日本ロジサポート部 部長 大野恭典氏
「顧客体験を向上させる『CRM物流』の重要性 ~物流でEC通販の売上を飛躍させる秘訣とは?~」をテーマに、セミナーに登壇した株式会社スクロール360 中日本ロジサポート部 部長 大野恭典氏