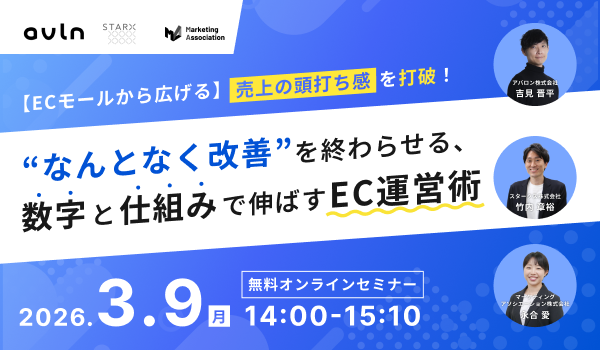「ファッションのパリ」VS「美容の東京」でアイスタイルが仕掛ける都市型フェス「Tokyo Beauty Week」の価値
 (左から)株式会社アイスタイル 代表取締役社長 遠藤宗氏、Tokyo Beauty Week総合スペシャルパートナー 千賀健永氏、Tokyo Beauty Week 総合プロデューサー/株式会社アイスタイル執行役員兼CCO 大木秀晃氏
(左から)株式会社アイスタイル 代表取締役社長 遠藤宗氏、Tokyo Beauty Week総合スペシャルパートナー 千賀健永氏、Tokyo Beauty Week 総合プロデューサー/株式会社アイスタイル執行役員兼CCO 大木秀晃氏
株式会社アイスタイルが企画・運営を手掛け、2025年11月19日から25日まで1週間にわたって開催されている都市型ビューティフェスティバル「Tokyo Beauty Week」。コンセプトは「ファッションの聖地パリ」に対する「美容の聖地・東京」の確立だ。
月間利用数約1900万人の美容プラットフォーム「アットコスメ(@cosme)」を展開するアイスタイルが、なぜ今、あえて「リアルな都市」にこだわるのか。そこには、ECとリアル店舗の垣根を超え、東京という街全体を巻き込んだ壮大なOMO戦略があった。本記事では、10月28日に行われたプロジェクト発表会の様子とともに、アイスタイルが描く次世代の顧客体験(CX)についてレポートする。
Tokyoの「美容の聖地化」をめざす、壮大なプロジェクトの第一歩
どうして今、「ファッションの聖地パリ」VS「美容の聖地東京」なのだろう?――2025年10月28日に開催された「Tokyo Beauty Week」プロジェクト発表会で浮かんだ最初の感想である。
リサーチプランナーの大木秀晃氏は、プロジェクトのコンセプトについて次のように説明した。
「Tokyo Beauty Weekはメイクやスキンケア、ウェルビーイングなどのビューティカルチャーの最前線を発信する新たなイベントです。テーマは「What’s your beauty? What’s next beauty?」。東京という街の多様性や創造性がビューティカルチャーの中心地となる可能性をアピールし、『ファッションの聖地パリ』に対する『美容の聖地』にします」
一見、「聖地」という言葉はレトロに響くかもしれない。今や世界中がインターネットでつながり、情報共有されている。先進国であれば地方にいても、懐事情が許す限りファッションでもコスメでも欲しいものを取り寄せることができる。そんな時代に、リアル世界での「聖地」が存在するのだろうか。少なくとも、社会や市場の中心となりつつあるZ世代に「ファッションの聖地はパリ」という概念は存在しないのではないだろうか。
たとえば、アニメのコスプレーヤーなら、聖地はお気に入りのアニメやお手本にしたい人(いわゆる“神”)の中にある。パリだの東京だのの“3次元世界”に聖地が存在するわけではない。聖地は人それぞれ。あるいは共通の価値観でつながったグループごとに存在する仮想空間だ。
Z世代の消費行動において、「聖地」が「推し活」や「コミュニティ」の象徴として再定義されていると考えて気が付いた。「ファッションの聖地パリ」と言われてしっくりくるのは、上の世代(Z世代の父母、祖父母)まで。「美容の聖地・東京」は、プロジェクトを企画・運営するアイスタイルがこれまで@cosmeで提供してきたネットとリアルが融合した「Tokyo」そのものなのではないかと。実際、アイスタイルはオンライン(@cosme)から出発した企業だが、現在では売上高の3分の1以上を実店舗「@cosme STORE」が占めているという。
「Tokyo Beauty Week」は、ネットとリアルの境界を取り払い、コスメ企業やファッション、メディアだけでなく、ビューティーにはもっとも疎遠なイメージがある自治体をも巻き込んで、ほぼオールジャパンでTokyoの「美容の聖地化」をめざした「体験価値」の創出であり、壮大なプロジェクトの新たな一歩なのである。
「失敗はもういらない」消費者インサイトを突くスペシャルパートナー千賀健永さんのメッセージ
「Tokyo Beauty Week」のスペシャルパートナーに就任した千賀健永氏は、男性アイドルグループKis-My-Ft2のメンバーだ。グループいちの「美容男子」で、成分を深掘りするシリーズ「エビデンスおばけ千賀くん」が好評なYouTubeのフォロワーは現在12.2万人。当日はラメが輝く白のスーツをまといランウェイに颯爽と登場した。さすがアイドルである。
 スペシャルパートナーの千賀健永氏は、「光栄な気持ちでいっぱいです。本当にうれしかったです。男女限らず1人でも多くの人に、美容の楽しさ、そして美容と向き合った先に幸せがあるんだよっていうことを届けたいと思います」と語った。
スペシャルパートナーの千賀健永氏は、「光栄な気持ちでいっぱいです。本当にうれしかったです。男女限らず1人でも多くの人に、美容の楽しさ、そして美容と向き合った先に幸せがあるんだよっていうことを届けたいと思います」と語った。
ランウェイを歩いた千賀氏は、「(ウォーキングは)少し恥ずかしいけど、今年Kis-My-Ft2のコンサートでランウェイのセットを組んでいたので、歩くっていうところで少しリンクしました。このイベントのテーマでもある『一歩踏み出す勇気』は、本当に僕も美を追求するようになって心も明るくなりましたし、人間関係もすごく豊かになりました。そういう変化を1人でも多くの人に知ってほしい」と感想を述べた。
続くトークセッションでは、「自分を知る」にフォーカスしたビューティー・プロフィールが披露され、司会者が舌を巻くほどの美容知識を披露。「美容関係の仕事をしていた母親の影響で、小学3年生の時には学校に、水筒ではなく、ヒアルロン酸と書かれた化粧水を持って行っていた」といった驚きのエピソードを明かし、会場を沸かせた。
ただ、この日、もっとも記者の心に刺さったコメントは、「失敗はもういらない」という言葉だった。これは、EC事業者にとっても、ハッとさせられるキーワードだろう。
美容は、ファッション以上にパーソナルで、その日その時の気分、ファッション、体調によっても合う・合わないが違ってくる。それゆえEC購入における最大の障壁は「自分に合うかわからない」という不安(失敗への恐れ)だ。生活者は通常、失敗をなんども繰り返して、本当に自分に合うコスメやメイクにたどり着く。メーカーや美容部員、インフルエンサーの言葉は参考にはなるが、最後に答えをくれるのは自分自身の感覚だ。今回のイベントが提供するのは、まさにこの「失敗のリスク」を取り除くためのリアル体験だ。
特に、東京・原宿のイベントスペース、ヨドバシJ6ビルディングで開催される体験型ビューティーイベント「Tokyo Beauty Studio」では、失敗の憂鬱から生活者を解き放ち、新しい自分の魅力に出会える、さまざまな体験型コンテンツが登場する。
ビューティークリエイターのカウンセリングによって自分を知り、メイクやスキンケアをアップデートし、仕上げに、プロカメラマンによるポートレートを撮影する一連の体験は、普段の日常ではなかなか出来ない特別なものになるだろう。
タブレットから肌質・パーソナルカラーがわかる肌質・パーソナルカラー診断。客観的なデータで自分の肌や魅力を知ることができ、今後のビューティーの参考にできる。診断結果はカードとして持ち帰ることができる。
ずらりと並んだビューティアイテムや、このイベントのために集結した国内外で話題の約50プランドが揃う、コスメ好きにはたまらないリアル空間。Beauty Checkの診断カードをもとに、新しいコスメとの出会いを楽しめる。
ブランドブースで紹介したアイテムを自由にタッチアップできるスペース、プロによるカウンセリングや撮影、ゲストによるコンテンツが用意されている。自分に合ったアイテムを探したり、メイクやスキンケアをアップデートしたり、思い切り使い倒して「新しい自分」に出会う成功体験が叶う。
2026年のビューティートレンドを予測する7日間が「ビジネスチャンス探索の場」に!
「Tokyo Beauty Week」は、@cosmeのプラットフォーム内に留まらず、ブランドやメディア、街、他産業、行政などとコラボレーションすることで生活者とブランドに新たな出会いの場を創造する。
アイスタイルの遠藤宗社長はプロジェクト発表会でメディアを前に、「@cosmeは25年にわたってオンライン・オフラインの双方でビューティーにまつわる情報や体験を提供してきました。今後は、『ビューティーの世界をアップデートしながら、多くの人を幸せにしよう』というミッションの実現に向け、@cosmeのプラットフォーム外での生活者とブランドの出会いを生み出す仕掛け作りや、さまざまなステークホルダーとの共創を積極的に推進していきます」と宣言した。
確かに、「Tokyo Beauty Week」のコンテンツは、生活者だけでなく、さまざまなステークホルダーにとっても興味を惹かれる魅力がある。
たとえばイベント期間中の11月20日には、美容および関連領域で革新的な企業・プロジェクトを表彰する「Japan BeautyTech Awards」第6回の授与式を行われた。
これに先立つ11月19日には、実際に商品を使用したメンバーから、この1年間に@cosmeに寄せられたクチコミ投稿をベースに、今、生活者が支持している商品をランキング形式で表彰する「@cosmeベストコスメアワード」(※1)が発表された。
さらに、@cosmeベストコスメアワードの関連企画であり、今後の生活者インサイトや美容トレンドを予測するべく発足された「@cosmeトレンド予測部」が、@cosmeに投稿されたクチコミや@cosme STORE/@cosme TOKYO、@cosme OSAKAでの売上等、その他ユーザーアンケートなど関連情報から見える生活者の意識変化と美容プラットフォーマーとしての知見を分析し、次の半年のトレンドキーワードを「2026上半期トレンド予測」として発表している(※2)。
生活者の購買行動が変容し続ける中、このコンシューマー向けのイベントは、EC事業者にとって見逃せないビジネスの場となる。最新のトレンド予測やOMOの成功事例を肌で感じる絶好の機会となるはずだ。好奇心を解き放ち、東京・原宿で「美容の未来」を目撃してはいかがだろうか。
※1:関連記事 「@cosmeベストコスメアワード2025」発表 2年連続スキンケアカテゴリが総合大賞
※2:関連記事 @cosmeが2026年上半期トレンド予測 「美湯~ティタイム」など6キーワードを発表