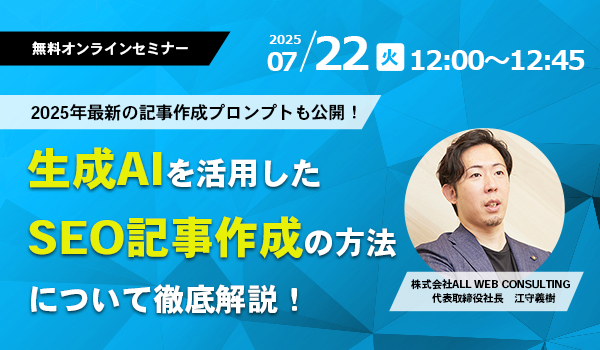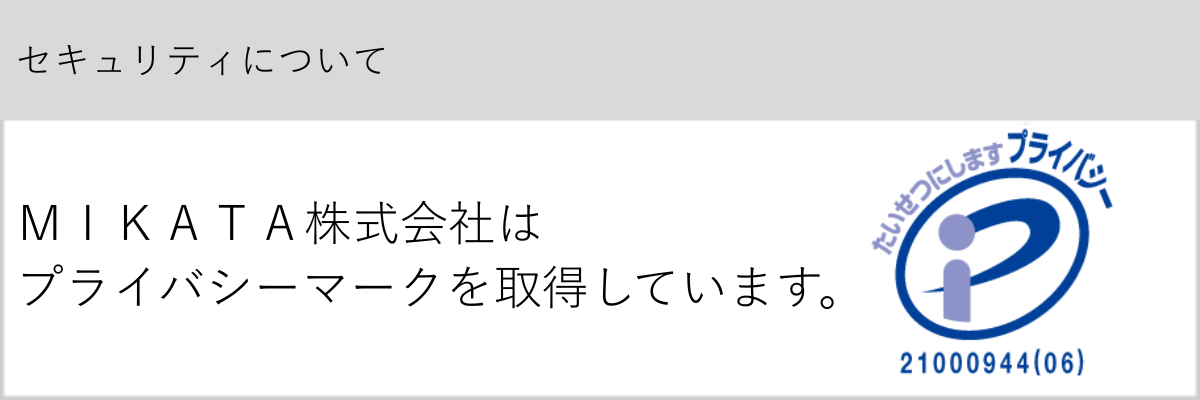利用規約、きちんと作れていますか?弁護士がポイントを徹底解説①

ECを始める際に必要になるのが、WEBページなどに置く利用規約です。作成の際にノウハウがなく、事業内容が似ている他社の例を参考にする事業者も多いのではないでしょうか。それだけではリスクにさらされる可能性も・・・。
本稿では2回にわたり、作成の際の注意点を大形航弁護士が解説します。どの法律が根拠になるのかも記しますので、法務担当者の方にお役立ていただければ幸いです。
利用規約とは?
ECサービス等において利用者に一律に適用される利用規約は、民法上は「定型約款」と位置付けられます。
①利用規約を利用者に表示し、②利用者から、利用規約を契約内容とすることの同意を得た場合には、利用者が個々の条項の内容について把握していなくとも、事業者と利用者との間で利用規約に基づく契約が締結されたものとみなされます(民法548条の2第1項)。
利用者の利益を一方的に害するものは無効の可能性も
ただし、「どのようなものでも良い」訳ではなく、利用者の利益を一方的に害するような内容の条項は、無効と判断される可能性があります(民法548条の2第2項、消費者契約法8~10条等参照)。
利用規約は、いざ利用者との間でトラブル等が生じた場合には、事業者の対応の正当性を裏付ける根拠となり得ます。クレーム対応に際しても、規約の内容をきちんと説明することで、利用者の理解を得られる場合もあり得ます。
利用規約は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、トラブル対応等を見越し、事前に十分な検討を行った上で作成することをお勧めします(なお、利用規約と別途に利用者の個人情報の取扱いについてプライバシーポリシーを定めることも多く、その内容については別の機会に解説する予定です)。
他社で使われているからOK!とも限らない
実際にどのように利用規約を作成するかについては、まずはウェブサイトで公表されている他社事例を参考にすることが便利ではありますが、有名企業の利用規約であっても法的に無効とされることもあります(近時では、ポータルサイトのサービスの利用規約につき、会員資格の停止・取消要件や事業者の免責について規定した条項が明確性を欠くとして、無効とされた事例もあります)。
他社の利用規約の条項が必ずしも自社のサービスに合致しているとも限りません。
そこで、以下では、利用規約作成にあたって、注意が必要だと思われるポイントを、いくつかご紹介していきます。
利用規約の内容

ここからは、具体的に利用規約で注意するべきポイントを解説していきます。
(1)個別契約の成立時期
物の売買を例にすると、民法の原則では、「申込み」に対する「承諾」が到達することにより、売買契約が成立することとなります(民法522条1項)。
つまり、利用者が(「購入」ボタンをクリックする等して)商品を購入するという申込みをしただけでは売買契約は成立せず、事業者側が申込みに応じる旨の意思表示を行うことにより、当該商品について売買契約が成立することとなります。どの時点で承諾が到達したといえるかについては、利用者が、事業者からの承諾メールを(文字化け等することなく)受信できた時点や、webサイト上で申込みを承諾する旨を表示した時点等がこれにあたると解されています。
どの時点で契約を成立させるかについては、具体的なサービスの内容を踏まえて利用規約で明記すべきですし(例えば、事業者側が在庫の有無を確認して利用者に通知を行うといったことも考えられます)、利用規約のみでなく、webサイトの運用にあたっては利用者にこれを分かりやすく示すこともトラブル回避に繋がります。
また、契約の成立時期に関連して、事業社側が申込みを拒否できる場合を予め明記するといったことも考えられます。一般的には、在庫の不足や、過度に大量の注文、転売目的が疑われる場合等が考えられるかと思いますが、具体的なサービスの内容を踏まえ、申込みを拒否できる場合を具体的に規定しておくことで、クレーム対応がしやすくなる場合もあります。
(2)利用対象者
利用対象者の限定を設けないECサービスも多いかと思いますが、未成年者の利用を認めるかどうかについては、予め検討した方が良いでしょう。
民法の規定上、未成年者の法律行為は、未成年者が単に権利を得るのみ(又は義務を免れるのみ)である場合や、小遣い等の処分を許された範囲に留まる場合を除き、法定代理人(親権者又は未成年後見人)の同意がない限りは、原則として取り消すことができます(民法5条2項、1項)。
民法の規定では、未成年者が「詐術」、すなわち、自身が未成年者でない、又は法定代理人の同意が得られていると偽った場合には取り消しは制限されるものの(民法21条)、ECサービスの利用等にあたって、どのような場合に「詐術」となるかは、明確な基準はありません。
事業者としては、未成年者の利用を認める場合には、(手間と費用をどの程度かけるかにもよりますが)webサイトの入力フォームでの年齢確認のみでなく、親権者の同意があることを書面や身分証等と供に確認する等の対策をすることで、取消しのリスクを低減させることができると考えられます。
事業者としては、以上の取消のリスクを加味した上で、法定代理人の同意を得ることを条件にサービスの利用を認めるのか、利用できるサービスに一定の制限を設けるのか、そもそも未成年者の利用を禁止するかについては、事前に検討を行い、利用規約にも明記した方が良いでしょう(なお、2022年4月1日以降は、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられますので、その点にも注意が必要となります)。
(3)返品特約
物の売買等においては、利用者から返品を求められる場合もあると思います。
特定商取引法上、通信販売においては、利用者は商品到着日から8日を経過するまでの間は申込みの撤回や契約解除をすることができるとされているものの、これとは異なる合意をすることも認められています(特定商取引法15条の3第1項)。
事業者において「返品特約」、すなわち取引で適用される返品に関するルールを定めた上で、利用者に対し明確に表示していた場合は当該8日以内の撤回・解除に関するルールは適用されないこととなっており(同法規則16条の3)、実際上は多くの事業者において、「返品特約」を定めることで、利用者からの返品を一定程度制限しています。
事業者においては、どのような場合に返品を認めるか(利用者の都合による返品は一切認めないのか、一定の場合には返品に応じることとするのか等)を定めた上で、利用規約に規定し、さらに、実際の取引に際してその内容をwebサイト等で消費者に示す必要があります(消費者庁が「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」を示しているので、webサイトでの表示方法について参考にすると良いと思います。)
(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2016/
(4)契約不適合責任
上記の返品特約とも関係しますが、利用者から商品の欠陥等を指摘される場合もあるかと思います。
民法の原則では、契約不適合責任(2020年4月1日からの民法改正以前は、瑕疵担保責任と呼ばれていました)として、商品の種類・品質・数量が契約内容に適合していない場合は、売主は履行の追完請求(補修や代替物等の引渡し請求)、代金の減額請求、損害賠償請求又は契約解除権等ができることとされています(民法562~564条)。
ここで、種類・品質の不適合については、買主は不適合を知ってから1年以内に通知をすることが必要とされています(民法566条1項)。
もっとも、これはあくまでも原則的なルールであり、それとは別途の合意をすることは可能です。例えば、利用者に購入後一定期間内に商品の状態を確認するといった義務を課した上で、それ以降は契約不適合責任を追及する権限を制限するといった規定を設けることが考えられます。
また、事業者の損害賠償の範囲を限定する条項を規定することも考えられますが、後述のとおり場合によっては無効とされる可能性もあります。
また、利用者に商品の欠陥等を伝えていなかった場合には、免責の効果が得られないとされており(民法572条)、例えば中古品の取引で顕出されていない欠陥等が存在し得る場合には、その旨を予め利用者に明示し、欠陥が存在し得ることを前提とした取引にすることが必要となります。
なお、契約不適合責任について利用規約等で規定を設ける場合には、その内容を利用者に対して示すことが求められるので(特商法11条5号、同法規則8条5号)、上記の返品特約を定める場合には、それと合わせてwebサイト等で表示するのが良いでしょう。
(5)免責条項
「事業者は一切責任を負わない」といった条項を利用規約で定めれば、利用者からの責任追及を防げるかというと、そうではありません。
消費者契約法は、事業者の責任を全部免除する条項、事業者に故意や重大な過失がある場合に責任の一部を免除する条項は無効とされており、この他にも、事業者の債務不履行が生じた場合の消費者の解除権を放棄させる条項等、消費者の利益を一方的に害する条項は、無効と判断される可能性があります(消費者契約法8条~10条、民法548条の2第2項)(「故意」とは、権利侵害が生じること(或いはその可能性)を認識しつつ、あえて行為を行うことをいい、「重大な過失」とは、著しい不注意により権利侵害を認識せずに、侵害を回避するために必要な対応を怠ることをいいます)。
どのような場合に「消費者の利益を一方的に害する」といえるかはケースバイケースの判断となりますが、例えば、事業者の損害賠償義務の上限額を設ける場合でも、利用者が被る損害と比較してあまりにも均衡がとれていない場合には、無効と判断されるリスクは高くなります。
もっとも、無効となっても良いから、とりあえずは事業者に有利な規定を設けておきたい、といった意見もあるかもしれません。しかしながら、近時ではインターネット検索により、利用者も法律のルールについてそれなりに容易にアクセス可能となってきていますし、あまりにも不平等な利用規約は、SNS等で批判され、サービスのレピュテーションが低下するといった可能性も否定できません。事業者側に有利な条項を設けるとしても、あまりにも一方的な内容は避けた方が良いという判断もあり得るところです。
次回は、利用規約の内容の続き「禁止事項」や「契約の終了」などを解説します。7月中旬ごろ公開予定です。