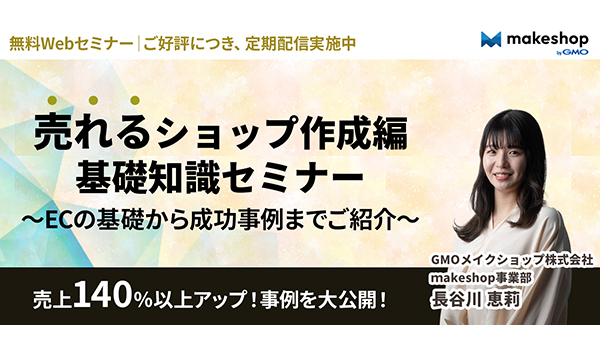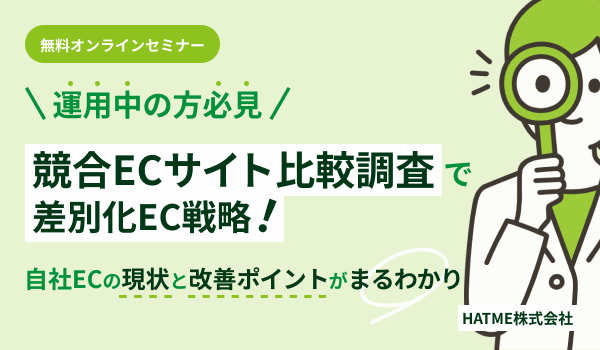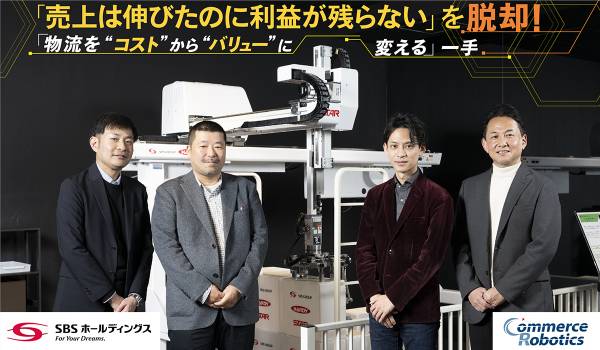UGCとは?コンテンツの種類や活用事例、施策案について解説

ECサイトを運営するうえで、広告やSEOだけに頼るのではなく、新しい集客方法を取り入れることが大切です。最近注目されているのが、一般のユーザーや購入者によって作られたコンテンツ(UGC:User Generated Content)です。
この記事では、ECサイトでUGCを活用するメリットや具体的な活用方法、注意点について分かりやすく解説します。商品の魅力をしっかり伝え、売上につなげるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
UGCとは?
UGC(User Generated Content)とは、商品やサービスを実際に使った一般ユーザーが作るコンテンツのことです。例えば、写真・動画・商品レビュー・SNSの投稿などがUGCにあたります。
ECサイトでよく見られるのは、商品を購入したユーザーが投稿する「使ってみた感想」や「実際に商品を使っている写真」などです。
企業が作る広告とは違い、実際の利用者のリアルな声が反映されるため、商品を検討している人にとって参考になりやすいという特徴があります。
PGCとの違い
PGC(Professional Generated Content)とは、企業やプロが作成する広告や商品紹介コンテンツのことです。例えば、専門の写真スタジオで撮影された商品写真、プロのライターが書いた商品紹介記事、企業の公式SNS投稿などがPGCにあたります。
一方、UGCは一般の購入者が発信するコンテンツで、例えばInstagramやX(旧Twitter)に投稿された商品を使った写真、ECサイトのレビューなどが該当します。
CGMとの違い
CGM(Consumer Generated Media)とは、消費者が自由に情報を発信できるメディアやプラットフォームのことです。例えば、InstagramやX(旧Twitter)などのSNS、食べログのような口コミサイトがCGMにあたります。
UGCは投稿されるコンテンツ、CGMはその投稿が集まる場という違いがあります。例えば、ECサイトの「商品レビュー機能」はCGMで、そこに投稿されたレビューや写真がUGCにあたります。
また、CGMには消費者同士がコミュニケーションを取る機能があるのが特徴です。「参考になった」ボタンや、質問に対する回答機能などもCGMの一部です。
UGCとCGMは密接な関係があり、使いやすいCGMを整えることで、より多くのUGCが集まりやすくなります。
UGCツールとは
UGCツールは、顧客が作成したコンテンツを効率的に集めて活用するためのシステムやプラットフォームのことです。
例えば、Instagramのハッシュタグをもとに、投稿された商品写真を自動で収集し、ECサイトの商品ページに表示できるツールがあります。また、投稿された商品レビューを管理し、不適切な内容を防いだり、投稿者とやり取りができる機能を備えたツールもあります。
ECサイトの商品数が多い場合や、大規模キャンペーンを実施してSNS上で多くのUGCが集まる場合、手作業での管理は大きな負担になります。UGCツールを活用することで、運営担当者の作業を効率化しながら、UGCを活用しやすくなり、商品の魅力をより効果的に伝えられます。
あわせて読みたい:
UGC活用ツールの特徴は?いろいろなUGC活用ツールを比較してみよう
UGCがマーケティングにおいて注目される背景
商品やサービスの評価につながるUGCは、マーケティングでも重要視されています。
その背景には、SNSの普及や消費者の購買行動の変化があります。XやInstagramなどのSNSでは、消費者が日常的に商品やサービスの感想を投稿し、企業にとっては消費者ニーズの把握や商品改善のヒントとなる貴重な情報源になっています。
また、Web広告やCMを「煩わしい」と感じる人が増える中、企業と利害関係のない一般消費者の意見であるUGCは、より信頼されやすい情報として価値が高まっています。
さらに、購買プロセスにも変化が起きており、「SNSで評判を確認してから購入する」という流れが浸透し始めています。特に、新型コロナの影響で外出を控え、オンライン上の情報を参考にする傾向が強まっており、UGCの重要性はさらに高まっているといえるでしょう。
UGCのコンテンツの種類
ECサイトで活用できるUGCにはさまざまな形があります。顧客が商品を使った感想や体験を共有する方法は年々増えており、それぞれ異なる効果があります。
ここでは、実際のECサイトで活用されているUGCの種類について、具体的な例を交えながら説明します。
SNSでの投稿
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでの投稿は、最も身近なUGCのひとつです。顧客が商品を使用している様子や、商品が生活の中でどのように役立っているかを写真や短い文章で紹介できます。
例えば、ファッションECでは、購入者が投稿したコーディネート写真を商品ページに掲載することで、実際の着こなしがイメージしやすくなります。
家具・インテリアのECサイトでは、実際の部屋に設置した写真を集めることで、サイズ感や空間での雰囲気が伝わりやすくなります。
このように、SNSでの投稿は視覚的な情報を提供し、購入を後押しする効果があります。
レビュー・評価・口コミ・ブログや掲示板での投稿
商品レビューや口コミは、ECサイトに欠かせないUGCのひとつで、購入を検討している人の意思決定に大きく影響します。 実際に商品を使った顧客が、使用感や満足度を投稿することで、ほかの消費者にとって貴重な参考情報になるからです。
例えば、化粧品のECサイトでは、肌質や年齢とともに使用感を詳しく書いてもらうことで、同じ悩みを持つ人の判断材料になります。
家電のECサイトでは、商品の性能だけでなく、設置のしやすさやメンテナンスのコツも共有されるため、購入前の不安を解消できるでしょう。
また、多くのECサイトでは、★の数で評価できる機能を導入し、商品の総合的な評価を分かりやすく表示しています。これにより、購入検討者が短時間で商品の良し悪しを判断しやすくなるのです。
動画コンテンツ
動画形式のUGCは、商品の使い方や機能を視覚的に伝えやすいのが特徴です。特にTikTok、YouTubeショート、Instagramリールなどの短尺動画プラットフォームでの活用が増えています。
例えば、調理家電のECサイトでは、購入者が実際に料理をしている様子を動画で紹介することで、商品の使い勝手や仕上がりのイメージを具体的に伝えられます。
動画コンテンツは情報量が多く、文章や写真では伝えにくい商品の魅力を直感的に表現できる点が強みです。
写真・画像コンテンツ
写真や画像のUGCは、商品の実物やサイズ感、色味をリアルに伝えられるのが特徴です。ECサイトでは、公式写真だけでなく、購入者が撮影した写真も掲載するのが一般的になっています。
例えば、アパレルECサイトでは、顧客の着用写真を掲載することで、服のシルエットやサイズ感、着こなし方のバリエーションを視覚的に伝えられます。 特に、SNSと連携した「#今日のコーデ」などのハッシュタグキャンペーンは、UGCを集める効果的な方法です。
Q&A(質問・回答機能)コンテンツ
Q&A形式のUGCは、顧客同士が商品に関する疑問を解決し合う仕組みで、FAQ(よくある質問集)を補完する役割があります。ECサイトに質問機能を設置することで、商品説明だけでは分からない細かな使用感や注意点を共有できるのが特徴です。
例えば、スポーツ用品のECサイトでは、初心者が経験者に用具の選び方やメンテナンス方法を質問することがあります。 家電のECサイトでは、設置方法や故障時の対処法など、具体的な困りごとについて質問し、実際の使用者からアドバイスを得られることもあります。
Q&A機能は、顧客のリアルな声をもとに商品理解を深められるため、購入を迷っている人の不安解消につながります。
ゲームコンテンツ
ゲーム要素を取り入れたUGCは、顧客の参加意欲を高め、楽しみながら情報発信を促す仕組みです。例えば、SNSでのハッシュタグを活用した参加型キャンペーンが挙げられます。
キッチン用品のECサイトでは、商品を使ったレシピコンテストを開催し、顧客が考案したレシピや調理風景を投稿してもらうことができます。
ゲーム的な要素を加えることで、顧客は投稿すること自体を楽しみながら、より詳しい商品活用法を共有してくれるため、効果的なUGCの獲得につながります。
UGCがマーケティングにおいて注目される背景
商品やサービスの評価につながるUGCは、マーケティングでも重要視されています。
その背景には、SNSの普及や消費者の購買行動の変化があります。XやInstagramなどのSNSでは、消費者が日常的に商品やサービスの感想を投稿し、企業にとっては消費者ニーズの把握や商品改善のヒントとなる貴重な情報源になっています。
また、Web広告やCMを「煩わしい」と感じる人が増える中、企業と利害関係のない一般消費者の意見であるUGCは、より信頼されやすい情報として価値が高まっています。
さらに、購買プロセスにも変化が起きており、「SNSで評判を確認してから購入する」という流れが浸透し始めています。特に、新型コロナの影響で外出を控え、オンライン上の情報を参考にする傾向が強まっており、UGCの重要性はさらに高まっているといえるでしょう。
UGCのコンテンツの種類
ECサイトで活用できるUGCにはさまざまな形があります。顧客が商品を使った感想や体験を共有する方法は年々増えており、それぞれ異なる効果があります。
ここでは、実際のECサイトで活用されているUGCの種類について、具体的な例を交えながら説明します。
SNSでの投稿
InstagramやX(旧Twitter)などのSNSでの投稿は、最も身近なUGCのひとつです。顧客が商品を使用している様子や、商品が生活の中でどのように役立っているかを写真や短い文章で紹介できます。
例えば、ファッションECでは、購入者が投稿したコーディネート写真を商品ページに掲載することで、実際の着こなしがイメージしやすくなります。
家具・インテリアのECサイトでは、実際の部屋に設置した写真を集めることで、サイズ感や空間での雰囲気が伝わりやすくなります。
このように、SNSでの投稿は視覚的な情報を提供し、購入を後押しする効果があります。
レビュー・評価・口コミ・ブログや掲示板での投稿
商品レビューや口コミは、ECサイトに欠かせないUGCのひとつで、購入を検討している人の意思決定に大きく影響します。 実際に商品を使った顧客が、使用感や満足度を投稿することで、ほかの消費者にとって貴重な参考情報になるからです。
例えば、化粧品のECサイトでは、肌質や年齢とともに使用感を詳しく書いてもらうことで、同じ悩みを持つ人の判断材料になります。
家電のECサイトでは、商品の性能だけでなく、設置のしやすさやメンテナンスのコツも共有されるため、購入前の不安を解消できるでしょう。
また、多くのECサイトでは、★の数で評価できる機能を導入し、商品の総合的な評価を分かりやすく表示しています。これにより、購入検討者が短時間で商品の良し悪しを判断しやすくなるのです。
動画コンテンツ
動画形式のUGCは、商品の使い方や機能を視覚的に伝えやすいのが特徴です。特にTikTok、YouTubeショート、Instagramリールなどの短尺動画プラットフォームでの活用が増えています。
例えば、調理家電のECサイトでは、購入者が実際に料理をしている様子を動画で紹介することで、商品の使い勝手や仕上がりのイメージを具体的に伝えられます。
動画コンテンツは情報量が多く、文章や写真では伝えにくい商品の魅力を直感的に表現できる点が強みです。
写真・画像コンテンツ
写真や画像のUGCは、商品の実物やサイズ感、色味をリアルに伝えられるのが特徴です。ECサイトでは、公式写真だけでなく、購入者が撮影した写真も掲載するのが一般的になっています。
例えば、アパレルECサイトでは、顧客の着用写真を掲載することで、服のシルエットやサイズ感、着こなし方のバリエーションを視覚的に伝えられます。 特に、SNSと連携した「#今日のコーデ」などのハッシュタグキャンペーンは、UGCを集める効果的な方法です。
Q&A(質問・回答機能)コンテンツ
Q&A形式のUGCは、顧客同士が商品に関する疑問を解決し合う仕組みで、FAQ(よくある質問集)を補完する役割があります。ECサイトに質問機能を設置することで、商品説明だけでは分からない細かな使用感や注意点を共有できるのが特徴です。
例えば、スポーツ用品のECサイトでは、初心者が経験者に用具の選び方やメンテナンス方法を質問することがあります。 家電のECサイトでは、設置方法や故障時の対処法など、具体的な困りごとについて質問し、実際の使用者からアドバイスを得られることもあります。
Q&A機能は、顧客のリアルな声をもとに商品理解を深められるため、購入を迷っている人の不安解消につながります。
ゲームコンテンツ
ゲーム要素を取り入れたUGCは、顧客の参加意欲を高め、楽しみながら情報発信を促す仕組みです。例えば、SNSでのハッシュタグを活用した参加型キャンペーンが挙げられます。
キッチン用品のECサイトでは、商品を使ったレシピコンテストを開催し、顧客が考案したレシピや調理風景を投稿してもらうことができます。
ゲーム的な要素を加えることで、顧客は投稿すること自体を楽しみながら、より詳しい商品活用法を共有してくれるため、効果的なUGCの獲得につながります。
ECサイトでUGC施策を行うメリット・期待される効果
ECサイトでUGC施策を展開することで、広告やプロモーションとは異なる効果が期待できます。
UGCを活用するメリットと期待される効果を見ていきましょう。
ユーザーの生の声による信頼性の向上
ECサイトの商品説明や広告は、企業が発信する情報ですが、消費者は企業の宣伝だけでなく、実際の購入者のレビューや体験談も重視します。
例えば、スキンケア商品のECサイトでは、肌質や年齢の近い購入者のレビューが、商品選びの参考になります。 実際に使った人のリアルな意見があることで、ユーザーは商品の使用感や効果を具体的にイメージしやすくなります。
企業が提供する公式情報に加え、UGCによる生活者目線の情報があることで、商品やECサイトへの信頼感が高まります。
コンテンツの自然な増加
UGCはSNSでの拡散力が高く、口コミのように自然に広がりやすいのが特徴です。購入者が自発的に投稿した写真や動画は信頼性が高く、友人やフォロワーの間で共有されやすくなります。
例えば、アパレルECサイトでは、購入者が着用写真をInstagramに投稿することで、それを見た友人がECサイトを訪れるきっかけになります。 キッチン用品のECサイトでは、購入者が作った料理の写真や動画がSNSで話題になり、新規顧客の獲得につながることもあるでしょう。
UGCを活用すれば、広告費をかけずに商品の認知度を高められるのが大きなメリットです。さらに、実際の使用者による自然な投稿は、広告よりも信頼されやすく、ECサイトのファン作りにもつながります。
購買率(CVR)の向上
ECサイトでは実物を確認できないため、購入前にさまざまな不安が生じます。 UGCは、企業が提供する情報では伝えきれない実際の使用感や注意点を補完し、不安を和らげる役割を果たしてくれます。
例えば、「サイズ感が分からない」「実際の色味が違うかも」といった不安も、購入者の投稿写真やレビューを参考にすることで解消できます。
UGCが充実すると、具体的な使用シーンや評価を知ることができ、購入を迷っている人の背中を押す効果が期待できます。商品説明や販売促進だけでなく、UGCを活用した不安解消策を取り入れることで、購買率の向上につながるでしょう。
UGCを活用したマーケティング施策の流れ
ECサイトでUGCを活用する際には、明確な目的と計画が必要です。闇雲にUGCを集めても効果が出るわけではありません。
ここでは、UGC活用の具体的な進め方について説明します。
1)UGC戦略の立案
UGC活用を始める前に、目的とターゲットを明確にすることが重要です。まず、UGCを通じて解決したい課題を特定します。例えば「商品の使用感が伝わりにくい」「新規顧客が増えない」といった具体的な課題です。
次に、どのような顧客からUGCを集めたいのかを考えます。アパレルECなら「20代の女性会社員」、家電ECなら「子育て中の主婦」など、具体的なターゲットを決めると施策が立てやすくなります。
そして、集めたいUGCの種類を決めます。商品レビュー、Instagram投稿、使用動画など、商品特性に合わせた最適な形式を選びましょう。
例えば、商品購入者にレビュー依頼メールを送る、SNSのハッシュタグキャンペーンを実施する、投稿者に特典を提供するなど、実行しやすい方法を検討します。
2)UGCの生成・収集
計画に沿って、実際にUGCを集めるフェーズに移ります。まず、商品を購入した顧客にレビューや写真投稿を依頼するメールを送ることが基本です。その際、投稿の目的や活用方法を明確に伝え、安心して投稿できる環境を整えることが大切です。
SNSでUGCを収集する場合は、商品に関連するハッシュタグを設定し、投稿を呼びかけます。 また、投稿のハードルを下げるために、撮影のコツや投稿例を示すのも効果的です。
例えば、アパレルなら「全身コーディネートの撮影方法」、食品なら「料理の盛り付け例」を紹介すると、投稿の質が向上するでしょう。さらに、投稿特典として割引クーポンを提供したり、優れた投稿を表彰したりすることで、ユーザーの参加意欲を高めることができます。
集めたUGCは、著作権や肖像権に配慮しながら適切に管理・保存し、次の活用フェーズにつなげます。
3)UGCの活用と効果測定
集めたUGCは、ECサイトの商品ページやメールマガジン、SNSなどで活用します。
商品ページでは、商品説明と一緒にレビューや使用写真を掲載し、購入を検討している人の参考情報として役立てます。メールマガジンでは、顧客の投稿を紹介しながら商品の魅力を伝え、SNSでは優れたUGCをシェアして、新たな投稿を促します。
UGCの効果は、商品ページの閲覧数や滞在時間、購入率の変化などで測定します。また、投稿数や内容の質、SNSでの反響なども確認し、施策を改善していくことが大切です。
ECサイトにおけるUGC施策の例
ECサイトでUGCを集める方法はさまざまですが、実際に効果を上げている具体的な施策を紹介します。
ここでは、ECサイトで実践しやすく、かつ効果が期待できる3つの代表的な施策について説明します。
購入後のレビュー獲得
商品レビューは、最も基本的なUGCのひとつです。
商品到着から1週間程度経過した顧客に、使用感想を投稿してもらいます。商品到着から1週間ほど経過したタイミングで、使用感の投稿を依頼しましょう。レビュー依頼メールには、書き方のポイントや参考になる投稿例を記載すると、顧客が書きやすくなります。
例えば、化粧品のECサイトでは「使用した時の肌の変化」「香りの印象」など、具体的な視点を示すと、詳細なレビューが集まりやすくなります。
また、レビュー投稿特典として次回使える割引クーポンを提供したり、写真付きレビューには追加ポイントを付与したりすると、投稿率を高めることができます。
投稿されたレビューは、商品ページに速やかに反映し、新鮮な情報として活用しましょう。
ハッシュタグを活用したSNSキャンペーン
InstagramやXなどのSNSで商品に関連するハッシュタグを設定し、投稿キャンペーンを実施しましょう。
例えば、アパレルECサイトでは「#春コーデ2024」のように季節感のあるハッシュタグを設定し、コーディネート写真の投稿を募集すると効果的です。投稿者には抽選で商品券をプレゼントしたり、優れた投稿を公式アカウントで紹介したりすることで、参加意欲を高められます。
キャンペーン期間は2週間〜1ヶ月程度が適切です。期間中は、定期的に投稿を呼びかけたり、「#私の定番コーデ」「#一押しのアクセサリ」など異なるテーマを設定することで、継続的に投稿することを促せます。
集まった投稿は、ECサイトのトップページや商品ページに掲載し、実際の着用イメージとして活用しましょう。
Q&A機能の設置
ECサイトに質問と回答の機能を設置し、顧客同士が商品に関する情報を共有できる場を作りましょう。
家電やインテリアなど、使い方や設置方法に不安が生じやすい商品カテゴリーで特に効果的です。
質問機能は商品ページに直接設置し、「この商品について質問する」ボタンから簡単に投稿できる仕組みを用意します。質問には、商品購入者が経験に基づいて回答できるようにするほか、ECサイト運営者や専門スタッフも補足できる体制を整えると、より信頼性が高まります。
また、特に参考になる質問と回答は「よくある質問」として商品ページの上部に表示し、同じ疑問を持つ人の参考情報として活用しましょう。
UGCの活用事例
ECサイトにおけるUGCの活用は、業界や商品特性によってさまざまな形があります。ここでは、実際に成果を上げている3つの企業の事例を紹介します。
老舗食品メーカーの事例
昭和初期に創業した老舗食品メーカーは、無添加の健康ジュースを扱うD2Cブランドを展開し、InstagramでのUGC施策を積極的に行っています。
同社は、インフルエンサーを起用したプロモーションを通じて、子供が商品を飲んでいる投稿が増加したことを受け、子育て世代向けの訴求を強化しました。また、女性向け健康食品ブランド「COREBI」では、UGCの活用により、1年で売上を10倍に伸ばすことに成功しています。
UGCの蓄積により、広告費をかけた際の費用対効果も大きく向上しています。
参考:【UGC活用事例第1弾】老舗食品D2Cメーカーの ECキャスティングを活用したSNS×UGC戦略
アウトドアブランドの事例
全国に店舗展開するアウトドアブランドは、会員制度と連動したUGCの収集に注力しています。
商品レビュー投稿時にキャンプ歴や利用人数などの属性情報も収集し、商品選びの参考となる詳細情報を提供する仕組みを作りました。
この取り組みにより、UGCコンテンツに接触したユーザーのコンバージョン率は、接触していないユーザーと比べて270%高くなりました。
さらに、600件以上のレビューデータから「ソロキャンプ需要の増加」などの市場トレンドも把握し、商品開発にも活用しています。
参考:売上2割がUGC経由、スノーピークが目指す「1対1でつながる人間味のある自社EC」
老舗建材メーカーの事例
創業100年以上の建材メーカーは、住宅の外壁材や内装材を扱うECサイトを運営しています。施工業者向けの商材は専門性が高く、一般的な商品レビューだけでは商品選びの判断材料になりませんでした。
そこで導入したのが、施工事例写真付きのレビューを投稿できる仕組みです。
実際に商品を使用した施工のプロによる詳細なレビューは、ほかの業者にとって貴重な情報源となり、施工前後の比較写真や経年変化の記録も、商品の品質や耐久性を示す重要なUGCとして活用されています。
この取り組みにより、商品ページの滞在時間が大幅に増加し、施工業者からの商品に関する具体的な問い合わせも30%増加する結果となりました。
さらに、ユーザーの投稿をECサイトやSNSで紹介することで、ブランドへの親近感や信頼感を高める効果も生まれています。
参考:老舗建材メーカーが、インスタグラムでデジタルマーケティング!【visumo】
UGC施策を進める際に直面しがちな課題
UGC施策を展開する際には、いくつかの重要な課題があります。
法的リスクや信頼性の確保について、具体的な対応方法を説明します。
著作権侵害への対応
UGCを活用する際に最も注意が必要なのが著作権の問題です。
ユーザーが作成した写真、動画、レビューなどのコンテンツは、投稿者自身が著作権を持っているため、企業が許可なく利用すると著作権侵害となる可能性があります。そのため、UGCをマーケティングやプロモーションに活用する際は、投稿者から明示的な使用許諾を取得する必要があります。
また、投稿内容に他者の著作物(背景に映り込んだアート作品や音楽など)が含まれている場合、その部分にも著作権侵害のリスクがあります。
企業がUGCを再利用する際は、第三者の著作物が含まれていないかを確認し、必要に応じて権利処理を行いましょう。
ステルスマーケティングの対策
UGCを活用したマーケティングでは、投稿の信頼性を担保することが重要です。
ECサイトが投稿者に報酬や商品を提供しているにもかかわらず、その事実を明記しないと、ステルスマーケティングと見なされる可能性があります。
これを防ぐため、インフルエンサーによる投稿には「PR表記」を必ず付けることや、商品提供を受けた場合はその旨を明記するなど、情報開示のルールを徹底しましょう。
また、レビュー投稿では「サンプル品を使用したレビュー」なのか「実際に購入した商品のレビュー」なのかを区別できるように表示し、消費者が適切に判断できる環境を整えることが大切です。
薬機法への注意
健康食品や化粧品など、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の規制対象となる商品のUGCには特に注意が必要です。
ユーザーのレビューやSNS投稿で、医薬品的な効能効果を暗示するような表現が含まれていないかを確認しなければなりません。例えば、「肌荒れが治った」「痩せた」といった表現は薬機法に抵触する可能性があるため、修正が必要です。
これを防ぐために、投稿ガイドラインで使用できない表現を具体的に示し、投稿内容の事前確認を徹底しましょう。また、投稿者にも薬機法の基本的な注意点を説明し、適切な表現での投稿を促すことが重要です。
ECサイトでのUGC戦略はプロのサポートで進めていくのがおすすめ◎
UGCマーケティングは、商品の魅力を生活者の視点で伝え、ECサイトの売上向上に大きく貢献する可能性を秘めています。しかし、効果的な施策の立案、投稿を促す仕組み作り、法的リスク管理など、専門的な知識が求められる領域も多くあります。
また、ECサイトの規模が大きくなるほど、UGCの収集・管理・活用の負担も増加します。インフルエンサーとの関係構築や、投稿に関する金銭のやり取りなど、細かな対応も必要になるでしょう。
こうした課題は、UGCツールの導入や、UGC活用の専門家に相談することで、より確実かつコストを抑えて進められます。
最適なUGCツールや専門家を探すなら、「ECのミカタ」のビジネスマッチングサービスを利用するのがおすすめです。ECのミカタでは、EC事業者の課題に合わせて最適なパートナー企業を無料で紹介しております。
まずは専任のコンシェルジュが、ご希望やお悩みについて丁寧にヒアリングさせていただいた後、2,000社以上の中から最適な委託先をご提案します。
ご利用は完全無料。まずはコンシェルジュへのご相談や情報収集など些細な内容でも問題ございません。ぜひ専用のフォームからお問い合わせください。