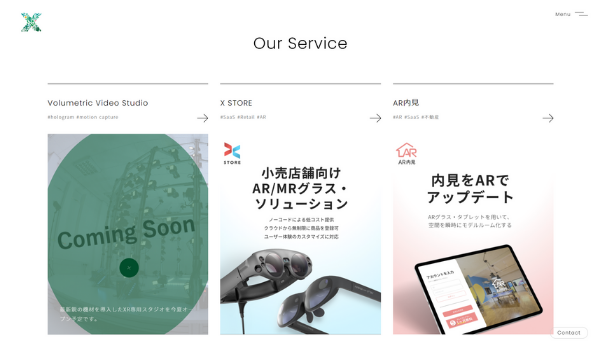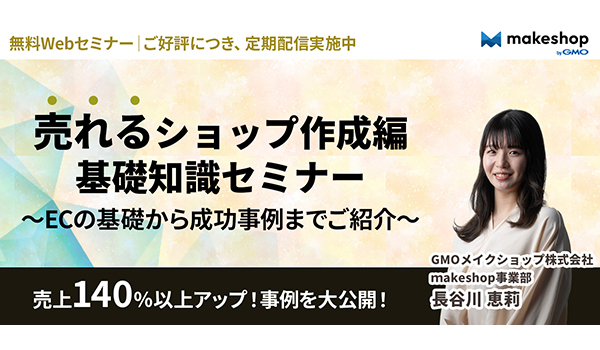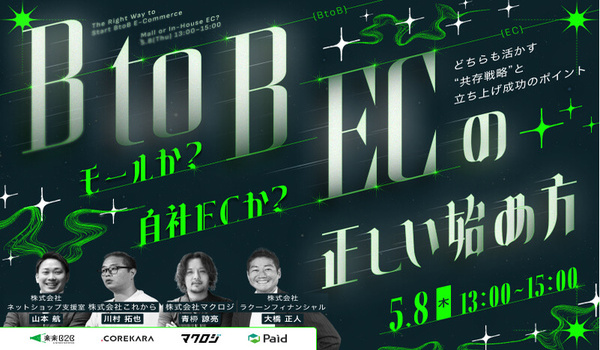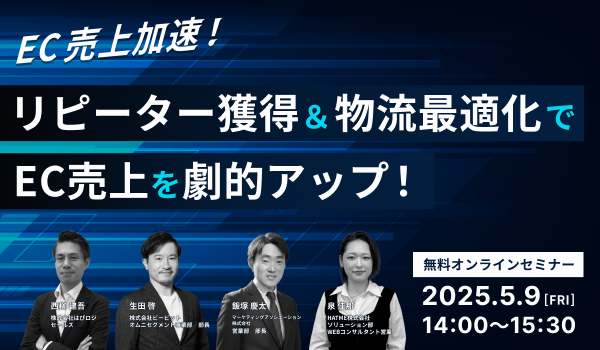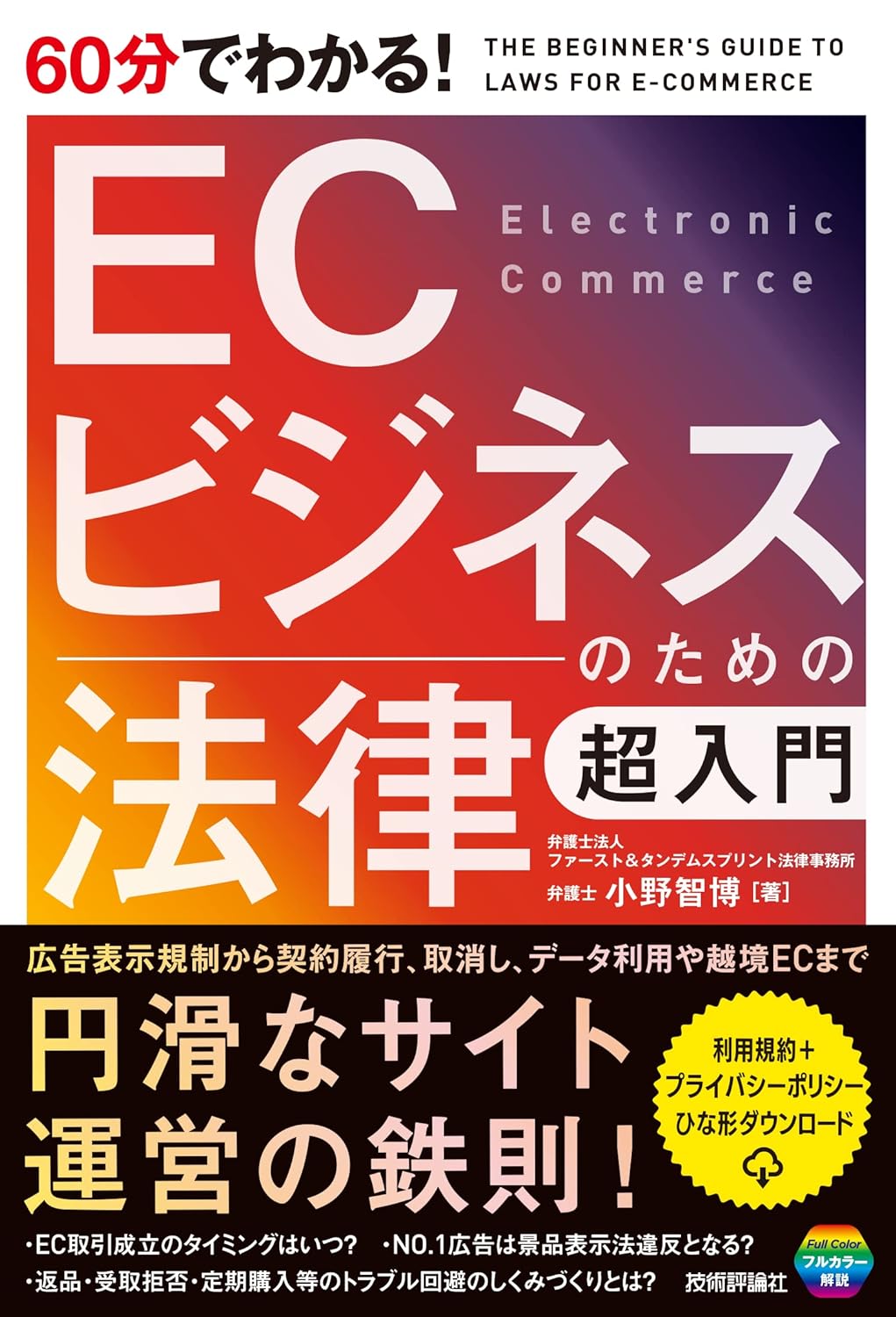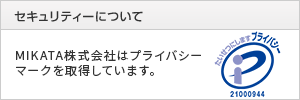OMSを導入することで得られるメリットとは?選定基準も紹介

ECサイトにおけるさまざまな情報を一元管理できる、「OMS」。自社サイトを運営するにあたり、「OMSを導入する効果を知りたい」「OMSを導入する際の注意点を把握したい」と考える担当者もいるだろう。
今回は、OMSの基本機能や重要性、メリット・デメリットに加え、OMSを選ぶ際のポイントを紹介する。それぞれの内容を把握し、サイト運営の一助としてほしい。
OMSとは
OMSとは、「Order Management System(オーダーマネジメントシステム)」の頭文字をとった言葉で、日本では「注文管理システム」「受注管理システム」とも呼ばれる。まずは、OMSの基本機能と、比較されることの多い「WMS」との違いを見ていこう。
OMSの基本機能
OMSを活用すると、他システムと連携し、ECサイトでの注文情報や顧客情報などを一元管理することができる。具体的に行えることは以下の通りだ。
・受注管理(受注登録、受注内容の変更、受注キャンセルなど)
・出荷管理(出荷指示、出荷の取消、出荷の手配、実績の登録など)
・商品管理(商品番号・商品名・規格値段の登録、ディスカウント設定など)
・在庫管理(入庫・出庫・引当など)
・顧客管理(顧客情報の登録、更新、退会手続きなど)
・アカウント管理(利用者によって操作の権限を制限する)
・プロモーション(キャンペーン設定、メルマガ配信、販促メール送信など)
・見積管理(見積書の作成、見積履歴の閲覧など)
・入金送金管理(入金の消込、入金の督促、返品・返金の管理など)
WMSとの違い
WMSは「Warehouse Management System」の略で、「倉庫管理システム」のこと。OMSとは、管理する情報の範囲が異なる。OMSが注文から出荷、在庫管理までを全てカバーしているのに対し、WMSは入出庫管理や検品などの倉庫内業務に特化していることが特徴だ。OMSを導入する際は、APIを通してWMSと自動連携をしている企業も多い。
OMSの重要性
近年は、EC需要の高まりにより、複数のサイトに商品を掲載する企業が急増している。一方で、各サイトの注文情報から一つひとつ在庫状況を照らし合わせたり、チャネルごとに管理している情報をすり合わせたりするには、膨大な時間と労力が必要であり、これまでのシステムでは対応しきれないという課題が発生していた。
また、実店舗とオンラインサイト双方で商品を販売している場合、それぞれに専用のシステムを導入して管理する企業も多く、運用コストやメンテナンスコストがかかることも懸念材料であった。
そこで、そのような課題を解決するために誕生したのが、情報を一元化・自動化できるOMSだ。コスト面や作業効率面など、さまざまな角度での効果が期待されている。
OMSのメリット・デメリット
OMSを導入することによるメリットとデメリットを、それぞれ紹介する。
【メリット①】業務の効率化が図れる
OMSは情報を一括管理することで「複数のECサイトからの注文情報を連携し、自動的に在庫に反映する」「オンラインとオフラインで分けていたシステムを統合する」などが可能になるため、業務の効率化を図れることがメリットだ。それにより、これまでかかっていた各システムのメンテナンスコストや人件費の削減も期待できるだろう。
【メリット②】ミスを削減できる
情報の一元管理と自動化によって、ミスを削減できることもOMSのメリットだ。手作業での入力や確認作業は手間や時間がかかり、その分ミスも発生しやすいと言える。OMSでは「伝票を自動で発行する」「最適なタイミングで発注する」などの機能があるため、ミスによる発送遅延やトラブルの防止にもつながり、自社サイトの品質向上が臨めるだろう。
【デメリット①】コストがかかる
OMSの導入には、初期費用や月々の利用料が発生する。利用できる機能はサービスによって異なるが、場合によっては数十万から数百万円のコストがかかることもある。また、システムのバージョンアップ費やアカウントの追加費用、システムの改造費用が発生する可能性もあるため、様々なランニングコストや費用対効果を想定した上で導入を検討することが必要だ。
【デメリット②】運用の定着までに時間と労力が必要
OMSを活用するためには、「既存システムとの連携」「作業フローの見直し」「マニュアル作成」「ルールの共有」などが必要となるため、運用が定着するまでに時間と労力がかかる点はデメリットと言えるだろう。作業に慣れるまでの期間は、一時的に作業効率が低下する可能性も念頭に入れておきたい。
OMSを選ぶ際の注意点
最後に、OMSを選ぶ際に注意すべきポイントを紹介する。
既存システムと連携が可能か
OMSにはさまざまな種類があり、機能も異なるため、既に利用しているシステムがある場合は、現在のシステムと連携できるかが最も重要なポイントとなる。連携の方法にも、CSVで手入力するケースやAPI接続で自動連携できる場合などがあるため、事前にどのような連携が可能であるのかをきちんと確認しておこう。万が一連携ができないと、システムを一新するなど多額のコストがかかる可能性もあるので、注意が必要だ。
自社の従業員が使いやすいか
自社の従業員にとって使いやすいシステムであることも大切だ。導入後の作業効率が下がることのないよう、デモサイトやトライアル期間を利用して、実際に作業するスタッフに使い心地を試してもらうとよいだろう。また、システムによっては一度に利用できるアカウント数が限られる場合もあるため、利用する人数や取り扱う商品などを加味した上で選択することが重要だ。
まとめ
OMSを活用すると、情報を一元管理し、少ない工数で業務を遂行できるため、「業務の効率化」や「ミスの削減」など、さまざまな効果が望めるだろう。一方で、「コストや時間がかかる」という懸念もあるため、システム選定では「コスト面」や「既存システムとの連携可否」をきちんと確認することが重要だ。今回紹介した内容を参考に一度自社の運営体制を振り返り、OMSの導入を検討してみてはいかがだろうか。
EC専門の委託先選定はECのミカタへ
ECのミカタが運営するマッチングサービスです。ECサイトに特化したメディアを運営する専門コンシェルジュが、丁寧なヒアリングを行った上で、最適な企業をご紹介します。
そのため業務の知識が全くなくても、マッチ度の高いパートナーさんと出会うことが可能です。希望する会社が決定すれば、最短1営業日で企業との商談のセッティングを行います。商談日や商談方法だけでなく、断りの依頼も全てコンシェルジュに任せることができるため、じっくり選定に時間をかけることが可能です。