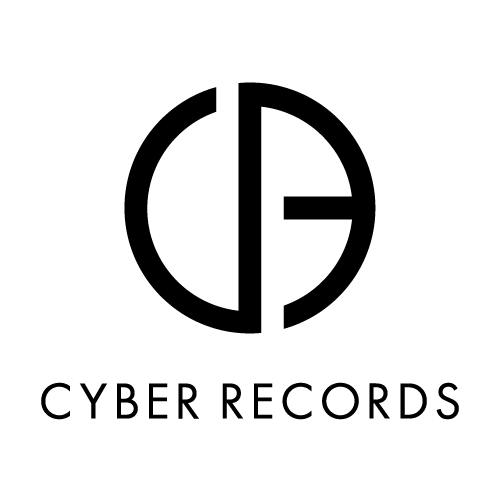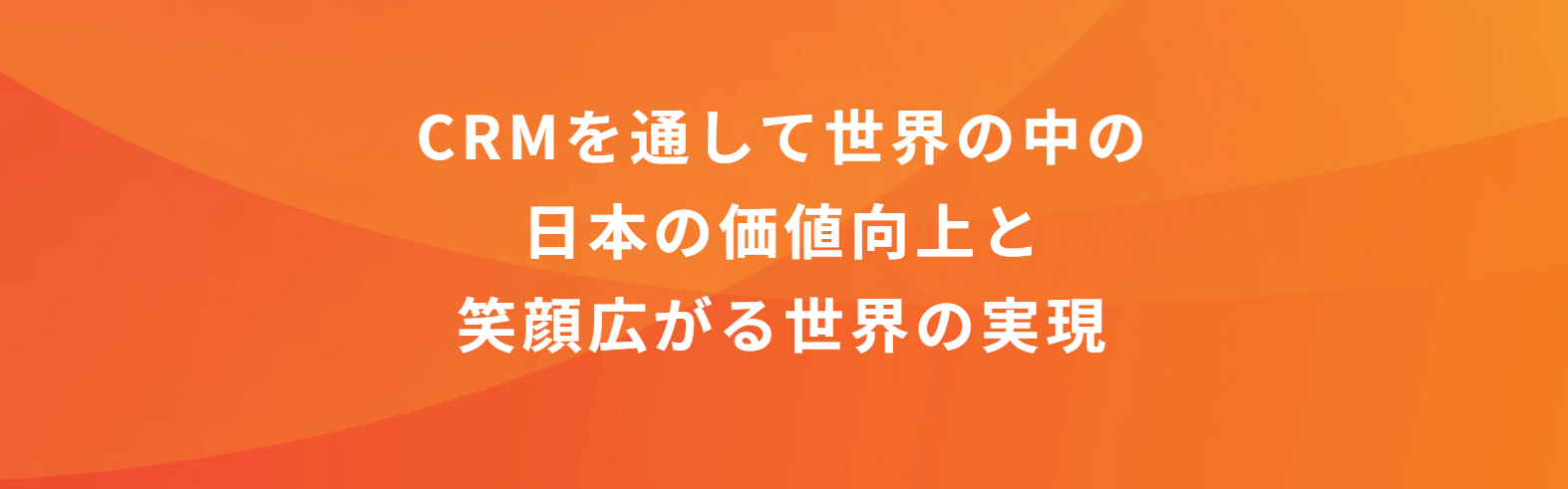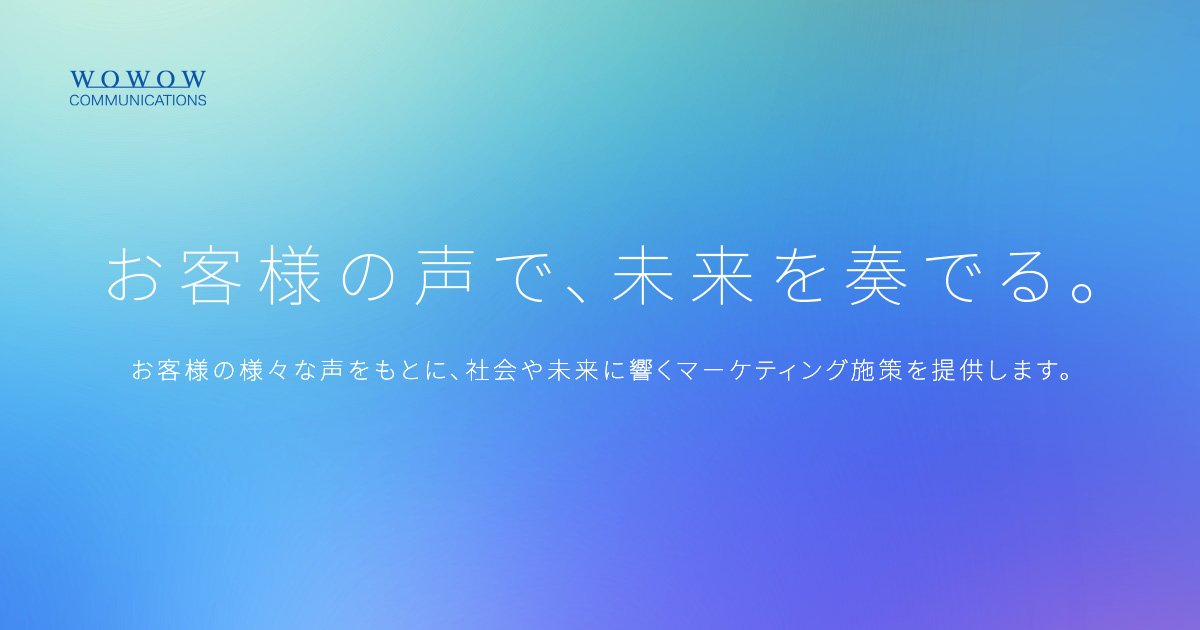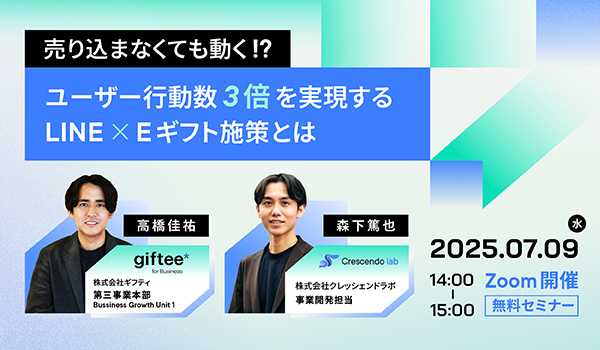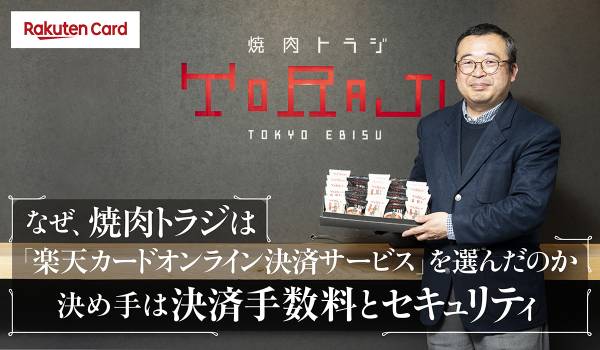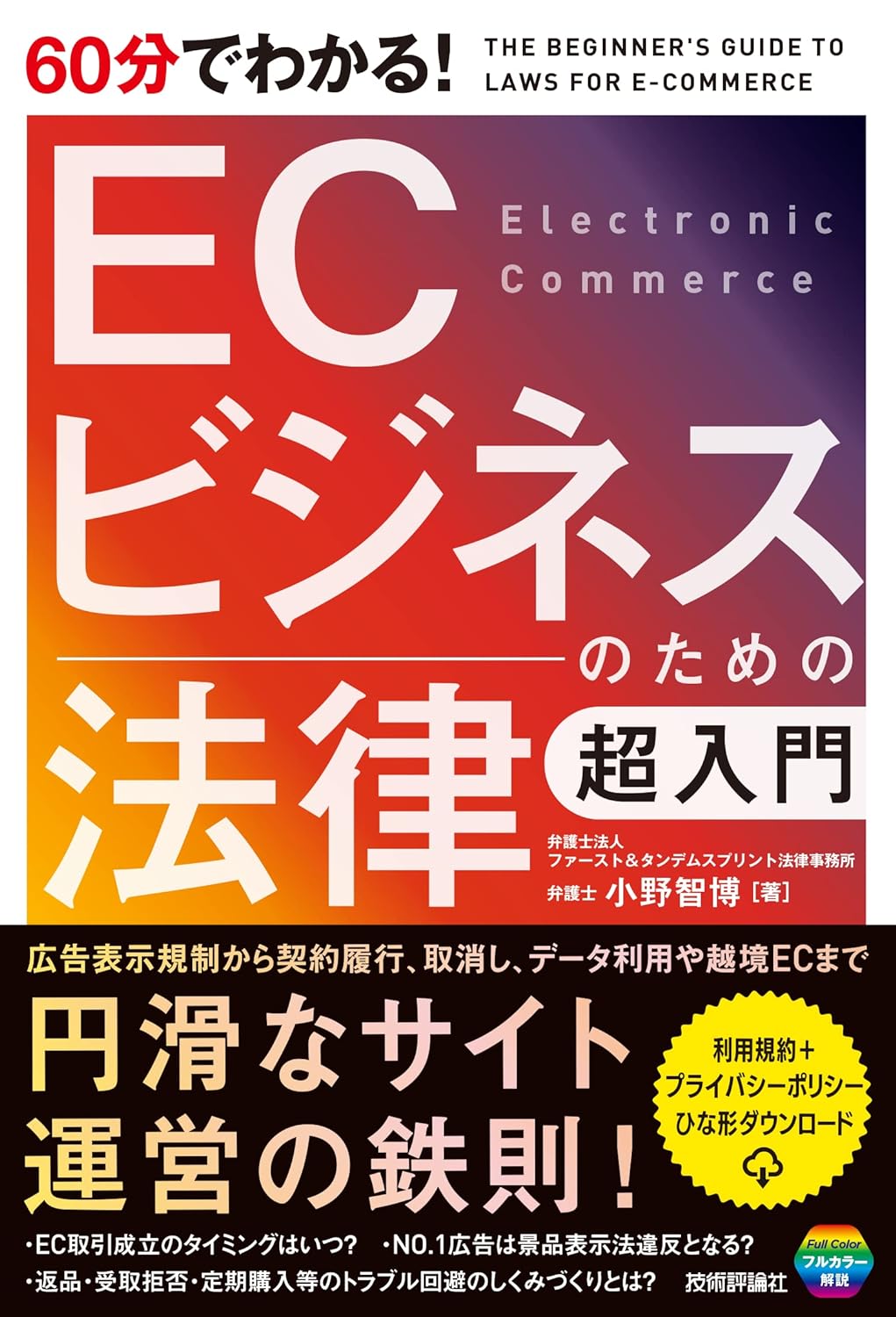発送代行とは?費用の相場や発送代行業者の選び方を解説!
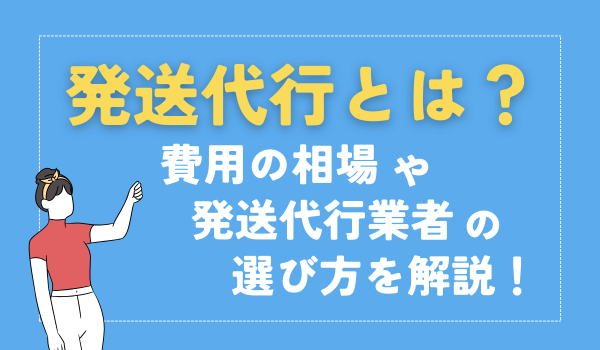
ECサイトなどで商品を取り扱う事業者にとって、発送業務は手間がかかるうえ、大きな負担にもなります。
「他の業務で忙しく、在庫管理まで手が回らない」
「商品の数が多すぎて倉庫に入りきらない」
「発送業務を担当する従業員を雇うほど余裕がない」
そんなお悩みの事業者にピッタリなサービスが発送代行です。
本記事では発送代行の種類や業務内容、費用の相場などを詳しく解説します。
発送代行とは?
発送代行とは、ECサイトなどで通販サービスを行う事業主の代わりに発送業務を行うサービスです。
商品管理や梱包、配送会社への引き渡しなど、業務内容は多岐にわたります。
発送業務は時間やコストがかかるため、他の業務に回す時間も削られてしまいます。
しかし発送代行サービスを利用すれば、事業者の業務負担が減るだけでなく、他の業務にも時間を費やすことが可能です。
発送代行の種類

発送代行にも種類があり、大きく分けて以下の2つです。
・3PL(サードパーティ・ロジスティクス)
・フルフィルメントサービス
それぞれ解説します。
◯3PL(サードパーティ・ロジスティクス)
3PLとはThird Party Logisticsの略称で、サードパーティ・ロジティクスと読みます。
「専門のノウハウを持つ第3者企業に物流業務を委託すること」という意味です。
サードだけでなくファーストやセカンドも存在します。ファーストパーティーは商品を売る事業者、セカンドパーティーは卸売業や小売業を指しています。
3PLでは調達物流、工場内物流、販売物流などを事業者に代わってトータルに請け負うサービスです。日立物流やSGホールディングス、日本通運などが代表的な企業です。
3PLは物流業務のみ委託するサービスのため、物流コストの削減ができます。
物流のプロに委託することで効率が上がり、自社で物流を行うよりも物流コストの低減が見込めるでしょう。
◯フルフィルメントサービス
フルフィルメントは受注や決済、在庫管理、発送などの業務を行うサービスです。
3PLとは異なり、発送業務以外の幅広い業務も委託できます。
異なる商品を発送してしまったり、不良品を送ってしまったりしたことによるお客様からのクレーム対応・返品対応も行っています。
受注からクレーム対応まで一括して代行できるため、事業者の負担も減らすことが可能です。
代表的なフルフィルメント業者として、Fulfillment by Amazon(フルフィルメント・バイ・アマゾン)や楽天スーパーロジスティクス、ヤマトシステム開発が挙げられます。
フルフィルメント業者に委託する場合、発送業務の一括をほぼ全て委託するため、当然コストもかかります。
しかし、作業の効率化を実現できるため迅速に商品を届けられるほか、顧客満足度にも貢献できます。ECサービスの効率化を目指す事業者にはピッタリなサービスです。
発送代行の業務内容
発送代行の業務内容は発送代行業者により異なりますが、主に以下の4つです。
・在庫管理
・入荷作業・検品
・ピッキング
・梱包・出荷
発送するうえで大切な業務は発送代行業者がサポートしてくれます。
それぞれ解説します。
◯在庫管理
倉庫にある商品の増減を管理・記録してくれます。
注文が入ったのに在庫がないといったトラブルが解消できるほか、足りない商品をピックアップできるため、商品がなくなる前に補充を行うことが可能です。
◯入荷作業・検品
在庫管理表をチェックし、所定の場所に入荷します。
商品に不良がないか検品を行うほか、広告やカタログの同梱作業といった流通加工もお任せできるのです。
業者によっては納品書の作成や発行も依頼できる場合があります。
◯ピッキング
注文のあった商品を倉庫から探し、集める作業です。
ピッキングも時間がかかる作業のため、事業者の負担になってしまいます。
しかし、ピッキングも発送作業の一つであるため委託が可能です。
業者により異なりますが、ピッキング費用はひとつの商品ごとに設定されているケースが多いです。中には梱包費用、出荷費用に含まれている場合もあります。
◯梱包・出荷
「発送代行サービス」と聞くと、商品の在庫管理や発送だけ行うのではないかと思われがちですが、梱包作業も行ってくれます。
運送業者に発送の手配をするだけでなく、箱詰めといった梱包も行うため、事業者の負担も軽減できます。
発送代行業者を選ぶポイントとは

発送代行業者を選ぶポイントとして以下の4点が重要です。
・対応している商材
・これまでの実績
・料金・費用
・サポート体制について
それぞれ解説します。
◯対応している商材
まず確認すべきポイントは対応している商材です。
発送代行業者によって対応している商材は異なるため、自社の商品に対応しているか確認しましょう。
例えば化粧品であれば、特定の法規制や品質管理に関する要件を満たす業者でなければ依頼できません。
食品の場合、定温保管ができる倉庫や冷蔵・冷凍が必要な食品を保管できる冷蔵・冷凍倉庫が必要です。
商品にはそれぞれに適した保管方法があるため、性質に応じた保管方法を行っている業者を選ぶことが重要なポイントなのです。
◯これまでの実績
発送代行を依頼する前にこれまでの実績を確認しましょう。
実績が豊富にある業者は。多くの事業者や取引先に選ばれた証拠です。
これまでの実績は発送代行の信頼性や安全性を確かめる基準になるため、発送代行を初めて利用する方は実績が豊富な業者に依頼すると安心でしょう。
また、実際に利用した事業者の口コミをチェックすると、実績だけでは分からない業者の裏側も確認できます。
◯料金・費用
料金・費用はどのくらいかかるのか確認するのも発送代行業者を選ぶポイントです。
基本料金などが安く設定されている業者には魅力を感じてしまいますが、注意が必要です。料金が安い分、それなりのサービスしか受けられなかったり、別途追加料金が加算される場合もあります。
業者に依頼する前にサービス内容を確認し、どの範囲までが基本料金なのか確認しましょう。
発送代行は発送業務を一括して代行するサービスですが、その分コストもかかります。実績のあるプロの業者やサービス内容が充実している業者の場合、費用も高くなるでしょう。
しかし、その分安心してサービスを利用できるため事業者も他業務に集中できます。
発送業者を選ぶ際は料金・費用をきちんと確認しましょう。
◯サポート体制について
発送中のトラブルや顧客からのクレーム対応など、サポート体制についても確認しておきましょう。
商品が違っていたり、住所が違っていたりと発送業務の家庭でトラブルが起きた場合に起きるトラブルへの対応も業者によって違います。
迅速に対応できなければ顧客への信頼も失う可能性もあるため、どこまでサポートしてもらえるかなどきちんと確認しておきましょう。
発送代行にまつわるよくある質問
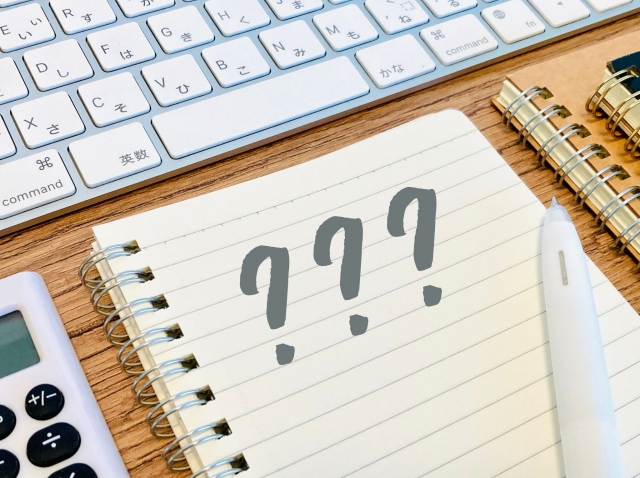
発送代行にまつわるよくある質問をまとめました。
・発送代行の費用相場ってどのくらい?
・発送代行はどこまで代わりにやってくれるの?
・発送代行を利用するうえでデメリットはある?
それぞれ解説していきます。
発送代行の費用相場ってどのくらい?
業者にもよりますが、発送代行の費用には固定費と変動費の2種類あります。
固定費は基本料金や商品を保管する倉庫利用料などです。
変動費は入庫費用や梱包費用、発送費用など、商品の数量によって変わります。
発送代行サービスの費用は主に以下の6点で成り立っています。
・基本費用
主にシステム料や事務手続き料を含む月額費用です。
1件あたり1万円〜3万円が目安となっています。
・入庫費用
商品到着時の検品や倉庫に運ぶ作業に対する費用です。
商品の量で費用が異なります。
16円〜40円が目安となっていますが、単品や箱ごとなど商品の状態によって変動します。
・保管費用
入庫された商品の保管にかかる費用を指します。
食品など温度調整が必要な場合もあるため、費用は変動しますが1坪4,500円〜7,000円が目安です。
・梱包費用
発送前の梱包にかかる費用です。
1件140円〜400円が目安ですが、梱包の仕方によっては500円以上になる場合もあります。
・配送費用
商品をお客様へ届けるために必要な費用です。
サイズにより費用は変動しますが、500円〜1000円が目安となっています。
・オプション費用
キャンセル対応や返品対応、ギフトラッピングなどに発生する費用です。
あくまでオプションになるため、業者によっては行っていない場合もあります。
発送代行はどこまで代わりにやってくれるの?
3PLやフルフィルメントでも業務内容は変わってきますが、業者によっても委託できる範囲は変わってきます。
梱包だけではなくギフトラッピングを無料で行ったり、24時間体制でサポートを行う業者もあります。
業者によって得意分野や「ここだけは他社には負けない」といったサービスを行う業者もあるため、発送業務の内容はきちんと確認しておきましょう。
発送代行を利用するうえでデメリットはある?
発送代行は便利なサービスですが、デメリットもあります。
まずは個人情報の流出の可能性がある点です。
顧客へ商品を発送する場合、氏名や住所を管理しなければなりません。事業者自身で発送業務を行う場合、個人情報漏洩の危険は少ないでしょう。
しかし、発送代行サービスを利用する場合、業者に顧客の情報を渡すことになります。顧客管理を管理する箇所が2箇所に増えるため、個人情報流出のリスクは上がってしまいます。
発送代行サービスを利用する業者を選ぶ際は、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
もう一つはノウハウが蓄積されにくい点です。
発送業務のほぼ全てを業者に委託するため、社内の従業員に発送業務のノウハウが蓄積されません。仮に将来何らかの理由で発送代行の利用を停止した際、発送業務を行える従業員が限られてしまいます。
このように便利なサービスにも必ずデメリットはあります。利用するうえで本当に発送代行は必要か、よく考えたうえで発送代行を依頼しましょう。
まとめ!発送代行を利用する時は自社に合った業者を選ぼう

本記事では、発送代行の種類や業務内容、費用相場、発送代行を選ぶポイントを詳しく解説しました。ECサイトで商品を扱っている事業者で発送業務に悩んでいる方には救世主のような存在です。
発送業務全般を行ってくれますが、デメリットもあります。自社に合った業者かどうか、信頼できる業者であるか確認しながら選びましょう。