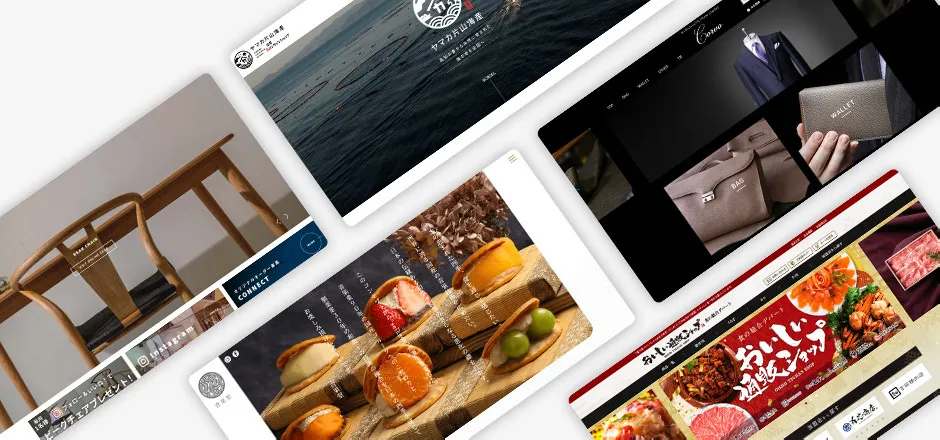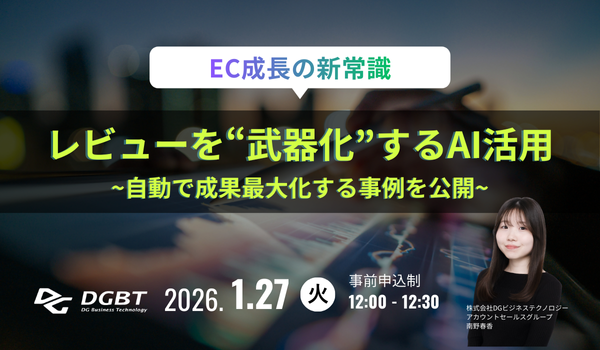こんなに違う!Amazonと楽天の決定的な違い7選
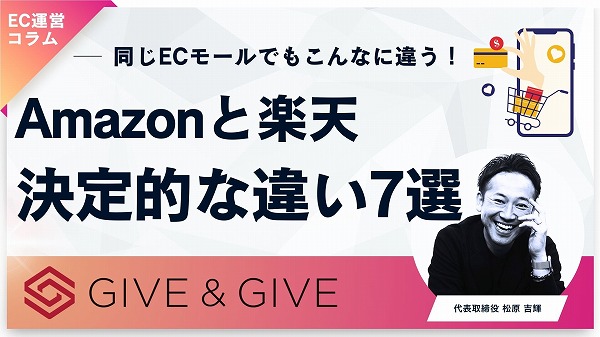
「ECモールに出店するなら楽天かAmazon」そう考えるEC事業者は多いのではないでしょうか?実は、Amazonと楽天では根本的な考え方が大きく異なります。
本記事では、楽天や自社EC運営者が驚く、Amazonならではのルールや仕様を7つに絞って解説します。
「1商品1ページ」の商品ページルールと「相乗り出品」
楽天では各出店者が自由に商品ページを作成することができます。しかし、Amazonでは「1商品1ページ」という独自ルールがあり、Amazon内に同一商品ページを複数作ることができません。
そのため、販売したい商品がAmazon内で既に出品されている場合、「相乗り出品」という形で、複数の出品者が一つの商品ページで商品を販売することになります。
自社ブランド商品をAmazonで販売する場合は、必ず「ブランド登録」を行いましょう。
ブランド登録することで、
・知的財産権の保護(商標権侵害などあった場合にAmazonに違反報告ができる)
・他の出品者の出品を制限できる(転売対策)
・ページの編集権限を得られる(ページ改ざんリスクを低減)
・ブランドページ構築(Amazon内でのブランディング向上)
など、ブランド保護やAmazon内での販促にも繋がります。
相乗り出品の売上を左右する「購入ボタン=カートボックス」争奪戦
複数の出品者がいる場合も、商品ページ内の購入ボタンは一つです。Amazonでは、その時一番Amazonからの評価の高い出品者が「購入ボタン=カートボックス」を獲得することができます。
他の出品者は「その他出品者」というタブを開かないと表示されないため、カートボックスを獲得できるかどうかで売上は大きく変わります。
カートボックス獲得者は常に変動するので、Amazonでは「カート獲得率(100回表示中50回自社のカートボックスが表示されたらカート獲得率50%)」を高めるために様々な対策を講じる必要があります。
特にカート獲得率に影響する要素が以下のとおりとされています。
・販売価格(市場価格を逸脱しない範囲での最安値)
・FBA(Amazon倉庫からの発送、Primeマークが付く)
・大口出品プラン(分析レポート機能や広告配信機能が使えるプラン)
・出品者の評価(出荷遅延がない、在庫切れを起こしていない、返品率が低いなどの指標)
※自社ブランド商品でブランド登録済み&他社の出品を制限している場合は、カート獲得対策は不要。
広告を配信しても「カート獲得率」が低いと無駄打ちに
楽天や自社ECであれば、配信した広告からのアクセスは必ず自社のものになりますが、Amazonの場合は、せっかく広告を配信しても無駄になってしまうことがあります。
それは、「カート獲得率」が広告配信の効果も左右するからです。
例えば、カート獲得率0%の出品者Aが広告で集客しようとしても、広告の遷移先にはカート獲得者Bのカートボックスが表示されてしまい、広告費をかけて集客しても、自社の売上に繋がらない可能性が非常に高いです。
楽天や自社ECでは「集客のために広告を配信する」という戦略が取れますが、Amazonの場合は「カート獲得率を上げないと、広告の配信効率が悪い」ため、広告戦略の使い所が大きく異なります。
ページが装飾できない!?Amazonは画像とテキストのシンプルな構成が基本
特に相乗り出品の場合、楽天のように自由にページをHTMLで作り込んだりすることができません。
Amazonの商品ページはシンプルなイメージがあると思いますが、これはAmazonが統一感や見やすさ(=顧客体験の向上)を重視しているためです。
そのため、特に相乗り出品が主流の型番商品では、数枚の画像とテキストのみというシンプルな構成になっており、商品情報を編集したい場合も、その内容が必ず反映されるとは限りません。
※例えばナイキのスポーツシューズであれば、ブランドオーナーはナイキであり、そこに相乗り出品している業者はそもそもページの編集権限が無かったり、仮に出品者が編集可能な商品ページであったとしても、出品者の評価が低いとページの修正希望が通らないことがあるため。
しかし、Amazonの商品ページを充実させる方法もあります。自社ブランドでブランド登録をした場合のみ、「A+コンテンツ」という画像とテキストで商品・ブランド紹介を充実させる機能を使うことができます。
複数のテンプレートが用意されており、動画コンテンツの追加や、関連商品の比較表などを作成することも可能です。
楽天以上に避けたい「在庫切れ」
Amazonでは「在庫切れを起こさない」ということが、出品者の評価として重要視されています。
相乗り出品の場合、直前まで高いカート獲得率を維持していたとしても、在庫切れを起こすと即時、他の出品者にカートボックスを奪われます。そして、再び在庫補充しても、在庫切れを起こす前よりカート獲得率が下がってしまう可能性もあります。
Amazonにおける在庫切れが、一時的な売上機会損失以上の影響力を持つ理由は大きく2点です。
①Amazonは「安定供給」できる出品者を評価する
顧客体験を何よりも重視するAmazonでは、商品を安定供給できるかどうかを評価しています。そのため、在庫切れは出品者評価にマイナスとなります。
②相対評価の低下
在庫が切れて再び在庫を補充するまでの間、他社が販売実績を作ることで評価が向上し、相対的に自社の出品者評価が下がる可能性があります。
Amazonのカート獲得率には、販売価格や販売実績、出品者評価などの複数要素が影響しているため、在庫切れにより「自社の評価低下」「他社の販売実績アップ」「出品者間での相対評価が下がる」という複数の要因が誘発され、カート獲得率に悪影響を与える可能性が高いのです。
レビューの影響力は楽天以上!?
まず、レビューの有無はAmazonでも楽天でも、ユーザーの購入を後押しする重要なポイントです。
しかし、Amazonの商品レビューには、相乗り出品特有のメリット・デメリットが存在します。
Amazonのレビュー機能の特徴として、どの出品者から購入したかに関わらず、全ての商品レビューは商品ページに紐づきます。それにより、良くも悪くも全ての出品者がレビューの影響を受けてしまいます。
◎メリット
商品レビューが「★4.5(100件)」という評価の高い商品の場合。新規参入した出品者も「★4.5の商品」という看板の元で販売することができる。
→競争は激しいが、レビューが良いため集客しやすく、最安値販売で購入確率・カート獲得率を高められる可能性がある。
△デメリット
商品レビューが「★2(1件)」という評価の低い商品の場合。新規参入した出品者も「★2の商品」というネガティブな看板で販売しなければいけない。
→カート獲得率は高めやすいが、低レビューにより購入に結びつけることが難しい。「対応が悪い」「不良品が届いた」など、悪質な出品者により低レビューがついてしまうと、他の出品者にも悪影響となる。
そして、相乗り出品の場合は自由にページを作り込むことも難しいので、低レビューを払拭するのは楽天以上にハードルが高いでしょう。
分析指標の違いーAmazon独自の「ユニットセッション率」とは
一般的なECサイトの売上分析指標はCV(コンバージョン)率が用いられますが、Amazonでは「ユニットセッション率」という指標が導入されています。
※セッション数=アクセス数
CV率はアクセス数に対して「何件注文されたか」で計算されますが、ユニットセッション率の場合はアクセス数に対して「何点購入されたか」を見る指標となっています。
具体的に数値にはどう影響するでしょうか。
例)アクセス数100、注文件数5、購入点数10 というデータの場合
▼CV(コンバージョン)率
計算式:注文件数÷アクセス数×100
→注文件数5 ÷ アクセス100 × 100 = 5%
▼ユニットセッション率
計算式:購入点数÷セッション数×100
→購入点数10 ÷ アクセス100 × 100 = 10%
このように、まとめ買いされやすい商品の場合、楽天や自社ECとAmazonでは数値の差異が出やすい(Amazonの方が数値がよく見える)傾向にあります。
一方で、Amazonでまとめ買い用のバリエーションを導入した場合、単品・3個セット・5個セット、どれも購入点数は1点とカウントされるため、売上が同等でも、導入前と比較してユニットセッション率が悪化するという可能性もあります。
そのため、楽天や自社ECと正確な比較をしたい場合は、Amazonのデータをもとに「注文件数 ÷ セッション数 × 100」でCV率を再計算する必要があります。
また、まとめ買い用バリエーションの導入などの変更があった場合も、ユニットセッション率だけでなく、様々な指標を元にデータを見ることが大切です。
まとめ
楽天や自社ECとは異なり、Amazonでは考え方・出品ルール・評価指標などが大きく異なります。
特に「カート獲得率」や「ユニットセッション率」など、Amazon特有の仕組みを理解していないと、広告や販促の効果が思うように出ないことも。
これまで楽天や自社ECを中心に運用してきた方ほど、Amazonならではのルールに戸惑うこともあるかもしれません。
だからこそ、事前に違いをしっかり把握し、Amazonに合った戦略を立てることが成功のカギとなります。
EC運営においては、SEO対策、広告、SNS、LINEなど様々なプロモーション施策を複合的に実施できるのが理想的です。
ぜひ、ECの売上拡大や各種プロモーション施策でお困りの方は、GIVE&GIVEまでお問い合わせください。