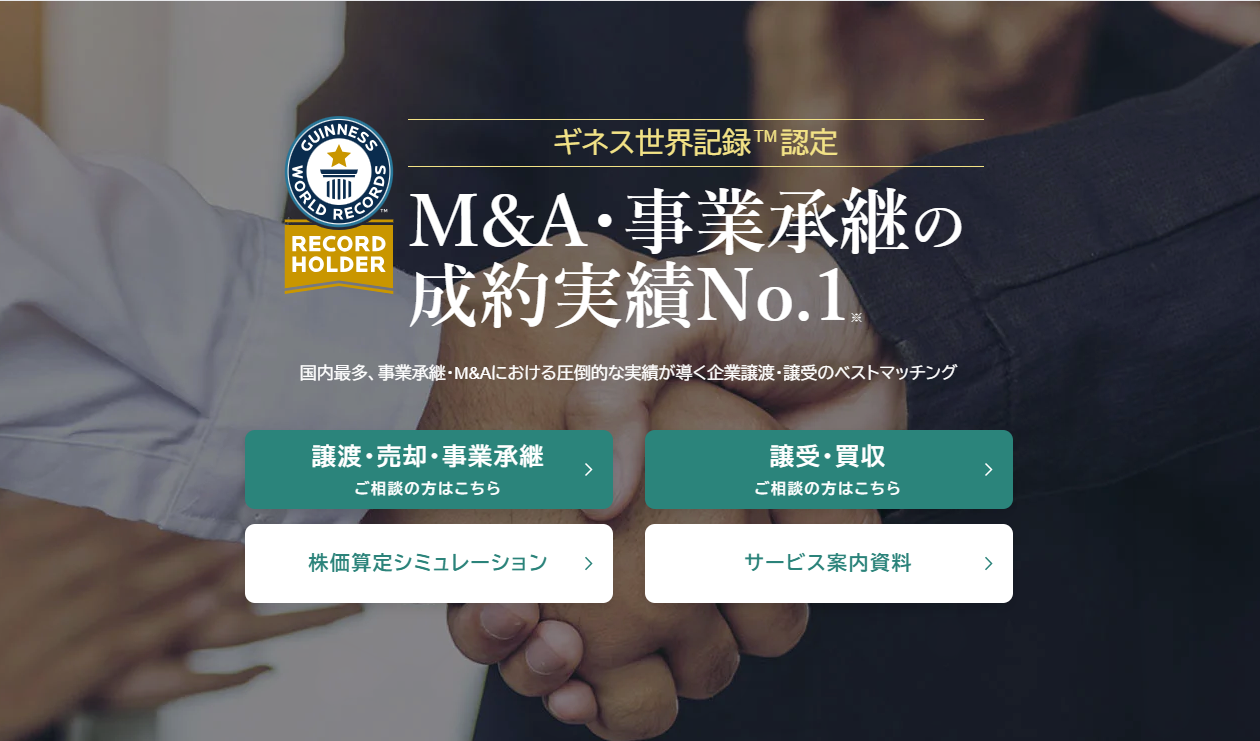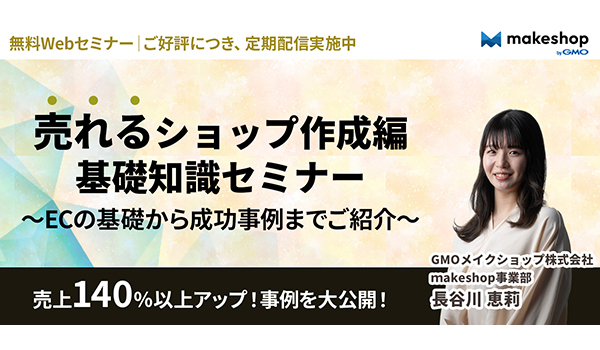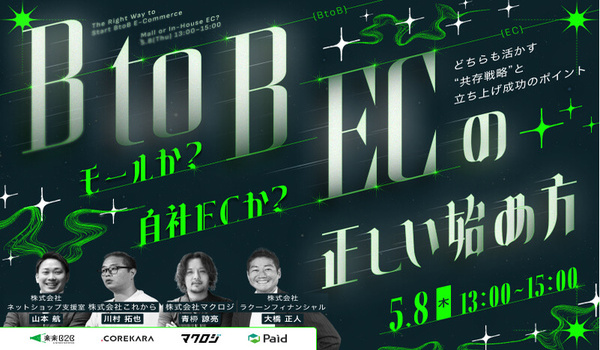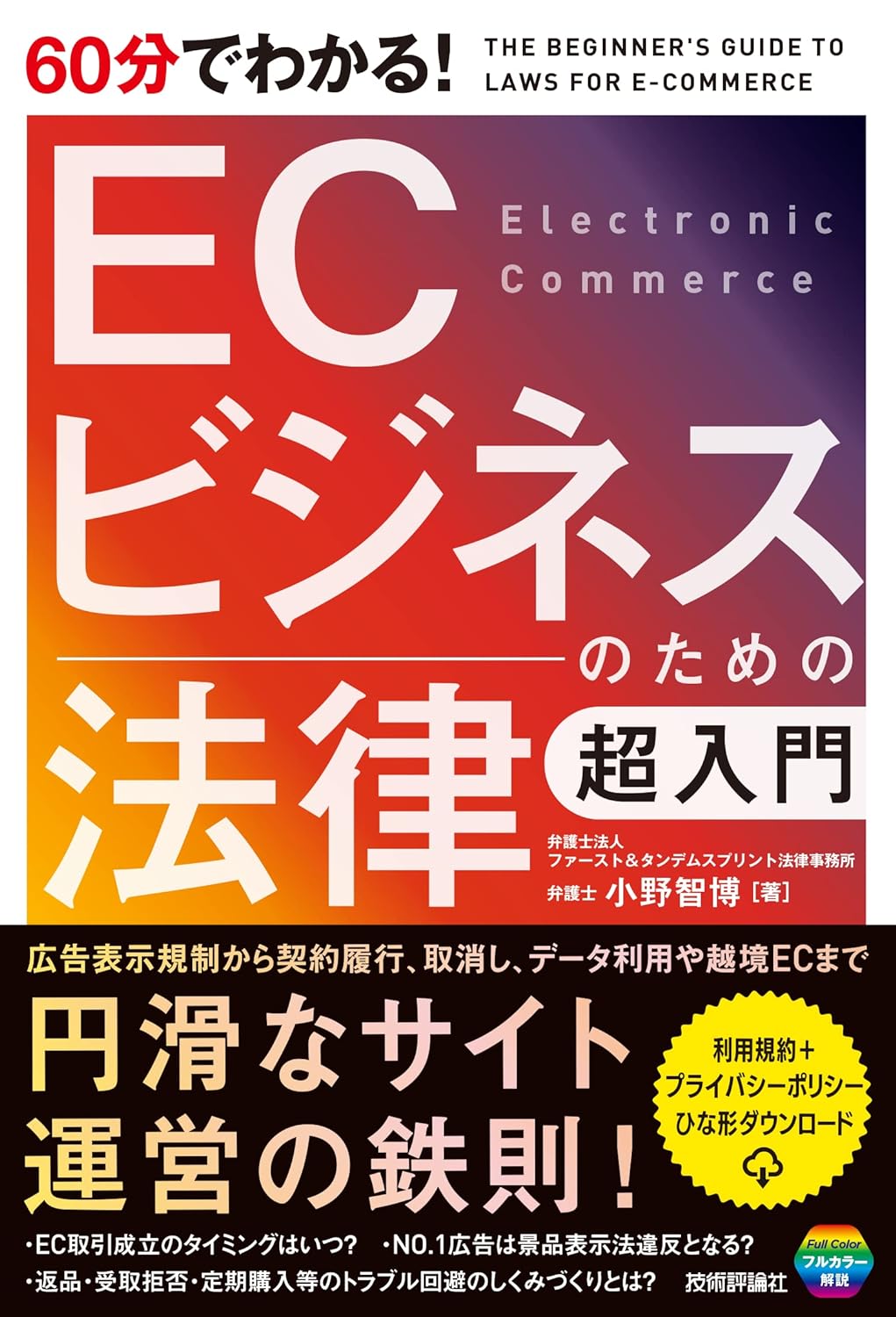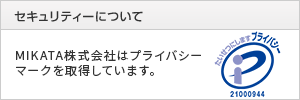ピッキングシステムとは? メリット/デメリット、比較ポイントまとめ

近年、ECの拡大や市場ニーズの多様化により、製造業では部品管理数が、小売業では取り扱うアイテム数が増加し、多品種少量生産が進んでいます。
多品種少量生産が進むに伴い、ピッキング作業の複雑化、作業時間の増加、さらにそれらに伴ったピッキングミスの増加といった課題が出てきます。
これらの課題を解決するのに役立つのが「ピッキングシステム」です。
今回は、ピッキングシステム導入を検討する人向けに、ピッキングシステムの概要や種類、検討時のポイントを紹介します。
ピッキングシステムとは
引用:https://pixabay.com/ja/images/search/%E5%80%89%E5%BA%AB/
ピッキングシステムとは倉庫や工場などで行われるピッキング作業を効率化するための仕組みのことです。
このピッキングシステムには大きく分けて二つのタイプがあります。
一つ目が、ピッキング作業を行う人の作業を補助するシステムです。
このシステムではハンディターミナルや表示器といったデジタル機器やITを活用して、ピッキング作業を効率化することができ、さまざまな業種・業界の物流や倉庫で利用されています。
そして2つ目がピッキング作業そのものを機械化・自動化する方法で、大型倉庫や工場で利用されています。
どちらもピッキング作業を仕組み化し、物流倉庫現場での、検品や出荷時の課題を解決するという目的で導入されています。
基本的仕組み
ピッキングシステムの基本的な仕組みは、それまで紙のリストを使って行なっていた下記の3つの作業をデジタルに置き換えるというものです。
・作業指示
・作業記録
・上位システムへの実績データ反映
したがってピッキングシステムは以下の3つの機能で構成されます。
・作業者にピッキング指示を出す機能
・実績を記録する機能
・WMS(Warehouse Management System 倉庫管理システム)や在庫管理システムなど、他のシステムと連携する機能
作業指示や実績記録はデジタル機器とシステムが連携する形で利用され、ソフトウェアやWEBシステムによって整備された作業項目に合わせて業務を行うことで、実績データの再入力や手入力による手間やミスを無くすことができます。
これらの機能の活用によって、紙で行っていた独立した作業を仕組み化して、一括で行えるようになります。
ピッキングシステム導入のメリット・デメリット
引用:https://x.gd/LGrXAl
ピッキングシステムの概要を理解したところで、これを導入した際のメリットデメリットを見ていきましょう。
ピッキングシステム導入のメリット
1.作業が効率化できる
紙のピッキングリストをデジタル化することにより、手打ちのミスが減り作業効率が向上します。
システムにより、倉庫内での位置と部品名、数量を照合することが可能なため、倉庫内で部品の場所を探す手間やリストを見ながら数量と部品を照合する手間が減り、さらに入力ミスのリスクも減らすことができます。
2.ピッキングの標準化による生産性向上
ピッキングシステムを導入することでピッキング作業の標準化が可能です。
標準化ができると、初心者でも熟練者と同等の作業が可能となり、スキルや習熟度に関係なくピッキング作業の生産性の向上が期待できます。
3.人件費の削減
作業の標準化や生産性の向上により、作業時間を短縮することが可能になり、さらに作業員一人当たりが行える作業量が増加します。
これにより、例えば5人で行っていた作業工程を3人で、さらに時間を短縮して行うことができ、ピッキング作業に要していた人件費を削減することができます。
4.作業ミスの抑止
ピッキング作業にミスがあった場合、タブレットにアラートを表示させるといったデジタル機器やITの活用によって、作業ミスの防止が可能になります。
作業者のスキルに依存することなく、システムによってミスを防ぐことができるため、誤出荷やピッキングミスを減らすことができ、結果的に物流品質の向上にもつながります。
ピッキングシステム導入のデメリット
1.システム導入コストがかかる
物流倉庫というアナログな環境にシステムを導入するには、システム用のパソコンやLANの配線といった機材の準備に加え、システム構築から導入までの作業が必要になります。
導入に一定のコストと期間がかかるという点はデメリットであるといえ、さらに現行のピッキング作業の規模では、ピッキングシステムを導入しても投資対効果が期待できない可能性があり、一定のリスクもあるといえます。
2.例外や緊急時の対応が難しい
計画していた以外でのピッキング作業をおこうなう必要がある場合、システムに落とし込むために時間がかかるため、ピッキングシステムの利用が追いつかない場合があります。
また、デジタルピッキングシステムの導入では、システムと各製品が1対1で紐づくことになるため、保管場所の変更も難しくなります。
従来よりも融通が効かなくなるという面ではデメリットとなり、例外としての対応や、柔軟な対応が必要な場合は紙のピッキング作業の方があっている倉庫もあります。
3.システムの運用管理が必要
ピッキングシステムの導入後、システムを運用管理する人材が必要になります。
高機能なピッキングシステムを導入したとしても、運用できる人材がいなければ、システムが使われない可能性があります。
さらに停電などによりシステムがダウンした際には、製品の読み取り機とシステム管理用のパソコンの連携ができなくなるため、ピッキング作業が行えなくなるというリスクもあります。

ピッキングシステムの種類
引用:https://x.gd/04BRu
上記メリット・デメリットにより、ピッキングシステムへの理解がより深まったのではないでしょうか。
ここでは、ピッキングシステムにどのような種類があるかご紹介します。
デジタルピッキングシステム
デジタルピッキングシステムはデジタル表示器を活用したピッキングシステムで、ピッキング指示をデジタル表示器で作業者に知らせることによってピッキング作業を進めていきます。
ピッキング指示にしたがってランプが点灯し、数量情報が表示できるようになっています。
作業者はランプが点灯した場所へ行き、表示器に表示された個数の商品や部品をピッキングすることでピッキング作業が完了します。
作業者は商品や部品を知らずともピッキング作業ができるようになり、ピッキングの効率化とペーパーレス化がはかれます。
ピッキングカートシステム
ピッキングカートシステムは台車の画面表示に従って、棚から商品をピッキングし、台車の各集品箱に仕分ける台車式のピッキングシステムです。
ピッキング、検品、仕分けを同時に行うことができ、複数オーダーを一度に処理することが可能です。
タブレット・スマートフォンピッキングシステム
タブレットピッキングシステム、スマートフォンピッキングシステムは、タブレットパソコンやスマートフォンを活用して、ピッキング先や数量、製品・部品の画像やマップ情報等を表示してピッキング作業をサポートするシステムです。
タブレットやスマートフォン端末はハンディターミナルと同様に多機能であり、製品を運ぶための台車やマテハン機器と組み合わせての利用も可能です。
商品や卯品アイテムが多くても、アイテム数と同じだけの表示器は必要なく、タブレットやスマートフォン上で棚の場所や必要数量の確認が可能なため、導入費用を抑えることができます。
さらに、スマートフォンピッキングシステムでは、ハンディターミナルと同様のデータ入力や修正が可能で、バーコードの読み取りにも対応しています。
音声認識/ボイスピッキングシステム
音声認識/ボイスピッキングシステムは作業者の装着するヘッドセットにピッキング指示を音声で行うシステムです。
作業者は紙やタブレットを見たり、入力したりする必要がなく、ハンズフリーでの作業が可能になります。
商品を見るという作業に集中できるため、作業ミスを減らし、商品を注意深く扱うことにもつながります。
フォークリフトなどを操作しながらも利用可能なため、さまざまな物流倉庫現場で利用できます。
プロジェクションマッピングによるピッキングシステム
映像投影によりピッキング指示が出せるので、作業者が理解しやすく、現場に合わせて投影情報を自由にカスタマイズできることが特徴のピッキングシステムです。
仕分け場所だけでなく、仕分け作業進捗情報を壁面に映すことで、管理者や作業者に視覚的に情報を伝えることが可能です。
自動倉庫システム
自動倉庫システムとは部品や材料などを荷棚に収納し、製品受注から出荷までの一連の流れをコンピューターで一括管理する「オートメーションシステム」を導入した倉庫を指します。
スタッカークレーンや制御装置などを必要に応じて設置し、入出庫作業を全て自動化していくので、作業員の作業工程が大幅に削減できることが特徴です。
倉庫に合わせたカスタマイズが可能ですが、倉庫の内装や作業内容に適したシステム構築のためにかかる費用が高額になる場合もあります。

ピッキングシステム比較時のポイント
引用:
https://x.gd/fgZ2o
さまざまな種類のピッキングシステムを紹介しましたが、どれを採用したら良いかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、下記ではピッキングシステムを比較する際に重要となる視点をご紹介します。
ピッキング作業の方式
まず、自社のピッキング作業の方式を確認することが大事です。
ピッキングの方式には「摘み取り方式」と「種まき方式」の2つの方式があります。
摘み取り方式
摘み取り方式はシングルピッキング、オーダーピッキング、リストピッキングなどとも呼ばれ、発注伝票を受け、保管場所から商品を取り出す作業のことです。
この方式は出荷数が多く、商品アイテム数が少ない場合に適しています。
ピッキング作業は簡単ですが、発注伝票ごとに作業するため、時間がかかったり、作業者の移動距離が長くなったりする傾向があります
種まき方式
種まき方式は、オーダーされた商品をまとめて保管場所から取り出し、その後捌き場などで発送先毎に仕分けを行う方式のことです。
出荷数が少なく、商品アイテム数が多い場合に適しています。
商品単位でまとめて作業するため、移動距離と時間が短縮できますが、仕分け作業を一度に行うだけの荷捌きスペースの確保が必要です。
一回にピッキングする商品数が少ない摘み取り方式では、タブレットやスマートフォンを用いたピッキングシステムの導入が効率的ですが、商品単位でまとめて作業する種まき方式では、視覚的にわかりやすい数量が表示されるデジタルピッキングシステムや、プロジェクションマッピングによるピッキングシステムが効率的であることがわかると思います。
無線式と有線式
デジタル表示器を使ったピッキングシステムの導入を考える場合、無線式のものにするか、有線式のものにするかも重要なポイントです。
無線式
無線式での導入では配線工事が必要ないため、導入が簡単で、さらに配置などの自由度も高くなります。
しかしデジタル表示器の充電に手間がかかるというデメリットもあります。
有線式
有線式での導入にデジタル表示器の充電は必要ありませんが、配線の工事が必要となってきます。
さらに配置が変わるたびに配線の見直しが必要となり、費用がさらにかかる可能性があります。
クラウド型とオンプレミス型
ピッキングシステムの導入には、インターネット上のサーバを利用してシステムを導入するクラウド型と、自社のサーバにソフトウェアをインストールしてシステムを利用するオンプレミス型の2つの方法があります。
クラウド型では初期費用を抑えることができ、さらにサーバーそのものの管理が不要であるというメリットがあります。
しかしながら、カスタマイズが難しく、既存のシステムとの連携の際に手動で行わなくてはいけない作業が多く残る場合があります。
さらに、外部サーバとのネットワークを介してアクセスを行うため、セキュリティ面での配慮が必要となります。
オンプレミス型は、クラウド型と比べて初期費用がかかり、サーバーの管理を行わなくてはならないというデメリットがありますが、自社でサーバー室やデータセンターを持っている場合、トータルコストを抑えられるというメリットもあります。
さらにカスタマイズがしやすく、既存のシステムとの連携が比較的容易で、自動でシステム連携が可能になります。
まとめ
いかがでしたか?
今回はピッキングシステムの概要、メリット・デメリットを紹介し、さまざまなピッキングシステムとそれらを比較する際のポイントを紹介しました。
ピッキングシステムは年々進化し、新しいシステムがどんどん構築されています。