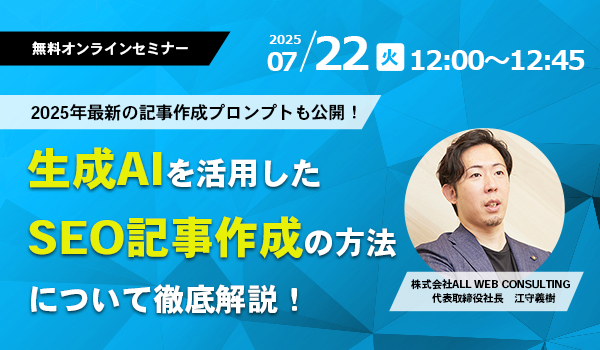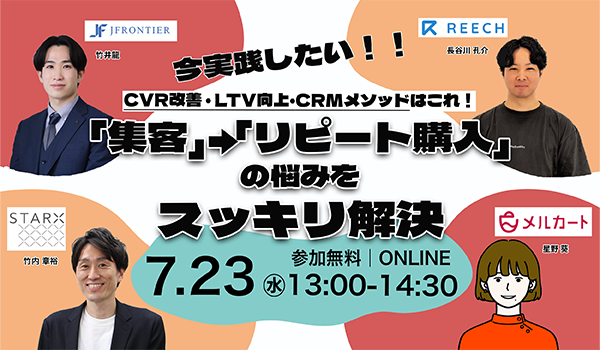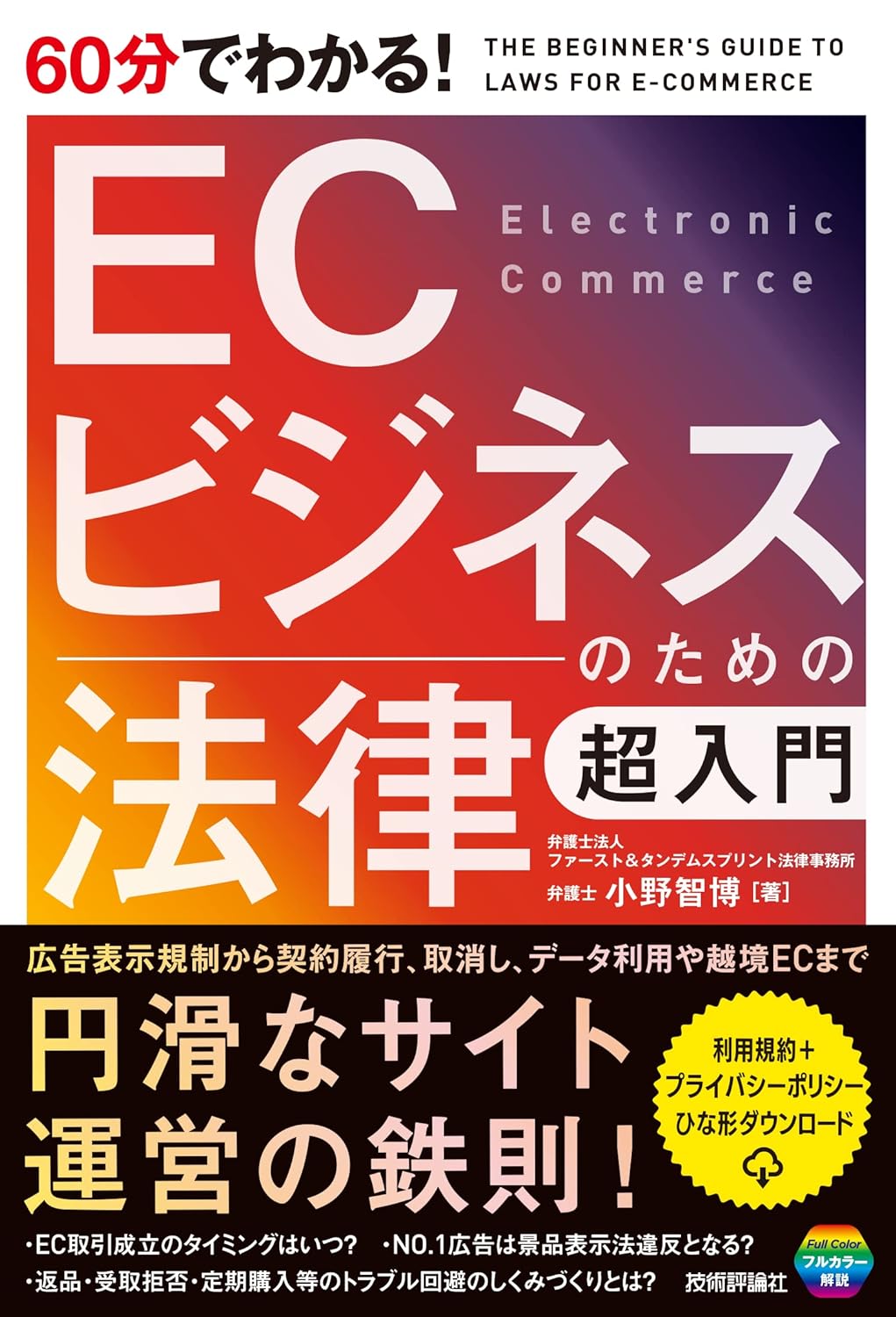カゴ落ちの防止対策。原因や計算方法、メールの活用も解説

「PV(ページビュー)数やUU(ユニークユーザー)数は上がっているのに、いまいち購入数が増えない……」と悩みを抱えていませんか?
もしかするとその原因は、カゴ落ちにあるかもしれません。
ECサイト運営において、カゴ落ち対策は必須です。本記事では、カゴ落ち率の計算方法やカゴ落ちの原因、効果的な対策方法について解説していきます。
なお、この記事では2024年2月時点の情報を掲載しています。
カゴ落ち(カート離脱)とは
カゴ落ちとは、ECサイト上で顧客が商品をカートに入れたまま、購入に至らず離脱することです。カート離脱やカート放棄、英語で「Cart Abandonment」とも呼ばれ、ECサイトの売上に大きく関わります。
例えば、顧客が商品を気に入ってカートに入れたものの、決済方法が複雑だったり購入までに多くの手順を踏まなければならなかったりすると、顧客の購入欲が冷め、購入を断念してしまいます。
広告運用やSEO対策をおこないサイトへの訪問者数が増加しても、カゴ落ちが多ければCVR(コンバージョンレート)も下がってしまうわけです。
カゴ落ち率(カート離脱率)の平均
ECサイトの調査をおこなっているアメリカのBaymard Instituteの2024年の発表によると、世界の平均カゴ落ち率は70.19%と計算されています。ECサイトの訪問者のうち、7割以上がカゴ落ちにより離脱しているのです。
また、カゴ落ちによる機会損失額は平均で売上の2.5倍との数値も出ており、カゴ落ちによる売上へのインパクトは非常に大きいといえるでしょう。
出典:49 Cart Abandonment Rate Statistics 2024|Baymard Institute
関連記事:【調査】「カゴ落ち」は最大70%・売上の2.5倍にも

カゴ落ち率(カート離脱率)の計算方法
ECサイトでどのくらいカゴ落ちが起こっているのかを把握するために、カゴ落ち率の計算方法を知っておきましょう。
カゴ落ち率の算出には、以下の計算式を使用します。
- カートに商品を入れた人数-購入者数=購入せずにサイトを離脱した人数
- (購入せずにサイトを離脱した人数÷カートに商品を入れた人数)×100=カゴ落ち率
計算式を使い、自社のECサイトのカゴ落ち率を計算してみましょう。
GA4でカゴ落ち率を確認する方法
GA4(Google Analytics4)では、ファネルデータ探索を使いカゴ落ち率を確認できます。
ファネルデータ探索では、ECサイト内で顧客が商品をカートに入れてから購入完了までの、どの段階で離脱しているか把握が可能です。GA4のファネルデータ探索でカゴ落ち率を確認する手順は以下のとおりです。
- ファネルデータ探索のステップを設定する
- データ探索を実行する
- 分析結果を活用する
1.ファネルデータ探索のステップを設定する
GA4画面内の「探索」から「ファネルデータ探索」をクリックします。手法は「ファネルデータ探索」を選択し、ビジュアリゼーションは「標準のファネル」を選択します。
設定内の「ステップ」を編集し、カートに商品を入れてから購入までの各段階を設定しましょう。最初のうちは分析しやすいよう、「カートに追加」や「注文者情報の入力」、「購入」など少ないステップで設定するのがおすすめです。
2.データ探索を実行する
ステップの設定ができたら、「適用」をクリックしましょう。各ステップごとの完了率と放棄率が確認できます。一度設定しておけば、GA4内の「探索」からすぐに確認が可能です。
3.分析結果を活用する
ファネルデータ探索から得たデータをもとに、顧客がどの時点でカゴ落ちをしているのかを特定しましょう。例えば、「注文者情報の入力」のステップでの離脱が多い場合は、入力フォームの複雑さや入力項目の多さなどの原因が考えられます。
データから得た問題点を改善し、カゴ落ち率を減らしましょう。
カゴ落ち(カート離脱)の原因・理由
カゴ落ちの原因や理由はさまざまですが、主に以下の6点が挙げられます。
- 送料や手数料が想定よりも高い
- クレジットカードの登録が面倒
- 決済時にアカウント作成が必要
- 意図しないスワイプバックで入力中のデータが消える
- 返品について詳しく書かれていない
- サイトのセキュリティ面が不安
送料や手数料が想定よりも高い
購入する商品の代金以外にかかる費用が顧客の想定よりも高い場合、カゴ落ちしやすくなります。ECサイトでは実店舗と違い、商品代金以外に送料や手数料などの費用がかかります。
またECサイトではほかの商品との比較が簡単なため、顧客は予想外の費用で想定よりも出費が多くなるとほかの商品やサイトへ離脱する傾向があります。
例えば、日本郵便のゆうパックの基本運賃は、東京都内での配送の場合、最小の60サイズのもので820円、最大の170サイズのもので3,000円です。送料は運送会社によって異なりますが、商品代金に上乗せされる送料の金額は顧客が購入するかどうかの判断材料となるでしょう。
そのため、ECサイトでは送料や手数料などの追加費用は事前に明示しておいたり、可能な限り低価格に抑えたりするなどの対策が必要です。
出典:基本運賃表(東京)|日本郵便公式サイト
クレジットカードの登録が面倒
近年はさまざまな決済方法が登場し、クレジットカードでの決済が面倒に思われる傾向があります。なぜなら、クレジットカードでの決済にはカード番号や名前、セキュリティコードの入力が必要だからです。
通勤中にECサイトを見ている顧客であれば、電車の中で商品を購入しようとする人もいるでしょう。しかし、満員電車の中ではクレジットカードを取り出すのが大変だったり、周りの人に個人情報を見られてしまうおそれがあり、その場での決済に至らない場合があります。すると、顧客の購入欲が冷めていき、結果カゴ落ちを招いてしまうのです。
これまでは一般的な決済方法だったクレジットカードですが、今後はほかの決済方法も充実させていくのが、カゴ落ち防止の対策の1つといえます。
決済時にアカウント作成が必要
ECサイトでは、決済時にアカウント作成が必要な場合が多くあります。しかし、アカウント作成が手間に感じられ、カゴ落ちされてしまうこともあります。
アカウント作成には名前や住所、クレジットカード情報などを入力する必要があるため、入力作業が手間に感じられるとカゴ落ちを招いてしまうでしょう。
ただし、アカウント作成には次回以降の購入が楽になるというメリットがあります。そのため、入力補助機能を導入したり、入力項目を最低限の数にするなど入力のハードルを下げるのが重要です。
顧客のアカウント情報はECサイト改善のための重要なデータとなります。カゴ落ち防止の対策をしながらも、しっかりとデータを入力してもらう工夫が必要です。
意図しないスワイプバックで入力中のデータが消える
スマートフォンでアカウント作成や購入時の必要項目を入力する際、意図しないスワイプでページが切り替わってしまう場合があります。
ページが切り替わったときにそれまで入力していた内容が消えてしまうと、顧客の購入意欲は冷めてしまうでしょう。
総務省が発表したデータによると、インターネットを利用する際に使われているデバイスは、約70%がスマートフォンだと示されています。そのため、カゴ落ち防止には、スマートフォンならではの操作に合わせた対策をおこなうのも重要です。
出典:令和3年通信利用動向調査ポイント|総務省
返品について詳しく書かれていない
商品の返品について詳しく書かれていない場合、顧客はサイトに不信感を抱き決済に至らない場合があります。
注文後何日以内であれば返品ができるのか、返品時の送料はどちらが支払うのかなど、顧客の不安を解決するための記載をしましょう。
返品についての記載はカゴ落ちだけでなく、ECサイト全体の信頼度に関わります。すぐに手直しできる部分なので、返品についての記載がない場合はすぐに改善しましょう。
サイトのセキュリティ面が不安
決済情報をはじめ、個人情報や購入履歴が残るECサイトでは、サイトのセキュリティ対策がされていない、もしくはそれが顧客に伝わっていない場合、カゴ落ちの要因となります。
ECサイトでは決済情報や個人情報を入力しなければならないため、セキュリティ面で不安があるサイトでは、どんなに良い商品を扱っていても購入されません。
サイトのセキュリティ対策をおこなうのはもちろん、きちんと対策をおこなっていることを顧客に伝えることも重要です。このサイトで商品を購入しても問題ないという安心感が、カゴ落ち防止の対策にもなります。

カゴ落ち防止の対策
カゴ落ち防止の対策は下記の6点から始めましょう。
- 送料や手数料の費用を下げる
- 決済方法の選択肢を増やす
- 入力フォームを最適化する
- 返品条件をわかりやすく表記する
- TLSを導入し、サイトの安全性を高める
- 3Dセキュアを導入し、カード情報を守る
送料や手数料の費用を下げる
送料や手数料の費用を下げ、顧客の想定外の支払いを生ませない対策が必要です。
とはいえ、すべての送料を無料にしたり、手数料を加味しない価格設定はECサイトの利益減に直結するため難しいでしょう。
そのため、例えばあらかじめ商品価格に送料を含んだ金額を商品ページに記載するのも有効です。この場合、早い段階で顧客は送料込みの金額を把握できるため、決済時に追加される金額がなくなり安心して商品を選べます。
また、サイト上に常に「〇〇円以上購入すると送料無料」のような記載をしておけば、いくら以上購入すれば追加の費用がかからなくなるかがわかり、買い回りのハードルが下がるでしょう。購入単価のアップも期待できます。
決済方法の選択肢を増やす
決済方法の選択肢を増やせば、顧客に合った決済方法を提供できる可能性が高まり、カゴ落ち防止の対策ができます。
近年はクレジットカード決済以外にも、PayPayやAmazon Pay、キャリア決済などさまざまな決済方法があります。
これらの決済方法を導入すると、顧客は個人情報やクレジットカード情報の入力を省けるため、よりスムーズに商品の決済が可能です。
ただ、すべての決済方法を導入するのは大変なので、メインの顧客層が多く使っている決済方法をリサーチし、導入するのをおすすめします。
入力フォームを最適化する
決済前の入力フォームは、顧客の使いやすさを重視するのが大切です。
項目が多すぎたり、複雑で入力しづらいデザインだったりすると、顧客のストレスを招きます。
特に、住所の入力はす手間に感じられるため、郵便番号をもとにした住所の自動入力機能を搭載するのはカゴ落ち防止の重要な対策といえます。
また、先述したスワイプバックへの対策も重要です。スワイプバックされた際にポップアップで本当に戻るかどうかの警告画面を表示させると、意図しない入力データのクリアを避けられます。顧客の購入意欲を下げないために、ぜひ検討しましょう。
シンプルでわかりやすい、顧客にとって使いやすい入力フォームを導入すれば、カゴ落ち防止に効果的です。
返品条件をわかりやすく表記する
返品条件を明記し、顧客に安心感を与えるのもカゴ落ち防止の対策の1つです。
商品が到着してから何日以内であれば返品ができるのか、返品時の送料はどちらが支払うのかなど、返品時の疑問をわかりやすく解決しておきましょう。
決済画面に詳しく返品条件を記載しておくのはもちろん、トップページのフッター部分に記載しておくのも効果的です。
TLSを導入し、サイトの安全性を高める
セキュリティ面に不安があるサイトでは、カゴ落ちの可能性が高くなります。
ECサイトのセキュリティを高めるには、TLS(Transport Layer Security)の導入が良策です。TLSとは、インターネット上でデータを暗号化して送受信する仕組みの1つ。TLSを導入すれば、クレジットカード情報や個人情報などを盗み取られるのを防止できます。
過去にはSSL(Secure Sockets Layer)が広く使用されていましたが、脆弱性が発見されたため現在はTLSが主流です。
TLSやSSLが導入されているサイトでは、URLの始まりが「http://」ではなく「https://」と表記されます。この表記の違いにより、顧客に安心感を与えられるでしょう。
サイトのセキュリティは、顧客が安全に決済できるかどうかの鍵です。
出典:SSL/TLSの仕組み|総務省
3Dセキュアを導入し、カード情報を守る
3Dセキュアとは、クレジットカードでの決済時に本人認証をおこなうサービスです。
Visa、Mastercard、JCB、American Expressの4ブランドで世界共通の本人認証サービスとして広く利用されています。
3Dセキュアではクレジットカードの情報以外に、カード発行会社に登録されているIDとパスワードの入力もおこないます。そのため、より安全に決済を進められるのです。
しかし、安全性が高い一方で購入までの手間が増え、カゴ落ちのリスクが高まります。そのため、ECサイト上で3Dセキュアのメリットを伝えるための工夫をしましょう。
効果的な「カゴ落ちメール」とは
カゴ落ち対策には、カゴ落ちメールを送信するのも効果的です。
カゴ落ちメールは、商品をカートに入れた状態で放置してしまっている顧客に向けて送信するメールを指します。
カゴ落ちメールの効果
カゴ落ちメールの対象者は商品を一度カートに入れた顧客です。カゴ落ちメールを送り、再度商品を思い出してもらうことで、購入につながる可能性が高まります。
また、カゴ落ちメール内で顧客の疑問や不安点を解決するためのアプローチをおこなえば、購入につながるだけでなく顧客満足度の向上も期待できるでしょう。
カゴ落ちメールには顧客の購入促進や売上の向上だけでなく、ECサイト全体の顧客満足度を向上させる効果があります。適切な内容やタイミングを知って、効果的に運用しましょう。
カゴ落ちメールの例文
カゴ落ちメールは、顧客一人ひとりに合わせた内容にするのが効果的です。
カゴ落ちメールの例文を紹介します。
<カゴ落ちメールの例文>
件名:
【サイト名】カートの中に買い忘れはありませんか?
本文:
こんにちは、【顧客の名前】様。
先日は【サイト名】をご覧いただき、ありがとうございました。
お客様のカートに商品が残っているのにお気づきでしょうか?
購入手続きが完了していないため、お客様が気に入った商品の確保ができておりません。
お客様がカートに追加された商品は以下のとおりです。
- 商品A【URL】
- 商品B【URL】
ご注文を完了させる場合は、下記のURLから直接購入手続きが可能です。
【購入手続きURL】
また、購入手続きについてご質問や不明点がある場合は、お気軽に当店までご連絡ください。
【顧客の名前】様のご購入を心よりお待ちしております。
【店舗名】
【メールアドレス】
【電話番号】
カゴ落ちメールを送るタイミング
カゴ落ちメールを複数回送付する場合は、送るタイミングに注意しましょう。カゴ落ちメールの効果的な送信のタイミングは、カートに入れてから数時間後や24時間後です。
顧客が忙しくて商品をカートに入れたまま決済に至らなかった場合は、数時間後のメールが効果的です。顧客の購入意欲が高い状態でアプローチできれば、再度購入手続きに戻り、決済をおこなってくれるでしょう。
また、24時間後のメールでは、顧客がじっくりと購入を検討したタイミングでのアプローチが可能です。ほかの商品と比較をする時間を与えたうえで再度購入を促せば、顧客の満足度も上がり購入をしてもらえるでしょう。
カゴ落ちメールは複数回送信しても問題ありませんが、あまり頻繁に送信すると顧客のストレスとなります。そのため、1人の顧客に対して3〜4回程度の送信を目安としましょう。

カゴ落ちの対策ツール
ここでは、カゴ落ち対策を効率的に実施できるツールを紹介します。
| ツール名 | 特徴 | 機能 | 料金体系 |
|---|---|---|---|
| SaleCycle | ・リアルタイムでのカゴ落ち対策。 ・1つのタグをサイトへ装備するだけなので簡単。 ・世界500社以上での導入実績。 |
・リアルタイムでカート放棄メール送信 ・リアルタイム分析、カゴ落ち商品の可視化、 ABテスト、パーソナライゼーション機能 |
・初期費用:無料 ・月額費用:無料 ※成果に応じた従量課金制 ※利用件数によって初期費用・月額費用が発生する場合あり |
| CART RECOVERY | ・アクセスユーザーにリアルタイムでメールアドレス登録の案内を出せる ・最短3日で導入可能 |
・在庫連動あり ・機会損失、メール配信効果、カート内トレンドなどリアルタイムで効果測定 |
・初期費用 50,000円 ・月額費用 39,000円 ※最大2カ月無料トライアル |
| NaviPlusリタゲメール | ・幅広い種類のメールを設定でき、 ニーズに合わせた複数のシナリオ・コンテンツが送信可能。 |
・カゴ落ちだけでなく再購入促進、カートに入った商品の値下げや在庫わずか、 再入荷のお知らせメール配信 ・キャンペーン設定、効果測定レポート、ABテストなどの管理機能 ・タグ設置によるユーザーやカートデータの収集、 IDとCookieによるユーザー特定が可能 |
・初期費用 200,000円 ・月額費用 50,000円 |
ECサイトの最適化はプロの運用代行業者に相談するのがおすすめ◎
ECサイトにおいて、カゴ落ち防止対策は売上の向上だけでなく、サイト全体の信頼感の向上にもつながります。
しかし、ECサイト全体の最適化には専門的な知識や人員のリソースも必要です。そのため、安心かつ確実に最適化をするために、プロへのアウトソーシングがおすすめです。
ECのミカタでは、ECサイトの悩みや要望を解決してくれる運営代行会社を紹介するサービスをおこなっています。
プロのコンシェルジュがあなたのECサイトの悩みを聞き、その悩みに合ったEC専門の運営代行会社をマッチングしてくれます。
ECサイトの最適化やカゴ落ち対策でお悩みの方は、ぜひ一度相談してみてください。