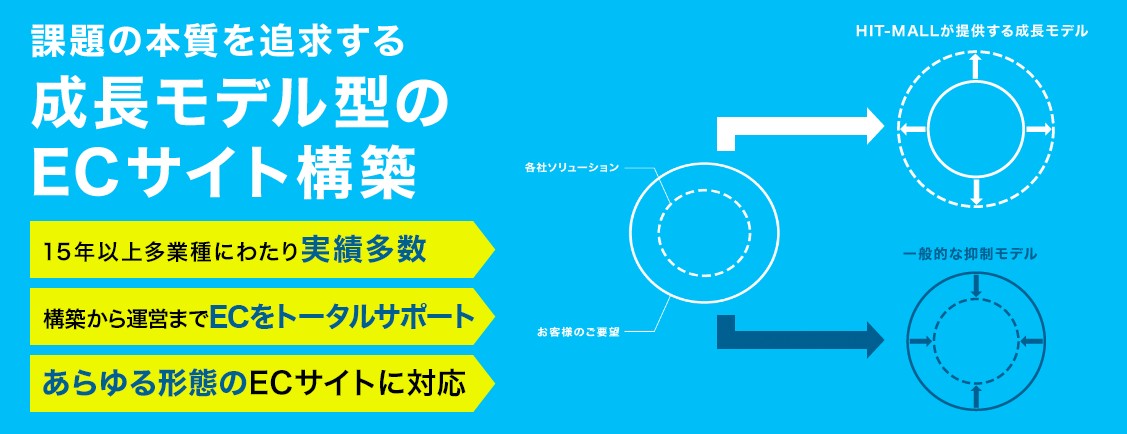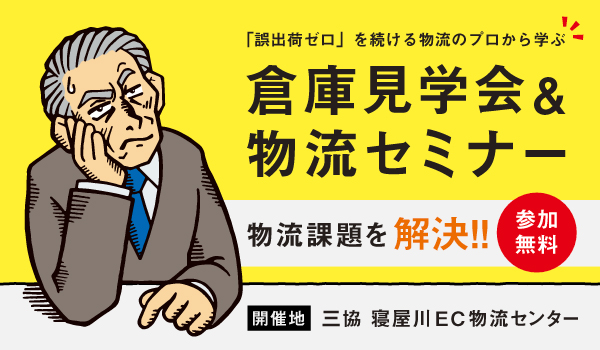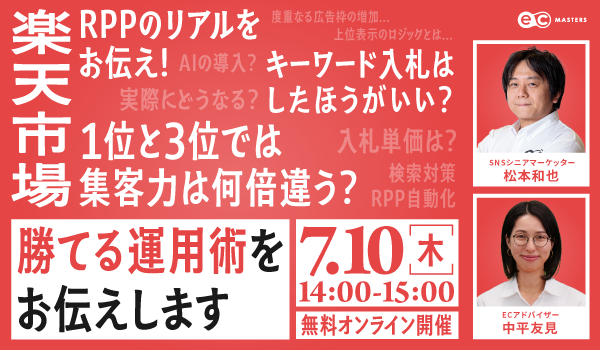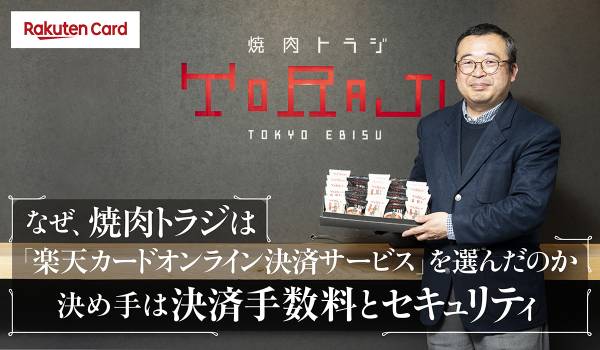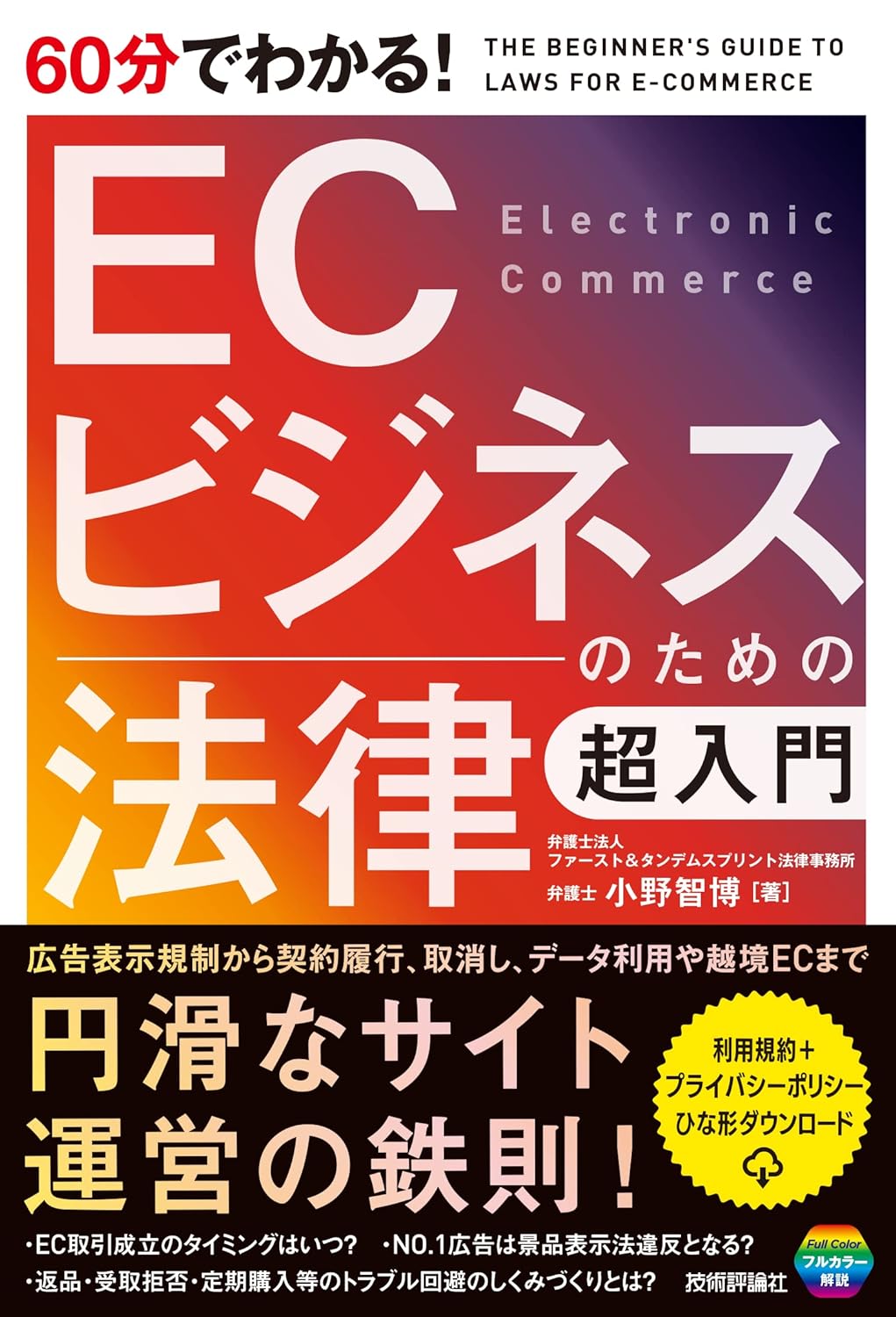D2C・サブスクを実践するスナックミーに極意を聞く

サブスクリプション・D2C。ECのみならず、小売業界のトレンドワードだ。
しかし、その意味を問われて、表面的な話はできる人はいても、現場に落とし込んだ形で話せる人はあまり多くない。
そこで今回は、様々な種類のおやつを個人にパーソナライズし、独自のおやつBOXをサブスクリプションサービスとして展開しているD2Cブランド、株式会社スナックミーの代表取締役 服部氏と廣濱氏に取材を行なった。
特に服部氏は自身のnoteでD2C・サブスクについて解説しており、有識者と言っても過言ではない。その服部氏が経営するスナックミーがどのようにビジネスを行なっているか教えていただく。
目次
MIKATA会員(無料)に登録して続きを読む
※登録は無料、MIKATA会員に登録することで、過去記事含め全記事が読み放題、サービス資料のダウンロード、セミナー参加が行えるようになります。
新規MIKATA会員登録
ログイン