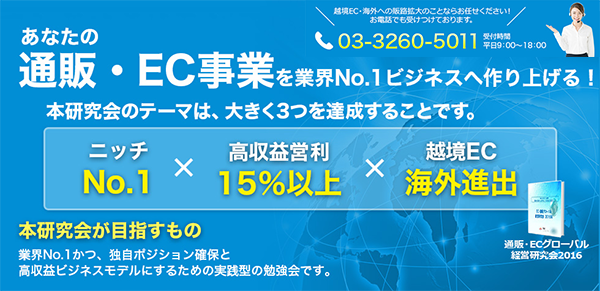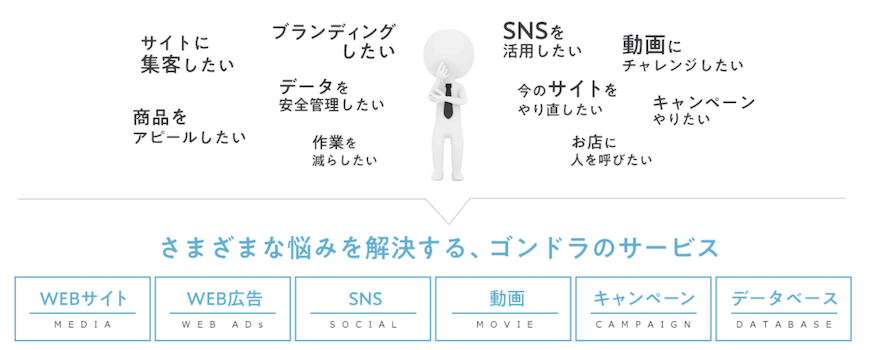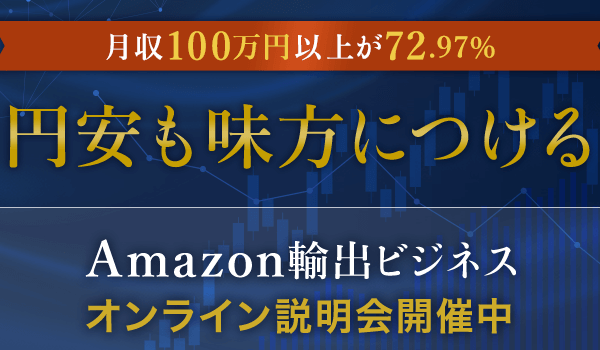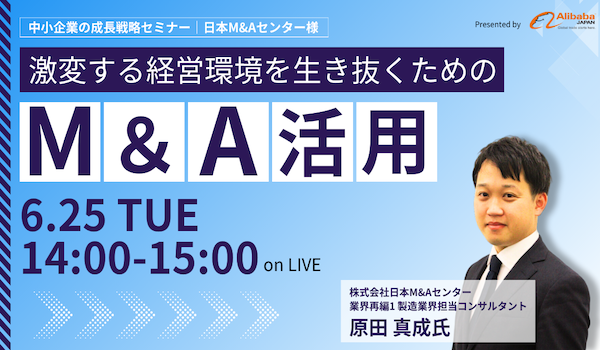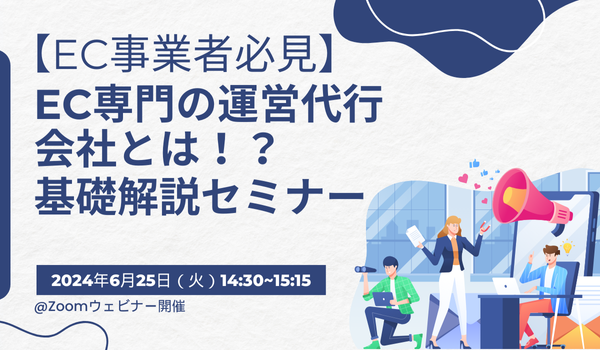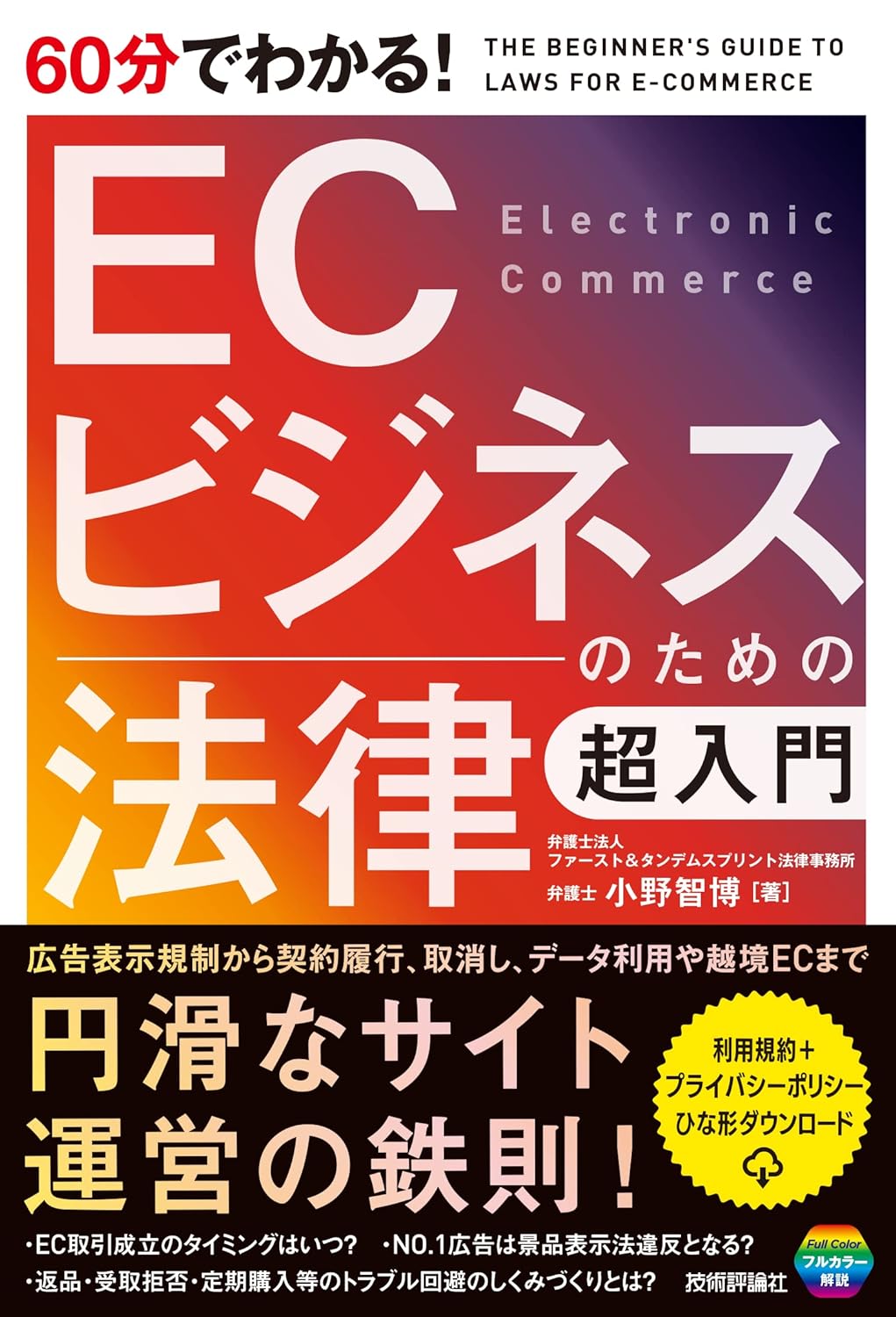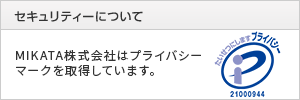顧客満足度とは?ECサイトの顧客満足度を向上させる方法を解説!

ECサイトで重要な要素として挙げられる顧客満足度。よく耳にするものの顧客満足度の意味や重要性をいまいち理解しきれていない担当者は多いのではないでしょうか。本記事では顧客満足度の意味や調査方法、さらには向上させるための施策まで解説します。
顧客満足度を上げることが社内の課題として上がっているEC運営者は必見です。
顧客満足度とは
顧客満足度とは?
顧客満足度とは自社サービスに対して顧客がどの程度満足しているかの度合いを示す言葉です。ECサイトの売り上げは新規顧客と既存顧客の2種類で成り立っていますが、既存顧客を増やす上で顧客満足度は重要です。
顧客が商品に期待する効果を上回らなかった場合、顧客満足度は低くなりますが期待値を大きく上回った場合、顧客満足度は高くなるとされています。顧客満足度が高ければ顧客が再度商品を購入してくれる可能性も見込め、既存顧客化へ繋げることもできます。実店舗と異なり顧客と直接コミュニケーションがとれないECサイトにおいて、顧客満足度は意識するべき重要な指標とも言えるでしょう。
ECサイトにおける顧客満足度の重要性
LTVが向上する
LTV(顧客生涯価値)とはLife Time Valueの略でマーケティング指標の1つです。LTVは購入単価×購入回数×継続期間で計算され、ECサイトが継続的に利益を出す上で無視できない数字です。顧客満足度が高ければ既存顧客になる可能性は高くなるため、購入回数と継続期間の2つが上がり、結果的にLTVの向上が期待できます。そのため、無料クーポンの配布や知り合いを紹介するとお得に購入できるなどLTVを上げるための対策がよくECサイトでは行われています。
競合他社と差別化できる
顧客満足度が向上することで競合他社との差別化が見込めます。ECサイトでは商品の質や価格といった機能的な面で競合と差別化することは時間もかかり難易度が高くなりますが、電話対応やメール対応、レビューの返信など属人的な業務のレベルが上がればダイレクトに満足度に反映することも可能です。商品やサービスの質以外の部分でも顧客満足度を高めることを視野にいれ、競合他社との差別化を図りましょう。
顧客満足度を知るための調査方法
アンケート調査
顧客満足度を知るための調査方法で最もスタンダードな方法がアンケート調査です。アンケート調査は自社が知り得たい情報を質問に落とし込めることが特徴的で、満足度だけではなく今まで見えてこなかった顧客のニーズなども拾うこともできるでしょう。また多くの顧客に回答してもらうためにもアンケート内容は工夫が必要です。冒頭に「アンケートを答えるとクーポンをプレゼント!」など、顧客がアンケートを答えるメリットを提示すると回答率は上がりやすいとされています。幅広く顧客の満足度を測るためにもアンケート内容にも工夫を散りばめることが必要です。
電話
顧客満足度を知るための2つ目の方法として電話が挙げられます。カスタマーサポートを代行会社に依頼しているECサイトは、よく顧客対応の業務と同時に電話でのアンケートも依頼していることがあります。電話の調査では1人の顧客に対してより深く質問できることが何よりの強みです。満足している点や不満な点を深掘ることもでき、会話によって改善点を拾うことにも繋げれられます。
リサーチ会社へ依頼
専門のリサーチ会社に依頼することで精度の高い顧客満足度に関する情報を入手できます。リサーチ会社は数多くの実績や幅広い業界との付き合いがあるため、多くのECサイトから利用されています。ただ、顧客満足度向上のために何を知りたいのか把握しておかなければ、期待していた効果を得られないケースもあります。知りたかった情報ではなかったということを避けるためにも、顧客満足度調査の目的を社内で決めてから依頼するようにしましょう。
顧客満足度を測るための指針・KPI
指針
NPS®
NPS®はNet Promoter Score(ネットプロモータースコア)」の略で顧客満足度を測る指針の1つです。「この商品を誰かにお勧めしたいか」などサービス満足度を中心に質問事項を作成します。0〜10点の11段階で評価され、0〜6点が若干の不満を持っている批判者、7〜8点が嫌いでは無いが特にファンでも無い中立者、9〜10点が強い好感を持っている推薦者に分類されます。
上記の分類のうち「推奨者の割合(%)− 批判者の割合(%)」が NPS® のスコアとなります。このスコアが高ければサービスに満足していると言えるため、推薦者の割合を高め批判者を少なくすることを目指しましょう。
CSI
CSI(Customer Satisfaction Index)は、自社サービスへの関連性が強い質問を行い顧客満足度を確かめる指標で世界約30か国で使われている最もポピュラーな指針です。多くのECサイトでは「期待値」、「不満度」、「顧客ファースト」、「商品に対する顧客の主観的な評価」、「価格に対する満足度」の5つを質問項目に入れています。1-100点の中で評価をしてもらい、その平均値を顧客満足度とするため80-90点をまずは目指してみることをお勧めします。
JCSI
JCSIは世界標準であったCSIを日本版にカスタマイズした指針です。CSIと異なる点は上記の5つの項目に加え、「推奨意向」を加えていることです。1項目ごとに3~4つの質問を行い、0~100点で評価してもらいます。顧客満足度=顧客が感じた価値 − 事前期待価値という計算式になっているため、高い数字を目指すようにしましょう。
KPI
購入率
サイトを訪れたユーザーのうち商品購入に至った人がどの程度いるのかを表しており、サービスを購入した人数÷サイトに訪れた人数で計算されます。購入率を明らかにすることでLPやサイトの設計にどれだけユーザが満足しているかを確かめることが可能です。「顧客がどのページで離脱してしまったか」「どのような経路だと購入率が悪いか」など商品別・ページ別に細かく分析することで具体的なアクションを定められます。ECの売り上げを上げる上でも大事な指標であるため、購入率は必ず確認しましょう。
リピート率
初回のサービスにどれだけ満足したかを示しているため、新規顧客を既存顧客にするために多くのECサイトはリピート率を重要視しています。
リピート率は顧客数÷累計新規顧客数で計算され、一般的なリピート率は15-18%と言われていますが商品購入後のフォローをするとリピート率は30-40%に上がるという調査結果もあります。商品発送後のアフターフォローを手厚く行うことで、リピート率を上げることにも繋げられます。
クレーム率
クレームが多いということは商品やサービスに対して不満を感じているため、次回購入する可能性は低くなります。
クレーム率はクレーム数÷問い合わせ数で計算され、改善するには商品などの機能的サービス、電話やメール対応などの情緒的サービスの質を上げることが有効です。クレームを受けた際は、サービス改善のチャンスだと思い詳しく顧客に状況をヒアリングを行い、同じようなクレームを受けないよう社内で対策を講じましょう。
解約率・返品率
解約率とは商品を購入することをやめる数値のことを指します。解約率・返品率はひと月の解約者数÷同期間の顧客数で計算して出すことができます。解約率は3%以内に抑えることが理想と言われているため、解約の原因を追求することも併せて行い、まずは3%以内で収めることを指標として置いてみましょう。
顧客満足度を向上させるには?
組織全体で顧客の満足度を定義する
顧客満足度を向上させるためにも、まずは会社全体で顧客満足度とは何かを定義することから着手しましょう。共通認識を持つことで顧客満足度を向上させるための施策に一貫性を持たせることができ、効果的な振り返りがしやすくなります。具体的なKPIを設定するためにも、クリエイティブ部門、ビジネス部門含めた関係者全員で顧客満足度の定義を擦り合わせましょう。
現状の顧客満足度・課題を把握する
まずは現状、顧客が自社に対してどのような評価をしているのかを知ることで、適切な打ち手が考えられます。また、ここでは顧客が回答した内容ばかりに注目するのではなく、どのような属性の顧客の回答なのかに注目する必要もあります。ここでの回答を軸として分析を行うか、顧客情報を軸として分析を行うかで対策の方向性が変動するので得た情報をより効率的に活用しましょう。
既存サービスの質を上げる
FAQを設置する
質問と回答が用意されているFAQ機能は顧客満足度を向上させるためにも必要なサービスです。顧客の中にはサービスに興味は持っているものの、疑問があり購入に踏み切れない顧客も存在します。このような時にFAQは役に立ちます。
FAQ機能があるだけで顧客自身が電話やメールをする時間を省け、速やかに問題を解決することができ顧客満足度が向上するとされています。社内でどの質問が多いかを確認し、質問が多いものから順にFAQに記載するようにしましょう。
顧客対応
顧客対応(カスタマーサポート)のレベル上げはどの企業も課題として捉えているでしょう。特にカスタマーサポートは顧客との接点が多いため、対応によっては売上げアップに貢献する時もあれば、下げてしまう要因の一つになる可能性もあります。顧客からの問い合わせが来た際に、スピーディー且つ適切で、丁寧な対応をすることによって、顧客満足度を上げることにも繋がります。
顧客満足度を上げるための3つの施策
ダイナミックプライシング
ダイナミックプライシングとは顧客の需要と供給を考慮しサービスの価格を変動させる手法です。サービスの原価をもとに価格を決めるのではなく、販売する時期における顧客の需要を予測して価格を決めます。企業側としては利益を最大化できる、在庫を抱えるリスクを軽減できるというメリットがあり、顧客はコストを抑えて商品を購入することができるという双方にメリットがあります。ただ、時期によって必ずしもサービスが売れるとは限らないため、実施する時期は慎重に見極めましょう。
ホスピタリティ
ホスピタリティとは顧客を心から大切に思うことです。「こんなことまでしてくれるのか」という期待を超える驚きは、顧客満足感を向上させる大きな要因です。小手先のテクニックで身につくものでなく、日々お客様について考え抜くことで身につくとされています。オイシックス・ラ・大地の社長の高島氏は顧客に感謝を伝えるために直接顧客の家を訪問したことで有名です。高いホスピタリティを持ってお客様と接することで顧客満足度の向上は見込めると言えるでしょう。
ユーザービリティのあるサイト設計にする
ECサイトを見やすく、購入まで迷うことのない設計にすることでサイトに訪問した顧客の回遊率や滞在時間の向上につなげられます。アパレルだったらブランド、シャツ、小物などでカテゴリを分けるなど顧客が商品を探しやすい設計にすることで商品を探す手間が省けスムーズに購入まで辿り着けます。また、コンテンツを充実させるなどの対策をすることによって、自社のECサイトが有益な情報を提供するサイトだと顧客に認識をさせることができます。
【事例紹介】顧客満足度を向上させる各社の取り組み
ユニクロ
ユニクロのECサイトでは実店舗では扱っていないサイズなどを展開しており、売上の機会損失を極力防ぐ取り組みをしています。またアプリ上でも誕生月の特典クーポンの発行や定期的なセールの告知をするなど顧客にとって有益な情報を常に提供することで、満足度の強化を図っています。
誕生日クーポンの配布などは立ち上げたばかりのECサイトでも取り組めることなので、是非実行してみてください。
snaq me
snaq.meはおやつが届く定期制サービスを提供している会社です。顧客の好みを知るためにサイト上で診断コーナーを設置し、結果をもとに顧客好みのおやつを配送しています。「次はどんなおやつが届くのか?」というワクワク感を演出するために、お菓子は毎回異なる設定にしています。たとえ味が合わなかったとしてもアンケートを送ったり、LINEでいつでもお問い合わせができるような導線を確保しています。いつでも相談できるという状態は顧客にとっても安心する材料の1つでもあるので、LINEやチャットボットを用いて顧客満足度を向上させましょう。
BASE FOOD
BASEFOODは、健康を維持するために必要な栄養素を全て含んだ食品を販売しており、パンやパスタを販売しています。最近ではオンラインだけでなく、コンビニ各所でも販売していることで有名です。BASEFOODは、顧客満足度を上げるための施策を多く行っていることで有名で、例えばSNSでフォロワーからの質問には必ず返信をしたり、定期購入者をニュースレターに掲載するなど積極的に顧客とのコミュニケーションを図っています。また、communeというアプリを用い顧客同士のコミュニティ形成も行なっており、スタッフからのおすすめレシピの紹介や、ユーザー同士での商品に関する情報交換する場所を設けたことで会員数は1万人に到達しています。
顧客満足度が上がるだけでなく、顧客が勝手に商品情報を発信してくれる可能性も高まるため、顧客同士のコミュニティを作ることは顧客満足度を上げる1つの手段です。
まとめ
本記事では顧客満足度の意味や向上させるための方法を解説しました。顧客満足度はLTVの改善や、リピーター獲得に向けてに欠かせない指標であり、向上することで高い効果を期待できます。アンケートの実施や向上方法を踏まえた上で、自社ECサイトの顧客満足度を上げるための施策を考え実行に移しましょう。